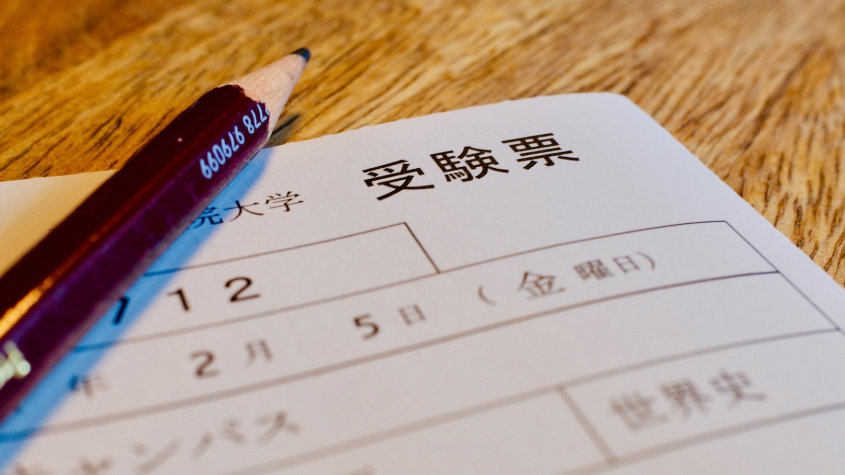社労士は、人気の資格の1つです。社労士に興味はあるものの、どのくらいの費用がかかるか知らないという人は少なくありません。この記事では社労士試験の受験料や資格取得のためにかかる費用、取得後にかかる費用について解説しています。社労士試験の受験料をはじめ、かかる費用を知りたい人は参考にしてください。
社労士試験の受験料
社労士試験の受験料は、いくらなのでしょうか。他の資格の受験料との比較とともに、解説します。
社労士試験の場合
社労士試験の受験料は15,000円です。令和3年度の試験から、それまでの9,000円から改定されました。改定は「試験の実施における新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の必要性や、積立金の状況、受験者数の実績などを踏まえて」という理由です。値上げによって、試験に向けた準備の重要性が増加しました。
他の資格における受験料の場合
2023年度時点の、社労士と同じ士業資格と比較します。他の士業資格の受験料は以下のとおりです。
- 行政書士:10,400円(システム手数料370円も負担)
- 司法書士:8,000円
- 税理士:1科目4,000円、2科目5,500円、3科目:7,000円、4科目:8,500円、5科目:10,000円
- 公認会計士:19,500円
- 通関士:3,000円
- 宅建士:8,200円
公認会計士よりは低いものの、社労士試験は士業資格のなかでは高額です。
スクールに通う場合の費用
社労士試験の合格を目指してスクールに通うにはいくらかかるのか、どのようなメリットがあるのか解説します。
スクールは費用が高額になる
通学のスクールの費用は、学校によって差があります。大手は概ね15万円を超え、20万円を超えるコースも珍しくありません。教室と映像(DVD)のコースにわかれている学校もありますが、大きな価格差はありません。
通学には交通費もかかる
スクールに通う場合、スクールに払う費用のほかに交通費がかかります。社労士に合格するには800~1,000時間とも言われる学習時間が必要で、スクールの場合10~11か月ほど通わなければなりません。その間電車やバスなどの交通費、もしくは定期券代が必要になる場合もあるでしょう。
集中力を保ちやすい
スクールは教室で授業を受けられるため、集中力を保ちやすいでしょう。カリキュラムによって講義が組まれており、学習のスケジュール作りを担ってくれるため、学習計画や進捗の管理が不要で勉強に集中できます。また、周りに仲間がいるため、モチベーションを維持しやすいこともメリットです。
独学の場合の費用
独学の場合は、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。独学の費用やメリットについて、解説します。
費用を最小限に抑えられる
かかる費用は、市販のテキストや問題集の購入代金程度で、数万円ほどで揃えられます。購入すれば学習を始められ、交通費もかかりません。ただし、独学で合格するのは難易度が高いとされ、合格できない年が続くと、年々費用がかさんでいきます。
自分のペースで勉強できる
スクールに通う場合は交通費だけでなく、移動時間もかかります。独学であれば、移動時間も学習する時間にあてられます。仕事や育児など自身の都合に合わせて、空いた時間で学習を進められるでしょう。
短期合格が難しい
独学はモチベーションの維持と、効率的に学習を進めることが難しいことが難点です。さらにわからない部分は自分で解決しなければなりません。合格のためには長期間学習を続ける必要がありますが、モチベーションも低下しやすいでしょう。
通信講座の場合の費用
続いて、通信講座の場合はどれくらいの費用がかかるのでしょうか。通信講座の費用やメリットを解説します。
通学スクールよりは費用を抑えられる
通信講座は、運営会社から送られてくるテキストと配信される講義映像によって学習を進めます。通学スクールに比べて運営する会社は教室を用意する必要がなく費用を抑えられるため、料金も通学スクールよりリーズナブルです。独学よりは費用がかかるものの、通学スクールのような交通費もかかりません。
通学スクールに劣らない質の授業を受けられる
通信講座のおもな学習方法は授業動画のため、通学スクールで授業を受ける感覚で学習できます。タブレット端末やスマートフォンのようなデバイスと、インターネットを使用できる環境さえあれば、場所と時間を選びません。そのため多忙な社会人であっても、自分の時間に合わせて勉強を進められます。
モチベーションの維持が難しい
いつでもどこでも学習できることが、デメリットになることもあります。容易に先延ばしできるため、モチベーションの低下につながりやすいのです。学習時間が不足して合格の確率を下げてしまわないよう、自分でスケジュールを管理して、毎日決まった時間に学習するとよいでしょう。
快適に勉強を進められる場所
社労士試験の合格を目指すには、快適に学習を進めることが重要です。どのような場所で学習すればよいでしょうか。
カフェ
独学や通信講座の場合、自宅で学習を続けるため飽きたり集中力が途切れたりすることがあります。時折カフェや喫茶店で学習すると、人の目があることで集中力が持続しやすくなります。また、場所を変えることで、気分転換につながるでしょう。ただし、学習が禁止されているカフェもあるため、注意が必要です。
有料の自習室
有料の自習室は、机と椅子が置かれたスペースで、月額制である場合が多いです。自宅と違い、誘惑するものがないため集中しやすいでしょう。無料Wi-Fiが用意されている場合もあり、調べ物もできます。
図書館
無料で使用でき、静かな環境のため学習に集中しやすいでしょう。図書館によっては、自習室が設けられていることもあります。ただし、学習が禁止されている図書館もあるため確認が必要です。
合格後にかかる費用
社労士試験に合格したのち、社労士として仕事をする際は登録しなければなりません。そのときには、登録手数料や入会金などの費用がかかります。具体的にいくらかかるのか、解説します。
社労士として独立する場合
登録する際に必ずかかる費用として、30,000円の全国社会保険労務士会連合会への「登録手数料」があり、30,000円の「登録免許税」も必要です。加えて、開業する場所の社労士会によって違いますが、「入会金」がかかります。東京都の社労士会への入会金は、開業登録する場合は50,000円です。入会金は、一度支払うとその後は不要です。
社労士として従事をする場合
会社に勤務する場合も、30,000円の全国社会保険労務士連合会への「登録料」と、30,000円の「登録免許税」が必要です。「入会金」は開業する場合より安いものの、東京都の社労士会の場合は30,000円かかります。各都道府県社労士会への入会金、年会費は都道府県により異なります。
その他にかかる費用
全国社会保険労務士連合会に登録するには、通算2年以上の実務経験が求められます。実務経験がないまま登録する場合は、代わりになる「事務指定講習」を受けなければなりません。
「事務指定講習」は77,000円かかります。社労士会への「年会費」もかかり、たとえば東京都の社会保険労務士会は、開業会員が96,000円、勤務等会員が42,000円かかります。
まとめ
社労士試験の受験料は15,000円です。学習方法により上下しますが試験対策にも費用がかかり、合格後にも登録料や登録免許税などがかかります。
クレアールは56年の歴史を持ち、社会保険労務士講座では非常識合格法という短期合格のための学習法を有しています。独自のセーフティコースでは、初年度の試験料負担があるため、かなりお得に学習が進められます。カリスマ講師が執筆した書籍を無料でプレゼントしているので、社労士試験の合格を目指している人は申し込んではいかがでしょうか。
クレアールでは、忙しくて時間が取れない方の相談窓口を開設しています。学習状況や1日に取れる学習時間など、ライフスタイルやご経歴に合わせて、社労士合格に向けた学習プランをメールでご返信いたします!講座内容や割引、資格の受験条件などにも、幅広く回答していますので、資格講座受講についての悩みをすっきり解消できます。
その他の記事を読む
-
社労士(社会保険労務士)とはわかりやすく言うとどんな仕事?
-
社労士は年末調整業務ができるか|税理士との比較や業務範囲、給与計算業務も解説
-
社労士試験の合格後に必要な手続きとは?流れや費用、代表的な働き方を解説
-
社労士の事務指定講習とは?受講のメリットやデメリットなどを解説
-
社労士の気になる平均年収とは?勤務形態や年齢・性別の違い、仕事内容も解説
-
社労士試験の難易度はどれくらい?司法書士や行政書士・税理士など人気資格と比較
-
社労士の受験資格はどうすれば得られる?要件や資格取得の注意点を解説
-
社労士の仕事内容とは?年収や資格取得の方法・メリットを解説
-
社労士資格で副業は可能?在宅・土日向けのダブルワークや業務のポイントを解説
-
社労士は就職・転職しやすい?社労士の就職事情と主な就職先を解説