社労士の資格試験における、通学講座、通信講座など予備校の必要性に関して、独学の場合と比較してそれぞれのメリット、デメリットを分析し、より合格の可能性が高くなる勉強の方法を考えていきます。
社労士試験合格に予備校が必要なワケ

社労士の資格取得を目指す上で、予備校の利用が現実的である理由のひとつに、試験範囲の広さと特性が挙げられます。社労士の資格試験では、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法その他、十科目に関しての法律や一般常識が問われます。
当然、覚えるべき知識も膨大になります。しかも社労士試験には科目ごとの合格基準点があります。これは十科目の科目ごとに、一定以上の得点を取らなければ合格できない制度です。つまり、全科目の総合得点では合格点を超えていても、一科目でも基準点を下回っていれば不合格になるのです。
結論として社労士試験は、試験の十科目に関する万遍ない知識が求められ、得意科目で不得意科目をカバーすることができません。十科目すべての知識をバランスよく習得することは、独学ではよほど学習スケジュールを工夫して、自身で厳しく守らない限り難しくなります。
一方、予備校では社労士試験で問われる全科目を効率的に学べるカリキュラムを組んでいるため、受験生は“必要な知識”を学ぶことに集中できるのです。合格を目指すなら予備校を利用することが合理的といえるでしょう。
社労士試験の予備校選び① 通学講座のメリット・デメリット
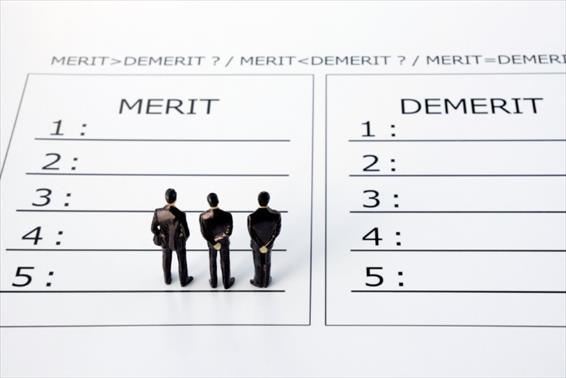
社労士試験のための予備校にもスタイルがありますが、現在でも人気が高いのは”通学講座”です。自ら予備校に通うメリットとしては、まずプロのカリキュラムで学ぶことができ、自ら教室に通うことで学習意欲が高まり、集中して勉強に取り組むことができるでしょう。
また、理解できない部分はその場で講師に質問できて理解が進むほか、予備校にある自習スペースや、オプションの応用講座、模擬試験などさまざまな施設、システムが利用でき、現在の自分の実力を確認し、弱点を補強することが容易になります。
また、他の受験生を意識することで、気の緩みを防げる面もあります。
一方、デメリットとしては、授業料が高額となり、また過剰なオプション講座などを追加してしまうことも多いこと、そして通学が負担となり、通い続けられなくなることなどが挙げられます。メンタル的には、ただ惰性で通っているだけで勉強した気になり、予習や復習、自宅学習がないがしろになる、またライバルの多さから挫折のきっかけになるという一面もあります。
社労士試験の予備校選び② 通信講座のメリット・デメリット

資格試験の予備校で、通学と並んで人気があるのが“通信講座”です。現在ではインターネットの進歩により、通信講座にもさまざまなスタイルが出ています。
通信教育のメリットとしては、何といっても“自宅で自身のスケジュールに合わせて勉強できる点”です。
通学では仕事の都合などで通いきれなくなることもありますが、通信教育にその心配はありません。その上、基本的な学習内容やスケジュールは通信教育側が組み立てるので、受験生は受身でも全科目をバランスよく学習できます。近年では、スマホを利用してスキマ時間に一問一答で勉強できる、メールやチャットで疑問点を質問できるなどのサービスもあります。受講料も、通学する予備校に比べて割安なケースが多くなります。
デメリットとしては、やはり自宅学習であるため、気持ちを切り替えにくく、さぼりがちになる場合もあることです。また、理解できない部分をその場ですぐ講師に質問できないため、学習上の弱点がそのままになりがちという面もあります。
社労士試験は独学でも合格できる?

社労士の資格試験に、もちろん独学で合格するケースもあります。
ただ、現実的に“独学”で合格を目指すには数々の高いハードルがあります。独学のメリットは、費用がかからず、完全に自分のペースで勉強できることですが、一方で効率的な学習カリキュラムやスケジュールを一から自分で立てなければなりません。
そのためには試験に対する知識が必要で、それを調べるだけでも大きな手間がかかり、すでに効率的ではありません。また、自分のペースで勉強できるということは、裏を返せば“好きなだけ怠けられる”ということでもあります。
独学で社労士試験に合格できる知識を習得するには、大量の学習量を的確にこなせるスケジュールと、実行する強い意志が必要です。さらにそれを果たしたとしても、独学では自分の実力や弱点を客観的に把握することが難しく、いざ試験本番で想定外の弱点が判明し、あえなく不合格ということも考えられます。
総じて独学で社労士試験に合格するには、よほどの才能と意思の強さ、そして運が必要となります。
やはり確実に合格を目指すには、予備校の利用が必須といえるでしょう。
まとめ
予備校を利用して社労士試験への合格を目指す場合、通学講座、通信講座とも、それぞれメリット、デメリットがあります。もちろん自分に合ったものを選ぶ必要はありますが、適切なカリキュラムやスケジュールが用意されていると、独学に比べてかなり効率的に学習を進められることは事実です。ただし最終的な合格の決め手になるのは、予備校のメリットを最大限に活かし、積極的に学習を進める自分の意思の強さだということは忘れてはいけません。
クレアールでは、忙しくて時間が取れない方の相談窓口を開設しています。学習状況や1日に取れる学習時間など、ライフスタイルやご経歴に合わせて、社労士合格に向けた学習プランをメールでご返信いたします!講座内容や割引、資格の受験条件などにも、幅広く回答していますので、資格講座受講についての悩みをすっきり解消できます。
その他の記事を読む
-
社労士(社会保険労務士)とはわかりやすく言うとどんな仕事?
-
社労士は年末調整業務ができるか|税理士との比較や業務範囲、給与計算業務も解説
-
社労士試験の合格後に必要な手続きとは?流れや費用、代表的な働き方を解説
-
社労士の事務指定講習とは?受講のメリットやデメリットなどを解説
-
社労士の気になる平均年収とは?勤務形態や年齢・性別の違い、仕事内容も解説
-
社労士試験の難易度はどれくらい?司法書士や行政書士・税理士など人気資格と比較
-
社労士の受験資格はどうすれば得られる?要件や資格取得の注意点を解説
-
社労士の仕事内容とは?年収や資格取得の方法・メリットを解説
-
社労士資格で副業は可能?在宅・土日向けのダブルワークや業務のポイントを解説
-
社労士は就職・転職しやすい?社労士の就職事情と主な就職先を解説







