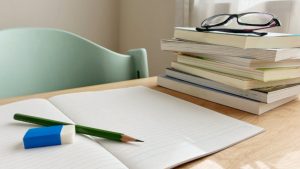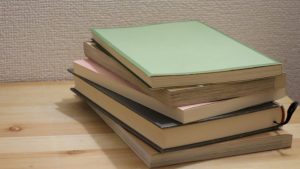社労士試験は、何年もチャレンジする人もいれば、一発合格する人もいます。一発合格するには、綿密なスケジュールと学習法が重要です。この記事では社労士を目指す人に向け、一発合格するための学習法について解説します。効果的な学習のための科目の順番や、年間スケジュールも解説しているので、参考にしてください。
社労士試験に一発合格するのは難しい?
厚生労働省によると、令和7年に行われた第57回社会保険労務士試験の合格率は5.5%です。受験者数43,421人に対して、合格者数は2,376人です。例年の合格率は変動がありますが、6〜7%程度と決して高くありません。何年も受験する人がいる難関試験ですが、しっかりと対策をすれば一発合格も可能です。
社労士試験に一発合格できる理由
難関試験といわれる社労士試験でも、一発合格を狙える理由があります。一発合格できる理由について解説します。
7割で合格できる
社労士試験は7割で合格できるため、満点を狙う必要はありません。第56回(令和6年度)社労士試験の合格基準は、以下のとおりです。
- 選択式試験は総得点40点中25点以上、かつ各科目5点中3点以上(ただし、労働者災害補償保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識は2点以上)である者
- 択一式試験は総得点70点中44点以上、かつ各他科目10点中4点以上(ただし、雇用保険法が3点以上)である者
各科目に基準点がありますが、総得点では7割得点できれば、合格になります。
※参考:第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答
1年間あれば1,000時間の学習時間を確保できる
社労士試験合格に必要な学習時間は800〜1,000時間といわれますが、1年間あれば社会人でも確保できる時間です。1週間に25時間確保できれば、8か月で800時間を達成できます。通勤時間や昼休憩などのすきま時間、休日を活用すれば、不可能な時間ではないでしょう。
社労士試験の合格率が低い理由
社労士試験に1回で合格できる人は少なく、複数回受験している人が多いのが現状です。合格率が低い理由について解説します。
1科目でも基準点に達しないと不合格になる
社労士試験は科目ごとの基準点を突破する必要があり、勉強範囲は膨大です。基準点に達しない科目が1科目あると、1点足りないだけでも不合格になります。また基本的な知識に加え、法改正などの最新情報にも目を配りながら、苦手分野を作らないようにしなければなりません。
科目合格制度がない
社労士試験は、一部合格による科目免除制度がありません。科目免除制度とは、合格基準を上回った科目は次回以降の試験で免除されるもので、税理士試験や中小企業診断士試験などで採用されています。社労士試験では合格基準を上回った科目でも、翌年の受験が必要です。合格するまで全範囲を学び直す必要があり、学習時間の短縮ができません。
準備不足の受験生が多い
働きながら学習時間を確保することは困難であるため、受験者の多くが合格レベルに達しないまま受験しているのも事実です。受験者は、会社員や公務員として日中働いている人が大多数で、平日の学習時間の確保は容易ではありません。合格レベルに達する実力をつけるためには、事前に綿密なスケジュールを立てることが必要です。
社労士試験に一発合格するための学習法
社労士試験の試験日は8月末です。この試験に一発合格するためには、学習法が重要です。ここでは、効果的な学習法について解説します。
受験日までのスケジュールを立てる
仕事や長期休暇を考慮しながら、受験日までの1年間の長期的なスケジュールを立てましょう。平日・休日の1日の学習時間も落とし込み、無理のないスケジュール作成が必要です。強い意志をもって学習を続けることと、1週間・1か月単位で、1日の予定のズレをカバーできるようなスケジュールを組むことも重要です。
数字やキーワードを意識する
社労士試験では、数字やキーワードと言われる、頻出・重要論点が存在します。闇雲に全てを暗記しようとするのではなく、合格点に到達するために効率の良い学習戦略を実践することが重要です。またテキストに記載されているポイントや、講師のアドバイスを素直に受け入れることも大切です。例えば全てを理解しようと深入りするのではなく、暗記と割り切って学習をした方が効率が良い部分もあります。効率的な学習が早期成績アップにつながります。
反復して記憶する
人は記憶したことを時間とともに忘れてしまうため、特に初期段階の学習では忘れることを前提に、躊躇なく前に進むことが重要です。そして記憶を定着させるためには、反復練習が必要です。さらに反復するなかで理解すれば、長期記憶として頭に残りやすくなります。とくに短期で効率的な学習をするには、高確率で出題される頻出問題を反復して学習し、確実に解答できる力をつけましょう。
効率的な学習ができる科目の順番
試験科目は、選択式8科目、択一式7科目で、以下のとおりです。
- 労働基準法及び労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
- 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 社会保険に関する一般常識
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
どの科目から学習しても問題ありませんが、学習効率を考えるなら、労働科目・社会保険科目・一般常識科目の3ジャンルに分けて学習するのがおすすめです。
労働基準法から始める
最初は労働基準法から始めるのがおすすめです。年次有給休暇や休日など、働くうえで身近な法律を扱う科目であるため、取り組みやすさもメリットです。労働基準法はすべての労働科目の基本となる法律で、ほかの科目の学習がスムーズになります。労働基準法を学習したら、労働に関する法律である労働安全衛生法や、労働災害補償保険法に進みましょう。
社会保険科目を学習する
労働科目ジャンルの次は、社会保険科目を学習します。社会保険科目でも基礎から応用の順番に学習できるよう、健康保険法から始めるとスムーズです。健康保険法は国民の健康を守るための制度が定められています。その後に年金について定められた国民年金法を学習し、厚生年金保険法へと進みましょう。厚生年金保険法は、国民年金法とは異なる複雑な制度の理解が必要です。
一般常識科目は最後に取り組む
一般常識科目は、労働科目・社会保険科目の学習終了後に、最後に取り組みます。出題範囲が広いものの、法律に関する学習をひと通り終えてから取り組むと、ほかの科目で学んだ内容が出てくるため理解を深めやすくなります。一般常識科目は、予備校のカリキュラム以外では対策が立てづらいのですが、テレビや新聞で目にする日々の関連ニュースにもアンテナを立てておくことも有効です。
社労士試験の年間スケジュール
正しいスケジュールに沿って学習できれば、一発合格も目指せます。年間スケジュールについて、3つの時期に区切って解説します。予備校では、学習時期に応じた講座提供があり、コース・カリキュラム通りに学習を進めていくことが一発合格の秘訣です。
9〜4月はインプット期
9〜4月はインプット期として、各科目の基本事項を理解し、知識の定着を目指しましょう。クレアールのカリキュラムでは、テキストを読み込んで理解を深め、単元ごとに過去問演習を挟むと効果的です。過去問演習により、社労士試験の問われ方を把握しながら、習熟度を高められます。4月頃までに全科目の学習をひと通り終えることを目指します。
4〜7月はアウトプット期
4〜7月はアウトプット期として、問題演習により、復習もかねて実力向上をはかりましょう。苦手科目や苦手分野の弱点克服も目指します。クレアールでは分野をまたいだ横断学習による知識の整理も重視しています。
7~8月は総まとめ期
7~8月は総まとめ期として、過去問や予想問題集の演習、復習、模試の受験をして最終調整します。直前期に新しいことに手を出してしまい、逆に今までやってきた重要論点が抜けてしまうくらいであれば、むやみに手を出さない方が良いでしょう。模試は他流試合をかねて、数種類受験することも有効です。本番を万全な状態で迎えられるよう、体調や精神面も考慮しましょう。
まとめ
社労士試験は難関試験ではありますが、一発合格も可能です。一発合格を目指すには、目安となる800〜1,000時間の学習時間が確保できるように綿密な年間スケジュールを立て、効率的な学習をすることが必須です。また、独学ではなく講座の利用がおすすめです。
クレアールは、56年の歴史のある資格の学校です。Web通信に特化した社会保険労務士講座講座では、非常識合格法という効率学習法で、有名講師陣が短期間の合格をサポートします。クレアールならではの質問無制限の手厚いフォロー体制も魅力です。
カリスマ講師が執筆した、一発合格のための書籍を先着100名にプレゼントしているので、ぜひご活用ください。
クレアールでは、忙しくて時間が取れない方の相談窓口を開設しています。学習状況や1日に取れる学習時間など、ライフスタイルやご経歴に合わせて、社労士合格に向けた学習プランをメールでご返信いたします!講座内容や割引、資格の受験条件などにも、幅広く回答していますので、資格講座受講についての悩みをすっきり解消できます。
その他の記事を読む
-
社労士は独学で合格できるのか|独学のメリットや効果的な学習法を解説
-
社労士試験には過去問が必須|過去問の活用方法や注意点を解説
-
社労士になるための勉強時間はどれくらい?必要時間を人気資格と比較
-
社労士試験合格を目指す勉強方法を紹介|スケジュールや独学のコツも解説
-
社労士試験の本番での時間配分や解く順番は?最短で合格できる学習のコツも解説
-
社労士の試験内容を把握しよう|問題数や配点、試験時間、科目や合格基準まで解説
-
社労士通信講座の選び方と注意点|オンラインで学ぶメリットも解説
-
社労士試験におすすめのテキスト|種類や特徴、選び方、活用の流れも解説
-
2025年度の社労士試験|試験のスケジュールや申し込み方法、手続きも解説
-
社労士の予備校を利用する意義と選び方|通学と通信との違いやメリット・デメリットも解説