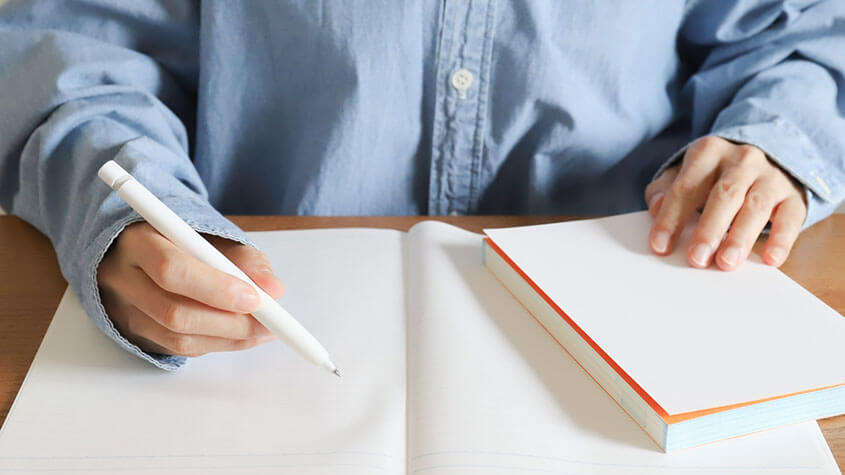2019年度の社会保険労務士資格試験について、基本事項を解説します。試験日程から、学歴・実務経験などによる受験資格、試験問題の形式や制限時間・試験科目、また経験により一部科目が免除される条件など、ここですべてわかります。
社労士(社会保険労務士)試験の内容について

社労士(社会保険労務士)資格試験は、選択式と択一式のふたつになっています。
選択式とは一問の文章に空欄部分が5つあり、20個の選択肢から適切な語句の番号を書き込む、いわゆる“穴埋め問題”です。
択一式は一問ごとに5つの文章の選択肢があり、適切なものをひとつ選ぶ形式です。試験は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働保険・労務管理・社会保険があり、それぞれ選択式と択一式での得点配分が異なります。
選択式は60分で8問解いて満点が40点。70問を解いて満点が70点という試験になります。また、それぞれに基準点があるため、総合的な知識が必要です。資格取得には平均して7割程度正解する必要があるとされています。
社労士(社会保険労務士)試験の受験資格

社会保険労務士(社労士)試験の受験資格は、学歴、実務経験、国家試験合格の3種類です。
学歴では、以下に該当する人が対象となります。
- 大学、短大、専門職大学、専門職短大か高等専門学校(4年生)を卒業か、専門職大学の前期課程修了。
- また、上記から短大を除き、学位取得に必要な一般教養科目、また卒業認定単位62単位以上を修得。
- 旧制高校高等科、大学予科、専門学校を卒業、修了。
- その他、厚生労働大臣が認める学校を卒業、所定課程の修了。
- 修業年限2年以上で授業時間数1700時間(62単位)以上の専修学校の修了。
実務経験では、以下に該当する人が対象となります。
- 法令に基づく法人の役員(非常勤除く)また従業員として同法令の実施事務。
- 国や地方公共団体の公務員として行政事務。
- 特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社に従事。
- 社労士、弁護士か同法人の業務補佐。
- 労働組合役員として労組業務に専従、また役員として労務に従事。
- 労働組合の職員、また法人や事業を営む個人の従業員として労働社会保険諸法令の事務(単純事務は除く)に従事。
- 上記に3年以上従事した人。
その他試験、資格では、以下に該当する人が対象となります。
- 厚生労働大臣が認めた国家試験。
- 司法試験予備試験、旧司法試験、高等試験予備試験。
- 行政書士の資格。
これらに該当する人に受験資格があります。
社労士(社会保険労務士)試験の日程(2019年度)

社労士の資格試験は、例年、8月の最終日曜日に行われます。
2019年度(平成31年・令和元年)の社労士試験の詳細は、同年の4月12日に公示されました。
本年度の社労士試験は、8月25日(日)に行われます。ちなみに2018年度の試験日程は8月26日(日)でした。なお、公示されたのは新元号「令和」が発表される前であるため、公式の年度表記は主に「平成31年」になっています。
会場での着席時間は午前が10:00、午後が12:50で、その時間から試験の説明があるため、席に着いている必要があります。
試験結果の発表は同年の11月8日(金)になります。なお試験会場は、東京都、北海道、埼玉県、大阪府、香川県、岡山県、熊本県、沖縄県など、全国19の主要都道府県で行われます。
なお受験申込書の受付期間は、4月15日(月)から5月31日(日)までになります。試験センター窓口への申し込みは17:30まで。また郵送の場合は消印までが受け付け対象になります。
ただし、書類に不備があると受付できませんので、余裕を見て早めに申し込んでおくほうがいいでしょう。
社労士(社会保険労務士)試験科目が免除されるケースがある?

社労士試験には、実務経験などがある場合、一部試験科目の免除を受けることができます。免除項目は以下となっています。
- 国か地方公務員として、労働社会保険法令の施行事務に10年以上従事。
- 厚生労働大臣指定の役員か従業員として、労働社会保険法令事務に15年以上従事。
- 社労士か社労士法人の補助として労働社会保険法令事務に15年以上従事、かつ全国社労士会連合会による免除指定講習を修了。
- 日本年金機構の役員か従業員として、社会保険諸法令の実務に15年以上従事。
- 全国健康保険協会の役員か従業員として、社会保険諸法令の実務に15年以上従事。
これらに該当する人は、受験申込みの際に資格を証明する書類を提出し、認められれば該当科目の試験が免除されます。この免除は一度認められれば生涯有効になります。
まとめ
社労士の資格試験には、さまざまな受験資格があり、多くの人に門戸を開いています。ただ、実務経験による受験資格や一部科目の免除については、申請しても厳密な条件から認められない場合があります。また書類の不備により、申込みが受け付けられず、再提出が必要になることもあります。受験を考えている人は、受付期間に余裕を持って申込みを行うことをおすすめします。
クレアールでは、忙しくて時間が取れない方の相談窓口を開設しています。学習状況や1日に取れる学習時間など、ライフスタイルやご経歴に合わせて、社労士合格に向けた学習プランをメールでご返信いたします!講座内容や割引、資格の受験条件などにも、幅広く回答していますので、資格講座受講についての悩みをすっきり解消できます。
その他の記事を読む
-
社労士(社会保険労務士)とはわかりやすく言うとどんな仕事?
-
社労士は年末調整業務ができるか|税理士との比較や業務範囲、給与計算業務も解説
-
社労士試験の合格後に必要な手続きとは?流れや費用、代表的な働き方を解説
-
社労士の事務指定講習とは?受講のメリットやデメリットなどを解説
-
社労士の気になる平均年収とは?勤務形態や年齢・性別の違い、仕事内容も解説
-
社労士試験の難易度はどれくらい?司法書士や行政書士・税理士など人気資格と比較
-
社労士の受験資格はどうすれば得られる?要件や資格取得の注意点を解説
-
社労士の仕事内容とは?年収や資格取得の方法・メリットを解説
-
社労士資格で副業は可能?在宅・土日向けのダブルワークや業務のポイントを解説
-
社労士は就職・転職しやすい?社労士の就職事情と主な就職先を解説