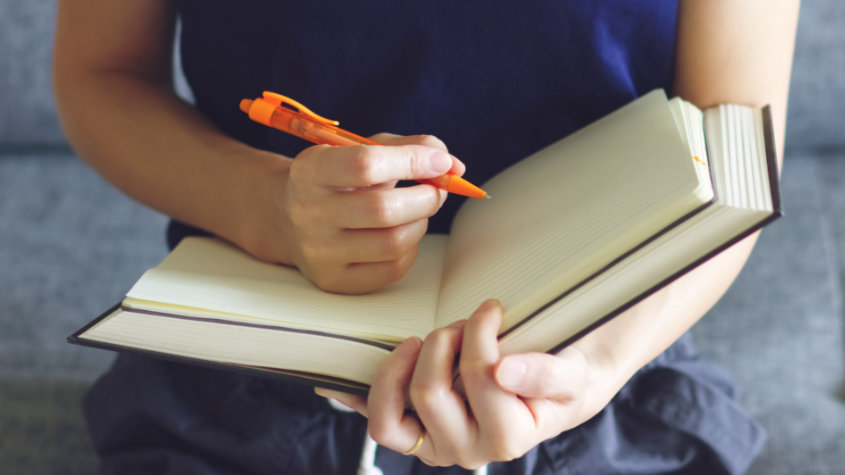社労士の受験者のなかには、独学で合格を目指したい人も多くいます。しかし、独学の場合は学習スケジュールに悩むことも多くあるようです。この記事では、社労士を独学で目指すためのスケジュールについて解説します。社労士を独学で目指す際のポイントや教材の選び方についても解説するため、参考にしてください。
社労士を独学で目指す際はスケジュール立案が大切
社労士を独学で目指す際には、試験日に向けて土台となる学習スケジュールを立てることが大切です。社労士の試験範囲は非常に広いため、学習スケジュールを立てないと、試験に間に合わない恐れがあります。ある程度スケジュール通りに学習することが、社労士合格に近づくためのポイントです。
余裕をもったスケジュールがおすすめの理由
社労士を独学で目指す際の学習スケジュールは、余裕を持って立てましょう。社労士の試験は毎年8月にあり、前年の9月から学習を始める人が多くいます。学習期間が1年あり、スケジュール通りに学習が進められると、社労士の合格を目指すにも無理がありません。
社労士合格までに必要な学習時間
社労士に合格するには、約800~1,000時間の学習時間が必要といわれています。社労士の試験範囲は広いため、しっかりと学習をして合格レベルまで力をつけるには、十分な学習時間を確保する必要があります。
社労士を独学する際のポイント
社労士を独学で目指す際には、ポイントがあります。以下で、4つのポイントについて解説します。
綿密な計画を立て実行する
社労士を独学で合格するには、学習スケジュールを綿密に立てることが欠かせません。社労士合格に最低限必要な約800〜1,000時間の学習時間を確保するために、いつから学習し始めるのか、1日何時間学習するのかなども決めましょう。計画的に学習しないと、試験日までに試験対策が間に合わない恐れもあるため、注意してください。
基礎から応用の順番に学習する
社労士を学習する際には、基本事項を理解してから、応用力強化へ取り組みましょう。科目で言うと、社労士の試験は、法律同士に関連性のあるものが多くあります。例えば、労働基準法は全ての労働科目の基礎です。基礎科目を理解せずに応用科目を学習しようとすると、理解できずに挫折する恐れもあります。また、法律には制度趣旨と呼ばれる法律が出来た背景があり、この背景を基礎として理解しておくと、その後の学習が効率的に進みます。
テキストをおろそかにしない
社労士の独学では、過去問だけでなくテキストも重視してください。社労士試験合格のためには、一部の難問・奇問より基本を確実にすることが近道になります。問題演習の前後に、テキストをしっかり読むと試験に出題される傾向を理解でき、基礎を固められます。その後、テキスト読みと問題演習を繰り返すことで、知識が定着するといえるでしょう。
バランスよく学習する
社労士を独学するには、バランスよく学習することが大切です。社労士試験は、選択式・記述式の出題形式ごとと、科目ごとに合格基準点があります。たとえ得意科目で高得点が取れて総合点を上げても、苦手科目が合格基準点に満たしていないと合格できません。そのため、苦手科目が作れない試験といわれています。
社労士の独学で効果的な科目の順番
社労士試験は科目数が多く、試験範囲が広いため、「記憶の試験」とも呼ばれています。試験で合格するには、学習する科目の順番が重要です。学習するジャンルは、労働科目・社会保険科目・一般知識科目の3つに分けることをおすすめします。実際に学習する順番は、以下の通りです。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労災保険法
- 雇用保険法
- 労働保険徴収法
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 労働に関する一般知識
- 社会保険に関する一般常識
社労士を独学する年間スケジュールについては4期に分けて、次から解説します。
【社労士の独学の年間スケジュール】準備・基礎固め
社労士試験は、毎年8月に実施されます。社労士試験に向けて独学で学習時間を確保するには、少なくとも前年9月頃から余裕を持った準備をしてください。まず始めに教材を選びます。教材が決まったら、各科目の概要に目を通しましょう。試験範囲の全体像を掴むことで、これからの勉強のイメージがわいてくるかと思います。
【社労士の独学の年間スケジュール】インプット期
準備が整ったら、社労士試験の前年9月から翌年4月まではインプット期として、各科目の基本事項を理解して知識を定着していきましょう。インプット期に学習する内容については、以下で解説していきます。
労働基準法と労働安全衛生法
まずは、社労士試験の全ての基礎となる労働基準法を学習しましょう。労働基準法は受験生にとって馴染みある科目ですが、出題内容は年々難しくなっています。規定の内容を正確に理解して記憶し、頻出項目を意識してください。労働安全衛生法は、理解ではなく暗記をメインとした学習がおすすめです。
労働者災害補償保険法と雇用保険法
労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)は過去問を基本に特に頻出論点を学習しましょう。労災保険法は難易度が安定しており、法改正事項が少なく、試験対策がしやすい科目といわれています。雇用保険法は労災保険法と比較しながら要点を押さえると良いでしょう。
健康保険法と国民年金法
健康保険法の出題内容は、基本事項が多く得点を稼ぎやすい科目のため、しっかり満遍なく学習しましょう。また、計算問題では数字の暗記や過去問対策も重要です。国民年金法は制度が複雑であり、理解と暗記を使い分けながら学習しましょう。
徴収法と労務管理など労働に関する一般常識
労働保険徴収法(以下、徴収法)は数字が多いため、過去問を解いて計算問題に慣れることがポイントです。学習範囲に対して配点が多く、点数を稼ぎやすい科目です。労働に関する一般常識(以下、労一)は、試験の中で非常に難しい科目といわれています。基本を押さえつつ、深入りしないこともポイントです。
厚生年金保険法と社会保険に関する一般常識
厚生年金保険法は、国民年金法との違いを意識しましょう。厚生年金保険法は頻繁に法改正が行われています。法改正の背景を理解しつつ、問題演習を進めてください。社会保険に関する一般常識(以下、社一)は、社会保障と法令があります。法令は労一よりは得点を取りやすい科目ですが、社会保障は対策が難しいため、広く浅く学習をして合格基準点を目指しましょう。
【社労士の独学の年間スケジュール】アウトプット期
社労士試験が実施される年の4月から7月はアウトプット期として、問題演習を解き応用力を身につけて、さらに復習をしましょう。アウトプット期では、実力向上と弱点の克服を目指します。
苦手科目の復習
独学でも、予備校を使っても、最初の方に勉強したことは必ず忘れていきます。また、テキストを1度学習しただけでは理解できないことも多いため、繰り返し学習が必要です。問題演習とテキスト読みを地道に繰り返し、記憶の定着を図りましょう。
頻出・重要論点を押さえる
基本知識がなんとなく頭に入ったら、試験でよく問われる頻出・重要論点を意識して徹底的に学習することが重要です。重要度の低い科目や領域を広くカバーすることより、よく問われるポイントを確実に押さえる方が合格に近づきます。
【社労士の独学の年間スケジュール】総まとめ期
社労士試験が実施される約2か月前の7月から8月は、総まとめ期として最終確認をしてください。この時期は、過去問や予想問題集の演習、復習、模試の受験などを中心に行いましょう。
総まとめ期では、繰り返し復習して記憶を定着させたり、理解と暗記を使い分け割り切って暗記をしたりします。また、科目を横断して問われる数字やキーワードを横断的に整理して覚えるなどもおすすめです。むやみに新しいことへ手を出さずに、体調や精神面にも気をつけましょう。
社労士の教材の選び方
独学で社労士の合格を目指すには、どのように教材を選べばよいのでしょうか。以下で教材を選ぶ3つのポイントを解説します。
問題演習がある
問題演習のあるテキストや、問題と解説が対になった問題集がおすすめです。テキストに問題演習があると、テキストを読んだ直後から問題に取り組めて理解が深まりやすくなります。問題と解説が対になった問題集は、照らし合わせるのに手間がかかりません。
教材が見やすい
独学の場合は、講義による解説がないため、図や表、イラストが多い教材を選ぶと良いでしょう。社労士試験は法律用語が多く、文字だけの教材一つで学習を続けるのはモチベーションが下がる可能性があります。ただし、カラフルすぎると重要な部分に意識が行きづらかったり、重要なポイントに対する注意が散漫になったりするデメリットもあるため注意しましょう。
シリーズ展開されている
テキストや問題集、過去問などがシリーズで展開されているものは、社労士を独学で目指す場合におすすめです。シリーズ展開された教材は、問題の解説やテキストがリンクしているものが多く、効率的に学習ができます。
まとめ
独学で社労士を目指す場合は、スケジュールを立て、スケジュールに沿ってコツコツと学習することが大切です。独学は自己流の学習法になる恐れもあります。スケジュールを立てることが苦手な場合には、通信教育の対策講座がおすすめです。
クレアールは56年の歴史があり、非常識合格法という効率学習法が特徴です。社会保険労務士講座では、有名講師陣による短期合格に特化した講義、質問無制限のサポート体制や2年学習のセーフティコースもあります。カリスマ講師が執筆した合格法の書籍を無料でプレゼントしていますので、興味がある人はお申し込みください。
クレアールでは、忙しくて時間が取れない方の相談窓口を開設しています。学習状況や1日に取れる学習時間など、ライフスタイルやご経歴に合わせて、社労士合格に向けた学習プランをメールでご返信いたします!講座内容や割引、資格の受験条件などにも、幅広く回答していますので、資格講座受講についての悩みをすっきり解消できます。
その他の記事を読む
-
社労士は独学で合格できるのか|独学のメリットや効果的な学習法を解説
-
社労士試験には過去問が必須|過去問の活用方法や注意点を解説
-
社労士になるための勉強時間はどれくらい?必要時間を人気資格と比較
-
社労士試験合格を目指す勉強方法を紹介|スケジュールや独学のコツも解説
-
社労士試験の本番での時間配分や解く順番は?最短で合格できる学習のコツも解説
-
社労士の試験内容を把握しよう|問題数や配点、試験時間、科目や合格基準まで解説
-
社労士通信講座の選び方と注意点|オンラインで学ぶメリットも解説
-
社労士試験におすすめのテキスト|種類や特徴、選び方、活用の流れも解説
-
2025年度の社労士試験|試験のスケジュールや申し込み方法、手続きも解説
-
社労士の予備校を利用する意義と選び方|通学と通信との違いやメリット・デメリットも解説