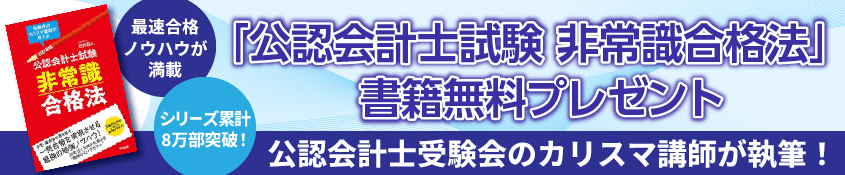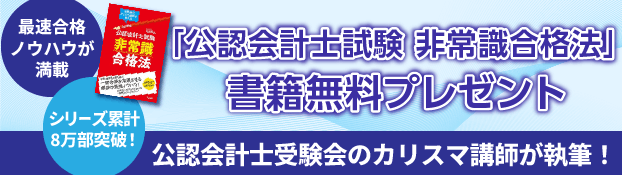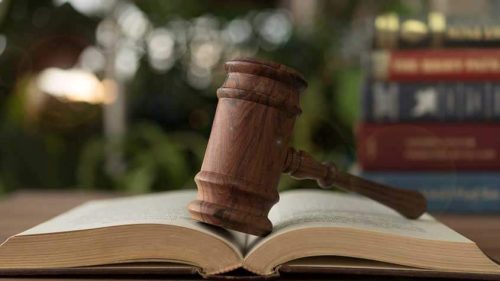独立した公認会計士はどのような業務を行うのでしょうか。そもそも独立は難しいのか、事前に準備すべきはあるのかなどが気になる人も多いでしょう。この記事では、公認会計士の独立の難易度、独立後の仕事内容や収入、独立のメリットやデメリット、そして開業準備の内容や独立の失敗を防ぐ方法まで、詳しく解説します。
公認会計士の独立は難しい?
公認会計士として独立することを検討する人は多くいます。独立というと大変なイメージがありますが、公認会計士にはさまざまな働き方と活躍の場があるため、幅広い業務経験や自分の得意分野を持つことができれば独立して活躍することは難しくありません。まずはキャリアプランを明確にし、独立のメリットやデメリットをしっかりと把握したうえで準備を進めていくことが大切です。
公認会計士の独立後の主な仕事内容

公認会計士の独立後の仕事は、どんな職場で働くかによってさまざまです。ここでは、主な仕事内容や活躍の場について、パターン別に解説します。
税理士事務所
公認会計士が独立する際は、税理士資格を取得して税理士事務所を開業するという選択肢があります。税理士事務所での主な仕事内容は、税務代理や各種税務書類の作成、税務相談や助言といった税務業務です。事務所によっては、これに加えて記帳代行などの周辺業務を幅広く行うところもあります。税務業務を通じて法人顧客から毎月の顧問料を受領できれば安定的な収入を得られますが、そのためには公認会計士試験で求められる以上の税務知識が求められます。
コンサルティング
コンサルティング業務は、経営戦略の立案から組織再編、システムコンサルティングなど、経営全般にわたる相談・助言を指します。税務業務や監査業務のように定期的な需要があるものではなく、単発での受注が一般的なため、税理士事務所を経営しながらコンサルティングも行う公認会計士が多い傾向にあります。
学校・セミナー講師
多くはありませんが、独立後に資格スクールの講師や、大学等の会計関連科目の講師になる公認会計士も一定数います。中には、企業や一般の人向けのセミナー講師としての依頼を受注するケースも。人にものを教えるのが好きな人や、わかりやすく丁寧に伝えることが得意な人は能力を発揮できるでしょう。講義を通じて人間関係が広がるため、人脈の構築にも役立つでしょう。
監査法人の非常勤
監査法人の非常勤職員では、常勤職員と同じようにクライアントの監査業務を行います。アルバイトよりも時給が高く、長時間労働にもなりにくいため、比較的、働き方の自由度が高いでしょう。ただし、監査業務の閑散期や、繁忙期であっても常勤の公認会計士が足りている場合は非常勤に頼る必要はないため、継続して契約できる保証がない点に注意が必要です。
公認会計士の独立後の収入
公認会計士の独立後の収入はどれぐらいの水準になるのでしょうか。ここでは、雇用されている公認会計士と独立している公認会計士とで比較して解説します。
【雇用されている場合の収入】
| 企業規模 | 平均年収 |
|---|---|
| 10~99人 | 約7,057,000円 |
| 100~999 | 約7,176,000円 |
| 1000人以上 | 約9,220,000円 |
| 合計 | 約7,466,400円 |
(参考 厚生労働省「令和5年賃金構造統計調査」をもとに自社で作成)
公認会計士が雇用されている場合、すなわち事業会社や監査法人などに勤務している場合の平均年収は約746万円です。ただし実際は、勤務する企業規模によってばらつきがあり、10人~99人の企業では平均年収が約705.7万円であるのに対し、1000人以上の企業では約922万円と、大きく異なります。
【独立した場合の収入】
| 1000万円~3000万円程度 |
独立後の公認会計士の平均年収は1000万円~3000万円程度で、企業に雇用されている公認会計士よりも高くなる傾向があります。監査法人の非常勤職員の場合、日給5万円ほど受け取っている場合もあり、効率的に稼ぐことで高収入を得ることができます。ただし働き方次第で年収は大きく変動するため、一概に年収が上がるとは言えないことに留意が必要です。
独立後の収入が上がる理由
| ・自分で案件の内容 ・数を選べる ・案件の単価を上げることができる ・非常勤として働いている |
公認会計士の収入が独立後に上がる理由の第一は、自分で案件の内容や件数を決定できるためです。もちろん相応の知識や経験は必要ですが、高い単価の案件を選んで取り組むことで、効率的に年収を上昇させることができます。実績を積んで信頼を得られれば、一依頼あたりの単価を上げることもできるでしょう。
また、監査法人などで非常勤職員として働く場合も同様に、高い時給で継続的に受注することができれば、そこで雇用されて働く場合よりも高収入につながることがあります。
公認会計士の独立に向いている人
公認会計士の中でも一体どんな人が独立に向いているのでしょうか。3つのポイントで解説します。
| ・積極的 ・自発的に行動できる ・コミュニケーション能力が高い ・柔軟な対応ができる |
公認会計士で独立に向いているのは、積極的・自発的に行動できる人、コミュニケーション能力が高い人、そして柔軟な対応ができる人です。継続して案件を獲得するためには、自分から行動する積極性や、人脈を作るコミュニケーション能力と営業力などが求められます。また、さまざまなクライアントと仕事をするための柔軟な対応力も必要でしょう。
一方で、決められた仕事をしっかりとこなしたい、組織で協力して働きたいという人は、組織勤務のほうが向いています。
公認会計士が独立するメリット・デメリット
公認会計士の独立は、必ずしもいいことばかりではありません。メリット・デメリットの両方を踏まえたうえで独立を検討する必要があります。それぞれ見ていきましょう。
| メリット | ・自分で仕事 ・働き方を選べる ・さまざまな分野にチャレンジできる ・高収入を狙える |
|---|---|
| デメリット | ・大きな案件の受注は難しい ・すべての責任を背負う必要がある ・不安定な収入 ・失敗のリスクがある |
公認会計士が独立するメリット
公認会計士が独立するメリットには、まず自分で仕事や働き方を選べることがあります。状況によっては、自分にとって難しい仕事は無理に引き受けず、得意な仕事に集中することも可能です。幅広い分野の依頼を受けることで、業務の幅を広げていくのもよいでしょう。
また、上司もいないので、勤務時間や勤務場所も自分で決定して管理できます。働き方、依頼の受け方次第で、高収入を狙えることも大きなメリットでしょう。
公認会計士が独立するデメリット
独立して個人事務所の所属になると、企業や監査法人への勤務時に経験できたような大きな案件の受注は難しくなります。さらに、依存できる組織がなくなるため、成功したときはもちろん、失敗したときもすべての責任を自分ひとりで背負わなくてはなりません。その結果、収入が不安定になったり、ライフワークバランスが崩れたりと、独立が失敗に終わるリスクも十分にあります。
公認会計士として独立すべきタイミングは?
公認会計士の独立のタイミングとしては、就職しさまざまな経験を積んでから独立する場合と、資格取得後すぐに独立する場合があります。それぞれのメリット・デメリットをまとめた表は以下の通りです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 経験を積んでから独立 | ・実務経験があるので専門性をもって仕事できる ・培ってきた人脈から業務を獲得しやすい | ・経験実務の幅が狭い場合、業務獲得に苦労することがある ・年齢的に失敗が許されない場合も多い |
| 資格登録後すぐ独立 | ・若さゆえに体力がある・失敗してもやり直しがきく ・独立する若手の公認会計士は少数派なので、差別化を図れる | ・実務経験不足により業務の遂行に苦労することがある ・人脈の不足により業務の獲得に苦労することがある |
監査法人や企業に勤務して経験を積んでから独立する場合、実務経験や専門性そして人脈がすでにあることがメリットですが、年齢的に失敗ができないといったデメリットもあります。
他方、資格取得後にすぐ独立する場合、年齢が若ければ体力がある等のメリットはありますが、経験不足や人脈不足により苦労するケースも多いです。
公認会計士が独立開業するうえで準備すべきこと
公認会計士が独立する場合は慎重に準備を進めることが必要です。ここでは、公認会計士が独立開業するうえで準備すべきことを解説します。
契約関連の手続きを行う
独立を考え始めたら、事前にさまざまな契約関連の手続きをしておく必要があります。
税理士登録は申請から登録まで数か月かかることもあるため、計画的に行いましょう。また独立後は、一定の収入が見込めていた会社員時代に比べて、クレジットカードなどの審査に通りにくくなることがあります。独立後に使用するカードの申し込みなどは退職前に手続を進めておくとスムーズでしょう。
受注経路を決める
独立開業を考え始めたら、まず考えたいのが仕事の受注経路です。会社員時代と異なり、独立後はすべての仕事を自分で取ってくる必要があります。最初はこれまでの人脈経由で仕事を請け負うケースが多くなりますが、それだけでは継続的な受注は難しい可能性が高いです。Webサイトを作成して露出を増やしたり、監査業務のアルバイトを通して人脈を広げたりしながら、受注経路を増やしていきましょう。
単価を決める
仕事の受注経路と並んで、その単価を決めておくことも重要です。独立後は報酬が収入に直結するため、この単価設定が年収に大きく関わってきます。
公認会計士としての業務は基本的に何かしらの経費がかかるものではないため、時間単価で考えると決めやすいでしょう。会社員時代の収入から当時の自分の時給を計算し、それと比較して収入が上がるような単価設定にすることが大切です。
公認会計士の独立に失敗しないためのポイント

公認会計士としての独立開業に際し、誰しも失敗は避けたいものです。ここでは、公認会計士の独立に失敗しないための4つのポイントを解説します。
進みたい方向性を明確にする
まずは独立後どのような業務や働き方をしたいのか、自分の進みたい方向性を明確にすることが重要です。具体的には、興味のある分野や得意な分野を見つけ、そのために何を習得すべきかを検討しておくとよいでしょう。例えばM&Aアドバイザリーに興味があれば、監査法人等に所属している頃から実務経験を積み、勉強するといった準備が必要です。
監査業務以外の得意分野を身につける
独立後、他の公認会計士との差別化を図るためにも、監査以外の得意分野を身に着けておくことが重要です。しかし、公認会計士資格の取得後の主な就職先である監査法人では監査以外の業務を行うチャンスは少なく、なかなか経験を積めないという現実があります。監査法人にいても監査以外の業務を経験できるチャンスを逃さず、そのために自分から行動する姿勢が大切です。
人脈を広げる
独立後は仕事を自分で見つける必要があるため、クライアントはもちろん、受注にあたって協力してくれる人の存在が非常に大切になってきます。業界の内外を問わず研修会や懇親会などに積極的に参加したり、公認会計士や税理士など同業の知り合いを増やしたりすることを心がけ、信頼関係を築くことを意識しましょう。
資金・事業計画を綿密に準備する
独立して自分の事務所を持つということは、経営者になることを意味します。このため独立に際して資金の準備は非常に重要です。自己資金だけでなく、融資を活用する方法もあるので、どれがベストかよく考えて準備を進めましょう。また今後のキャリアプランとともに、収支についても慎重に計画していく必要があります。
公認会計士は能力と努力次第で独立のメリットを享受できる
公認会計士の独立は決して難しいことではありませんが、向き不向きがあり、適切な準備と努力を怠れば失敗のリスクもあります。一方で、進みたい方向を明確にし、入念な準備のもとベストなタイミングで独立すれば、より自由な働き方でより高い収入を見込めるはずです。人脈や資金などの準備を行いながら、知識と経験を積み、独立後も求められる公認会計士を目指しましょう。
クレアール公認会計士講座では独自の「非常識合格法」を採用しています。重要な論点にポイントを絞って学習するため、効率良く、しかし質を落とすことのない学習で合格を目指すことができます。将来の独立を目指し、短期合格して早くキャリアアップしたい人には最適の学習法です。「非常識合格法」に興味のある方は、書籍プレゼントに応募してみてください。

監修:公認会計士 森 大地
大学在学中に公認会計士の勉強をはじめ、公認会計士論文式試験に一発合格。現在は、クレアールの公式YouTubeチャンネル「公認会計士対策ワンポイントアドバイス」にて、監査法人での仕事や試験対策の学習法などを紹介している。