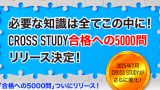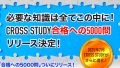皆さんこんにちは。クレアール司法書士講座受験対策室のR.Nです。
8月12日、令和7年度司法書士試験の基準点が法務省ホームページにて発表されました。
今回の基準点は午前の部が26問(78点)、午後の部が24問(72点)と、令和6年度の択一式基準点と全く同じ結果となりました。
個人的な意見ですが、午前の部は、民法の担保物権・債権総論分野、刑法で例年よりもやや細かい知識や初出の論点が問われたこともあり、似たような傾向にあった昨年と同水準となったと思われます。
また午後の部は、特に商業登記法について、本試験会場で冷静に正解の組み合わせを導き出すのが難しい問題が多かったものの、不動産登記法及びマイナー科目について基本的な出題が多く、やはり昨年と同水準に落ち着いた印象です。
※午後の部の第33問については、「解なし」であったため、全員正答扱いとして採点するとの発表がありました。
今回は、8月中旬の基準点発表~10月初旬の筆記試験合格発表の時期にどのような過ごし方をするのがお勧めか、ご参考となるような記事を書いていけたらと思います。
午前の部・午後の部の択一式でどちらか一方でも基準点に達しなかった方
午前の部・午後の部の択一式で、どちらか一方でも基準点に達しなかった方は、今すぐに択一式の学習にとりかかりましょう。
7月6日に本試験が終わり、7月・8月と例年以上の厳しい暑さが続いていますので、なかなか「勉強を再開しよう」という気持ちになれないのも無理はないと思います。
ですが、この時期から択一式の学習を本格的に再開しないと、筆記試験の合格発表(10月2日)後に本格的な学習を開始する方が多いと予想される、今年合格推定であったけれど惜しくも及ばなかった方(令和8年度で合格される蓋然性が高い実力者)との差を埋めることが、非常に難しくなってしまいます。
択一式で基準点に到達していない方は、がむしゃらに問題演習のみの学習を行うのではなく、講義をしっかりと受講してください。そして、基本テキストや択一六法等のインプット教材を活用し、基礎的な知識を再確認し、抜け漏れや苦手分野が何であったかを1つ1つ丁寧に把握していってください。
問題演習のみの学習は、達成感が得られやすいかもしれませんが、例えばCROSS STUDYの正答率を上げたいがためにその問題の解答だけを覚えてしまったり、過去問のみの学習では出題が偏っていて、分野によっては必要十分な量の基本事項を押さえることができなかったりと、弊害も大きいです。
基礎知識の理解と記憶が曖昧な場合、過去問と異なる表現で問われたときに、知っている知識であっても試験会場でピンと来ずに、正解できないケースが多いと思われます。「講義だけ聴く、あるいは問題演習だけをやって勉強した気になり、基本知識が身に付いていると思い込んでいる状態」が最も危険です。
まだまだ来年の試験まで時間はありますので、1つ1つの知識の積み上げを大切に、結論を覚える際に可能なら簡単な理由付けを確認しながら、丁寧に講義を受講するところから学習再開しましょう。
なお、講義を受け直す際には、日頃から「この1回でなるべく全部覚えてしまおう」という気概で臨むことが大切です。もちろんそのようなことは不可能ですが、講義を漫然と聞き流してしまうと、勉強した気になるだけで、いつまで経っても知識が定着しません。
ですので、たとえ苦手科目の苦手分野の講義であったとしても、「その1回で頭に叩き込むつもり」で視聴していただくことをおすすめします。 そして、10月2日の筆記試験の合格発表までは、基本的に民法・不動産登記法・商法(会社法)・商業登記法の基本4法を中心に、択一式の学習に力を入れていただきたいと考えております。
なお、どうしても記述式の学習から離れることが不安であるという方は、登記法の択一式の学習の合間に、合格書式マニュアルや合格書式マニュアル対応問題集を用いて、最低限のひな形を忘れないように随時記憶喚起するのがよろしいかと考えます。
付け加えて言うと、記述式の配点が2倍になったこともあり、ひな形暗記以外に問題演習も行いたいという方は、本番と同程度の長文問題を解く必要はまだ無いと考えておりますが、ハイパートレーニングの短めの問題等を時折演習するとよいかと思います。
択一式の基準点は午前・午後ともに超えたものの上乗せ点が足りず、総合点が厳しい方
司法書士試験に合格するためには、択一式・記述式の各基準点の合計にプラスして、択一式問題で換算して30点(10問)程度(※)の更なる上乗せ点が必要であり、このハードルの高さが、司法書士試験を難関資格試験たらしめている所以です。
(※)令和6年度は、記述式の基準点が140点満点中83点(約60%)と高かったのもあり、択一式問題だけで上乗せ点をカバーするためには、基準点+12問(34点)もの正解が必要でした。
午前の部・午後の部ともに択一式の基準点を超えた方は、司法書士試験の全科目・全範囲を一通り学習し終え、繰り返し演習し、基本的な知識をある程度網羅的に習得済みであると考えられます。
そのような方に、次に意識して頂きたいのは、「確実に合格するために、午前・午後ともに30問、つまり合計で60問以上の択一式問題を正解すること」を目標として、得点プランを考える必要があるということです。
そこで、30問に達するために、
① 午前の部・午後の部それぞれについて、どの科目であと何問正解する必要があるか
② スクールの分析で正答率50%以上であったが間違えてしまった問題について、特定の科目や分野に偏りがあるか
を、よく振り返ってください。
特に②について、よほどの苦手分野で完全に捨てていた(※このような姿勢は司法書士試験においては絶対に取らないでいただきたいですが…)という理由でもない限り、過半数の受験生が正解しているの問題を間違ってしまうことには、どなたにも多少の悔しさがあると思います。
なぜその問題を間違えてしまったか…以下のどのパターンに当てはまるか分析してください。
・問題文の読み間違い(ケアレスミス)なのか?
・他の知識との勘違い(知識が増えてきたが故の混同)なのか?
・全く知らない知識だった場合は、間違えてもやむを得ない(他の受験生も解けない)難問だったのか?
・他の肢の方がどうしても正解に見えてしまった理由は何か?
★本試験でのミスは、日頃の演習や直前期の答練・模試のミスよりも、本番の緊張した状態でのサンプルとして非常に有効です。
この分析を通じて自分のミスの傾向を把握し、日頃の学習でどのように注意力を高めるべきか、自律していただきたいです。そして、基本4法の苦手科目・苦手分野の知識(本試験で直接問われた事項のみならず、併せて押さえておくべき事項も含む)を入れ直すことから、可能な限り早めに学習を再開すると良いと考えます。
択一式の基準点は午前・午後ともに大幅に超えたものの、記述式で失敗してしまった方
ここで言う「択一式の基準点は午前・午後ともに大幅に超えた方」の目安としましては、いわゆる上乗せ点も取れている見込みがある方、すなわち択一式問題を60問程度以上取れている方を指します。
択一式で60問程度取れているにも関わらず、記述式の基準点が未達である可能性が高い方は、総合点は超えているにも関わらず記述式で基準点落ちしてしまう可能性があり、悔しくて夜も眠れないと思います。
令和7年度は、記述式の配点が2倍になってから2回目の試験となりますが、令和6年度の試験結果によると、記述式の基準点は140点満点中83点(約60%)に設定されていました。令和5年度以前は記述式基準点が5割前後の年が多かったため、「記述式で失敗してしまうと合格が遠のく」と、従来以上に感じてしまうと思います。
今は色々なスクールで、記述式の採点に関する分析等が公表されていますが、採点方法については毎年一律で同じというわけではなく、その年々の受験生の出来等によって調整されていると思われます。
本試験で失敗してしまうと、記述式のことで頭がいっぱいになってしまう気持ちはわかります。しかし、「令和7年度の採点」について現状では全くのブラックボックスである以上、一旦脇に置いておきましょう。
とはいえ、司法書士試験は「午前の部」と「午後の部」、「択一式」と「記述式」のいずれについても基準点が設定されている以上、極端な得意分野がある方よりも、全範囲についてバランス良く学習し、かつ得点できている方が合格しやすい試験であることには間違いありません。
すなわち、択一式と記述式の得点率や、得意な科目と苦手な科目の差が大きすぎることは、なかなか合格することができない原因となってしまいます。
そこで、そもそもの択一式の学習と記述式の学習がアンバランスである場合、学習方法を根本から見直す必要があると言えます。
これは、今すぐにというよりも、年明け以降、特に4月以降の直前期に言える話です。
確実に3点ずつ得点できるという理由で択一式の学習に注力しすぎるあまり、直前期の学習で記述式の演習を後回しにし、本試験で記述式を解く感覚を忘れてしまう、ということは、特に初学者の短期合格・一発合格を目指す方は往々にしてあり得ますので、是非気を付けてください。
択一式試験で60問程度取れている方は、司法書士試験全体においての知識は十分に備わっていますので、まずは何よりその択一式の得点力を維持できるように、少しずつ基本4法の学習を再開しましょう。
今年の本試験において、択一式と記述式の得点率に差があるという場合であっても、択一式の学習によって勉強の感覚を取り戻してから記述式の演習を行った方が効率が良いため、筆記試験の合格発表に向けた今の時期は、まず基本4法を中心に択一式の知識を維持しておくことを優先してください。
いざ記述式の演習を再開したときに、択一式の学習の進捗に気を取られないように、少しずつコツコツと進めていきましょう。
答練・模試では安定して択一式は30問程度正解、記述式でも基準点を突破しているにも関わらず、本試験では総合点が厳しい、あるいは合否線上だと思われる方
答練・模試では十分な成績であったにもかかわらず合否線上にいらっしゃる方は、誰よりも悔しい思いをされていると思いますが、まずは、「なぜ日頃の実力を司法書士試験当日に発揮できなかったのか」をよく分析してください。本試験当日にしかない過度の緊張によることはもちろんであると思いますが、それ以上にしっかりと問題や自分の解答の具体的な中身を見ていただきたいです。そして、
① 平常時の自分であったら到底しそうにないミス(本番で初めてしてしまったミス)がどの程度あるか
② どういったパターンのミスが多いか(択一式問題の読み間違いや思い込み・他の知識との混同、記述式問題の事例・別紙・注意書きの読み飛ばしや単純な転記ミス等)
について、よく確認してください。
本試験時の極限状態の自分と向き合わなければならないこの作業は、多大な心労を伴うと思います。
ですが、今後二度と同じ轍を踏まないように、日頃の学習で気付く苦手科目・苦手分野に対する弱点分析のみならず、極度の緊張状態に置かれた自分の“司法書士試験そのもの”に対する弱点分析をしっかり行うことはとても大切です。
筆記試験の合格発表に向けた今の時期にすぐに学習を再開するかは、ご本人のご判断に委ねたいと思います。もし、今すぐに今年の本試験を思い出そうとすると精神的に追い込まれてしまい、もう二度と司法書士試験を受けたくなくなってしまいそうな方は、暫くは思い切ってリフレッシュしてください(その場合は、上記の自己分析も行わなくて良いと思います)。
ですが、その場合であっても、万が一残念な結果であったときの覚悟を持って、すぐに勉強モードに切り替えられるように、教材や学習環境を整理整頓しておくことをおすすめします。
最後に
以上、8月中旬の基準点発表~10月初旬の筆記試験合格発表の時期のおすすめの過ごし方について書かせて頂きました。
特に記述式の問題演習の開始時期については、昨年から配点が2倍になったこともあり、様々なご意見があるかと思いますが、折角直前期に追い込んだ知識が抜け過ぎないように、まずは択一式対策を優先していただきたいです。
まだまだ暑い日が続きますので、体調に十分ご留意の上、日々の学習に励んでください。
*~*~*~BACK NUMBER~*~*~*