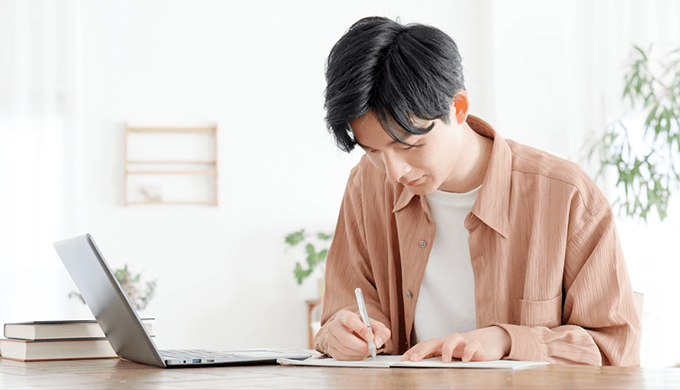主に社会人を対象とした学習アドバイスの続きです!
- 自分の標準学習時間を決めること
- まずは全範囲を終わらせること
- 全ての教材を可能な限り繰り返すこと ←ココ
- 答練の点数は気にせず、全ての答練を全部解くこと
- 基礎テキストと基礎問題集を重視すること
全ての教材を可能な限り繰り返すこと
基本となる事項を繰り返す。これは何事においても非常に重要であると思います。
私は昔からギターを練習していますが、経験ある方はよくご存じのように、楽器というのは基本となる動きを繰り返し繰り返し行わないと、弾けるようになりません。
アマチュアだろうがプロだろうが、とてつもない量の基礎練習を繰り返しています。ちなみに天才はちょっと教えられただけでいきなり弾けるらしいです。
天才の自覚が1ミリもない私は、基礎練習はほぼ毎日繰り返し練習するようにしています。
何かをできるようになるということは、まずは繰り返すこと。同じことを繰り返すので、どんなにモチベーションが高くても、いずれ必ず「飽きる」というフェーズが来ます。それを織り込んだうえで、それでも繰り返すことができるかどうかが大事だと思います。
そこまで言っておきながらなんですが、言うほどギター上手くないです笑。
さて、この「繰り返し」に関しては、全く同じことが資格試験においても言えます。
教材を何回繰り返せばいいのか、というのは正解がなく非常に悩ましいところです。もし聞かれたら「時間が許す限り、可能な限り」と答えます。前提として、テキストや基礎問題集は、1~2回読んだだけでは不十分ですし、読んだときは理解したつもりでも、すぐに忘れてしまいます。
資格試験の学習経験があまりない方は、まずここを理解する必要があります。膨大な範囲をカバーするテキストや問題集を1~2回読んだ(解いた)だけでは、すぐに記憶から抜け落ちてしまうということは、普通のことなのです。
テキストや問題集を1~2回読んだ(解いた)状態で、答練や過去問を解いても、知識の抜けが多すぎて、手も足も出ない、ということになります。よって、答練や過去問といった応用的な問題を解く前に、テキストや問題集を十分に繰り返し回しているか、確認する必要があります。
答練が全然解けない、という相談の大半は、基礎テキスト、基礎問題集を十分に繰り返して復習していない、ということに原因があります。
で、結局何回繰り返せばいいの?ということがどうしても気になるという方に、無理やりお答えするとしたら、「最低8回」と答えます。
この数字の根拠は非常に薄いのですが、まず自分の経験としてそれくらい繰り返してようやくできるようになった、という記憶があること。あと、私が通っていた予備校の講師の方が「最低8回繰り返さないとできるようにならない」と仰っていて、それが腹落ちしたこと、という感覚的なものとなります。
もちろん人によっては8回よりも少ない回数になるでしょうし、10回、15回といった回数になるかもしれません。科目によっても異なると思います。
いずれにしても、1~2回読んだだけ、解いただけでは天才でもない限り足りないということです。
定期的に復習する時間を日々のスケジュールに織り込んでおく
ということで、各科目の基礎テキスト精読・基礎問題集を繰り返す時間を日々のスケジュールに設けておくことをお勧めします。
私は通勤電車の中で理論科目を曜日ごとに分けて復習していました。例えば月曜:監査論、火曜日:企業法、水曜日:財務諸表論、木曜日:租税法理論、金曜日:経営学のように。
そして電車の中ではやりづらい計算科目の復習を家でやるようにしていました。月・水・金:簿記、火・木:管理会計、のように。
上記は一例ですが、いずれにしてもポイントは、定期的に繰り返す機会を織り込んでおく、というものです。
基礎を何回繰り返したか、科目ごとに記録しておく、というのもお勧めです。何回もやった気になっていたけど、記録を見ると実はそれほど繰り返していない、ということはよくありますので。
「基礎を繰り返すことができる」、というのは実はけっこう難しいものです。それほどエキサイティングではないですし、飽きます。それでもいかにモチベーションを保って継続して取り組めるかが、大事です。

【次回に続く】