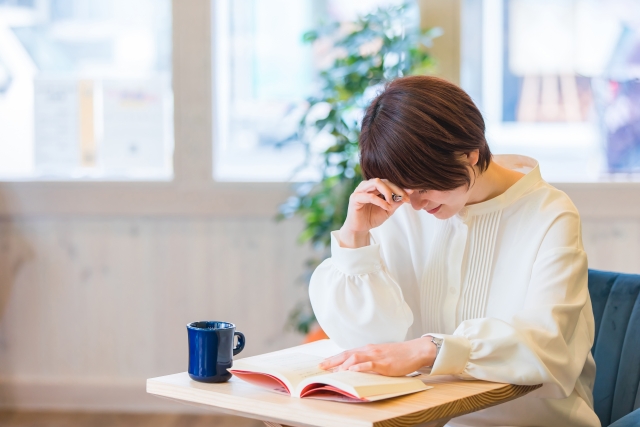はじめに
こんにちは、講師・司法書士・行政書士の米谷です。
司法書士試験の筆記試験の合格発表、口述試験も終わり、もうすぐ最終合格発表の時期ですね。
私は令和元年度合格ですが、日常では実務に追われ、司法書士試験のことを思い出すこともだんだん減ってきました。
一方で、講師の仕事をしているとき、あるいは、司法書士会で新人研修のための会務をしているときなどには、いまでもあの当時の気持ちをはっきりと思い出すことができます。
今回は、残念ながら今年度は司法書士試験合格とはならなかった方々にも、ささやかですが、これからの勉強の励ましになれば良いな、と思って、私の思い出話をしたいと思います。
私の司法書士試験の思い出
まずは、私の司法書士試験の受験歴及び全成績をお示しします。
左から順に、年度(概算の積算勉強時間)、択一式の自分の正解問数/基準点の正解問数、記述式の自分の得点/基準点となっております。
平成24年度(350H) 午前基準点未達 午後基準点未達(詳細記録無し)
平成25年度(700H) 午前基準点未達 午後基準点未達(詳細記録無し)
平成26年度(1050H) 午前基準点未達 午後基準点未達(詳細記録無し)
平成27年度(1400H) 午前25/30 午後23/24 →午前、午後ともに基準点未達
平成28年度(1750H) 午前28/25 午後25/24 記述18/30.5 →合格点-23点
平成29年度(2100H) 午前27/25 午後32/24 記述15.5/34 →合格点-14点
平成30年度(2450H) 午前28/26 午後27/24 記述43.5/37 →合格点-4点
令和元年度(2800H) 午前29/25 午後27/22 記述45/32.5 →合格点+16点
司法書士試験は、択一式の基準点を超えられるようになってからが本当の勝負です。
上記の通り、私は平成28年度にそれができるようになり、「合格が見えた!」と思いました。
それ以降の試験は、試験本番当日、本気で受かろうとの意気で、必死に取り組んでおり、どの年も強く記憶に残っています。
平成29年度:時間配分の重要性を痛感する
いまから考えれば、この年は、午後の部の、合格するための時間配分戦略がまったくできていませんでした。それまで、本気で合格しようという気持ちで試験を受けたことがなかったことと、なんと、模試を一度も受けたこともなかったからです
(皆さん、模試は午後の部の時間配分のシミュレーションに最適です。積極的に利用しましょう)。
午後の部の択一式をしっかり考えて(当然全ての肢を確認して)、記述式の問題に進んだときは、すでに2時間を経過していました。そのかいもあって(?)、32問正解と、長い試験人生でも最高得点をとることができました。
もちろんその反動で、60分間での記述試験問題の対応は、つらい思い出となっています。
まず、40分間をかけて不動産登記法に取り組み、それでも全体の3分の1は白紙の状態で、商業登記法の問題に進みました。残り20分です。
問題文を読むのもそこそこに、それこそ必死の形相で手を動かしました。何とか試験終了の時には、商業登記法の答案用紙の欄は全て埋めて試験を終えました。
帰宅して、自己採点すると、択一式の出来が思いのほか良く、基準点からの上積みがかなりできそうです(基準点の公表後に、10問分の上積みができていると判明。当時は8問分の上積みをして、記述式が基準点に達していれば合格できると計算できました)。
よって、あれだけ必死に解答欄を埋めた記述式が基準点にさえ達していれば合格している、という強い期待をもって、記述式試験合格発表を待ったのでした。
そして合格者発表の日が来ましたが、自分の受験番号は見当たらず、後から届いた得点票には、記述式不動産登記法が11.5点、商業登記法が4点!で、基準点に(そして総合合格点に)はるかに届かない、という結果でした。
「20分間でとにかく必死で答案用紙を埋めたという記憶しかないけど、いったい自分はどのような答案を書いたのだろう?」と初めて自分の書いた答案用紙を、法務省の情報開示制度(保有個人情報開示請求)を利用して取り寄せました。
それを見ると、例えば、「○年○月○日解散」とだいたい似たようなことを書いているのですが、その日付が1日ずれていたりしているものがほとんどでした。
それらしきことを書いて答案用紙を埋めていたとしても、1つ1つが正確に書かれていないと、部分点は一切もらえない(もしくは大幅減点である)ことを思い知ったのでした。
まあ、今から考えると、記述式問題について、不動産登記法でも商業登記法でも、たった20分間で合格点を取るのは無理、ということです。
平成30年度:初めて総合点が足らず不合格
今度こそ、午後の部の時間配分対策(練習)をしっかりして臨みました。択一式35問を70分で解いて、記述式不動産登記に60分、記述式商業登記に50分を使うという作戦でした(本当は、択一式35問を60分間で解くことを目標にしましたが、どれだけ練習しても、最後まで70分以内には縮まりませんでした)。
作戦通りに、午後の部の択一式は、70分で解いて記述式には想定通りの時間をかけることができました。
自己採点では、択一式での上積みが5問分しかできていませんでしたが、それでも、記述式も自分のできる限りのがんばりで、答案用紙を埋めることができたので、ぎりぎりいい勝負だと平成29年度以上の期待を持って、合格発表の日を迎えましたが、結果は、総合点で4点足りませんでした。
4点といえば、択一式問題1問分と記述式の部分点1点分ですので、あのケアレスミスがなかったら、と何度もため息はでましたが、もうどうにもならないのでした。
令和元年度(合格):なんと受験番号を書き間違える!
この年も、午後の部の時間配分(択一式70分、記述式110分)は事前のシミュレーションを十分にして臨みました。
午後の部の択一式は、近年まれにみる難易度であったようで、「もしかしたら基準点にいっていないかも…」という恐怖にかられながらも80分で何とか終了し、またもや必死で記述式に取り組みました。
商業登記では、全く見ていない別紙に試験終了後に気が付くなど、かなりテンパっていましたが、とにかく死力は尽くして、人生でも本当に久しぶりに「精魂尽き果てた」状態になったのでした。
自宅に戻り、自己採点してみると、択一式は基準点から8問分以上の上積みが可能そうであり(結果としては9問分)、記述式にも手応えがあったので、これは合格したかもと、少し高揚した気分で眠りにつきました。
ところが、朝方、変な夢を見て、記述式答案用紙に自分の受験番号を書いていないことに気づいてしまいました(代わりに千葉県の受験地番号を書いてしまっていた)。
「お前はいったい何回司法書士試験を受けているのだ!」という自分への突っ込みもむなしく、それから合格発表までの3か月間、試験の出来とは全く違うところで、本当に悶々とした時間を過ごすことになりました。
記述式試験合格発表当日も、「名前は書いてあるので、受験番号が間違っていても、答案を特定して、採点してもらえるだろう」という期待と、「もうだめだろう。採点してもらえなくても文句は言えないし、言うまい。」という心の揺れがものすごいものでしたが、結果は、採点してもらって合格しており、忘れられない1日となりました。
合格直近の4年間を振り返って
基準点をその年の試験問題の難易度と考えて、午前の部の択一式の成績を振り返ると、
基準点からの上積み問題数 3問 → 2問 → 2問 → 4問
であり、少し悲しいですが、平成28年度から令和元年度まで、ほとんど実力がアップしていないことが分かります。
違う言い方をすると、正解数28問~35問の領域で、得点をアップしていくことは大変難しいということだと思います。
一方で、午後の部の択一式を見てみると、
基準点からの上積み問題数 1問 → 8問 → 3問 → 5問
初めて基準点を超えた平成28年度は別として、こちらは実力アップというよりは、実感としては、そのときの時間配分、自分の集中力、問題との相性、そして運で、かなり得点が乱高下してしまう印象です。
最後に、記述式は、
基準点との差異 -12.5 → -18.5 → 6.5 → 12.5
記述式については、試験時間の配分も含めて、徐々に実力アップしており、平成30年度に初めて合格レベルになったと言えると思います。
以上から、私は、平成29年度以降は、択一式は実力維持だけに努めて、時間配分を含めた記述式対策に集中すれば、もう1~2年早く、合格できた(かもしれない)ということだと思います。
いまさら反省してもどうにもなりませんが…
司法書士になって言えること
司法書士試験に合格すると、新人研修、特別研修など、合格年度の近い人との交流が始まりますが、その飲み会で盛り上がる話題の一つが、それぞれの司法書士試験体験です。
私は総合点4点差で落ちた経験を書きましたが、0.5点差、1点差などで、不合格になった方(そして今は司法書士の方)はざらにいます。
しかも1点差等の僅差の不合格の翌年に合格できた方ばかりでない(さらに2~3年後に合格する方も多い)のが、司法書士試験の恐ろしいところです。
前述の私の体験談どおり、午後の部については、そのときの時間配分、集中力、問題との相性、そして運などの影響を強く受けるため、なかなか実力通りの結果を出すことが難しいということと、また、私を含めて数点差の不合格で涙を飲んだ人が大勢いて、その大勢の受験生が、また翌年死力を尽くして取り組むのですから、その中で、合格の順番を手繰り寄せるのは、なかなかに大変だということだと思います。
司法書士試験講師としては、「こうすれば、少しでも早く合格できます」という方法をアドバイスしたいのはやまやまです。けれども、合格できる実力の領域に早く達するためのサポートはできるものの、最後は、一人一人の「精根尽き果てるほどの」(そして強い思い出になるほどの)頑張りがなければ、合格にはなかなか達しない、ということだと思います。
それでも、司法書士の皆さんと話していて、いつも感じることは、「途中でやめようと思った」という人はほとんどいない、ということです。
私も含めて、数点差で結果がダメというようなことが続いたとしても、当然のように合格するまでチャレンジを続ける、という精神的にタフな人(というか平然と勉強を続けられる人)が結果的に司法書士になっている、というように思います。
そして、1回合格してしまいさえすれば、合格するまで何年間かかったかだとか、何点で合格したかなどは、司法書士の仕事をする上で全く関係のないこととなり、それこそ飲み会での思い出話にしかなりません。全ては司法書士になってからの頑張りだけです。
不運にも、今年度、不合格となって涙を飲んだ方々も、多くの司法書士が通る道ですので、1回の結果に落ち込みすぎることなく、タフな心持ちで、平然と、チャレンジを続けてもらいたいと思っています。
最後に 受験生へのエールとなる言葉の紹介
最後に、私が見つけたり、聞いたりした、受験生に対するエールになるかな、と思った言葉を紹介します。
「択一式の基準点を毎回超える実力があれば、試験を受け続けてさえいれば、巡りあわせの良いときに、いつか必ず合格する。」(某司法書士会の大先輩)
…それだけ、基準点を超えてからも合格まで長くかかることも多いということですが、続けていればいつかは受かります。
「成果を出せるかどうかは確率の問題であり、長期的なチャレンジを続けた者だけが、成果を出すことができる。」(安達裕哉さんの著書より)
…司法書士試験の成果(合格)は全てが確率の問題ではありませんが、長い努力の先にある、最後の一押しの部分については、あきらめないで長くチャレンジを続けて合格の順番が来るのを待つ姿勢も大事であるように思います。
「ゲームをおりないこと。運がいい人はここを徹底しています。(中略)運がいい人というのは、自分が「これぞ」と思っているゲームからはけっして自分からはおりないのです。」(中野信子さんの著書より)
…苦しくて長い司法書士試験の勉強が、決しておりることのないゲームとして客観視できたときに、合格はすぐそこまで近づいているように思います。
~米谷先生のブログのご紹介~
★米谷先生の司法書士試験の全成績や
合格した年の記述式解答用紙への受験番号誤記入について
是非こちらのブログもご覧ください!