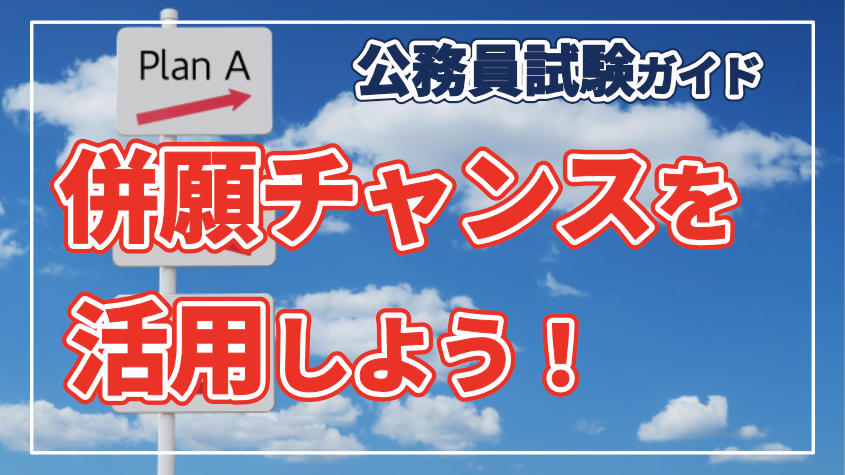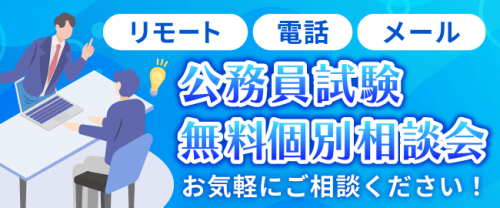公務員試験における「併願」とメリット
公務員試験の種類や試験内容についてイメージができたうえで、第一志望が決まったら併願プランを立てておくこともおすすめです。
公務員試験は原則、無料で受験できるため、日程が重ならなければいくつでも併願できます。
滑り止めという役割だけでなく、本命の前に本試験を体感しておくということも大きな意味がありますので、
注意点やポイントを読みながらチャンスをご活用ください!
併願のメリット➀ 合格の可能性を広げられる
公務員試験の受験をお考えの方には、「なにがなんでも第一志望に合格したい!」というタイプの方もいますが、複数の選択肢をお考えの方もいると思います。
そうした方にとって、試験を無料でいくつでも受験できるということは、受験年度内に合格を手にするチャンスを、より確実なものにできることにもつながります。
また、複数の受験先の中では特にこだわりがなかったり、第一志望と呼べる受験先が複数あるような方の場合は、内定が取れたところが結果的に第一志望となることもあります。
受験中は「採用してくれるところがあれば、そこで働かせてもらいたい」という立場だったのに、複数の受験先で内定が取れれば、その中でどの受験先で働くかを決める権利が得られるため、最後は自分が「選ぶ立場」になれるのです。
併願のメリット② 本番の空気を体感できる
本番の雰囲気や緊張感を体感するためには、予備校の模擬試験を受けることも効果的ですが、やはり本物の試験を受験しておくことがおすすめといえます。
逆に、本試験の経験値が0のままで本命試験を迎えてしまうことがあると、すべてが初めての経験となり、場合によっては会場の雰囲気に飲まれてしまうことも。
一部を除くと、地方公務員の試験は問題の持ち帰りができないため、本試験の問題に触れることができるのは本番の会場のみといったことも考えると、問題のレベルや時間配分などを知ることのできるチャンスを活用しておくべきといえましょう。
併願のメリット③ 万が一の滑り止めができる
難関と呼ばれるような受験先を第一志望としてお考えの方にとって、合格できなかった時は翌年も受験したいと思いながらも、「就職浪人はしたくない」という気持ちもあり、リスクの高さに受験の意欲がそがれてしまうこともあるようです。
こうした方も併願チャンスを活用するメリットは高く、例えばその年の第一志望で合格に手が届かなかった場合、いったん併願して合格できれば内定を受けておくこともできます。
そうすることで就職浪人になるという不安は解消されるので、あとは翌年に向けて学習を継続し、次回の試験で第一志望の合格ができたら公務員間の転職をする…このような受験プランも選択肢の一つにできます。

併願って、どんなところを、いくつくらいできるんですか?
さまざまな併願パターン
行政事務職(教養+専門)の場合
大卒程度の行政事務職試験では、例年4月から10月頃まで様々な採用試験が行われています。
教養試験と専門試験のどちらも学習をしてきた人であれば、年齢上限を超えていない限り以下のような受験先で併願をすることができます。
【教養・専門の対策を立てた人の併願先】
| 実施日 | 受験先 | 年齢上限 | 試験タイプ |
| 4/21頃 | 東京都Ⅰ類B(一般方式) 東京都Ⅰ類B(新方式) 特別区Ⅰ類 | 29歳 29歳 31歳 | 教養+専門(記述) SPI3 教養+専門 |
| 5/11頃 | 裁判所一般職(事務官) | 30歳 | 教養+専門 |
| 5/14頃 | 北海道A区分(第1回) | 30歳 | 職務基礎力試験 |
| 5/26頃 | 国家専門職(★) | 30歳 | 教養+専門 |
| 6/2頃 | 国家一般職(大卒) | 30歳 | 教養+専門 |
| 6/16頃 | 地方上級(県庁・政令市) 市役所A日程 | 自治体別 自治体別 | 自治体による 自治体による |
| 7/7頃 | 国立大学法人等 | 30歳 | 教養 |
| 7/14頃 | 市役所B日程 | 自治体別 | 自治体による |
| 9/22頃 | 市役所C日程 | 自治体別 | 自治体による |
教養・専門試験の対策を立てている方であれば、上記の試験から最大8つの併願をすることができますが、これ以外にも独自の日程で試験を行なっている市役所の併願ができます。
近年、筆記試験を決まった日時ではなく、定められた期間内にテストセンターで受験するタイプの市役所も増えているため、そうした受験先を加えると10以上の併願プランを組むことも可能です。
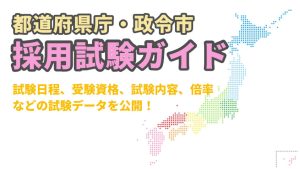
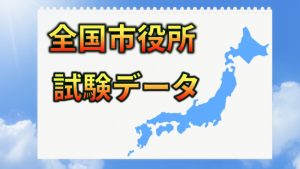
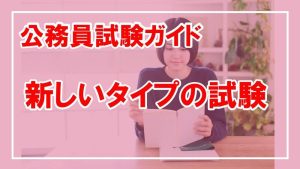

教養しか勉強していない人は、どのくらい併願できるんですか?
行政事務職(教養のみ)の場合
第一志望が教養試験のみで受験できる試験を行なっている場合は、同じタイプの試験が併願可能な試験となります。
| 実施日 | 受験先 | 年齢上限 | 試験タイプ |
| 4/21頃 | 東京都Ⅰ類B(新方式) | 29歳 | 教養 |
| 5/14頃 | 北海道A区分(第1回) | 30歳 | 職務基礎力試験 |
| 6/16頃 | 地方上級(県庁・政令市) 市役所A日程 | 自治体別 自治体別 | 教養(※) 教養(※) |
| 7/7頃 | 国立大学法人等 | 30歳 | 教養 |
| 7/14頃 | 市役所B日程 | 自治体別 | 教養(※) |
| 9/22頃 | 市役所B日程 | 自治体別 | 教養(※) |
この併願プランにも独自の日程で試験を行なっている市役所を加えることができますが、プラスαで併願できる試験が他にもあります。
県庁・政令市が行う特別枠の試験について
大卒程度の県庁、政令市(地方上級)試験は、例年6月下旬に全国一斉実施されていますが、ここ数年、独自の日程で「特別枠」「先行枠」のような募集を行う自治体も増えています。(試験方式や年齢上限は自治体ごとに異なります)
【独自日程の試験を行なう県の一例】
4/1頃 長野県(行政B)、福岡市(行政特別枠)、愛媛県(行政事務B)
4/2頃 茨城県(早期日程)、岐阜県(行政Ⅱ)、栃木県(早期枠)、群馬県(行政事務B)
4/3頃 広島市(SPI枠)、和歌山県(早期募集枠)
4/4頃 京都市(京都方式)、札幌市(SPI)
4/5頃 宮崎県(特別枠)
4/9頃 福井県(アピール枠)
4/11頃 神戸市(適性検査方式)
4/12頃 大阪府(大卒程度)
4/13頃 兵庫県(早期SPI枠)
4/14頃 福島県(先行実施)、富山県(先行実施)、島根県(行政B)、高知県(チャレンジ型)、鹿児島県(先行実施)、石川県(先行枠)、奈良県(春実施)、熊本県(SPI 方式)、岡山市(早期実施枠)、
4/21頃 名古屋市(春実施)、山形県(先行実施枠)、岩手県(アピール型)、静岡県(早期試験)、静岡市(早期枠)、浜松市、新潟県(先行実施枠)、岡山県(Aアピール型)
10/21頃 神奈川県(秋季チャレンジ)
このような試験が増えた背景としては、自治体ごとにもっと多くの受験生を確保したいという考えがあると思われます。
これまで行っていた統一日程の試験では、受験生は一箇所しか受けることができなかったため、このように別の日程で試験を行なうことで併願ができるようになり、受験先の自治体としてもトータルでの受験者数増加を図ることができるのです。
社会人受験者の併願について
大卒程度の受験をお考えの方以外にも、20代後半以降の社会人を対象とする併願プランがあります。
社会人の方には、年齢上限の高い大卒区分と、一部の社会人経験者区分を組み合わせた併願スケジュールを立てることもできるようになっており、学習の負担なく併願チャンスを活用できます。
[職務経験5年以上の20代後半受験者の場合]
| 実施日 | 受験先 | 受験資格 | 試験タイプ |
| 4/21頃 | 東京都Ⅰ類B(新方式) | 29歳 | SPI3 |
| 6/16頃 | 横浜市(大卒程度) | 30歳 | 教養(※) |
| 7/7頃 | 国立大学法人等 | 30歳 | 教養 |
| 7/14頃 | 市役所B日程 | 自治体別 | 教養 |
| 9/1頃 | 特別区(経験者1級職) | 26歳以上(職務経験4年) | 教養 |
| 9/22頃 | 市役所C日程 | 自治体別 | 教養 |
| 9/22頃 | さいたま市(経験者) | 28歳以上(職務経験5年) | 教養 |
仮に28歳で職務経験が5年を迎えた方であれば、上記の日程で東京都、特別区、横浜市をすべて含んだ併願プランを立てることもできます。特に東京都と特別区は大卒程度試験が同一日程で実施されるため、一般的に併願不可の組み合わせですが、このような組み合わせであればどちらも受験することができます。
関東以外のエリアについては組み合わせパターンも異なりますが、一般枠と経験者枠という組み合わせは20代後半から30代前半の方が得られる希少なチャンスと言えます。
事務職以外での併願プラン
心理職・福祉職・技術職・公安職など、事務職以外の職種についても、併願プランをご紹介します。
心理職・福祉職
【心理職・福祉職の併願パターン】
| 実施日 | 受験先 | 受験資格 | 試験タイプ |
| 3/17頃 | 国家総合職(人間科学) | 30歳 | 教養・専門 |
| 4/21頃 | 東京都Ⅰ類B(心理/福祉) 特別区Ⅰ類(心理/福祉) | 29歳 39歳 | 教養・専門 教養・専門 |
| 5/11頃 | 裁判所総合職(家裁調査官) | 30歳 | 教養(専門は二次) |
| 5/19頃 | 愛知県(心理)特別募集 愛知県(社会福祉士)特別募集 | 59歳 59歳 | 教養・専門 教養・専門 |
| 5/26頃 | 法務省専門職(矯正心理専門職) 法務省専門職(法務教官) 法務省専門職(保護観察官) | 30歳 30歳 30歳 | 教養・専門 教養・専門 教養・専門 |
| 6/16頃 | 地方上級(心理/福祉) | 自治体別 | 教養・専門 |
心理職・福祉職は、いずれも専門的な知識が必要とされるので専門試験が行われますが、受験先によって出題科目や解答方式が異なります。
事務職との併願でチャンス倍増!
心理職・福祉職は事務職と比べて受験先が少ないことで不安に感じる方もいますが、そうした時は事務職との併願プランを立てることをおすすめします。
ただし、事務職といっても専門試験が課される受験先ではなく、教養試験のみで受験できる試験をピックアップして併願しましょう。そうすると、無理に学習の負担は増やさずに、受験のチャンスだけ増やすことができます。
もし、「家裁が第一志望だけれど、万が一合格できなかった時は翌年も受けたい!でも就職浪人もしたくないし…」といった不安があれば、併願先の一つで合格できれば就職浪人をせずに、公務員になってから翌年の家裁を再受験できます。(もちろん、卒業までに学習を継続しておくことが大事です)
学生時代は家裁を志望していた方で、いったん事務職についてから再受験をして公務員から公務員への転職をされたという方もいますので、リスク回避のためにぜひ併願チャンスをご活用ください。
技術職
| 実施日 | 受験先 | 受験資格 | 試験タイプ |
| 3/17頃 | 国家総合職(技術) | 30歳 | 教養・専門 |
| 4/21頃 | 東京都Ⅰ類B(技術) 特別区Ⅰ類(技術) | 29歳 31歳 | 教養・専門 教養・専門 |
| 5/26頃 | 労働基準監督官B(理工系) | 30歳 | 教養・専門 |
| 6/2頃 | 国家一般職(技術) | 30歳 | 教養・専門 |
| 6/16頃 | 地方上級(技術) 市役所A日程(技術) | 自治体別 自治体別 | 教養・専門 教養・専門 |
| 7/7頃 | 国立大学法人(技術) | 30歳 | 教養 |
| 7/14頃 | 市役所B日程(技術) | 自治体別 | 教養・専門※ |
| 9/22頃 | 市役所C日程(技術) | 自治体別 | 教養・専門※ |
技術系といっても、土木、建築、機械、電子・電機・情報、農学、水産、林業…など、募集区分は異なります。
また、市役所単位でも技術の募集は活発に行われていたり、県庁・政令市でも事務職のように特別枠の募集が多くの自治体で行われています。
併願をする際の注意点
➀あくまでも第一志望を優先!
②日程が重ならないか注意!
③併願数を増やしすぎて負担にならないようにする
➀あくまでも第一志望を優先!
併願チャンスが増えることはメリットばかりではありません。注意しておかないとムダ・無理が増えてしまい、効率的な試験対策から遠ざかってしまうこともあります。
まず、併願先を決める時の鉄則として、「第一志望の試験で必要のないことはできるだけやらない」ということが挙げられます。例えば、第一志望が教養試験のみで受験できる自治体で、第二志望以下の自治体で専門試験が課されるというパターンもありますが、これは慎重に考える必要があります。
なぜなら、専門試験の学習をするという「学習の負担」は、最も志望度の高い試験では必要とされないため、「目的」と「負担」を天秤にかけたときにバランスが崩れてしまうからです。
なんとなく、併願数を増やせるというだけで専門試験対策まで手をつけてみたものの、その負担が重荷になった時の目的が漠然としていると、意味がないと感じて手を付けなくなってしまったり、場合によっては公務員試験そのものが辛くなってリタイアしてしまうことにもなりかねません。
併願先を決める時は、あくまでも第一志望の対策で必要となることを重視して、そこで学習した内容で対応できる試験を併願プランに入れていくことが大切です。
②日程が重ならないか注意!
一次試験の日程であれば、受験をする際に確認ができますが、二次試験以降の日程は後で判明することもあります。
場合によっては、第二志望の二次試験と第一志望の一次試験がバッティングしてしまう…といったこともあるのですが、こうした時のよくある悩みとしては、「第二志望は面接まで進めたけれど、第一志望はこれから一次試験なので、どちらを優先すればよいかわからない」といったものです。
手にした一次合格を捨てて第一志望にこだわるか、少しでも可能性の高い受験先に優先順位を変えるか、どちらにも正解はないと思いますが、そういった時は「後悔しないと思える選択をする」ことが一番大切です。
例えば、もし第一志望は受けずに第二志望の面接を受けに行って不合格となってしまった時と、第二志望の面接は辞退して第一志望の筆記試験を受けて不合格になったしまった時をそれぞれ想像した時に、どちらの方が後悔がないかを考えると、自分の中で納得した判断もできます。
日程のバッティングは注意しても自分で決めることのできないものですが、併願をするうえではこうした事態も起こりうることを念頭に置いていただければと思います。
③併願数を増やしすぎて負担にならないようにする
併願数を増やすということは、エネルギーを分散させることでもあります。
一つの試験を受験するためには申込手続きを行い、試験会場に足を運び、ほぼ1日拘束された上に会場まで行き来しなければなりません。試験シーズンになると毎週のように本試験が行われるので、肉体的・精神的な消耗が続くと万全のコンディションとは言えなくなってしまう可能性もあるでしょう。
特に気を付けなければいけないのは、本命の受験先までに試験スケジュールを詰め込みすぎて、望ましくない状態となってしまうことです。
これは➀でもお話したことですが、優先すべきことは第一志望ですので、闇雲に試験を受けるだけではなく、その中で第一志望の合格という軸を見据えて併願チャンスを十分活用してください。

この記事を書いた人
クレアール公務員相談室タニオカ
これまで、公務員試験の受験・学習を考える3,000人以上の相談に答えた実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」などを執筆。