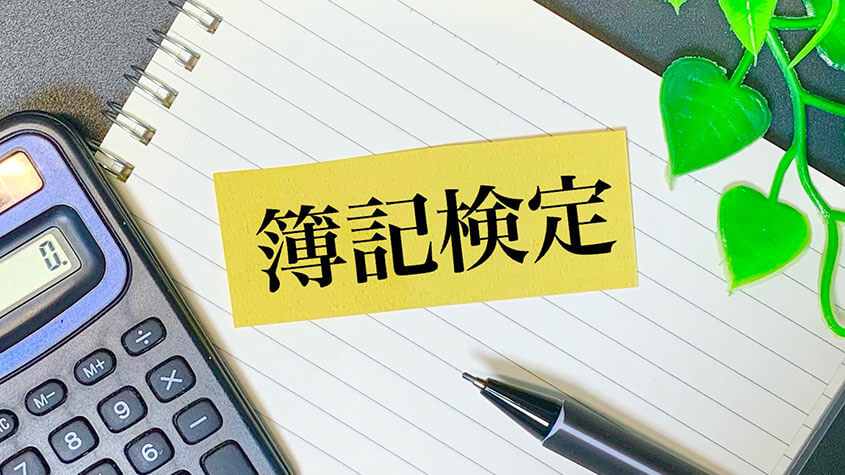今回は170回簿記1級本試験のX上の得点を分析します。Xで得点を投稿された方のうち、70点台の方と60点台の方の各科目別得点を集計しました。
これを踏まえて今後の対策を考えていきたいと思います。
| 商業簿記 | 会計学 | 工業簿記 | 原価計算 | |
| 70点台 | 14.5 | 20.7 | 22 | 17.9 |
| 60点台 | 12.1 | 16.1 | 21.4 | 14.6 |
受験者の半数以上が商業簿記で足切りになる。
1級本試験では各科目のうち、1つでも得点が満点の40%(10点)未満であれば不合格となります。
過去のデータでは、商業簿記の受験者平均点は8点台でした。おそらく今回も変わらない点数と思われます。換言すると、受験者の半分以上が商業簿記の足切り対象となります。
商業簿記は「半分正答」でも合格ライン
商業簿記は合格された方でも60%以下の得点です。商業簿記はほぼ毎回配点調整が入り、今回もそれが行われたと推測されます。素点ベースでは上記の点数よりもさらに2〜3点低いと考えられます。
つまり、半分程度正答できれば商業簿記は合格ラインに乗ります。この意識を持つことは重要です。
作戦を立てて試験に挑もう
「半分程度の正答を目指す」ことが目標と考えると、捨てる箇所が明確になります。損益計算書作成問題が出題された場合、売上総利益より上の箇所(売上高、当期仕入、期末商品棚卸高)の算出は難しいことが多いです。
問題文冒頭で商品関連の資料が与えられるため、つい手を出しがちになりますが、後回しにする勇気が必要です。
反対に、売上総利益より下の箇所は他の資料と複合的に読み取る箇所も少ないため、平易な問題が多いです。法人税等や経過勘定等、金額を書き写すだけで正答できる箇所もあるため、問題全体を眺めて解答順序を考えることが重要です。
細かい計算は慎重に
筆者の推測となりますが、168回試験より作問者が変更となった可能性があります(問題の特徴が変わりました)。より細かい計算が求められるようになり、古典的な論点が増えた印象です。
具体的には
- 定率法の減価償却費の計算で、前年度から改訂償却率を用いた減価償却が行われてるため、複数年に渡る計算が求められた(168回)
- 新株予約権付社債で償却原価法(利息法)の計算を複数年行う必要があること(170回)
- 割賦売掛金の計算が登場(170回)
上記2つは四捨五入を間違えると、最終値がズレる恐れがあります。問題自体は平易なため、慎重に解き進めていきましょう。
次回は会計学です。