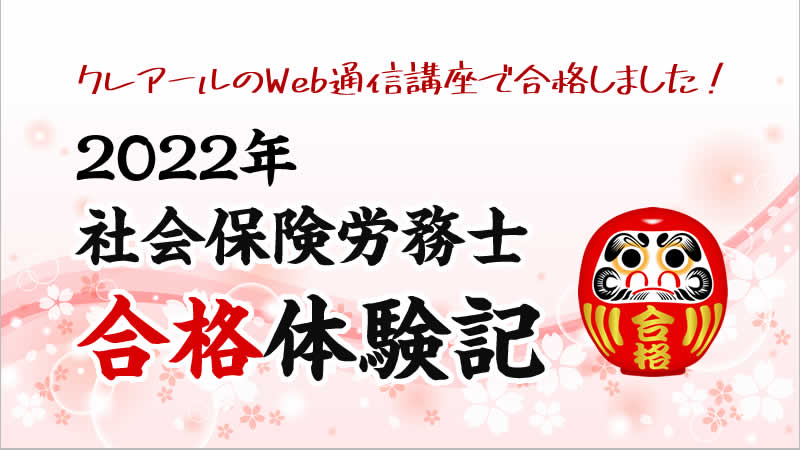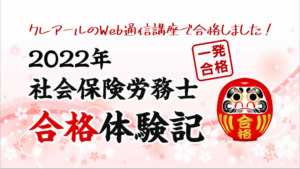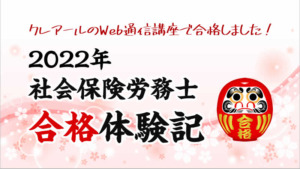畠 聖弥さん
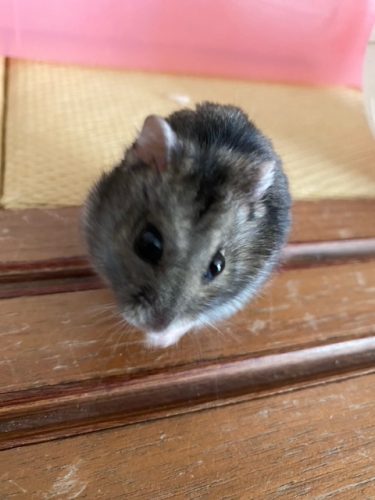
- 受験回数:2回
- 受講コース:一発合格ストレート15カ月セーフティAコース
社会保険労務士を目指したきっかけ
私が社労士を目指したきっかけは、日本の労働環境について疑問を持ったからです。昨今のニュースで、大企業が、違法な時間外労働やパワハラなどが原因の労働問題を行っていることが報じられています。注目されるような企業でさえ、このような事態に陥っているということは、中小企業でも、問題の大小の差や、故意か、そうでないかの違いはあるにしろ、起こっていることであると想像することは容易でした。したがって、法律という絶対的観点から、日本の労働環境を前時代的なものから、少しでも変えていくことが出来る職に就きたいと思い、社労士を目指しました。
情報収集の方法
私は、初めにクレアールの資料請求をし、送られてきた答練を解き、直観でいいと思いました。
学校選びのポイント
私の予備校選択の判断材料の1つとして、地域の近くに予備校がないので、オンライン授業の体制が整っていることがありました。クレアールでは、ちょうどよい間隔でテキスト等を送ってくれるのでよかったです。また、1年目は独学だったので、法改正の対策をすることが出来ていなかったのですが、通常の授業の中はもちろん、対策講義もあって助かりました。
学習をする上での心構え
私は、会計士や税理士などの資格の勉強をしたことはありませんが、社労士試験は科目数の多さと、その振り幅の大きさが特徴的だと思います。特に安全衛生法や一般常識は、テキストでやらないような細かい数値問題が毎年出ると思うので、そういうものだと割り切ることも1つ必要かと思います。また、実体験から、選択問題は、いかに足切りに引っかからないかの勝負だと思うので、択一よりも細かいところまで気を配って学習する必要があると思いました。
効果的な学習方法
苦手科目の克服法
私は、労働安全衛生法と一般常識が苦手でした。労働安全衛生法は、テキストレベルの問題はできるようにし、1年目の失敗を基に、改正点や労働局で配られるパンフレットやホームページを見て、選択問題の数値などを抜かれたときに対応できるように心がけました。一般常識は、答練や模試ででた問題を覚え、同一労働同一賃金のQ&Aなどを見ながら、事例問題が出たときに対応できるようにしました。
主な学習の流れ
私の学習の流れは、問題を解くときに1週目は、普通に解いて、間違えた問題にチェックを付けて置き、その後1カ月など経ち、少し忘れたころに2週目でもう一度全部解き、3週目は1,2週目で間違えた問題を解くという方法でした。こうすることで、偶然間違った問題なのか、本当に理解できていない問題なのかを分けることができ、直前期に学習すべきところが明確になったとおもいます。
印象的なエピソード
答練を行った際のことです。それまでテキストや過去問を繰り返し行い、知識が十分に詰まっていると自分で思い込んでいるところに、それまで考えたことの無かった論点や視点から問題が出てきたりして、知識の隙間を埋めるような学習ができ感動しました。また、直前期には、今まで間違えた答練の問題を繰り返し行い、知識の定着化を図り、焦る時期を乗り切りました。
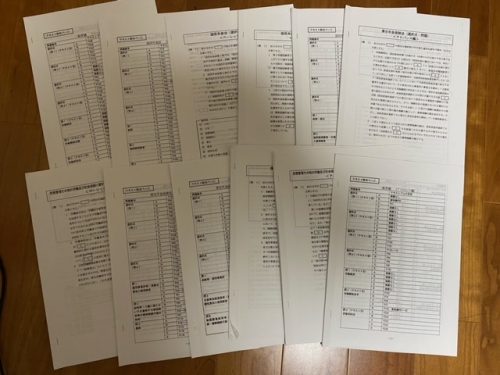
今後の展望
今後は今働いている会社で、手続き業務や給与計算をはじめとする仕事を行いながら、開業したいと思います。また、先輩社労士の方々と差別化できるように、これからの時代に対応できるよう、デジタル化や働き方改革に強い社労士になりたいと思います。
推奨メッセージ(ご経験者の方へ)
社労士の試験は、合格ラインが科目ごとにあることにより、1つの小さなミスが命取りになると思います。正直自分ももう一度同じ試験を受けたら受かると断言することはできません。しかし、完全な運だけでなく、学習量に比例して合格確率は上げていくことが出来ると思うので、めげずに頑張ってください。