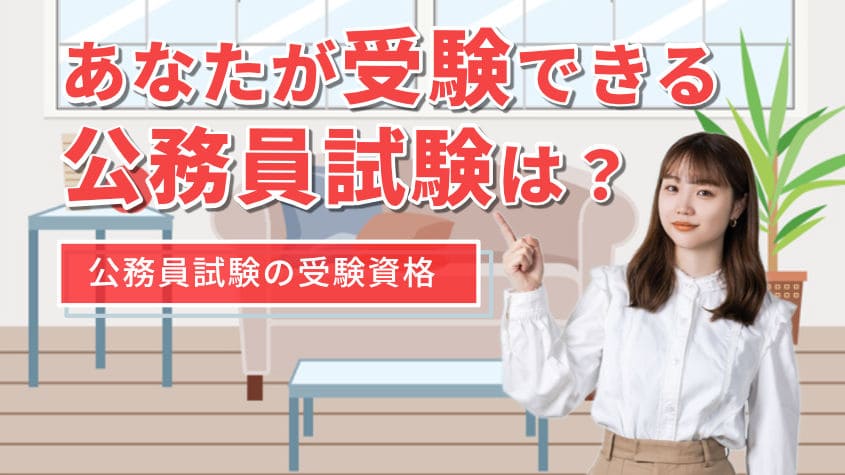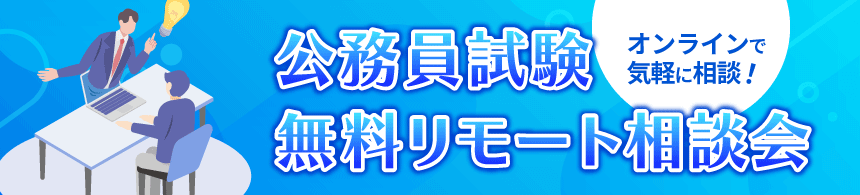このページでは、試験区分や年齢条件など、公務員試験の受験資格の読み方・調べ方をご紹介します。自分が受験できる公務員試験について、一緒に考えていきましょう。

公務員試験の受験資格について
公務員試験というと、現役の高校生か大学生が受験するもの…というイメージをお持ちの方もいると思いますが、学生以外の人も受験対象となっています。
たとえば、高校や大学を卒業してから民間企業などで働いている社会人であったり、結婚して専業主婦をされている女性、非正規労働者、失業者の方なども受験対象といえます。
ただし、受験先によって受験資格が設定されているので、誰でもどこでも受験できるというわけではありません。
受験先では、年齢や職務経験などによって「試験区分」を分けていることが多く、区分ごとに受験可能な年齢やその他の要件が示されています。
さまざまな試験区分
試験区分(採用区分とも言います)は、レベル別と職種別に分かれていますが、レベル別には「大卒程度(上級)」、「高卒程度(初級)」、「社会人経験者」などの区分があります。

最終学歴が高卒で25歳の場合はどの区分を受けるの?
「大卒」や「高卒」などは原則として試験問題の難易度で区分を整理するための表現で、実際は学歴不問となっていることが多いようです。その場合は最終学歴が高卒でも大卒区分を受験することとなります。
ただし、一部の受験先(主に市町村)では大卒区分の受験資格が「大学卒業または卒業見込みの人」とされていることもありますので、必ず受験先の自治体HPなどで確認しておく必要があります。
[国家一般職の場合]
| 区分 | 受験資格 |
| 高卒程度 | 受験をする年の4月1日時点で、高校、中等学校を卒業した翌日から2年を経過していない者、卒業見込みの者 |
| 大卒程度 | 22歳以上31歳未満 |
[特別区(東京23区)の場合]
| 区分 | 受験資格 |
| Ⅲ類(高卒程度) | 18歳以上22歳未満 |
| Ⅰ類(大卒程度) | 22歳以上32歳未満 |
| 1級職(経験者) | 60歳未満で、職務経験が直近10年中4年以上 |
| 2級職(経験者:主任) | 60歳未満で職務経験が直近14年中8年以上 |
[横浜市の場合]
| 採用区分 | 受験資格 |
| 高卒程度 | 18歳以上22歳未満 |
| 大卒程度 | 22歳以上31歳未満 |
| 社会人経験者 | 31歳以上60歳未満で、職務経験が直近7年中5年以上 |
社会人経験者の職務経験年数
社会人経験者区分では、年齢だけでなく職務経験年数が必要となることもあります。
その場合は概ね4.5年であることが多いのですが、職務経験の長さによって社会人経験者の中でも採用区分を分けている場合があります。(例:特別区)
また、職務経験年数は1社だけでなく複数の企業で合算できることも多いので、転職歴のある方でも受験資格を満たすことが可能と言えます。(1社あたりの職務経験年数が1年以上とされるなどの条件があります)
正社員として勤務していなかった人も、1週間当たりの勤務時間が条件を満たせば雇用形態を問わず受験できることもあります。

試験案内で確認しておくことがオススメ!
その他の受験資格
これまで説明したものは最も受験者が多い「行政職(事務職)」に関するものですが、専門性を活かした職種で受験するに場合は年齢以外の資格要件が必要となることがあります。
たとえば、「心理職」や「福祉職」では、大学で専門分野を専攻した人であったり、社会福祉主事任用資格が必要な場合もあります。
また、「保育士」「栄養士」などの資格免許職であれば資格を有している人(または受験翌年度末までに取得予定の人)を受験対象としていることもあるので、これらについても事前に確認しておくことが大切です。
自治体ごとの年齢上限
受験者が最も多い採用区分である「大卒程度区分」ですが、受験先によって年齢上限が異なります。
現役大学生の方であれば、あまり気にすることではないとしても、既卒者の方であれば、年齢によって受験できる試験が変わるので要注意です。
まず、国家公務員ですが、大卒程度区分の年齢上限は、一般的に30歳で統一されています。
問題は地方公務員です。国家公務員とは比較にならない数の自治体があり、自治体ごとに年齢上限が異なります。
全国の県庁・政令市については、それぞれ以下のような年齢上限が設定されています。
※年齢上限は変更となることがございます。必ず受験先の自治体でもご確認ください。
| 年齢上限 | 自治体・区分 |
| 24歳 | 神戸市(総合事務) |
| 25歳 | 名古屋市(春実施)、大阪府(22-25)、大阪市(22-25)、堺市、佐賀県(特別枠)、大分県(特別枠)、鹿児島県(特別枠) |
| 26歳 | 滋賀県(アピール試験型)、京都府、京都市(京都方式)、岡山県(アピール型)、広島県(事務B) |
| 27歳 | さいたま市、京都府(10月)、兵庫県、神戸市、愛媛県(事務B) |
| 28歳 | 千葉市、新潟市、静岡県(行政:従来型)、浜松市、堺市 |
| 29歳 | 札幌市、茨城県、栃木県、群馬県、東京都Ⅰ類B、川崎市、長野県(行政A・B)、岐阜県(行政Ⅰ)、愛知県、三重県、石川県、奈良県、島根県、広島県(事務A)、広島市、山口県、香川県、高知県、福岡県、福岡市(行政)、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 30歳 | 北海道、埼玉県、千葉県(行政A、C)、神奈川県、横浜市、新潟県、静岡県(行政Ⅰ)、静岡市、滋賀県、京都市、岡山県、岡山市(事務一般枠)、北九州市、福岡市(行政特別募集) |
| 31歳 | 東京都Ⅰ類A、特別区Ⅰ類 |
| 32歳 | 青森県、愛知県、三重県(行政Ⅱ)、熊本市 |
| 34歳 | 秋田県、福井県、大阪府(26-34)、大阪市(26-34)、愛媛県(事務A) 高知県(行政チャレンジ型) |
| 35歳 | 岩手県(行政A)、宮城県、仙台市、福島県、千葉県(行政B)、相模原市、山梨県、静岡県(行政:総合型)、京都府(行政Ⅱ)、富山県、和歌山県、鳥取県、熊本県、沖縄県 |
| 36歳 | 徳島県 |
| 39歳 | 山形県、岐阜県(行政Ⅱ)、名古屋市(夏実施、社会人枠)、岡山市(事務特別枠) |
| 40歳 | 静岡市(創造力枠)、岡山市(特別枠) |
| 59歳 | 千葉市(行政B) |
同じ自治体の中に「行政A」「行政B」あるいは「行政Ⅰ」「行政Ⅱ」、「特別枠」のように、複数の採用区分を設けている自治体もあるため、「受験可能な自治体」に加えて「受験可能な区分」まで確認が必要となります。
市役所については800近くの自治体があるので、全国の実施データをまとめたPDFをご覧いただけばと思います。
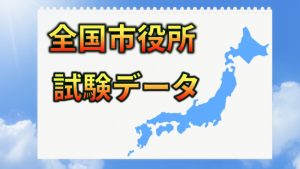
まとめ
いかがでしたでしょうか。
公務員試験の受験資格は複雑でわかりにくい側面も持っていますが、調べ方や読み方さえわかれば、自分が受験できる試験かどうかが確認しやすくなります。
もちろん、ここでご紹介をした試験はあくまでも一例ですので、専門職や資格免許職、試験区分によっては判断が難しいケースもあると思います。
今回の内容を踏まえたうえでご不明な点があれば、ぜひお気軽にクレアール公務員相談室までお申しつけください。

この記事を書いた人
クレアール公務員相談室アドバイザー タニオカ
公務員試験の受験に関して、3,000件以上の相談実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「公務員試験 入門ハンドブック」などの執筆も担当。