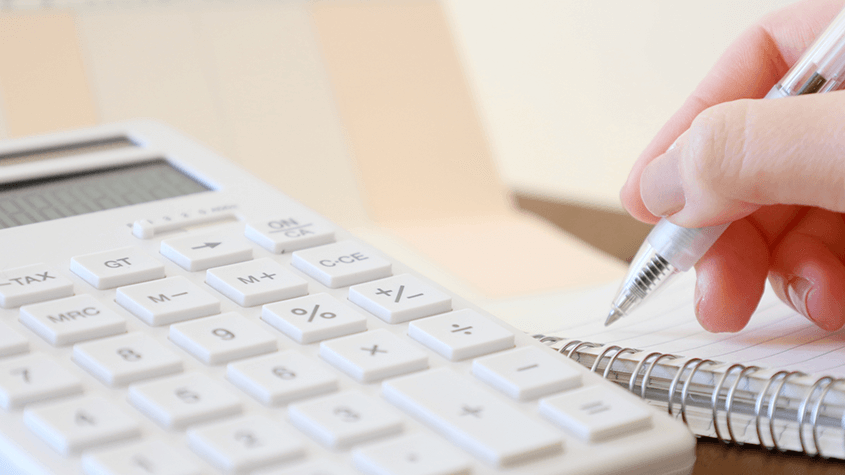日本商工会議所から発表されている講評から、今後の試験対策に役立ちそうなものをピックアップし解説するこのシリーズ。今回は原価計算編です。
前回の記事はこちら
原価計算は簡単な問題の出題が多い
| 162回 | 165回 | 165回 | 167回 | 168回 |
| 10.4% | 12.5% | 16.8% | 10.5% | 15.1% |
上記の表は過去本試験の合格率です。簿記1級の合格率は10%前後と言われていますが、赤字のように、通常の合格率を上回る回が増えています。
この理由は原価計算(あるいは工業簿記)で満点、もしくはそれに近い点数を取る受験者が続出し、配点調整を行えなかったことによるものと推測されます。
162回以降、原価計算はごく基本的事項の出題が続いており、正答率が著しく低いと思われる問題の出題はありません。
試験委員の講評を読み解く
以下は165回試験・原価計算の講評です。
「得点分布は正規分布ではなく、一様分布に近いものになり、0点から25点まで均等に散らばりました。(中略) 単に解法を覚えているかどうかではなく、真の実力を反映できる問題になったと考えております。」
https://www.kentei.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/01/165-1-kouhyou-1.pdf
この講評は、近年の原価計算の試験問題の特徴をよく表していると思います。
得点分布が一様分布となる理由
検定試験等の得点分布は正規分布のような形(釣鐘型)をとるのが通常です。平均点付近に多くの受験者が集まり、高得点・低得点につれて受験者数が減ります。
ところが、原価計算では講評のように得点分布が一様分布の形(長方形型)となっているようです。
その理由は以下にあると推測します。
文章が長文かつ文体のクセが強く、ミスを誘発しやすい
165回原価計算では、問題用紙のほぼ全てに渡って長文の文章が詰め込まれ、空所内の金額や用語を記入させる問題が出題されました(空所補充の問題は頻繁に出題されています)。
試験委員の文章の特徴として、一文が長文かつ文体にクセが強いため(一つの段落に同じ接続語を使う、「要するに」「どうして」等、話し言葉が混在するなど)、問題の指示や意図を掴み取ることに相当な労力を費やします。
当然ミスが誘発されやく、その差が得点の差と表れていると考えられます。
各問題の難易度に差がない
合格者の多くが満点に近い点数を取れていることからも、各問題に難易度の差が少ないことが近年の原価計算の特徴です。
168回試験・原価計算の業務的意思決定の問題も、(1)さえ解けてしまえば(2)(3)と続けて正答できる内容でした。「わかる人には簡単に満点が取れてしまうけど、わからない人には0点」となるような形式の出題が続いています。
この「わかる人」のミスの数の多寡が一様分布となって表れているのではないのでしょうか。
現実的な対策を考えよう
上述の通り、全体として原価計算は易化傾向にあります。
難問が出題されない以上、試験対策として時間のかけ過ぎはNGです。日頃の学習で以下の点に注意してください。
①テキストの解説から用語を理解する
長文空所補充形式の出題は今後も予想されます。問われている内容はテキスト等の基本的な事項です。言い回しを変えて出題されても対応できるように、自分の言葉で各用語の意味や計算式を押さえておく必要があります。
(例えば、設備投資意思決定について、回収期間法・正味現在価値法などの利点・欠点等)
②難問には手をださない
難問は出題されない以上、日頃の学習で使用する問題集のCランク問題は捨てることも有効です。時間に余裕のない方はBランク問題も取捨選択の範囲に入れて構いません。そこで空いた時間を会計学の連結や企業結合の学習に充てることも有効です。
基本的な問題を確実に解けるようにしましょう。
③予備校間で解答が割れる問題は飛ばそう
工業簿記・原価計算では解釈の違いにより、予備校間で解答が割れる問題の出題が続いています。合否に影響を与える問題ではないため、このような問題は深追いする必要はありません。
次回は工業簿記について解説いたします。