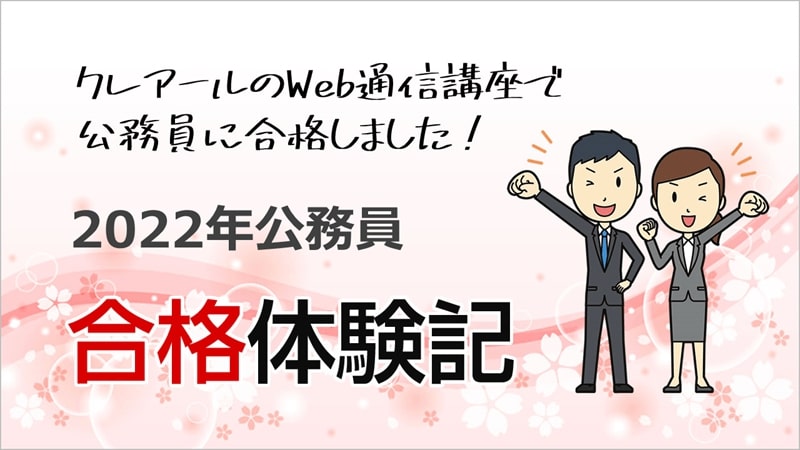■A.Yさん[最終合格先:東京都Ⅰ類B(心理)]
■出身校:神戸大学
■合格時の年齢:21歳
公務員を目指したきっかけや、志望された理由をお聞かせください
大学で心理学を専攻していて、漠然とカウンセラー系の仕事に就きたいと元々考えていました。心理職は民間だと非正規雇用が多いため、正規雇用の心理職に就きたいと思うと、公務員が最適に思えました。大学院に進学してからの就職も考えましたが、心理職として早く働きたいという思いが強まったので、心理系公務員を目指すことにしました。
クレアールを選んだ理由をお聞かせください
決め手は受講料がリーズナブルな点でした。自分のアルバイト代で払える予備校にしようと決めていたからです。インターネットで情報収集すると、料金プランがシンプルでわかりやすく、その上心理系公務員に強いと書かれていたので魅力を感じました。同時期に予備校を探していた大学の友人から、部活の先輩が通っていたと教えてもらったことも、安心材料になりました。
クレアールを利用してよかったことがあればお聞かせください
1点目は、学習計画を自由に立てることができた点です。私の場合は大学3年の秋まで部活が忙しかったので、引退してから本腰を入れて勉強しようと思っていました。進捗を聞かれたり他の受講生と比較されたりなどがなかったため、自分のペースで焦らず勉強を進めることができました。2点目は担任の先生のサポートが充実している点です。メールで色々疑問に答えてくださったり、面接対策を何度も実施してくださりました。
筆記試験対策にあたって、大変だったことや工夫されたことをお聞かせください
筆記試験対策で大変だったのは、二次試験の専門記述対策です。当然かもしれませんが、択一形式よりも記述形式の方が、求められる知識量が多いかと思います。クレアールの講義を受講してインプットした情報を、自分のものになるよう整理する過程に時間をかけました。私は新しいノートを1冊用意し、主にクレアールのテキストを参考にしながら、ジャンルごとに自分の言葉で整理しました。理論の名前をみたときにその説明が文章で書けるようになるまで、知識の定着に力を入れました。他に工夫した点としては、数的処理などでわかると思った分野は動画を見る前に問題に取り掛かるようにしたことです。限られた時間のなかで、どこに時間をかけるべきか考えるようにしていました。
面接対策の進め方や、本番に臨むうえで工夫したことや力を入れたことがあればお書きください。
面接対策の進め方としては、まず主に大学時代に力を入れたエピソードと、自分の長所短所などを書き出しました。次に志望先の面接で聞かれることを、クレアールの担任の先生やインターネットから情報収集し、それに対して1問1答で答えらえれるようにしました。
最も意識したことは、(過去ー現在ー未来)の整合性が取れた話をすることです。短所に基づく挫折経験(過去)と、大学時代に力を入れたこと(現在)と、就職後に自分にできる貢献(未来)などをそれぞれ結び付けられるようにしました。面接当日には、自分より面接マナーがしっかりしていて、むしろやりすぎなのではないかと思えた受験生を数名見かけたので、「よほど中身に自信がないんだろうな」と考えるようにしました。それくらい、自分に自信をもって臨むようにしました。
今回受験された上で、同じ受験先をこれから受ける後輩の方々にアドバイスやメッセージがございましたら、お聞かせください。
東京都庁の心理職の面接は、話に聞いていた通り、矢継ぎ早にどんどん質問が飛んでくるような感じでした。卓球のラリーのように、一つ一つの質問を確実に返すことが有効かと思います。また、「もし東京都に就職しないことになっても、一生懸命頑張ってください」と面接中に怖いことを言われましたが、特に関係ないようなので気にせず頑張っていただきたいと思います。
最終合格後の採用面談はオンラインでしたが、おそらく席次順に、ほぼ確認作業のような形で形式的に進められました。質問内容は短所や周囲からの評価など、オーソドックスな質問が多かったです。
兵庫県庁の心理職(特別枠)では、「兵庫県の児童相談所は何か所あると思いますか」とクイズのような質問が印象的でした。念のため志望先の自治体の基本情報を押さえておくと良いかと思います。
国家総合職については、1次の筆記試験でかなり時間が余るので、終わって暇になったら途中退出した方が体力消耗しないかなと思います。官庁訪問で私は厚生労働省を訪問しましたが、他の省庁の受験生の話とは異なり、拘束時間が短く事前の囲い込みも個人的には感じられませんでした。『ソファがふわふわだと選考が順調な証拠』、などは、厚生労働省に関しては都市伝説だと感じました。ただ、自分が総合職としてどの施策に力を入れたいか、というポイントはプレゼンできるレベルのものを2、3個しっかり用意していくべきだと思います。