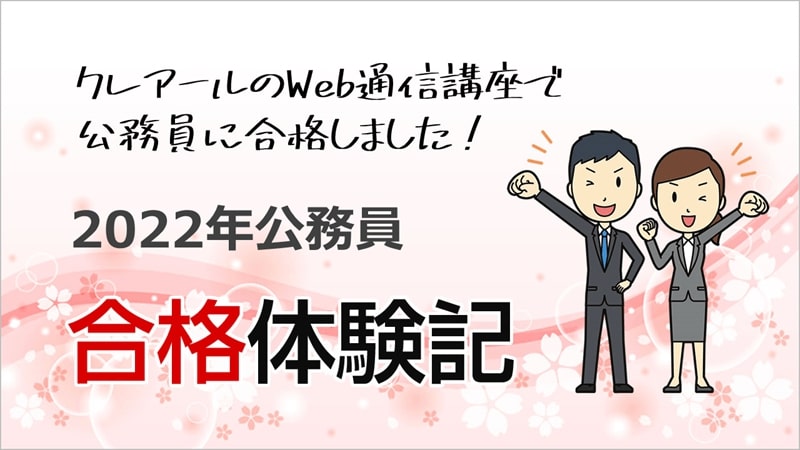■おひるねさん[最終合格先:国家総合職(法務省保護局 )]
■出身校:早稲田大学
■合格時の年齢:22歳
公務員を目指したきっかけや、志望された理由をお聞かせください
もともと更生保護の分野に興味があり、大学生活のなかでその分野で働きたいという思いを強めたからです。また、公務員系だけでなく民間企業のインターンや説明会に参加する中で、自分の進路として、最もしっくりきたのが心理系の公務員でした。
同時に、院進という選択肢も考えたのですが、①心理学専攻であるものの、そこまで心理職であることにこだわりがなかったこと、②所属ゼミに社会人の方が多く在籍されており、私も(チャンスがあればですが)働き始めて大学院で研究活動をできればいいなあと思ったこと、から学部卒で就職することにしました。
クレアールを選んだ理由をお聞かせください
①心理系公務員に内定した先輩がおすすめされていたこと、②しけしんの著者である高橋先生の心理学を受講できること、③全てオンラインで受講できること、が決め手でした。 また、他社の説明会や相談会に参加して比較する中で、心理系に絞るならクレアールが良さそうだな、と思ったことも大きな理由です。
試験までまだ日数があって迷っている方は、とりあえず生協主催の相談会に参加してみたり、いろいろ資料を取り寄せてみたりするのもおすすめです。
クレアールを利用してよかったことがあればお聞かせください
特によかったと感じていることを2つ挙げたいと思います。 1つ目は「オンラインで完結すること」です。私の家から校舎は、通えなくもないが遠い、という距離だったため、講義はもちろん、添削や面接練習も全てオンラインで受けられるのはとてもありがたかったです。このご時世でなければ、公開収録や模擬面接等で校舎に行く機会もあるもしれませんが、家が遠かったり、課外活動が忙しかったりして、それができないからといって不安に思う必要はないと思います。ただし、積極的に自分から相談したり、質問したりする、という姿勢は大切だと思います。 2つ目は「担任制で、指導経験の豊富な先生に気軽に相談できること」です。模擬面接や、面接カードのチェックなど本当にお世話になりました。また、面談の中で、志望先に関する情報も沢山教えていただきました。(面接カードの添削は早めにお願いしましょう…!)
筆記試験対策にあたって、大変だったことや工夫されたことをお聞かせください
大変だったことは、数的処理、時事、そして心理学択一・記述の対策でした。
①数的処理
中学入試の算数のような問題が苦手だったので、苦しみました。
対策する前は、センター試験の数学そこまで苦手じゃなかったし大丈夫なはず、と思っていたのですが、テキストを開いて解いてみて、「あれ〜解けない〜〜」となりました。そのため、大学3年の10月までにテキストにある例題を1周し、問題のパターンを把握するようにしました。10月以降は過去問フォーカスを用いて、とにかく毎日解くようにしていました。
②時事
最も勉強の方法が分かりませんでした&勉強を始めるのが遅すぎました。日頃からニュースを見ておくことが大事だとは思いますが、やはり出題傾向はあります。そこで講義やレジュメが役立ちました。特に直前期は、朝の支度をしているときに講義動画を流したり、寝る前に速攻の時事とレジュメをつき合わせて眺めたりしました。それでも分からない問題は沢山あったため、ある程度で諦める、ということも必要かもしれません。簡単な問題が出たときに落とさないようにすることが大切な気がします。
③心理学択一・記述
主に、講義動画と過去問(試験に出る心理学、過去問フォーカス)を用いて学習を進めました。
講義動画の使い方についてですが、1周目は、大学のオンデマンド講義の要領で、テキストにメモをしながら試聴しました。そして、講義の音声ファイルをダウンロードしてスマホに取り込み、得意な分野は2~3周、苦手な分野は3~4周聴きました。特に直前期は、移動時間や、家事をする時間、大学の休み時間など、耳が空いている時間はできるだけ聴くようにしていました。
また、過去問について、択一は2〜3周、記述は1周しました。択一問題で初めて知った知識は、テキストに書き込むことを心がけていました。また、記述問題は、3分の1くらいは時間を測って自分で書いて練習し、残りは、自分で書くとしたらどう書くか想像しつつ、知識を箇条書きにしたり、模範解答を読み込んだりしました。
面接対策の進め方や、本番に臨むうえで工夫したことや力を入れたことがあればお書きください
面接対策では、とにかく場数を踏んで自分のアピールポイントやアピール方法を確立していくこと、を心がけていました。そのため、クレアールの模擬面接だけでなく、大学のキャリアセンター開催の面接練習にも参加しました。また、(必ずしもする必要はないと思いますが)大学3年の1月までは、サマーインターンの選考や本選考で、民間企業の面接も受けていました。
民間企業と公務員(特に心理や福祉系の公務員)では、志望動機やアピールすべきポイントは全く異なりますが、実際に面接を受ける中で、「自分」をうまく伝えられるエピソードや、面接のお作法を知ることができたのは良かったです。また、受けた企業は少ないのであまり偉そうなことは言えませんが、公務員という選択によって切ることになった「民間企業で働く」という選択肢も検討できたのは良かったと思います。(本当にわずかな検討ではありましたが…。)
あとは、面接に関するアドバイスで、よく、「素直に、ありのままの自分を伝えるのが良い」という記述を見かけます。これは正しいのですが、就活生にとって要注意なアドバイスなのではないかと思っています。私は、この言葉を文字通り受け取り、初期に受けた面接(民間のサマーインターン選考)でことごとく失敗しました(笑)。そもそも面接に慣れていなかったのもあると思いますが、ありのまますぎました。素直に自分の人柄や経験を伝えるのは大切なことですが、不利になるようなことをわざわざ言ったり、過度に謙虚になったりする必要はありません。嘘をつくのではなく、背伸びをしすぎることもなく、礼節を弁えたうえで、しっかり自分を売り込みましょう! と、言葉にするのは簡単ですが、私はとても難しいと感じたので、クレアールの担任の先生に相談しつつ、早めに!!!対策を始めるのが良いと思います。
これから公務員試験の受験をお考えの方にアドバイスやメッセージなどがございましたら、お聞かせください
私は受験前、いろいろな体験記を読みました。しかし、たまに違うことが書いてあったり、真似しようとしてもあまり自分に向いていなかったりして、「どうすればいいの〜〜」となることがありました。
例えば、“シケシン”の体験記にもある、まとめノートづくりです。私はまとめノートを作成するのが苦手でした。細かい知識にこだわってしまって、全く前に進まないからです。そこで、思い切ってまとめノートづくりは諦め、まずは、講義とテキストを自分のものにする、と決めました。すると、別の問題が生じました。「映像講義、どう頑張ってもスライドに注意が向いてしまう問題」です。先生の口頭での説明を聴き逃していることが多く、問題集を解こうにも知識不足、ということがありました。そこで、「聴く」方法を採用しました。
これは一例ですが、自分に合う方法を模索し、確立して(ときにある程度で諦めて確立したことにして)、継続することが、遠回りなようで近道なのではないでしょうか。
最後に、公務員受験を考える上で、倍率を見て無理では?となったり、筆記試験の勉強が捗らず焦ったりすることもあると思います。それでも諦めず、最後まで足掻くことが大切です。試験会場に向かう電車の中で、試験の休み時間で、確認したことが意外と出題されたりします。試験の始まる直前に、これだけ頑張ったんだから大丈夫、これで落ちたらこの仕事に向いてなかっただけ、と思えるくらい、最後の最後まで準備をすることが合格につながると思います。ただし、適度な息抜きは大切です。からだを大切に、後悔のないよう、頑張ってください。皆さんが納得のいく進路を選ぶことができるよう、応援しています!