公務員を目指している方の中には「特別区」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。この記事では、公務員試験の特別区について、日程や試験科目、東京都庁との違い、試験内容や対策方法について解説します。合格に必要な内容を徹底解説しているので、特別区で働きたい方はぜひ最後までご覧ください。
公務員試験の「特別区」とは?
公務員試験の「特別区」とは、東京23区のことを指します。
23区はそれぞれが東京の中核を担う基礎自治体として独立して存在しており、地方自治体と同程度の機能を有しています。特別区で働く公務員は地方公務員となり、各区の地域特性に応じた業務に取り組むことになります。
公務員試験でも特に人気が高い受験先の1つです。
特別区と東京都庁の違い
| 特別区 | 東京都庁 | |
|---|---|---|
| 公務員の種類 | 地方公務員 | 地方公務員 |
| 仕事内容 | 「市役所」のようなイメージ。基礎自治体の職員として、区役所等に勤務する。区民にとって最も身近な行政機関としての役割を果たしており、住民との距離感が近いのが特徴。東京都庁と比べると、区民と直接触れ合う仕事が多い。 | 「県庁」のようなイメージ。広域自治体の職員として、東京都全体が抱える課題の解決に取り組んでいる。特別区と比較すると、住民との距離感が遠く、担当する仕事の範囲も広い傾向がある。 |
特別区と東京都庁で働く公務員はどちらも地方公務員に分類されます。
しかし仕事内容はやや異なり、都庁が都全体に関わる課題に対してアプローチするのに対し、特別区の担当はあくまで各区の範囲に限られます。特別区の方が対応範囲が狭い分、区民と近い距離で接する業務が多い点が特徴です。
特別区で働く魅力
特別区で働く魅力は、大都市東京の中枢を担いながらも、約950万人の区民の生活を直接支援できることです。
特別区では23区それぞれに、地域特性に応じた先進的でダイナミックな取り組みが求められています。特別区職員として、その一翼を担えることは、大きなやりがいに繋がるでしょう。
また特別区は基礎自治体としての役割も果たしているため、区民の要望などに素早く対応でき、その反応を直に見ることができる点が特徴。大都市でありつつも、住民との距離が近い特別区は、他の自治体や東京都庁とは一線を画しており、唯一無二の魅力を持った職場といえるでしょう。
特別区で働く公務員の仕事内容

特別区で働く公務員の仕事内容は、所属する部署によって大きく異なります。この章では、各部署の概要や業務内容について紹介します。なお、各部署間の業務の分け方や名称は、区によって違う場合もあるので、志望する区のHP等で確認しましょう。
部署
総合政策部
主な業務:企画・計画・評価の取りまとめ など
所属課例:政策企画課、財政課、広報課、秘書課、情報システム課、危機管理課
総合政策部は、区の基本構想や総合計画などを策定し、その実現のため、予算編成、組織全体の進行管理、行政評価等に取り組む部署です。政策の策定や管理等の区政全般に関わる業務を中心に担います。区長と直接接する機会の多い秘書課や、各施策の予算管理等を担う財政課等もここに含まれることが多く、区の中枢を担っている部署の一つです。
総務部
主な業務:区政運営上の事務 など
所属課例:庶務課、納税課、財政課、職員課
総務部は、主に区政の運営上の事務を行う部署です。例えば、職員の人事管理・人材育成等の人事業務や、区役所の広報活動、庶務業務などが主な役割です。
納税課を除けば、区民と直接接することは少なく、組織の内政に関わる業務がメインとなrるので、他部署と接する機会が多くなります。区役所全体の調整業務を行うことも多く、縁の下の力持ちともいえる存在です。
区民生活部
主な業務:住民の届け出管理、地域文化や産業等の振興 など
所属課例:区民課、地域振興課、産業振興課、文化観光課、スポーツ課
区民生活部は、戸籍、住民登録、地域・産業振興など、区民生活に密接した業務を行う部署です。区民と直接接する機会が多く、身近な存在として頼りにされる仕事です。
例えば、区役所の窓口に行った際に見かける職員の多くが区民生活部の職員です。区役所で働く公務員として、最もイメージしやすい部署といえるでしょう。
保健福祉部
主な業務:各種健康保険や障害者・高齢者・生活困窮者の支援 など
所属課例:保健健康課、生活支援課、障害福祉課、長寿支援課、保険年金課、介護保険課
保健福祉部は、区民の福祉や健康保持・増進に関する業務を行う部署です。地域の生活衛生面に関する管理や、区民の健康を守るための活動、生活に困っている方々の支援等を主に行います。「ケースワーカー」もこの保健福祉部の仕事の1つです。
子ども未来部
主な業務:子ども関連の施設(保育園・児童施設)運営や管理など
所属課例:子育て支援課、保育課
子ども未来部は、主に児童福祉に関する施策や活動を行う部署です。子育て中の家庭への支援や、地域の子育てコミュニティの育成、地域の児童福祉に関する行政活動全般を担当しています。
保育所の待機児童問題や、子育て参加のためのワーク・ライフバランス実現に向けた取り組みも、子ども未来部が担当していることが多いです。
環境部
主な業務:交通安全・環境整備・廃棄物資源に関する業務など
所属課例:交通対策課、環境課、くらし安全課
環境部は、主に地域が抱える環境問題の解決に向けた施策・活動を担当する部署です。身近な事例では、ゴミの収集・運搬や資源回収が挙げられます。他にも、地球温暖化への対策や、循環型社会の形成に向けた取り組み、再生エネルギーの利用促進など、地域の環境を守るための業務を行っています。
都市整備部
主な業務:公園・道路・建物を含む土地整備に関する業務など
所属課例:都市計画課、みどり公園課、道路課、建築指導課
都市整備部は、地域のまちづくりに関する施策・活動を担当している部署です。地域の都市計画の策定や、道路や橋・公園や公共施設などのインフラ整備、防災対策など、都市の基盤づくり等を行います。
自分が担当した仕事の結果が、直接目に見える形となって現れることも多く、仕事に対するやりがいを感じやすい部署の一つです。
その他
教育委員会:区立学校や図書館などの管理・運営 など
選挙管理委員会 選挙の管理・運営 など
会計課:区政運営上の会計事務 など
監査委員会:区政運営上の各種監査事務の確認 など
議会事務局;議会の運営に関する事務 など
他にも、区政の中で独立した組織として、「会計課」や「監査事務局」などがあります。
これらの機関は、区長への権限集中を防ぎ、行政運営の公正を保つため、区長から独立した機関であるべきとされています。そのため、特別区の組織でありつつも、独立した部署として位置づけられ、区長から独立して業務を行っています。
職種
| 職種 | 仕事内容 |
|---|---|
| 事務 | 区の基本構想や各分野の事業計画の策定と実施、施設の管理・運営、窓口業務などを行います。幅広い部署で活躍するジェネラリストです。 |
| 土木(土木造園) | 道路や橋、河川の整備・維持など都市基盤の形成など、地域住民や関係機関と連携して、まちの生活基盤を整備する仕事です。 |
| 造園(土木造園) | 公園や児童遊園の新設・改修の計画立案、設計・維持管理などを担当します。緑化の普及・啓発に向けたイベント・講座も行います。 |
| 建築 | 建築基準法に基づく審査や指導・公共施設の設計、都市計画の策定を行います。地域住民と意見交換しつつ、「まちづくり」に携わる仕事です。 |
| 機械 | 設備機械のプロフェッショナルとして、公共施設における建設設備の中でも、機械関係に特化して、設計や施工、維持を担当します。 |
| 電気 | 地域の電気系統の安全環境を整備するため、電気関係に特化して、設計や工事監理を行います。 |
| 福祉 | 幅広い世代の住民と直接関わり、その人にあった福祉サービスを提供して、地域住民の生活支援を行います。 |
| 心理 | 区の福祉施設等に勤務し、心理の専門知識を活かして、子どもや保護者からの相談対応や、面接・心理査定などを担当します。 |
| 衛生(衛星監視) | 食品衛生の対策、診療所や薬局の監視指導、大気汚染や交通騒音の調査・分析、飲用水やブールの水質検査などを担当します。 |
| 化学(衛星監視) | 排ガス、排水管理など、化学技術を活用しながらさまざまな調査を行い、公害防止に向けた取り組みを行います。 |
| 保健師 | 区民の健康を守るため、心や体の健康相談や健康教育、感染症の予防や対応に取り組みます。 |
| ICT(事務) | 区民の利便性を高めるため、ICTに関する知見を活用し、行政のデジタル化の推進に向けた業務を担います。 |
特別区に設けられている職種や仕事内容は上記のとおりです。一口に特別区職員といっても、多様な職種があり、それぞれのスキルや経験に応じた職種を目指すことができます。
なお、事務以外の仕事の多くは専門職となっており、出身学部や資格・経験等の受験資格が設けられています。職種ごとに試験日や受験申し込み期間も異なるため、必ず最新の情報を確認するように注意しましょう。
特別区で働く公務員の給与
| 23区 | 平均給与額 |
|---|---|
| 足立区 | 374,521円 |
| 荒川区 | 380,326円 |
| 板橋区 | 370,214円 |
| 江戸川区 | 374,851円 |
| 大田区 | 376,239円 |
| 葛飾区 | 364,656円 |
| 北区 | 375,186円 |
| 江東区 | 380,469円 |
| 品川区 | 368,226円 |
| 渋谷区 | 369,627円 |
| 新宿区 | 377,604円 |
| 杉並区 | 373,070円 |
| 墨田区 | 388,961円 |
| 世田谷区 | 378,102円 |
| 台東区 | 383,289円 |
| 中央区 | 359,544円 |
| 千代田区 | 361,655円 |
| 豊島区 | 381,345円 |
| 中野区 | 373,707円 |
| 練馬区 | 374,880円 |
| 文京区 | 367,993円 |
| 港区 | 379,970円 |
| 目黒区 | 377,136円 |
特別区で働く公務員の平均給与月額は上記のとおりです。
特別区人事委員会「令和6年 職員の給与等に関する報告及び勧告の概要」によると、令和6年8月時点で平均月給は約40万円程度となっています。
なお、地方公務員の給与は自治体によって異なっていますが、23区の職員は全てが同一の基準で支給されています。区によって平均支給月額に差があるのは、職員の年齢構成や手当の支給状況に差があるためです。
地方公務員の給与は毎年改定されており、特別区でも、人事委員会による勧告により、毎年の具体的な給与改定方針が決定されます。
特別区の公務員試験の内容

この章では、特別区の公務員試験の内容について解説します。
特別区の採用試験の概要を理解し、合格に向けた道のりをイメージしましょう。
採用されるまでの道のり
特別区職員として採用されるには、まず、特別区人事委員会が実施する筆記試験・面接試験に合格し、採用候補者名簿に登載される必要があります。その後、採用候補者名簿をもとに、特別区人事委員会が各特別区に採用候補者を提示して、区の面接が実施されます。この面接に合格すれば内定となります。
特別区人事委員会から特別区への採用候補者の提示は、原則として名簿の高得点順に行われます。そのため、国家公務員の官庁訪問のように、必ずしも希望する区の面接が受けられるわけではありません。なお、提示後の面接で不合格となった場合は、他の区へ再提示されるのを待つことになります。
採用区分と受験資格
特別区職員の採用区分と受験資格は下記のとおりです。
なお、年齢は試験が実施される翌年の4月1日を基準として算出されます。
受験資格は、さらに細かい補足があり、年度により変更される可能性があります。近年では、新たに「就職氷河期世代」選考が設けられる等、試験区分自体が大きく変更される場合もあるため注意が必要です。
受験する際は、必ず特別区人事委員会のホームページで最新の情報を確認しましょう。
Ⅰ類(春試験)
試験・選考区分:事務・土木造園(土木)・土木造園(造園)・建築・機械・電気
主な受験資格:22歳以上32歳未満の人など
試験・選考区分:福祉・衛生監視(衛生)
主な受験資格:22歳以上30歳未満の人で、必要な資格・免許を有する人など
試験・選考区分:心理
主な受験資格:40歳未満の人で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)の心理学科を卒業した人、またはこれに相当する人など
試験・選考区分:衛生監視(化学)
主な受験資格:22歳以上30歳未満の人など
試験・選考区分:保健師
主な受験資格:22歳以上40歳未満の人で、保健師免許を有する人など
Ⅰ類(秋試験)
試験・選考区分:土木造園(土木)・建築
主な受験資格:22歳以上32歳未満の人など
Ⅲ類
試験・選考区分:事務
主な受験資格:18歳以上22歳未満の人など
試験・選考区分:障害者を対象とする採用選考(事務)
主な受験資格:18歳以上61歳未満の人で、身体障害者手帳の交付を受けている、などの項目を満たす人など
経験者
試験・選考区分:選考区分1級職【事務(一般事務)・事務(ICT)・土木造園(土木)・建築・機械・電気・福祉・児童福祉・児童指導・児童心理】
主な受験資格:61歳未満で、民間企業等における業務従事歴が、試験受験日の属する年度の末日において、直近10年中4年以上ある人など
試験・選考区分:選考区分2級職(主任)【事務(一般事務)・事務(ICT)・土木造園(土木)・建築・福祉・児童福祉・児童指導・児童心理】
主な受験資格:主な受験資格:61歳未満で、民間企業等における業務従事歴が、選考受験日の属する年度の末日において、直近14年中8年以上ある人など
試験・選考区分:選考区分3級職(係長級)【 事務(ICT)・児童福祉・児童指導・児童心理】
主な受験資格:61歳未満で、民間企業等における業務従事歴が、選考受験日の属する年度の末日において、直近18年中12年以上ある人など
就職氷河期世代
試験・選考区分:事務
主な受験資格:38歳以上54歳未満の人など
試験日程(Ⅰ類(事務)の場合)
【Ⅰ類(事務)の場合】
告示:3月中旬
申込受付:3月中旬〜4月初旬
1次試験:4月下旬〜5月初旬(例年4月最終週又は5月1周目であることが多い)1次試験合格発表:6月後半
2次試験・7月中旬
最終合格発表・8月初旬
特別区(1類(事務))の試験日程は上記のとおりです。
例年、4月下旬〜5月上旬に筆記試験が行われ、面接試験を経て、8月初旬に最終合格者が発表されます。なお、前述のとおり、最終合格発表後に各特別区の面接が開始されます。そのため、実質的には8月以降も試験が続くことに注意が必要です。
また、筆記試験の時期は年度によって変更される場合があります。試験日によっては、他の受験先との併願可否にも影響が出るため、必ずホームページ等で最新の情報を確認しましょう。
試験内容(Ⅰ類(事務)の場合)
| 1次試験の内容 | 詳細 |
|---|---|
| 教養試験(2時間) | 一般教養についての五肢択一式(48 題中 40 題解答) ①知能分野(28 題必須解答) 文章理解(英文を含む)・判断推理・数的処理・資料解釈及び空間把握 ②知識分野(20 題中 12 題選択解答) 人文科学4 題(倫理・哲学、歴史及び地理)・社会科学4 題(法律、政治及び経済)・自然科学8 題(物理、化学、生物及び地学)・社会事情4 題(社会事情) |
| 専門試験(1時間30分) | 一般行政事務に必要な基礎知識についての五肢択一式(55 題中 40 題選択解答) 出題分野:憲法・行政法・民法①[総則・物権]・民法②[債権・親族・相続]・ミクロ経済学・マクロ経済学・財政学・経営学・政治学・行政学・社会学 |
| 論文(1時間20分) | 課題式(2題中1題選択解答)字数は 1,000~1,500 字程度 |
| 2次試験の内容 | 詳細 |
|---|---|
| 口述試験 | 人物及び職務に関連する知識等についての個別面接 |
特別区の試験は、筆記試験である一次試験と、面接試験である二次試験に分かれています。
一次試験では「教養試験」「専門試験」「論文試験」が実施されます。いずれも受験生が問題を選べる「選択式」となっていることが大きな特徴です。
二次試験では、一次試験合格者を対象に30分程度の個別面接が実施されます。面接の冒頭で、必ず3分間の自己PR(挑戦したい仕事、強み、志望動機など)が求められるため、事前にプレゼンテーションに向けた準備をしておきましょう。
合格基準
特別区試験では、合否判定における配点比率が明かされていないため、合格基準ははっきりとは分かりません。しかし、受験生の過去の傾向から、択一試験(教養と専門)の合格ラインは5割程度といわれています。また、択一試験が高得点であったにも関わらず、最終的に不合格となった受験生も少なくないため、2次試験(口述試験)の配点がかなり高いことも予想されます。
いずれにせよ、特別区の採用試験は、相対的に合否判定がされる相対試験です。あらかじめ採用人数が決まっており、得点が高かった者から優先的に採用されます。そして、合格者の各区への提示も、得点順に行われます。第一志望の希望区へ採用されるためにも、「最終合格」ではなく、「上位合格」を目標とした対策を行うことが重要です。
試験倍率(Ⅰ類(事務)の場合)
| 採用予定数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 1,312名程度 | 6,868名 | 3,035名 | 2.3倍 |
| 2023年度 | 1181名程度 | 7668名 | 3013名 | 2.5倍 |
| 2022年度 | 983名程度 | 8417名 | 2308名 | 3.6倍 |
| 2021年度 | 874名程度 | 9019名 | 1881名 | 4.8倍 |
特別区試験の試験倍率推移(Ⅰ類(事務)の場合)は上記のとおりです。
近年、倍率が著しく低下傾向にあることが分かります。しかし、これは特別区の人気が低下しているためではなく、定年退職者の増加等により、採用予定数が毎年大きく増加していることに起因しています。
特別区で働くことを希望している受験生にとっては比較的、合格しやすいタイミングといえるでしょう。
特別区の公務員試験の対策方法
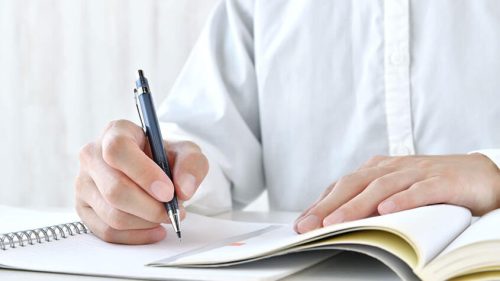
特別区の公務員試験では各試験ごとに進めていく必要があります。それぞれ解説していきます。
教養試験対策
特別区の教養試験は、必須科目である「知能分野」と、選択科目である「知識分野」から構成される択一試験です。「知能分野」は、「数的処理(数的推理、判断推理、空間把握、資料解釈)」と「文章理解(現代文、英文)」で構成されており、「知識分野」は「人文科学」「社会科学」「自然科学」「社会事情」で構成されています。
教養試験対策では、「知能分野」が全て必須解答科目で配点比率の7割を占めているため、こちらを優先的に行うのが効果的です。
一方で、「知識分野」は、20題中12題を選択して解答する選択式であり、配点比率は3割程度しかありません。特に「社会科学」と「社会事情」の問題は、専門試験の知識で十分に対応できる可能性が高いです。
専門試験対策
特別区の専門試験は、50題中40題を選択して解答する、選択式の択一試験です。
「憲法」「行政法」「民法①[総則・物権]」「民法②[債権・親族・相続]」「ミクロ経済学」「マクロ経済学」「財政学」「経営学」「政治学」「行政学」「社会学」の11科目55題(1科目5題)で構成されており、ここから40題を選択して解答します。
特別区のみを受験する方以外は、他の試験種と共通する科目を選択するのがおすすめ。特に、多くの公務員試験で必須となる「憲法」「行政法」「民法①[総則・物権]」「民法②[債権・親族・相続]」「ミクロ経済学」「マクロ経済学」の6科目は重点的に対策しましょう。これら6科目30題を選択することを基本としつつ、自分の得意不得意や、当日の問題の難易度に応じて、残り10題を選択するのが効果的です。
論文対策
特別区の論文試験は、提示された2つの課題から、1つを選択して解答する選択式の論述試験です。与えられた課題に沿って、制限時間90分で、1000字以上1500字程度の小論文を書くことが求められます。
例年、社会的に問題となったテーマを取り上げたうえで、「特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。」と問いかける形で出題されるのが大きな特徴です。
対策としては、ニュース等で話題となった時事問題を押さえることや、特別区等の自治体で行われている施策について調べておくことが挙げられます。
ただし、論文は知識だけで書くことは非常に困難です。事前の知識対策以上に、予備校等の添削講座等を活用して、何度も「書く練習」をしておくことが重要になるでしょう。
口述試験対策
特別区の口述試験は、受験生1人に対して、面接官3人で実施される個別面接です。
30分程度の長時間にわたり実施され、冒頭の3分間で面接カードに沿った形での自己PRが求められます。また、回答に対する深堀りや「他に?」といった突発的な質問がされることが多い試験です。一人で対策するのが非常に難しいため、積極的に予備校の面接対策等を活用することをおすすめします。
例えば、クレアールの面接対策では、「全16テーマの面接対策講義」で考え方や実例が学べることに加え、面接シートの添削や講師による模擬面接も用意されています。口述試験は、対策方法による差が顕著に現れる試験です。早い時期から、講師にチェックしてもらいながら、確実に力をつける方法が合格への一番の近道です。
公務員試験で志望する特別区を選ぶポイント
志望する区は、地元など自分に何かしらの縁がある区や、自分が興味のある施策に取り組んでいる区を選ぶのがおすすめです。ただし3つの希望区を選ぶ際は、志望者が多いといわれている人気区(千代田区、港区、文京区、渋谷区、杉並区、豊島区)のみにしてしまうと声がかからなくなる可能性があるため、バランスを考えて選択しましょう。また、江戸川区は単願のみでしか出願できないため、3つの区に入れないよう注意が必要です。
どうしても志望区が見つからないという方は、23区合同説明会へ参加してみましょう。それぞれの区がブースを設けて、各区の特色ややりがい、業務内容について説明してくれます。職員のリアルな声も聞くことができるため、面接対策で役立つ可能性も高いです。人気区では、ブースに行列ができることもあるため、早めの来場を心がけましょう。
特別区の合格には効率的な対策が必要!
特別区は、公務員試験受験生からの人気も高く、非常に魅力的な仕事です。
しかし、魅力的な仕事だけに、採用までの道のりは険しく、一人で突破するには相当な努力が必要になります。
もし、本気で特別区で働きたいと考えている方は、予備校の利用を検討することをおすすめします。特にクレアールは、長年の指導実績で蓄積されたノウハウと、面倒見の良いサポートで、合格への最短ルートへ導いてくれます。少しでも合格率を上げたい場合は、予備校を選択肢の1つとして考えた上で、自分にあった方法を選びましょう!




