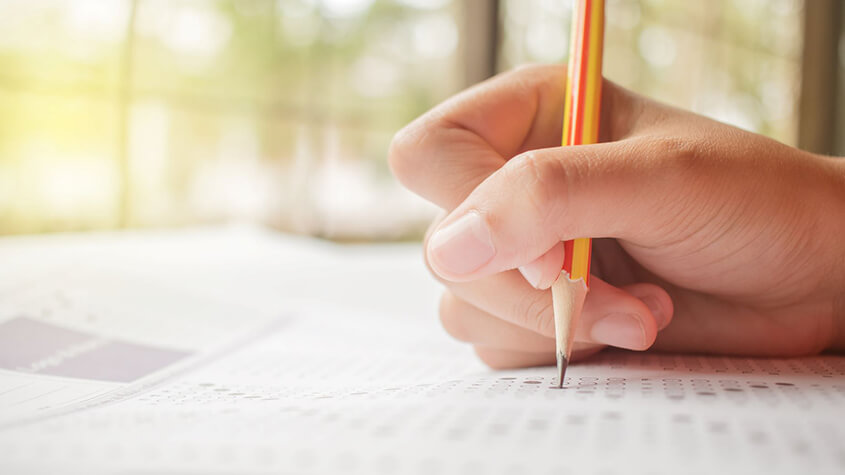地方公務員の試験概要はどのようなものなのでしょうか。この記事では、地方公務員の種類や仕事内容、試験内容や難易度、日程など網羅的に解説します。試験対策のポイントなど、受験生が気になるポイントも紹介するので、志望先選びや試験対策に迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
地方公務員とは?

地方公務員とは、都道府県庁や市町村などの地方自治体に勤務する職員のことです。県庁や市役所で勤務する事務職員だけでなく、警察官や消防官などの公安職も含まれます。
国家公務員と比べると、住民との距離が近いのが特徴で、住民生活を直接的に支える役割を担います。
地方公務員になるには、各自治体が独自に実施する地方公務員試験に合格することが必要です。試験内容は自治体によって異なるため、志望先に合わせた対策を行いましょう。
地方公務員の種類
地方公務員の主な種類は、次のとおりです。
都道府県庁職員・政令都市職員・特別区職員・市町村職員・警察官・消防官
など
地方公務員には、行政職、技術職、心理・福祉職、専門職、公安職など様々な職種があります。具体的な仕事内容は職種や勤務する機関によって大きく異なりますが、いずれの職種も行政サービスを提供し、地域住民の生活を支えることが目的です。
たとえば、都道府県庁職員は広域的な行政サービスを担当していますが、市町村職員は地域住民の生活に直結するサービスを担当します。
また、技術職や心理・福祉職、専門職が担当するのは、特定の専門知識を活かした業務です。さまざまな職種が連携し、地域社会を発展させ、住民の生活を支えるために尽力しています。
勤務先による地方公務員の仕事の違い
ここでは、勤務先による地方公務員の仕事の違いを解説します。都道府県、政令指定都市、特別区、市町村に分けて見ていきましょう。
都道府県庁職員
都道府県庁職員は、都道府県を管轄し市町村の枠を超えた広域的な業務を担当します。たとえば、教育、福祉、保健、道路、環境保全など多岐にわたる業務に携わっており、国や関連機関との連携や調整を行いつつ、地域社会の発展に貢献しています。
また、災害時の迅速な対応や住民の安全確保、復旧支援なども、都道府県庁職員の重要な業務です。
政令指定都市職員
政令指定都市とは、政令で指定する人口50万以上の市のことを指します。大規模な人口を抱えるため、政令指定都市の業務は、通常の市町村よりも規模が大きく事務権限も大きい点が特徴です。
政令指定都市職員は、一般的な市町村職員の業務に加え、通常であれば都道府県庁が担う事務も一部担当しています。たとえば、児童福祉、母子保健、食品衛生など健康や福祉の事務、土地区画整理事業や都市計画など、さまざまな業務に携わっています。
特別区職員
特別区とは、東京23区のことを指します。区によって業務内容は異なるものの、いずれの特別区職員も、区民の生活に直結する業務を行っています。
たとえば、区の基本構想の策定や、区民と直接接する窓口業務、子育て支援のための児童福祉業務などはすべて特別区職員の業務です。
区長公選制や区議会、条例制定権、課税権などを持っている点で、政令指定都市の業務とは大きく異なります。
市町村職員
市町村職員は、地域住民に密着した行政サービスを提供しています。主な業務としては、住民登録、税務、福祉、教育、環境保全、地域の振興や観光の推進、災害対策などがあります。
たとえば、住民票や戸籍の管理、税金の徴収、ゴミ収集の管理、妊娠・出産や子育ての支援などを担当し、市民生活を直接的に支えるのが市町村職員の役割です。地域住民とのコミュニケーションを通じて、住みやすい環境の実現を目指します。
職種による地方公務員の仕事の違い

ここでは職種による地方公務員の違いを説明します。行政、技術、心理・福祉、専門職、公安職など、5つの職種について見ていきましょう。
行政職
行政職は、行政事務全般を担当しており、業務内容は多岐にわたります。たとえば、窓口対応や電話応対、証明書類の発行、書類・資料の作成、データの入力などの行政サービスを行う一方で、施策の企画立案など自治体の未来を切り開く仕事も担当します。
行政職は、住民との直接的な接点となる職種です。各自治体の抱える課題や特徴を理解し、適切な行政サービスを提供することが求められます。
技術職
技術職は、専門的な知識と技術を活かした業務を担当する職種です。自治体によって様々な職種が設けられており、たとえば、土木職・建築職・農業/農学職・造園職・化学職・電気・電子・情報職などがあります。
主な業務内容としては、ライフラインの管理、公共施設の設計・建設・維持管理などが挙げられます。専門的な知識を活かして、まちづくりのために貢献するのが技術職の公務員です。
心理・福祉職
心理・福祉職は、地域住民の心の健康や福祉を支えるための職種です。たとえば、カウンセリングや心理検査などさまざまな福祉サービスの提供に携わり、地域の福祉施設や学校などで住民のニーズに応じた支援を行います。
心理・福祉職の公務員は、関連機関や他の専門職と連携し、総合的な支援を提供する重要な役割を担っています。
専門職
専門職は、資格や免許が必要となる職種です。教員、保育士、幼稚園教諭、栄養士、保健師、看護師、獣医師、司書などが専門職として挙げられます。
専門職は、専門的な知識を活用して現場の第一線で活躍している仕事です。たとえば、教員免許を活かして学校教育の現場で働いたり、保健師や看護師免許を活用して地域住民の健康管理に携わったりするなど、重要な役割を担っています。
公安職(警察・消防)
公安職は、公共の安全と秩序を守るための重要な役割を果たします。たとえば、犯罪の予防や捜査、交通の取り締まりを行う「警察官」、火災の消火や救助活動を担当し災害時の対応も行う「消防官」などが公安職公務員の代表例です。
公安職として活躍するには、試験合格後に、専門的な訓練を受ける必要があります。高い責任感と迅速な判断力が求められるのが公安職です。
【区分別】地方公務員試験の概要
地方公務員試験の「地方上級」とは、都道府県庁職員・政令指定都市職員・特別区の大卒程度の試験の総称です。政令指定都市以外の市町村職員の採用試験は「市役所試験」と呼ばれています。
なお、地方公務員試験の試験区分は上級・中級・初級の3つに別れていることが一般的です。
上級は大卒程度、中級は短大卒程度、初級は高卒程度を対象としていますが、あくまでも試験難易度の目安であり、学歴は関係ありません。基本的には、年齢の受験資格さえ満たしていれば受験できる自治体が多いです。
地方上級公務員試験(大卒程度)
地方公務員試験の中でも「地方上級」はとくに競争率が高い傾向にあります。試験内容は自治体によって異なりますが、1次試験で教養試験と専門試験が行われ、2次試験で面接試験と論文試験が行われることが一般的です。
【千葉市の地方上級公務員試験(事務行政A)の受験資格】
次のいずれかに該当する人
(1)平成 8 年4 月2 日から平成 15 年4 月1 日までに生まれた人(学歴は問わない)(28歳〜21歳で)
(2)平成 15 年4 月2 日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人(21歳以下で)
ア 学校教育法による大学(短期大学を除く。)を卒業した人又は令和 7 年3 月 31 日までに卒業見込みの人
イ 人事委員会がアと同等の資格があると認める人
上記は「千葉市役所職員採用試験」の受験資格です。受験資格は年齢要件のみ設けられており、学歴は問われていません。
なお、上限年齢も自治体によって異なります。千葉市役所の場合は28歳となっていますが、30歳を超えていても受験できる自治体もあります。
【千葉市の地方上級公務員試験(事務行政A)の日程】
申込期間:5月8日(水)午前9時〜5月21日(火)午後5時
第1次試験日:6月16日(日)
※面談試験、集団討論試験対象者の発表:令和6年6月21日(金)
第1次試験合格発表日:令和6年7月8日(月)
第2次試験日
適性検査:令和6年7月8日(月)午前9時~11日(木)午後5時(WEB方式)
論文試験:令和6年7月13日(土)面接試験:令和6年7月18日(木)~8月2日(金)のうち1日
最終合格発表日:令和6年8月中旬~下旬
地方上級試験の多くは、6月の中旬に第1次試験が実施されます。その後、論文試験・人物試験などの第2次試験が実施され、8月に最終的な合格者が発表されます。
なお地方上級試験は、自治体が異なっていても同一の試験日に筆記試験が実施されるため、併願できないケースが多いです。
【千葉市の地方上級公務員試験(事務行政A)の試験内容】
- 第1次試験
【教養試験】配点:100点 試験時間:2時間30分
[内容]筆記試験:55問中45問選択解答・知識分野(社会科学、人文科学、自然科学)※30問中20問選択解答・知能分野(文章理解・判断推理・数的推理・資料解釈)※25問全問解答
【専門試験】配点:100点 試験時間:2時間
[内容]・筆記試験:50問中40問選択解答:政治学・行政学・憲法・行政法・民法・労働法・経済学・財政学・社会政策・国際関係・経営学・教育学・社会福祉概論(社会保障を含む。)・社会学概論
【面接試験】配点:200点
[内容]・WEB方式・主として人物、性格等についての個別面接による試験(態度・表現力・積極性・協調性・専門性・堅実性・ストレス耐性等)- 第2次試験
【面接試験】配点:150点 試験時間:20〜30分程度
[内容]主として人物、性格等についての個別面接による試験(態度・表現力・積極性・協調性・専門性・堅実性・ストレス耐性等)
【論文試験】配点:50点 試験時間:1時間
[内容]与えられたテーマについて記述する筆記試験(800 字程度)
【適性検査】(WEB方式)性格適性及び職務適性等についての検査
地方上級試験では、教養試験・専門試験・論文試験・面接試験などが実施されます。市役所試験の行政職では、専門試験は実施されないケースも多いです。この専門試験の実施が、地方上級試験の難易度を高くする要因といえます。
最近は、人物試験の配点が高く設定されている自治体も増えてきており、筆記試験・人物試験ともに入念な対策が必要です。
【神奈川県の地方上級公務員試験(警察官)の受験資格】
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した人又は令和7(2025)年3月までに卒業見込みの人(警察本部長が同等の資格があると認める人を含む。)で、かつ、平成元(1989)年4月2日以降に生まれた人(35歳まで)
ただし、次のいずれかに該当しないこと。
1 日本国籍を有しない人
2 地方公務員法第16条の規定に該当する人
3 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
上記は、神奈川県警察の令和6年度警察官採用試験の受験資格です。警察官(公安職)の場合は行政職と異なり、学歴要件や国籍要件が受験資格となっている場合も多いです。情報を核にする際は注意しましょう。
【神奈川県の地方上級公務員試験(警察官)の日程】
申込期間: 令和6年3月1日(金曜日)午前9時〜4月15日(月曜日)最終日午後5時まで
第1次試験日:令和6年5月12日(日)
第1次試験合格発表日:令和6年5月20日(月)
第2次試験日:令和6年5月25日(土曜日)から6月14日(金曜日)までのうち指定する1日
最終合格発表日:令和6年8月下旬
警察官(公安職)の採用試験では、5月中旬に筆記試験が実施され、第2次試験を経て、8月に最終合格者が発表されるケースが多いです。自治体によって異なるものの、基本的には行政職とは異なる日程で実施されます。
【神奈川県の地方上級公務員試験(警察官)の試験内容】
- 第1次試験
【教養試験】配点:100点 試験時間:2時間
[内容]
筆記試験:50問
一般的知識(25問)
文章理解(英文を含む。)・判断推理(言語、非言語)・数的処理・資料解釈
知能問題(25問)
法律・政治・経済・社会一般・日本史・世界史・地理・数学・物理・化学・生物・地学- 第2次試験
【人物試験】配点:200点 試験時間:約20分
[内容]人柄、性向等についての個別面接試験
【論文試験】配点:100点 試験時間:1時間
[内容]思考力、構成力等についての筆記試験・1題必須解答 800字程度
【適性検査】職務遂行上必要な素質及び適性についての検査(第1次試験日に実施)
【体格検査・体力検査】配点:適否のみ
[内容]職務遂行上必要な体格・体力についての検査
【身体検査】配点:適否のみ
[内容]主として胸部疾患、性病等の伝染性疾患、痔疾、眼疾、耳鼻咽喉、聴力、血圧、尿及び肝機能等についての医師による検査
警察官(公安職)の試験では、筆記試験や人物試験、適性検査、体格や体力検査が行われます。第1次試験では専門試験は実施されず、教養試験のみの出題となるケースが一般的です。
一方、第2次試験では、人物試験の他に各種の検査が実施されます。警察官(公安職)として働くことができるのか、受験生の資質が確認されます。
【千葉県の地方上級公務員試験(心理職)の受験資格】
次のいずれかに該当する者
1.平成元年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた者(学歴は問わない)(35歳から21歳で)
2.平成 15 年 4 月 2 日以降に生まれた者で次に掲げるもの(21歳以下で)
イ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)を卒業した者及び令和 7 年 3 月までに大学を卒業する見込みの者
ロ 千葉県人事委員会がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
上記は、千葉県の心理職の受験資格です。基本的には、年齢要件のみが設けられており、学歴は問われないケースが多く見られます。年齢要件は行政職と比べて緩く設定されている傾向があります。
【千葉県の地方上級公務員試験(心理職)の日程】
申込期間: 令和6年4月19日(金)午前9時~5月13日(月)
第1次試験日:令和6年6月16日(日)
第1次試験合格発表日:6月27日(木)
第2次試験日:令和6年7月10日(水)~8月1日(木)のうち1日
最終合格発表日:8月下旬
地方上級公務員試験(心理職)の試験も、行政職と同様のスケジュールで実施されることが多いです。6月中旬に1次試験(筆記試験)が実施され、2次試験を経て、8月に最終合格者が発表されます。
【千葉県の地方上級公務員試験(心理職)の試験内容】
- 第1次試験
【専門試験】配点:100点 試験時間:2時間
[内容]筆記試験:40問一般心理学(心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。)、応用心理学(教育心理学・産業心理学・臨床心理学)、調査・研究法、統計学
【論文試験】配点:100点 試験時間:1時間30分
[内容]各試験職種共通の課題についての判断力、専門的知識、文章による表現力、文章構成力その他の能力についての筆記試験。- 第2次試験
【人物試験】配点:400点 試験時間:20分〜30分
[内容]主として人柄・性向等についての個別面接による試験(評定項目:積極性・堅実性・社会性・職務適性等)
【適性検査】職員として職務遂行上必要な素質・性格についての検査(質問紙法及び作業検査法)
地方上級公務員試験(心理職)の試験では、筆記試験や論文試験、人物試験が実施されます。筆記試験の内容は自治体によって異なりますが、教養試験を廃止して、専門試験のみ実施する自治体が増えてきています。
人物試験の配点が高く設定されているケースも多いため、入念に人物試験対策するのが合格のポイントです。
地方初級公務員試験(高卒程度)
地方初級公務員試験は、高卒程度の学力を持つ人を対象とした試験です。受験資格には年齢要件が設定されており、自治体によっては年齢要件の上限が高く設定されている場合もあります。
1次試験では教養試験と作文試験が実施されることが多いです。その後、2次試験で面接試験や集団討論などが実施され、人間性やコミュニケーション能力が評価されます。
【神奈川県の地方初級公務員試験(行政事務)の受験資格】
平成15(2003)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までに生まれた人(外国籍の人も受験可能)(17歳から21歳で)
上記は、神奈川県の地方初級公務員試験(行政事務)の受験資格です。学歴要件は設けられていませんが、上級試験と比べると年齢要件の上限が低く設定されている傾向にあります。
【神奈川県の地方初級公務員試験(行政事務)の日程】
申込期間:8月9日(金)午前10時~同月26日(月)午後5時
第1次試験日:9月29日(日)
第1次試験合格発表日:10月11日(金)
第2次試験日:10月21日(月)~11月1日(金)のうち指定する1日
最終合格発表日:11月15日(金)
地方初級公務員試験(行政事務)は、例年夏頃から申し込みが開始されます。その後、9月頃に第1次試験が実施され、10月頃の2次試験を経て、11月頃に最終合格者が発表されます。
【神奈川県の地方初級公務員試験(行政事務)の試験内容】
- 第1次試験
【教養試験】配点:100点 試験時間:2時間
[内容]
筆記試験:50問
知識分野:25問必須解答
法律・政治・経済・社会一般・日本史・世界史・地理・国語・物理・化学・生物・地学
数学知能分野:25問必須解答
文章理解(英文を含む。)・判断推理(言語・非言語)・数的処理・資料解釈- 第2次試験
【作文試験】配点:50点 試験時間:1時間
[内容]記述式1題必須解答600字程度
表現力・理解力等についての筆記試験
【人物試験】配点:250点 試験時間:約30分
[内容]個別面接1回・人柄、性向等についての試験
地方初級公務員試験(行政事務)の試験では、一般的には筆記試験と作文試験、人物試験が実施されます。筆記試験では、専門試験は実施されず、教養試験のみであることが多いです。教養試験では、高校で学習する程度の知識・知能問題が出題されます。
人物試験の配点が高く設定されているケースも多く、最終合格するには自己PRや志望動機などの人物試験対策も非常に重要です。
民間企業経験者採用試験
民間企業経験者採用試験は、民間企業での実務経験がある人を対象とした試験です。この試験では応募者は、豊富な実務経験を活かし即戦力として活躍することが期待されています。
試験では、書類選考、筆記試験、面接試験などが実施され、民間での実務経験に基づく問題が出題されることもあります。年齢要件が緩和されているため、キャリアチェンジを考えている幅広い年代の方にチャンスがある採用試験です。
【神奈川県の民間企業経験者採用試験の受験資格】
昭和39(1964)年4月2日から平成6(1994)年4月1日までに生まれた人(外国籍の人も受験可能)(60歳から30歳まで)
上記は神奈川県の民間企業経験者採用試験の受験資格です。年齢要件の上限が60歳と高く設定されているのが特徴といえます。
なお、受験資格は自治体によって異なっており、民間企業等での一定年数の勤務経験が設けられている場合もあります。
【神奈川県の民間企業経験者採用試験の日程】
申込期間:6月28日(金)午前10時~7月12日(金)
第1次試験(経験小論文)の受付期限:8月13日(火)
第1次試験合格発表日:9月13日(金)
第2次試験日:10月3日(木)~同月17日(木)のうち指定する1日
最終合格発表日:10月25日(金)
民間企業経験者採用試験の日程は、自治体によって異なります。上記は神奈川県の民間企業経験者採用試験の日程です。
試験形式もさまざまで、神奈川県のように経験小論文の提出が1次試験となっているケースもあります。1次試験実施後、人物試験などの2次試験が実施され、最終合格者が決定されます。
【神奈川県の民間企業経験者採用試験の試験内容】
- 第1次試験
【経験小論文試験】配点:100点
[内容]記述式・2題必須解答・各800字程度- 第2次試験
【人物試験】配点:200点 試験時間:約35分
[内容]
個別面接1回
人柄、性向等についての試験
個別面接の中で、事前に示した課題について5分程度のプレゼンテーションあり
民間企業経験者採用試験の試験内容は、自治体によってさまざまです。ただし、大卒程度試験のような専門試験が実施されるケースは少なく、実務経験やプレゼンテーション能力、人物試験などに重点が置かれている傾向にあります。
民間企業経験者採用試験は倍率が非常に高くなる傾向があるため、入念な対策が求められます。
地方公務員試験の難易度

地方公務員試験の難易度は、受験する区分や職種によって大きく異なります。とくに地方上級試験は最も難易度が高く、幅広い知識やスキルが求められます。各自治体では求める人材像や試験内容を公表しているため、自治体に合わせた対策が必要です。
また、応募者の数や競争率が高い地域や職種では、合格ラインが非常に高くなります。受験する自治体の試験の傾向をつかみ、学習計画を立て効率的に準備を進めることが合格への鍵です。
効率よく勉強し地方公務員試験の合格を目指すなら、「クレアール」のWeb通信講座がおすすめです。クレアールでは、自宅や外出先から、自由に学ぶことのできるWeb通信の公務員講座を提供しています。
筆記試験対策はもちろん、人物試験対策においても手厚いサポートを受けられるのがクレアールの魅力です。実際に、クレアールの公務員通信講座では数多くの合格者を輩出しています。まずは学習相談から始めることもできるので、ぜひお気軽にクレアールにお問合せください。
地方公務員試験の対策ポイント
職種や区分によっても異なりますが、地方公務員試験の試験範囲は全部で30科目ほどと非常に広いです。やみくもに勉強するのではなく、頻出範囲に絞って効率的に対策することが合格するためのポイントです。
出題されやすい内容を把握するためには、公務員講座などを活用するとよいでしょう。
地方公務員試験を含む、公務員試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に800~1200時間程度といわれています。1日に確保できる勉強時間を計算し、計画的に学習を進めていくことが必要です。
地方公務員試験の合格にはクレアールがおすすめ
地方公務員にはさまざまな職種があり、試験の日程や内容も区分によって異なります。そのため、地方公務員試験の合格には、自治体や試験種ごとの傾向を抑えた効率的な対策が必要です。
とくに最近は、人物試験の配点が高い自治体が増えています。最終合格には、筆記試験だけでなく、人物試験対策も重点的に行うことが欠かせません。
地方公務員試験の合格を目指す方は、「クレアール」の公務員通信講座を検討してはいかがでしょうか。クレアールでは、筆記試験対策はもちろん、エントリーシートの添削や模擬面接など人物試験対策も重視しております。
さらに、時間や場所を問わないweb学習のため自分のペースで学習を進められるのも魅力です。合格に最適な学習環境を整えておりますので、ぜひお気軽にクレアールへお問い合わせください。