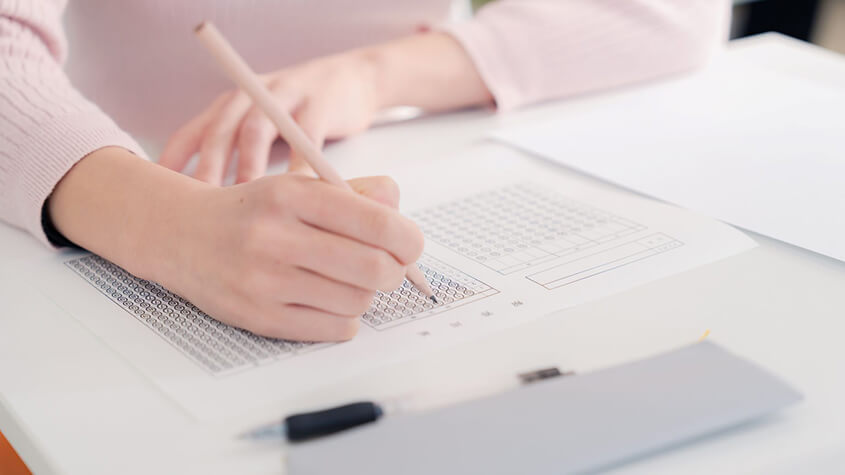「市役所の公務員試験の難易度は高い?」「合格するにはどのように勉強したらいい?」
など気になる方もいるでしょう。本記事では、市役所試験の難易度や倍率、合格率のほか、試験内容や対策方法について徹底解説します。市役所への就職、転職をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
市役所の公務員試験の難易度は高い?
市役所の公務員試験の難易度は、自治体によって大きく差があります。そのため、難易度は、「高い」とも「低い」とも言い切れません。
これは、自治体によって採用人数や試験形式が異なっており、それにより難易度も変わるためです。受験する自治体の過去の倍率や合格率を確認し、難易度を把握したうえで対策を立てるのが大切といえます。
市役所の公務員試験の合格率・倍率は?
| 合格率 | 約15~17% |
|---|---|
| 倍率 | 約5~7倍 |
※令和5年度試験は、受験者・合格者数は未公表
総務省の調査結果によると、令和元年から令和4年までの市役所の公務員試験の合格率は約15~17%、平均倍率は約5~7倍です。この数字から、市役所の公務員試験は全体的には難易度が高く、競争率も高い試験だと考えられます。
ただし、これはあくまで平均値であり、実際は自治体によって合格率と倍率に大きなばらつきがあります。以下で、市役所以外の地方公務員試験の倍率とも比較してみましょう。
| 地方公務員別 | 受験者数 | 合格者数 | 採用者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 136,307人 | 30,548人 | 20,246人 | 4.5 |
| 市区 | 273,300人 | 47,149人 | 36,248人 | 5.8 |
| 町村 | 29,044人 | 7,107人 | 5,792人 | 4.1 |
| 合計 | 438,651人 | 84,804人 | 62,286人 | 5.2 |
※令和5年度試験は、受験者・合格者数は未公表
令和4年度の地方公務員試験の倍率は、都道府県や町村と比べて市区が高くなっていると分かります。地元志向の高まりから受験生の人気が集中しやすい一方で、採用人数が限られているのが大きな要因でしょう。
また都道府県と異なり、転居を伴う異動がない点も市役所の人気が高い理由だと考えられます。
市役所の公務員試験の概要

次に、市役所の公務員試験の概要について見ていきましょう。「試験区分」「受験資格」「試験日程」「試験内容」に分けて、それぞれ説明します。
試験区分
市役所試験の試験区分は、主に職種や学力の目安などによって分けられています。職種による区分は大きく分けて2つで、1つは一般行政職を中心とした事務系職員、もう1つは土木職や建築職などの技術系職員です。
一方、「大卒程度」や「高卒程度」など、学力の目安による試験区分も設けられています。大卒程度は主に23歳以上の方や大学卒業見込みの方、高卒程度は主に21歳以下の人や高校卒業見込みの方が対象です。
自分がどの区分に該当するかを確認し、適切な試験を選ぶのが重要といえます。
| 職種 | 特徴 |
|---|---|
| 事務職 | 住民対応や政策の立案、予算の編成など、行政の運営に関する業務を行う |
| 技術職 | 土木職、建築職などで、専門スキルを活かした仕事を行う |
以上のように、市役所の公務員試験の職種は主に事務系と技術系の2つに大別されます。事務系の試験は、主に書類の作成や窓口対応、政策の企画立案など、幅広い行政事務に携わる職員を採用するための試験です。
一方、技術系の試験は、土木や建築、農業などの専門的な知識を持った職員を採用するための試験を指します。事務系と技術系では、試験内容も大きく異なります。
また市役所には、他にも資格免許職や消防士、技能員など幅広い職種の試験が設けられているため、どの職種を志望するか検討してみましょう。
| 試験の種類 | 学力の目安 |
|---|---|
| 上級試験 | 大学卒業程度 |
| 中級試験 | 短大卒業程度 |
| 初級試験 | 高校卒業程度 |
以上のように、市役所試験の種類は学力の目安によって分けられているケースも多くあります。たとえば、「大学卒業程度」を目安とした「上級試験」、「短大卒業程度」を目安とした「中級試験」、「高校卒業程度」を目安とした「初級試験」などです。
なお、「○○卒業程度」などはあくまでも学力の目安であり、学歴は問われません。
受験資格
市役所の公務員試験の受験では、基本的に年齢制限が設けられています。最終学歴が高卒であっても年齢制限さえ満たしていれば大卒程度試験の受験が可能です。一方で市役所試験では学歴が問われることもありますので、注意が必要です。
受験の年齢制限は自治体や試験区分によって異なります。市役所試験の年齢上限は、おおむね30歳前後に設定されていることが多いですが、30歳を超えて受験できる自治体も少なくありません。
また年齢以外にも、消防士などの試験では身体的条件が問われるケースがあります。自分が受験する自治体・職種の受験資格については、事前にしっかり確認しておきましょう。
試験日程
| 試験日程の種類 | 試験日程 | 特徴 |
|---|---|---|
| A日程 | 6月・第4日曜日 | 政令指定都市や県庁所在地のある市役所などの実施が多い |
| B日程 | 7月・第2日曜日 | ― |
| C日程 | 9月・第3日曜日 | 全国の市役所にて最も実施が多い |
| D日程 | 10月・第3日曜日 | ― |
※日程は変更される場合があるうえ、自治体によっても異なる
市役所の公務員試験は、おおむね4つの日程に分かれています。6月に行われるのがA日程で、政令指定都市や県庁所在地のある市役所などの試験はこの日程で実施されるケースが多いです。
7月に入ると、一部の自治体でB日程試験が実施されます。その後、最も多くの市役所試験が実施されるC日程試験(9月)が実施されます。最後に行われるのが、10月のD日程です。
これらはあくまでおおよその日程であり、自治体によって細かい時期は異なります。志望する市役所の試験日程を事前に調べておくことが必要です。
試験内容
多くの市役所試験は、第1次試験と第2次試験に分かれています。試験区分によって試験内容や科目は異なりますが、主な試験内容は以下の通りです。
| 第1次試験 | 教養試験、専門試験、論文試験(作文試験)など (SPI試験やSCOA試験を課す市役所も増えている) |
|---|---|
| 第2次試験 | 面接試験 (個別面接・集団面接・集団討論⦅グループディスカッション⦆)など |
第1次試験では、筆記試験が行われるのが一般的です。通常、教養試験、専門試験、論文試験(作文試験)などが実施されますが、近年は筆記試験を「SPI試験」や「SCOA試験」に置き換える市役所も増えています。
第2次試験では、面接試験が行われます。面接試験では、個別面接、集団面接、集団討論(グループディスカッション)などが行われるケースが多いです。
教養試験
教養試験は、公務員として必要な一般知識や一般常識を問う試験です。文系・理系の両方の分野から、広い範囲の問題が出題されます。
大きく「一般知能」と「一般知識」に分けられており、出題内容は一般知能では文章理解や数的処理、一般知識では社会、人文、自然科学などです。国家公務員試験と比較すると、教養試験の難易度は低いといわれています。
専門試験
専門試験は、公務員として必要な専門知識を問うための試験です。試験の出題範囲は試験区分によって異なります。
たとえば、事務系の試験では憲法や民法、行政法などの法律科目を中心に、ミクロ経済学やマクロ経済学など幅広いジャンルの科目から出題されるケースが多いです。自治体によっては専門試験が設けられていない場合もあります。
論文試験(作文試験)
論文試験(作文試験)は、与えられたテーマについて意見を論理的にまとめる能力を問われる試験です。文章力だけでなく、課題文や資料を正確に読み取り分析する力も問われます。
論文試験の対策として、日頃から社会問題に関心を持ち、自分の意見を言葉にする練習を積むことが重要です。新聞やニュースに触れ、様々な立場の意見を知ることで多角的な視点を身につけましょう。
SPI試験
SPI試験とは、民間企業で用いられることの多い適性検査です。近年では、公務員試験でもSPI試験を導入する自治体が増えています。
SPI試験の内容は、主に「能力検査」と「性格検査」の2種類です。「能力検査」では、「言語能力」と「非言語能力」が測定されており、それぞれ「文章理解」「数的処理」に近い能力が求められます。
そのため、公務員試験の教養試験対策を行うことで、SPI試験も同時に対策できるでしょう。
SCOA試験
SCOA試験は、公務員試験で導入する自治体が増えている試験です。「知」「情」「意」の3つの側面から個人を多面的に評価するのが特徴で、主に「能力テスト」と「性格テスト」から構成されています。
試験では、言語、数理、論理、常識、英語、パーソナリティの幅広い分野が出題されます。60分で120問の問題に解答しなければいけないため、素早く正確に解答する能力が必要です。
また、近年の就職試験は、能力だけでなくパーソナリティも重視されている傾向にあります。パーソナリティの科目では、素直に、かつ求められる人物像から逸れないように回答するのが重要です。
面接試験
面接試験は、公務員としての適性を判断する重要な試験です。個別面接、集団面接、集団討論(グループディスカッション)など、さまざまな形式で行われます。
最近の市役所試験では、人物試験が重要視されているため、人物試験対策を怠ると最終合格は難しくなります。自己分析を深め、自分の強みや志望動機を明確に回答できるようにしておきましょう。
面接官の質問に対して具体例を交えながら論理的に答えられるよう、模擬面接などで練習を繰り返すのが大切です。
市役所の公務員試験に向けた勉強スケジュール
市役所の公務員試験に合格するには、計画的な勉強が欠かせません。ここでは、9月から6月までの勉強スケジュールを3つの期間に分けて解説します。
勉強スケジュール:9~12月
9月から12月は、一般知能を中心に学習する時期です。文章理解や数的処理など、基礎能力試験で配点の高い科目を中心に勉強していきましょう。
また、筆記試験対策と並行して、ES対策も早めに始めるのをおすすめします。ES対策では自己分析を深め、なぜ公務員を目指すのかを明確にしておくのが大切です。
勉強スケジュール:1~3月
1月から3月は、一般知能と並行して一般知識の対策も始めましょう。自然科学や人文科学など、幅広い分野の知識を身につける必要があります。
また、この時期から徐々に論文試験対策も始めるのがよいでしょう。過去問を活用し、小論文の構成の作り方や意見の論じ方など、論理的な文章を書くための基礎を身につけていくのが大切です。
勉強スケジュール:4~6月
4月から6月は、これまでの学習内容の総復習を行います。苦手分野を克服しつつ、得意分野をさらに伸ばすことで実力を高めていきましょう。
同時に面接試験の準備も、本格的に進めていく必要があります。自己PR や志望動機を深掘りして、面接官の質問に的確に答えられるよう何度も練習するのが重要です。
試験日程が近づいても最後まで諦めずに対策を続けることで、市役所の公務員試験合格の可能性を高められます。
市役所の公務員試験に合格するための対策方法
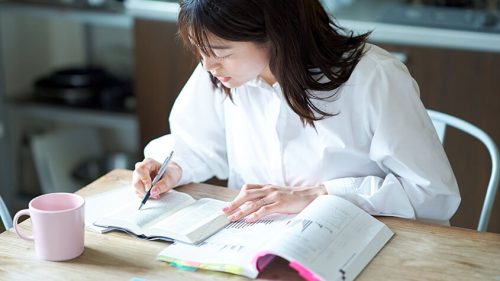
それでは、市役所の公務員試験に合格するためには、どのように対策を進めていけばよいのでしょうか。ここでは、筆記試験、論文試験、面接試験の対策方法をそれぞれ紹介します。
筆記試験の対策方法
筆記試験の対策では、出題傾向を分析し効率的に学習するのがポイントです。知能分野は出題数が多く、とくに数的処理はマスターするのに時間がかかるため、早くから準備を始める必要があります。
知識分野は、膨大な量の暗記が必要となるため、得点が伸びづらいと感じる方もいるかもしれません。専門科目を学習する人は、学習範囲の重なりやすい社会科学を得点源にするのがよいでしょう。
受験直前期には、過去問を活用して実際の試験形式に慣れておくのも有効な方法です。なお、勉強の進捗状況や確保できる勉強時間によっては、専門試験を実施しない自治体を選ぶのも一つの手段となります。
論文試験(作文試験)の対策方法
論文試験対策では、過去に出題されたテーマで実際に論文を書き、模範解答と照らし合わせるのが効果的です。この対策方法で、論理的な文章の構成や説得力のある意見の書き方を身につけましょう。
また、出題者の意図を的確に捉え、自分の考えを述べる練習を重ねるのも重要です。日頃から社会問題への関心を持ち、多角的に考える習慣をつけることで、試験本番で実力を発揮できるでしょう。
面接試験の対策方法
面接試験対策として、聞かれる質問を想定し、的確に回答できるよう練習しておくのが大切です。志望動機や自己PRなどよく聞かれる質問に対して、具体例を交えながら論理的に答えられるよう模擬面接を重ねておきましょう。
また、面接官に好印象を与えるためには、人当たりの良さも重要です。笑顔で話すことを心がけるほか、相手の目を見て話すなど基本的なマナーにも気をつけて対策を行いましょう。
市役所の公務員試験に合格した人の体験談
ここでは、クレアールを活用して、実際に市役所の公務員試験に合格した人の体験談を紹介します。合格者の勉強方法や試験対策、心構えなどを参考にして合格を目指していきしょう。
R.Tさん[最終合格先:立川市役所(社会人経験者・一般事務)]
クレアールは、好きな時間に勉強できることが良かったです。働きながら勉強するにあたり、残業が多い仕事だったため、通勤時間や隙間時間を利用して勉強できる環境が良かったため、受講を決めました。
公務員試験は筆記試験が重要視されがちですが、最近はSPI試験などに簡略化する試験も多く、面接試験に重きを置く自治体も増えています。特に社会人の方は勉強が大変だからと諦めてしまいがちですが、毎日少しずつ行うことで、筆記試験突破は十分可能ですし、面接試験も社会人で培ったコミュニケーション能力を発揮できれば戦えると思います。皆さんの合格を願っています!
Y.Kさん[最終合格先:富里市役所(一般事務)]
クレアールは、オンライン授業で融通がきくところや、丁寧な対応で助かりました。筆記試験では、何度も繰り返し解くことが重要であると気付かされました。わからないところは講義をみて何度も復習するように心がけていました。捨て科目を作り、効率よく取捨選択をし、学習を進めていく事もとても重要であると思います。あとは息抜きも必要で、オンオフの切り替え、メリハリが大事です。
最後まで諦めなければ必ず夢は叶います。僕は公務員試験からその事を教わりました。忍耐力も身につけることができ、一つのことを続けることができ、公務員試験を合格できた方ならこの先なにがあっても、乗り越えていけると思います。そう信じて毎日頑張って下さい。何事も諦めないでほしいです。
Kさん[最終合格先:青梅市役所]
通う時間なしで自分の好きな時間や隙間時間を活用しながら勉強することができました。バイトの休憩時間で集中してやったり、自分の好きな時間に受講することができて、途中で中断することができて、何回も見ることができたのがよかったです。他の予備校といろいろ比べて比較的安く、また次の年も1年間受けることのできる保証がついていたのがよかったです。
面接試験では、まずは志望動機をしっかり伝えられるように覚えることと、自分の興味のある分野やその自治体で興味を持った政策を調べていくことが大事だと思います。
今からじゃ遅い・・・と思っている方もいるかもしれませんが、私はやらないで後悔するよりやって後悔した方がいいと思っています。教養問題のみ使う試験やSPIを使っている自治体も増えてきているのでぜひトライしてみてください。
クレアールの公務員講座では、毎年多くの市役所試験の合格者を輩出しています。効率の良い学習環境、面接指導も含めたオールインワンのサポート、受験先別の豊富なコースプランなどがクレアール通信講座の大きな魅力です。
さらに、面倒見の良いサポートと安心の担任制で、通信講座にありがちな「孤独とつまずき」を解消しています。市役所試験合格を目指したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
市役所の公務員試験に関するよくある質問
市役所試験を目指すなら、クレアールの通信講座がおすすめ
市役所の公務員試験は地域や区分によって試験内容などが異なるため、難易度の高さは一概にはいえません。ただし、市役所試験の平均合格率は15~17%、平均倍率は5~7%のため、全体的に難易度は高めだと考えてよいでしょう。
そのため、市役所試験に合格するには、事前に勉強スケジュールを立て、戦略的な対策を取る必要があります。
限られた時間で、効率良く学習を進めたい方は、ぜひクレアールの通信講座をご活用ください。クレアールの通信講座はweb場所や時間を問わないweb学習のため、忙しい社会人の方も自分のペースで勉強できる点が魅力です。
社会人から公務員試験に合格した実績も多くあります。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。