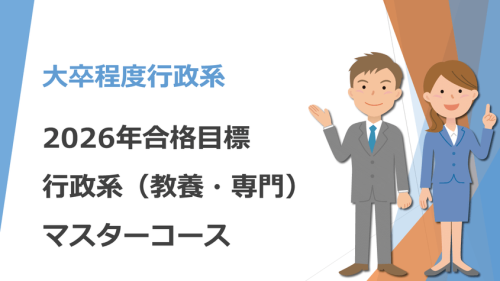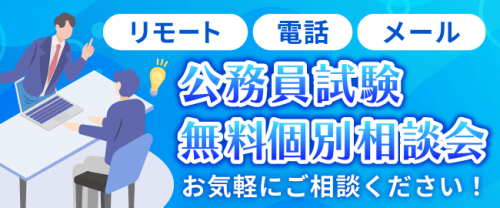警察事務は警察官と異なり、表立って活動する機会が少ないため知らない方も多いかもしれません。しかし、警察事務のおかげで組織が円滑に運営できているといえるほど警察には欠かせない重要な存在です。このコラムでは、警察事務の仕事内容や給料、採用試験に関する情報などを解説します。
警察事務とは?
警察事務は、警察の運営にかかわる事務作業を担当する職業です。警察事務は地方公務員であり、各自治体における「警察事務職員採用試験」に合格し、警察学校を卒業することで警察事務職員として働けるようになります。
警察事務は「警察行政」とも呼ばれることもあり、警察の円滑な運営には欠かせない重要な役割を果たしています。
警察事務と警察官の違い
| 警察事務 | 組織運営や予算管理、人事などの事務業務を担当し、警察活動の円滑な運営を支える。 |
| 警察官 | 犯罪の予防、捜査、逮捕、交通指導取り締まりなどの任務に従事し、個人や公共の安全を守る。 |
警察事務と警察官は、同じ警察に勤める公務員でありながら、役割と業務内容が大きく異なります。警察事務は、警察署や警察本部で組織運営や予算管理、人事などの事務業務に従事し、警察活動の円滑な運営を支えるのが役割です。一方、警察官は個人や公共の安全を守るために犯罪の予防、捜査、逮捕、交通指導取り締まりなどの任務に従事します。
また、公務員としての立場も異なります。警察事務は地方公務員である一方、警察官は国家公務員または地方公務員です。
警察事務の仕事内容

- 電話対応・窓口対応
- 予算執行
- 設備・備品の管理
- 遺失届・拾得物の取り扱い
- 職員の給与支給・福利厚生に関する事務
- 犯罪統計資料の作成
- 鑑定 など
警察事務の仕事は、警察の運営を円滑にすることです。業務内容は、窓口対応や落とし物・紛失物の取り扱い、職員の給与や経費の管理などの会計業務、現場の証拠鑑定による事件解決など、所属する部署によって異なります。
警察事務の配属先
警察事務は、採用試験に合格して警察学校を卒業すると、都道府県の警察本部や警察署(所轄署)に配属されます。ここでは、各配属先での役割や仕事内容について、詳しく解説します。
【警察本部】
会計課・施設課・情報管理課・警務課・厚生課
刑事総務課・鑑識課・交通総務課・交通捜査課・運転免許課
【警察署】
会計課・刑事課・交通課
警察本部
【会計課】
警察本部の会計課では、警察組織全体の会計業務を担当します。一般的な経理業務や予算編成、会計監査などの業務だけでなく、産業廃棄物の業者の選定や鑑識用品の運搬業者の選定など、警察ならではの特殊な業務も担当します。
【施設課】
警察本部の施設課では、警察署や交番など警察施設の管理を行います。警察事務は、建物の新設や維持、改修工事の計画立案や実施を担当し、ハード面から警察活動を支えるのが役割です。信号機や交通規制標識の設置に関する事務なども行っています。
【情報管理課】
警察本部の情報管理課では、警察職員が業務で使うシステムの開発やメンテナンスを担当します。システムの導入や改修によって、職員の事務業務の効率化を図り、警察官が治安を守ることに集中できるようにするのが警察事務の役割です。
【警務課】
警察本部の警務課は、行政面から警察官をサポートする部署です。警察業務の施策立案にかかわることで、警察官とともに社会の安全と安心を守るのが役割です。各種会議や行事の運営、会議資料の準備や会議の日程調整なども、警察事務が担当します。
【厚生課】
警察本部の厚生課では、警察職員の福利厚生制度の申請や支払い手続き、新たな補助事業の計画などを警察事務が担当します。警察官により良い仕事をしてもらえるように、生活の質向上に取り組んでいます。
【刑事総務課】
警察本部の刑事総務課では、刑事捜査にかかわる総務業務を担当します。毎日届く、犯罪統計データを審査して、警察庁に送付する業務を行います。犯罪情報のチェックを通して、捜査活動の支援をするのが刑事総務課の役割です。
【鑑識課】
警察本部の鑑識課には、警察官が現場で採取した指紋の資料が全て集まります。鑑識課では、その資料を選別・対照して、犯人に結びつく一致鑑定を行うのが仕事です。犯人の特定や、犯行を証明する証拠になり得るものにかかわる、責任のある業務を担当します。
【交通総務課】
警察本部の交通総務課では、交通安全対策や交通ルールの啓発、違反取り締まりの支援などを行います。過去の統計から、交通事故の発生が多い交差点や道を選別し、警察官とともに、交通事故抑制のためのイベント企画をすることもあります。
【交通捜査課】
警察本部の交通捜査課では、重大な交通事故の現場に臨場して、捜査や裁判のための資料を作成します。図化係では、ステレオカメラで現場の写真を撮影し、専用の測量機器で観測して図面化する仕事を行なっています。
【運転免許課】
警察本部の運転免許課では、運転免許を取得する人の情報登録、免許更新・失効の手続きを担当します。繁忙期には1日1,000件以上のデータを取り扱うこともあるため、警察事務には、迅速かつ的確な対応が求められます。
警察署
【会計課】
警察署の会計課は、唯一、事務職員だけで構成されている部署です。警察事務は、署内の予算管理や職員の給与事務、庁舎の維持管理などを担当します。また、警察署や交番に届けられた落とし物のチェックなど、遺失物に関する業務も担当しています。
【刑事課】
警察署の刑事課では、警察官が作成した被害届や犯罪統計資料が、正しく記載されているかチェックをしたり、被害届や捜査資料を管理したりします。刑事課では、警察官と協力しながら、犯罪分析や抑制活動につなげるための、大切な資料の作成にかかわっています。
【交通課】
警察署の交通課では、車庫証明や道路工事の許可申請の受付を担当します。主には、警察署内での窓口業務を担いますが、時には、警察署の外で交通安全の啓発活動を行うこともあります。
警察事務の一日のスケジュール

| 8:15 | 出勤 |
| 8:30 | 窓口業務開始 落とし物・遺失物の受理・返還 |
| 10:00 | 各交番からの落とし物や遺失物についての引継ぎ |
| 12:00 | 昼休憩・窓口業務 |
| 13:30 | 警察署外における連絡業務など |
| 15:00 | 書類の確認・上長への報告・消耗品の管理 |
| 17:30 | 退勤 |
所属する課によって異なりますが、警察事務の1日のスケジュールの一例をご紹介します。仕事のスタートは8時30分で、10時には各交番からの引継ぎ作業があります。午後は警察署外での連絡業務などを担当し、15時には書類の確認や上長への報告を行います。17時30分に退勤となります。窓口対応や電話対応は、お昼の休憩時間中も行われることが多いです。
警察事務の給料
警察事務の初任給は以下のようになっています。
| Ⅰ類採用者(大卒程度) | 225,500円 |
| Ⅲ類採用者(高卒程度) | 188,000円 |
また、警察職の平均基本給は2024年に総務省が調査した「地方公務員給与の実態」資料によると369,082円となっています。
警察事務のやりがい

警察事務は、警察の裏方として運営をサポートする仕事ですが、その存在は警察の円滑な運営にとって欠かせない重要なポジションです。ここでは、警察事務のやりがいについて詳しく解説します。
地域に貢献できる
警察事務は、地域に貢献できる仕事です。警察の運営を円滑にサポートすることで、間接的に地域の治安向上に結びついています。窓口業務では、運転免許証の手続きや紛失物の対応など、地域の住民と直接かかわる機会があり、地域の人々から直接感謝の言葉をもらえることもあります。警察事務の仕事は、地域の安全と住民の安心を支える、やりがいのある仕事です。
さまざまな経験を積むことができる
警察事務のやりがいとして、さまざまな経験を積める点も挙げられます。警察事務の働く場所は細かく分類されており、異動で配属先が変わることも少なくありません。会計課や交通課など、配属される部署によって業務内容はさまざまです。いろいろな配属先を経験することで、幅広いスキルを身につけられます。
縁の下の力持ちとして組織全体に貢献できる
警察事務は裏方の仕事でありながら、組織全体に欠かせない存在です。警察事務の働きがなければ、警察の円滑な運営は成り立ちません。警察事務は、縁の下の力持ちとして、地域の安心と治安の維持に貢献できる仕事です。
警察事務に向いている人
- 真面目で真摯な人
- 適応力がある人
- 学び続けられる人
- 淡々と業務をこなせる人
警察事務の仕事は、ほとんどが事務作業です。部署によっては人に感謝される機会が少なく、サポートする仕事のため自分の成果が見えにくいこともあります。そのため、裏方として淡々と作業をこなし、組織の円滑な運営に貢献することに魅力を感じられる人が向いています。また、部署が頻繁に変わるため、新しい業務に対して抵抗がなく、好奇心を持って学べる人も適しています。警察事務は、警察官や地域住民のために真摯に業務を遂行し、社会をより良くしたいという意欲を持っている人に適した仕事です。
警察事務職員になる方法

警察事務職員になるためには、各都道府県が実施する「警察事務(警察行政)職員採用試験」に合格する必要があります。自治体にもよりますが、年齢や資格の有無によって、試験区分が分かれることが多く、例えば、警視庁では年齢のほかに保健師免許の有無によって「警察行政職員Ⅰ類」と「警察行政職員Ⅱ類」に分かれます。
採用試験に合格できたら、警察学校で約1か月間の研修を受け、卒業後は都道府県の警察本部や警察署に配属されます。
警察事務の試験概要

警察事務職員になるためには、指定の試験に合格しなければなりません。ここでは、東京都を管轄している警視庁の「警察行政職員採用試験」のうち「警察行政職員Ⅰ類」の試験内容について解説します。
引用元:警視庁公式サイト
受験資格
| Ⅰ類(大学卒業程度) | ・受験する年の4月1日時点で21歳以上28歳以下の人 ・受験する年の4月1日時点で21歳以下かつ、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)を卒業・卒業見込みの人、または、これと同等の資格があると認められる人 |
警察行政職員Ⅰ類を受験できるのは、日本国籍を有する人で、年齢要件を満たして活字印刷文による出題に対応できる人です。2025度の採用試験の場合、受験できるのは1996年4月2日から2004年4月1日までに生まれた人でした。また、2004年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく短大以外の大学を卒業した人、これと同等の資格があると認められる人も含まれています。
受験できないケース
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(注) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者は受験できません。
試験内容
| 第1次試験 | 教養試験 | 一般教養についての五肢択一式 |
| 第1次試験 | 専門試験 | 職務に必要な専門知識についての記述式 |
| 第1次試験 | 論文 | 課題式(1,000字以上1,500字程度) |
| 第2次試験 | 面接試験 | 主として人物についての個別面接 |
| 第2次試験 | 身体検査 | 職務遂行に必要な健康度について検査 |
| 第2次試験 | 適性検査 | 警察行政職員としての適性についての検査 |
第1次試験では、一般教養と専門知識の記述式試験、論文があります。第2次試験では個別面接、身体検査、適性検査が行われます。第2次試験を受けられるのは、第1次試験を通過した方のみです。警察官とは異なり、細かい身体要件や体力検査はありません。
クレアールでは1次試験と2次試験の面接試験を対策できるコースをご用意しています。
警察事務官になりたい方にピッタリのコースとなっていますので、是非ご利用ください。
また、併願状況や志望状況、年度によっておすすめのコースが変わる場合もございます。
気になることがございましたら、是非公務員無料学習相談をご利用ください。
合格率
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 321 | 116 | 2.8 | 450 | 49 | 9.2 | 511 | 99 | 5.2 |
警察事務にまつわるQ&A
警察事務職員は、警察官とは異なり目立った業務を行うことが少ないため、一般の人々にとってはイメージしにくい存在かもしれません。ここでは、警察事務に関してよくある質問に回答します。
警察事務を目指してみませんか?
警察事務は表立って活動する機会が少なく、多くの人にとってイメージしづらい存在かもしれません。しかし、裏方の仕事でありながら警察組織全体には欠かせない重要な存在です。警察事務になるには、「警察事務(警察行政)職員採用試験」に合格する必要がありますが、学歴は不問とされており、指定の学校に通う必要はありません。ただし、採用試験では法律に関する知識や専門知識が問われることもあるため、予備校や通信教育を活用するのがおすすめです。
クレアールの公務員コースは、効率的な学習の支援と手厚いサポートで、通信講座にありがちな孤独感やつまずきの放置がなく、毎年数多くの方が最終合格までたどり着いています。警察事務を目指す方はぜひ、クレアールの公務員講座をご検討ください。

この記事を監修した人
クレアール公務員相談室タニオカ
これまで、公務員試験の受験・学習を考える3,000人以上の相談に答えた実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」などを執筆。