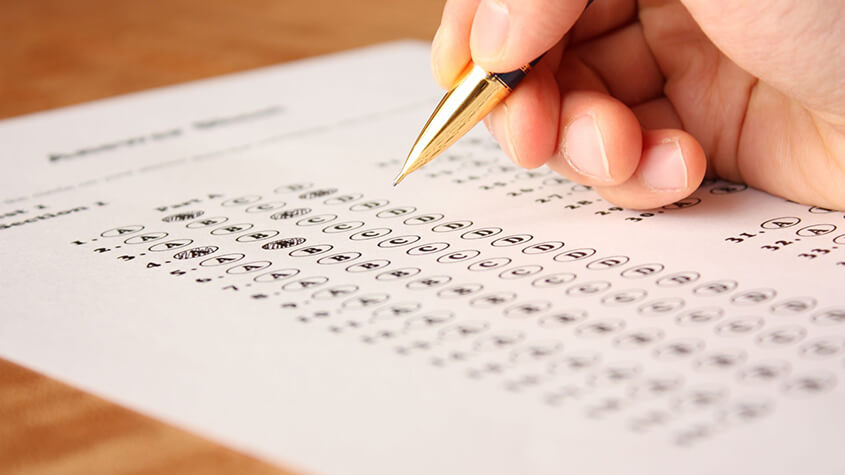「国税専門官の採用試験の難易度は低い?」「合格するには、どのように勉強したらいい?」と気になる方もいるでしょう。ここでは、国税専門官試験の倍率や合格率、国家一般職との難易度の比較、試験内容から効果的な対策方法まで徹底解説します。国税専門官を目指したい方はぜひ参考にしてみてください。
国税専門官の試験の難易度は?
単純に倍率や合格率の推移だけをみると、国税専門官試験の難易度はそこまで高くないといえます。したがって、対策をしっかりと行えば十分に合格を目指すことが可能です。
ただし、試験では専門知識の理解が必須となるため、決して簡単な試験ではありません。それでは、倍率や合格率について詳しく見ていきましょう。
他区分と比較した倍率
| 区分 | 受験者数 | 第1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 総合職(大卒) | 12,736人 | 3,400人 | 1,783人 | 7.1倍 |
| 一般職(大卒) | 18,946人 | 11,558人 | 8,269人 | 2.3倍 |
| 国税専門官A | 9,555人 | 5,511人 | 3,127人 | 3.0倍 |
| 国税専門官B | 263人 | 218人 | 147人 | 1.8倍 |
上記の表は、国家公務員(総合職・一般職)と、国税専門官試験の2023年度の合格倍率を比較したものです。
国家総合職は7倍以上の競争倍率があるのに対し、国税専門官試験(A・B)の倍率は2〜3倍にとどまっています。国家総合職と比較すると、国税専門官試験の難易度は低いといえるでしょう。
なお、国税専門官試験にはAとBの2つの区分があります。Aは事務系の受験者向け、2023年度に新設されたBは理工・デジタル系の受験者向けの試験です。
合格率の推移
| 年度 | 受験者数 | 第1次合格者数 | 最終合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 9,818人 | 5,729人 | 3,274人 | 約33% |
| 2022年 | 11,098人 | 7,283人 | 4,106人 | 約37% |
| 2021年 | 9,733人 | 7,415人 | 4,193人 | 約43% |
最終的な合格率は受験年度によって異なるものの、例年約30%〜40%の間で安定して推移しています。なお、第1次試験(筆記試験)、第2次試験(個別面接)の、試験毎の合格率はそれぞれ60%程度です。
最終合格するために、筆記対策・人物試験どちらもバランス良く対策を行っていく必要があるでしょう。
そもそも国税専門官とは?

国税専門官は、国税局や税務署に勤務する税のスペシャリストで、税務に関する幅広い業務を担当する職種です。国税専門官には法律、経済、会計などの専門知識や、コミュニケーション能力が求められます。
採用後は、全国各地の税務署に勤務するのが一般的ですが、本人の能力と希望に応じて国税局に勤務する場合もあります。
さらに、努力次第では国税庁本庁や財務省本省への異動や、税理士としての独立開業が可能です。
国税専門官の仕事内容
国税専門官は、税務の専門家として会計や法律の知識を活用しながら幅広い業務を担当します。具体的な仕事内容は、国税調査官、国税徴収官、国税査察官の3つの職種に分けられます。
| 職種 | 概要 |
|---|---|
| 国税調査官 | 個人や会社を対象に、税の申告に関する調査・検査を行う |
| 国税徴収官 | 税金の督促や滞納処分、納税に関する指導などを行う |
| 国税査察官 | 悪質な脱税者に対して捜索・差押等の強制調査を行う |
以下で、それぞれの職種について詳しく見ていきましょう。
国税調査官
国税調査官は全国の税務署に勤務し、仕事内容としては主に納税者から提出された申告書の内容が適正かどうかを調べます。たとえば、個人事業主や会社を訪問して、帳簿や伝票などの会計書類をチェックする「税務調査」も国税調査官の仕事です。
申告内容に誤りがないか、所得の計算は正しく行われているかなどを調査する役割を担っています。
国税徴収官
国税徴収官は、期限までに税金を納めない滞納者に対する徴収業務を担当しています。納税の督促や滞納処分などを行う一方で、滞納者の生活状況に配慮して分納や納付期限の延長などの相談に応じることも、国税調査官の仕事の1つです。
国税徴収官は強力な権限を持つ一方で、納税者の事情に寄り添う姿勢も求められる仕事だといえます。
国税査察官
国税査察官は、悪質な脱税者に対する強制調査を担当します。いわゆる「マルサ」と呼ばれているのも国税査察官です。
脱税の疑いがある者に対し、裁判官から許可状を得て、事前予告なしの強制調査を行います。帳簿や書類を差し押さえ、脱税の事実関係を徹底的に解明するのが国税査察官の仕事です。
国税専門官になるには?必要なステップを図解
それでは、国税専門官になるにはどのようなルートがあるのでしょうか。ここでは、必要なステップを図解で解説します。
【出願~採用までの流れ】
基礎能力試験・専門試験
人物試験(個別面接)・身体検査
国税専門官になるには、まず試験の受験資格を満たしているか確認し、出願手続きを行いましょう。出願後、第1次試験(筆記試験)、第2次試験(人物試験)を経て、最終合格者が決定されます。
その後、採用候補者名簿から各年の採用環境を考慮したうえで、全国の国税局の採用者が決定され国税局に配属されます。配属先が決まれば、各管内の税務署での勤務開始です。
【採用~研修修了までの流れ】
国税専門官として採用されたら、まず3ヶ月間の「専門官基礎研修」により、税務職員に求められる基礎知識を身につけることが必要です。その後、より実践的な「専攻税法研修(1カ月間)」を受けて各税務署に配属されます。
税務署で2年間の実務経験を経た後、「専科」と呼ばれる7カ月間の研修を受け、専門官職として必要な知識・技能を習得します。その後、国税調査官・徴収官・査察官などに任用される流れです。
国税専門官の採用試験の概要
ここでは、国税専門官の採用試験の概要について解説します。以下で詳しく見ていきましょう。
受験資格
【受験資格】
①21歳以上30歳未満の者
②以下を満たす21歳未満の者
⑴大学を卒業した者・実施年度の3月に卒業見込みの者
⑵人事院が上記⑴と同等の資格があると認める者
国税専門官試験の受験資格は「21歳以上30歳未満の者」と定められています。また、「21歳未満でも大学を卒業見込みの者」なども受験可能です。学歴は問われていないため、年齢要件さえクリアしていれば誰でも受験できます。
国税専門官は高度な専門職のイメージがありますが、実は広く門戸が開かれた試験だといえます。
試験日程
| 受付期間 | 2月22日(木)~3月25日(月)【申し込みはインターネットより】 |
|---|---|
| 第1次試験 | 5月26日(日) |
| 第1次試験合格発表 | 6月18日(火) |
| 第2次試験 | 6月24日(月)~7月5日(金) |
| 最終合格者発表 | 8月13日(火) |
2024年度の国税専門官試験の日程は、上記の表のとおりです。概ね、2023年度と同様のスケジュールですが、筆記試験の日程は1週間程度早まっています。
なお、日程は変更になる場合もあるため、詳しい日程は必ず人事院国家公務員試験採用情報NAVI「国税専門官採用試験」を確認しましょう。
試験地
| 第1次試験地 | 札幌市・盛岡市・仙台市・高崎市・さいたま市・東京都・新潟市・松本市・名古屋市・金沢市・京都市・大阪市・松江市・岡山市・広島市・高松市・松山市・福岡市・熊本市・鹿児島市・那覇市 |
|---|---|
| 第2次試験地 | 札幌市・仙台市・さいたま市・東京都・名古屋市・金沢市・大阪市・広島市・高松市・福岡市・熊本市・那覇市 |
国税専門官試験の試験会場は、以上の都市内に設置されます。受験者は、第1次試験と第2次試験のそれぞれ1都市ずつ試験地を選択可能です。
ただし、申込者数などの状況によっては、上記の都市周辺に試験会場が設けられる場合もあります。なお、一度申し込みが完了すると、試験地の変更はできないため注意しましょう。
試験内容
国税専門官試験では、第1次試験で筆記試験が実施され、筆記試験合格者を対象に2次試験で個別面接が実施されます。筆記試験で高い点数を記録しても、面接で低評価を受ければ、最終合格は難しいでしょう。
筆記試験と個別面接、どちらもバランス良く対策を行っていく必要があります。
第1次試験(筆記試験)
| 種目 | 時間・解答題数 | 内容 |
|---|---|---|
| 基礎能力試験 | 1時間50分・30題 | 公務員として必要な基礎的な能力・知識についての筆記試験【内容はA・B共通】 |
| 専門試験(多肢選択式) | 2時間20分・40題 | 専門知識についての多肢選択式試験【内容はA・Bそれぞれ異なる】 |
| 専門試験(記述式) | 1時間20分・1題 | 専門知識についての記述式試験【内容はA・Bそれぞれ異なる】 |
国税専門官の筆記試験は、大きく「基礎能力試験」と「専門試験」の2つに分類されます。
基礎能力試験は、国税専門官AとBで共通の内容です。
一方、「専門試験」は「多肢選択式」と「記述式」の2種類に分かれており、国税専門官A・Bで試験内容が異なります。詳しい試験内容や、出題科目については次章で詳しく解説します。
第2次試験(個別面接)
| 人物試験 | 人柄、対人的能力などについての個別面接 |
|---|---|
| 身体検査 | 主に一般内科系検査 |
第2次試験では個別面接と身体検査が行われ、これは国税専門官A・Bで共通の内容です。身体検査では、視診、問診、聴打診などの方法で行われ、主に一般内科系の検査が実施されます。
国税専門官試験の詳しい内容と対策ポイント

それでは、国税専門官試験に最終合格するためには、どのように対策をすれば良いのでしょうか。この章では、試験の詳しい内容と対策のポイントについて解説します。
基礎能力試験【A・B共通】
| 知能分野(24題) | ・文章理解(10題)・判断推理(7題)・数的推理(4題)・資料解釈(3題) |
|---|---|
| 知識分野(6題) | ・自然・人文・社会に関する時事、情報(6題) |
基礎能力試験は、国税専門官AとBで共通の試験です。5つの選択肢から正答を選ぶ「多肢選択式」のマークシート形式で実施されます。
基礎能力試験の出題内容は大きく「知能分野」と「知識分野」の2つに分かれており、「知能分野」の配点が圧倒的に高いです。そのため、基礎能力試験の対策は「知能分野」に重点をおいて進めていくとよいでしょう。
✓対策のポイント
・出題範囲が広いため、過去問で傾向を掴むのが大切
・数的処理、文章理解といった出題数の多い科目を重点的に対策
・知識分野は、専門試験の知識で正答できる「社会」分野や頻出ジャンルに絞って対策
専門試験(多肢選択式)
| 【国税専門A】 | 【国税専門B】 | |
|---|---|---|
| 必須 | 【16題】 ・民法・商法(8 題) ・会計学(簿記含む)(8題) | 【16題】 ・基礎数学(12題) ・民法・商法(2題) ・会計学(2題) |
| 選択 | 【下記から4科目・24題を選択】 ・憲法・行政法(6題) ・経済学(6題) ・財政学(6題) ・経済学(6題) ・政治学・社会学・社会事情(6題) ・英語(6題) ・商業英語(6題) | 【下記から24題を選択】 ・情報数学・情報工学(10題) ・統計学(6題) ・物理(8題) ・化学(6題) ・経済学(6題) ・英語(6題) |
国税専門A
国税専門Aの試験は、16題の必須科目と24題の選択科目によって構成されます。
最も大きな特徴は、「商法」や「会計学(簿記含む)」が必須科目として設けられていることです。「商法」「会計学」は国税専門官特有の科目であり、他の公務員試験ではあまり出題されません。
国税専門Aの試験では、「商法」「会計学」の出題数は16題と多く配点割合も高いため、これらの科目を入念に対策するのがポイントです。
国税専門B
国税専門Bは、(理工・デジタル系)の区分として設けられた試験種です。試験内容も、「必須科目」「選択科目」ともに理工・デジタル系の問題が中心となっています。
そのため、大学で理系・デジタル系の科目を学んでいた方は、国税専門Bを選択することで効率的に試験対策を進めていけるでしょう。
ただし、国税専門Bは2023年度(令和5年度)から新たに設けられた試験区分のため、過去問が少ない点が懸念されます。
✓対策のポイント
・専門試験の配点は基礎能力試験の1.5倍高い
・国税専門官特有の科目(商法・会計学など)の対策が合格のポイント
・他の試験種と併願する場合は国税専門Aがおすすめ
専門試験(記述式)
| 【国税専門A】 | 【国税専門B】 |
|---|---|
| 【下記から1題選択】 ・憲法、民法、経済学、会計学、社会学 | 【1題必須】 ・科学技術に関する領域 |
国税専門A
国税専門Aの専門試験(記述式)では、憲法、民法、経済学、会計学、社会学の5科目の中から1題を選択して回答します。出題形式は、事例問題や論述問題などが中心です。
たとえば、憲法であれば具体的な事例に憲法の条文をあてはめて論じ、民法であれば条文の解釈や適用について論じる能力が求められます。
国税専門B
国税専門Bの専門試験(記述式)は、情報、理学、工学などに関連する時事問題や社会情勢についての知識が問われる試験です。科学技術に関する領域から1題が出題されます。
解答には、科学技術に関する知識だけでなく、論理的思考力や文章表現力も必要です。日頃から、科学技術分野の話題に関心を持ち、自分の意見を言語化する訓練を積んでおくのが大切といえます。
✓対策のポイント
・国税専門Aは、憲法、民法、経済学、会計学、社会学から」の1題選択式で出題
・多肢選択式の知識をベースに、記述式特有の対策を進めていくのがおすすめ
・国税専門Bの専門試験(記述式)は知識だけでなく、論理的思考力や文章表現力も必要
人物試験(個別面接)【A・B共通】
人物試験は、筆記試験では測れない受験者の人物像を評価するのが目的です。面接官との質疑応答を通じて、受験者のコミュニケーション能力、論理的思考力、判断力などが見られます。
人物試験は、筆記試験と並んで合否を左右する重要な試験です。筆記試験で高得点を取っても、面接で低評価を受けてしまうと合格は難しくなるでしょう。そのため、筆記試験対策と並行して、面接対策にも十分な時間を割くことが合格への近道です。
✓対策のポイント
・自己分析を行い、志望動機や自分の強みやPRポイントを理解する
・自分の能力や経験が、国税専門官としてどのように発揮できるのか伝えるのが大切
・予想される質問を想定し、模擬面接などを利用して答え方を練習しておく
国税専門官採用試験に合格するのに必要な勉強時間は?
国税専門官試験の合格には、一般的に「800~1200時間」の勉強が必要といわれています。たとえば、試験本番まで半年間が残されている場合、1日に必要な勉強時間は「6〜7時間」程度です。
なお、一般的には試験の半年〜1年前から学習をスタートさせる人が多いですが、個人の学習環境によっても異なります。自身の学習環境を理解し、1日に確保できる勉強時間から逆算して勉強の開始時期を設定しましょう。
効率よく勉強を進めていくために、クレアールの通信講座を受講するのをおすすめします。クレアールの「2024年合格目標 速修国税専門官Aコース」は、国税専門官の志望度が高い人に向けた国税専門官特化の通信講座です。
国税専門官を第一志望とした併願プランに対応しており、効率の良い学習環境と面倒見の良いサポートで、国税専門官試験の最終合格に導きます。時間や場所と問わないweb学習で、最短で合格を目指したい方はぜひクレアールをご検討ください。
国税専門官の難易度に関するよくある質問
国税専門官を目指すならクレアールがおすすめ
国税専門官の試験の難易度は、国家一般職よりは低いとされています。しかし、専門知識を問われる試験のため、簡単に合格できるわけではありません。
合格には、一般的に800~1200時間の勉強時間が必要といわれています。1日に確保できる勉強時間を計算して計画的に学習を進めていきましょう。
国税専門官試験の合格を目指す方が、クレアールの通信講座を受講するのがおすすめです。
クレアールの「2026年合格 行政系(教養・専門)マスターコース」は、国税専門官の志望度が高い人におすすめの通信コースです。
国税専門官を第一志望とした併願プランに対応しており、効率の良い学習環境と面倒見の良いサポートで、国税専門官試験の最終合格に導きます。社会人からでも合格を目指せる環境が整っているため、最短で国税専門官試験に最終合格したい方はぜひクレアールをご活用ください。