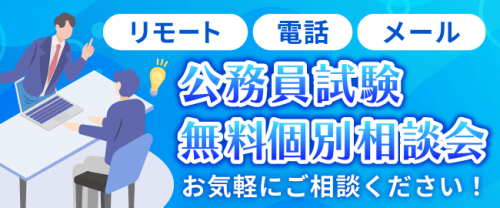公務員を目指している方の中には公務員予備校の費用相場が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、費用相場と併せて公務員予備校の選び方、公務員予備校の費用を安く抑える方法についても解説しています。ぜひ、ご参照ください。
公務員試験突破に必要な学力レベル
公務員には国家公務員と地方公務員の2種類があります。国家公務員は国全体に関わる業務を行い、地方公務員は地方自治体のサービスに関わる仕事です。公務員試験には院卒程度、大卒程度など、それぞれ学力の目安があり、そのレベルに到達するために予備校・通信講座・独学などで勉強する必要があります。
本章では「国家公務員」と「地方公務員」に分けて公務員試験合格に必要な学力レベルについて解説します。
国家公務員の場合
国家公務員は、「総合職」「一般職」「専門職」の3種類に分かれます。
「総合職」はキャリア官僚とも呼ばれるいわゆるエリート職です。公務員試験の中で最も難易度が高いと言われており、受験レベルは「院卒者」「大卒程度」です。「一般職」の受験資格は「大卒程度」「高卒程度」があります。「専門職」とは「国税専門官」や「財務専門官」などが該当し、特定の分野のスペシャリストとしての知識が求められます。
また、受験レベルは受験資格と関係ありません。公務員試験のほとんどは、学歴不問です。ただし、年齢制限があり試験によって異なります。高校卒業程度は20代前半まで、大学卒業程度は30代前半まで、社会人経験者は59歳までです。
地方公務員の場合
地方公務員試験は「初級」「中級」「上級」の3つの種類があります。試験のレベルは、「初級」が高卒程度、「中級」が短大卒程度、「上級」は大卒程度が目安となります。
地方公務員も学歴は関係なく、年齢制限があります。年齢制限は、自治体にもよりますが、初級は21歳を上限、中級は25歳、上級レベルは30歳前後にしている場合が多いです。
公務員予備校の費用相場は?

公務員予備校の費用相場は、以下のとおりです。大手の予備校にするか、中小かで料金に差があります。中小の場合は、通信講座を取り入れている予備校が多いです。大手は実績がある分費用が高くなる傾向にあります。
| 国家公務員(総合職) | 300,000円~560,000円 |
|---|---|
| 国家公務員(一般職) 地方公務員(上級) | 200,000円~300,000円 |
また、国家公務員総合職は、一般職や地方公務員上級よりも金額が高くなります。理由は、総合職は試験の難易度が高いためです。総合職は将来の幹部候補生として採用されます。そのため試験の範囲も広く、一般職試験にはない「政策論文試験」や「政策課題討議試験」が出題されるなど試験内容に違いがあります。
大手とそうでない予備校はカリキュラムや費用に違いがあります。大手予備校では、通学教室での学習に力を入れていることが多く、そうでない予備校と比較して費用が上がる傾向があります。大手でない予備校は通信がメインのカリキュラムである場合が多く費用が安く抑えられる傾向にあります。
公務員予備校のメリット・デメリット
公務員試験合格を目指すために公務員予備校を利用するメリットとデメリットを以下の表にまとめました。ぜひご参照ください。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| カリキュラムがあり、計画的に学習を進められる 講師に直接質問できる 最新の試験情報を得やすい 予備校仲間ができる(通学) 1,2年で一通り必要な範囲を学習できる 自分の時間に合わせて勉強できる(通信) 自分のペースに合わせて分からない講義は何度でも視聴できる(通信) | 費用が高額な傾向にある 通学に時間と費用がかかる(通学) 授業スケジュールに合わせて一日の予定を決めなければならない(通学) 柔軟に学習を進めるのが難しい |
予備校は、試験情報が得られ、無駄のないカリキュラムで学習できる反面、独学に比べて費用がかかります。
また、通学の必要な予備校である場合は、移動費が必要であることと学業や仕事に移動時間を踏まえて日々スケジュールを立てなければならないのがネックです。
ただし、通信講座の予備校を利用すれば自分のライフスタイルに合わせて勉強ができます。それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、自分に合った勉強方法を選択しましょう。
公務員予備校の選び方
公務員予備校はたくさんあるため、どうやって選んだら良いか分からない方も多いでしょう。本章では公務員予備校の選び方についてお伝えします。
費用
なるべく費用は抑えられると良いですが、安いなりの内容であれば、公務員予備校に入学する意味がないでしょう。たとえば、公務員試験には必ず面接試験もあります。どんなに筆記試験の点数が良くても面接で不合格になるケースもあります。そのため面接が苦手な方は、面接対策ができる予備校を選ぶのが良いでしょう。
また、授業内容だけでなく、分からない点を講師に直接質問できるのか、学習相談のサポートの有無なども加味したうえで妥当な費用かを考えましょう。
希望する公務員試験のレベルに対応しているか
国家公務員の総合職と地方公務員では必要な学力レベルが異なります。また、自分が目指す職種によっても必要なカリキュラムが違ってきます。たとえば、国家公務員総合試験には「政策論文」の試験があるため、論文添削のサポートが含まれていると安心でしょう。
自分が目指す試験のコースがあり、試験科目をしっかりと網羅できるカリキュラムとなっているか、チェックしましょう。
合格実績
合格実績は公務員予備校を選ぶ際の、一つの目安となります。直近の合格者数を確認する際は、自分の目指す試験で何人合格しているのかを確認しましょう。合格者の多い予備校は、試験合格のためのノウハウや情報をたくさんもっていることが多いです。また、合格実績の数で予備校がどの職種に強い学校なのかも分かります。
カリキュラム
予備校のカリキュラムが綿密に組まれているかチェックしましょう。また、自分にとってスケジュールが、無理なく最後まで受講できるペースなのかも大切です。スケジュールに余裕がないと予習や復習をする時間がなく、授業を効率的に活用できない可能性が高くなります。
公務員試験は多岐にわたる知識とスキルを要求されるため、計画的に学習を進めることが重要です。たとえば、カリキュラムが段階的に進められる設計となっている予備校を選ぶことで、効率的に学習を進められるでしょう。
自宅・学校・会社からの距離
通学の場合、通いやすい距離であることが大切です。通学に時間がかかると勉強時間の確保にも影響がでる可能性もあります。通学できる公務員予備校を探す場合は、金額やカリキュラムの内容だけでなく、通学が負担にならない範囲であるかも大切なポイントです。
もし、カリキュラムの内容が自分に合っていても、通学には適していない場合は、通信講座に対応した講座がないか、予備校に問い合わせをしてみましょう。
雰囲気
通学で公務員予備校に通う場合は、必ず実際の学校の雰囲気を見ましょう。体験入学を設定している予備校もあります。予備校の雰囲気や、通っている生徒は大学生が多いのか、社会人が多いのかなど、行ってみないと分からないことも多いでしょう。
また、空調設備がきちんと整っているか、自習室が騒音を気にせず集中できる環境かなども通学で勉強するには大切な要素です。入学前に自分の目で確認しましょう。
公務員試験の学習費用を安く抑える方法
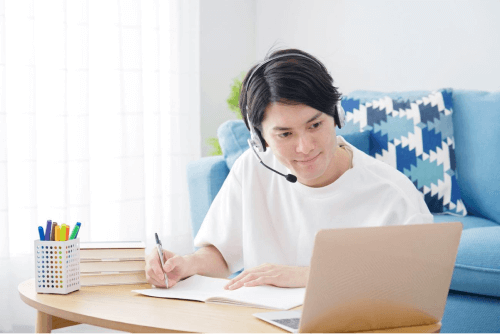
予備校に入るとしても、少しでも費用は安く抑えたい。という方は多いでしょう。公務員試験の学習費用を安く抑える方法についてお伝えします。
予備校の割引やキャンペーンを利用する
公務員予備校では、予備校独自のキャンペーンを実施していることがよくあります。期間限定でキャンペーンを実施していることも多いため、まずは自分の気になるコースが割引の対象になるか、各予備校サイトをのぞいてみるとよいでしょう。
大手の予備校は候補から外す
大手の予備校は、費用が高額の傾向があります。大手だけでなく中小の予備校も検討全体的にしてみましょう。
中小の予備校になると通信講座がメインの所もありますが、カリキュラムが充実した学校もたくさんあります。大手だけに絞らず中小規模の予備校も検討しましょう。
通信講座を利用する
通信講座は、通学タイプに比べて費用が安く抑えられます。通信講座の場合は、通学にかかる交通費もかかりません。
クレアールは通信講座に特化した予備校で、時間の縛りを感じず、大手通学スクール並みに充実したカリキュラムでありながら重要度に分けて学習を行える非常識合格法を採用しているため、講義を効率的に学習できます。また校舎コストがかからない分リーズナブルに学習できることも大きなメリットです。
公務員予備校の費用にまつわるQ&A
公務員予備校の費用を抑えたいなら通信講座がおすすめ
公務員予備校の費用相場や選び方、費用を安く抑える方法についてお伝えしてきました。
費用を安く抑えたい方には、通信講座がおすすめです。
クレアールの公務員講座は「合格できる通信講座」をモットーにカリキュラムが組まれています。また、通信講座は1人で頑張れるか不安な方もいるかもしれませんが、クレアールでは専任のサポート制なので安心です。ぜひ、お問い合わせください。

この記事を監修した人
クレアール公務員相談室タニオカ
これまで、公務員試験の受験・学習を考える3,000人以上の相談に答えた実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」などを執筆。