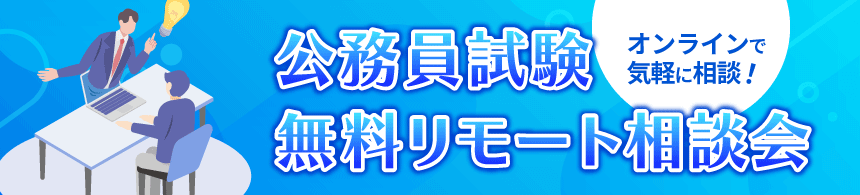仕事との両立はできる?
公務員への転職を考える多くの社会人にとって、最も気がかりな点が、「仕事と学習の両立」です。
今回は、働きながら公務員試験の合格を目指せるかどうかを一緒に考えていきましょう。
合格に必要な時間をイメージする
仕事の忙しさや勤務体系、生活環境は人によって異なるため、まずは受験先の試験タイプと学習期間をもとに、1週間あたりの平均学習時間を算出してみることがおすすめです。
| 試験のタイプ | 学習時間の目安 | 学習期間が1年間の場合 |
| 教養+専門タイプ | 1,000時間 | 1週間あたり19時間 |
| 教養試験のみタイプ | 500時間 | 1週間あたり9.5時間 |
地方上級や国家一般職などの大卒程度試験は、教養試験と専門試験が課されるため、トータルで1,000時間程度の学習時間が必要と言われます。
もし、ちょうど1年間で学習しようと考えた場合は、1,000時間÷52週間=19時間が1週間あたりの学習時間ということになるため、1週間の中で19時間が消化できるかをシミュレーションしてください。
「平日は2時間、土日はそれぞれ5時間ずつ勉強できそうだ…」
「残業が多いから仕事の日は30分できるかどうか…。休みの日に頑張ろうかな」
このように、学習ペースを週単位でイメージすることで、仕事と学習が両立できるかどうかを判断できるのです。
学習時間の確保が難しい場合
学習時間をシミュレーションした時に、人によっては仕事との両立が難しく感じることもあると思います。
そんな時は「自分には公務員への転職は不可能だ」と悲嘆せず、今度は受験プランの見直しをしていただくことをおすすめします。
学習時間の確保が難しい場合は、次のような視点で受験プランの見直しをしてみましょう。
➀受験先を変更する
先ほどのシミュレーションでは、1年間をかけて教養・専門試験の対策を立てることを前提にしましたが、教養・専門試験の学習が難しい場合は、学習負担の少ない受験先に変更することもおすすめです。
例えば、教養試験のみで受験できる自治体を受けるのであれば、学習時間は半分になるので週に9時間弱です。
昨今では、県庁・政令市などで教養・専門が課される枠と、教養のみで受験可能な枠を用意しているケースもあるため、もし志望先にそのような枠があれば、教養のみでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
②受験の時期を変更する
受験先にこだわりたい、とお考えの方には学習期間の見直しをしていただくことも選択肢の一つです。
学習期間が1年間では仕事との両立が難しい、教養のみで受験できる枠もない…ということになったら、1年後ではなく2年後の試験を目標にして学習すれば、日々の学習時間は軽減できます。
ただし、学習期間が長くなるということは、仕事をしながら学習する生活が長期に渡ることでもあるため、その負担と上手に付き合っていくことが必要です。

1年間だと微妙に時間が足りるか不安だけど、最初から2年後の合格を
目指すのも悩ましいですね…
もし、あなたがこのように悩まれているのであれば、2年後の合格を目指すという方法はなるべく避けて、1年後の試験に向けてチャレンジしていただくことをおすすめします。
なぜなら、目標地点を2年後にした場合、時間的なゆとりと引き換えに「エンジンをかけるタイミング」を失う可能性があるからです。
ゆとりがあると、「まだまだ時間がある」という気持ちから、今すぐ頑張る理由が見つからなくなってしまうため、エンジンがかからないまま1年間を過ごしてしまい、結局学習もあまり進まないまま、2年目に慌ててエンジンをかけ始めたものの、最終的には学習時間が足りなくなってしまうのです。
(これはまだ良いほうで、場合によっては気持ちが弛緩してしまい、気が付くとモチベーションも消えていることも考えられます)
2年かかるかもしれないのであれば、1年目は最初からエンジンをかけた状態で本試験に臨んだ方が、質の高い学習ができます。
もちろん、十分な学習時間が確保できない可能性もあるので、出題ウェイトの高い科目に絞って得点効率の高い学習を進めていくことも大切ですが、もし1年目に残念な結果になったとしても、2年目のチャレンジは最初から2年後を目指した時よりも力をつけた状態で臨むことができるのです。

一度不合格になってしまった自治体で、翌年受験する時に不利になりませんか?
大丈夫です。何回か同じ自治体を受験して合格したという方もいらっしゃいます。
③学習環境を変える
これは最後の手段ですが、「受験先にはこだわりたいけれど、来年が年齢上限ラストなので必ず合格したい!」という方は、会社を辞めて学習時間を確保するということも、考えておいてもよいと思います。
ただ、これは「仕事との両立」ができないということにもなるので、➀や②の選択が難しい場合に残された選択肢とお考え下さい。

いったん会社を辞めて、転職してから受験しても問題ないですか?
今の仕事を退職をすることで「無職のまま受験をする」ことや、「後ろ盾のない状態で受験をする」ことへの不安から、このようなご相談をいただくこともありますが、これは必ずしもよい選択とは言えません。
なぜなら、せっかく退職をして学習時間を確保できる状況になったのに、入った会社が思ったよりも忙しくてなかなか学習ができなくなってしまう可能性があるからです。
それだけでなく、無職の状態で受験をすることのリスクをなくすために転職したとしても、面接で「なぜ転職したばかりで公務員試験を受けているのか」と聞かれた時に先方の納得いく回答が難しくなる恐れもあります。
「公務員試験を受験するために残業のない企業に転職した」という回答をしてしまうわけにもいかないため、場合によっては面接のムードが悪くなってしまうことも考えられます。
もちろん、あくまでも推測ですが、受験期間中に転職をするのであれば、こうしたことも考えて判断することが大切です。また、無職の状態で受験をすることは、ここまでしなければいけないほど不利な受験ではないと思います。
学習時間の作り方と、おすすめの学習法
忙しい社会人の皆さんにとって、まとまった学習時間を確保するのは容易なことではないでしょう。
また、働きながら学習を進める上では、どのような手段を選べばよいのか迷われる方も少なくないため、ここでは「学習時間の作り方」と、「おすすめの学習法」についてお話させていただきます。
学習時間の作り方
学生時代と比べて、まとまった時間を確保できないことが、社会人受験生共通の悩みですが、無理に作ろうとするのはおすすめできません。
例えば、仕事から帰って3~4時間学習しようと思っても、帰宅時間が遅い方は、疲れて集中できないだけでなく、十分な休養が取れなくなり、次の日の仕事にも影響が出てしまいます。
このような生活を長期間にわたって続けることは難しく、学習効果も決して高いものとはいえなくなります。
無理に夜更かしをするよりも、少しでも早く寝て、次の日に30分、1時間でも早く起きる習慣をつけることがおすすめです。
「朝活」という言葉もすっかり定着しましたが、やはり睡眠を取ってリフレッシュしてからのほうが勉強したことは身につきやすいという認識が広まったのではないでしょうか。
もちろん、仕事が朝早い方もいると思いますので、すべての方が同じように実践するのは難しいのですが、そういう方は帰宅が早ければ無理のない範囲で学習しましょう。
次に、日常生活の中に素材する「すきま時間」の活用についてお話いたします。
例えば、食事中や休憩中、移動中など5分でも時間があれば、1問でも問題を解くなど、短い時間でできることを決めて取り組んでいけば、小さな積み重ねが大きな効果を生むことにもつながります。
ある合格者の方は、問題集を手にベッドに入り、寝る前に10分程度は問題を解いたり、通勤中は講義の音声をスマートフォンで流しながら移動するなど、日々の生活にある、すきま時間を学習に充てる習慣づけをされていました。
おすすめの学習法
公務員試験の学習方法には、「予備校に通う」「通信講座を受講する」「市販の書籍で学習する」など、様々な方法がありますが、社会人の方にとっては、講義の時間が決まっている通学講座よりも自分のペースで学習できる通信講座は最後まで続けやすい学習方法といえます。
もちろん、通信講座は「仲間づくりができない」「自習室での学習ができない場合がある」「疑問をその場で質問できない」といった点をデメリットに感じる方もいると思いますが、何よりも「通信講座は最後まで続けるのが難しい」「一人で学習するのは大変」といった不安を持たれる方もいらっしゃいますので、皆さんには通信講座でよくある「挫折の原因」と、「最後まで続けるコツ」についてお話させていただければと思います。
ぜひ、こちらの記事もご参考ください!。


監修:クレアール公務員相談室タニオカ
これまで、公務員試験の受験・学習を考える3,000人以上の相談に答えた実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」などを執筆。