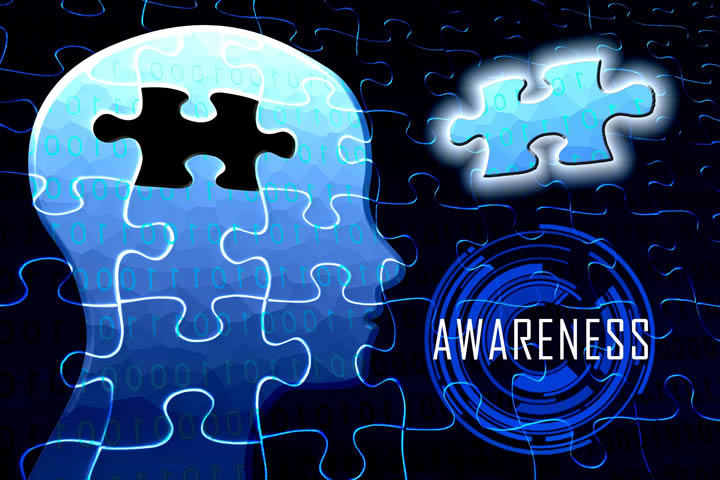1. はじめに
簿記の学習では、取引に応じた仕訳をすることが多くあります。簿記を始めて間もない方であれば、1つ1つの仕訳を書きながら仕訳のルールや勘定科目を身体で覚え込んでいくことが多いと思います。
しかし、ある程度学習が進んで簿記という科目に慣れてくれば、「仕訳を1つ1つ丁寧に書く」ことが必ずしも良いこととは限らなくなってきます。日商簿記1級以上の高いレベルはもちろん、日商簿記3級対策の中でも「仕訳をなるべく書かない」学習が役に立つことがあります。
ということで今回は、学習の中で「仕訳を書くかどうか」というテーマに基づき、学習の生産性について考えていきたいと思います。
2. 入門期における仕訳の思考プロセス
仕訳という作業に慣れていないころ、仕訳1つ1つを丁寧に考えると次のような感じになるでしょうか?
(例①:現金200円を銀行から借り入れた。)

え~と、現金200円増えているなぁ…。 現金は資産で、資産が増えたら左(借方)だったはず…。 だから、左に「現金200」と書こう。
| (借) | 現 金 | 200 | (貸) |

それから、右側にも何か書かなきゃいけないんだよな~。 え~と、借金しているから負債が増えるんだよな…。科目名なんだっけ? あ、思い出した!「借入金」だ!
| (借) | 現 金 | 200 | (貸) | 借入金 | 200 |
(例②:商品300円を売り上げ、代金は相手先振出しの約束手形で受け取った。)

え~と、「現金」は出てこなさそうだなぁ…。何がどうなるか…。 とりあえず、商品を売ってるから「売上」って科目使うんだっけ? たしか、「売上」っていう収益の発生と考えるんだっけ? 収益って、右(貸方)?左(借方)? そういえば、損益計算書の場所と整合してたはず! 損益計算書では右(貸方)に書くから、仕訳も右か!
| (借) | (貸) | 売上 | 300 |

そして、「約束手形で受け取った」ってあるけど、「約束手形」っていう資産あったかな? ちょっとテキスト見てみよ…。あ、「受取手形」って科目が載ってる!これだ!
| (借) | 受取手形 | 300 | (貸) | 売上 | 300 |
少し脚色しすぎでしょうか?(^_^;)
ですが、簿記の仕組みがあやふやな人にとっては、「何をどっちに書くべきか?」「勘定科目(科目の名称)が何だったか?」「そもそもこの取引は何をしているのか?」などといった初歩的な部分で悩むものです。簿記に慣れた人に比べると、仕訳1本を切る時間は当然長くなります。
この段階では、同じ問題を何回も繰り返す形で良いので、たくさん仕訳を書きながら、仕訳のルールや勘定科目をマスターしていくことが重要です。答えやテキストを見ながらでもいい(むしろガンガン見た方が良い)ので、どんどん手を動かし、手を動かしながら一生懸命仕組みを考えましょう。そうすることで、仕訳や複式簿記の仕組みに慣れていくことができますし、勘定科目(科目の名称)も自然と覚えていくことができます。
3. 簿記に慣れてきたら
複式簿記の仕組み(とくに仕訳)に慣れるとともに、基本的な勘定科目がスラスラ出てくる状態になれば簿記に慣れてきたといえるでしょう。日商簿記3級の受験生であっても、テキストや問題集の復習が一通り終わり、過去問や答練を使ってバリバリ実践対策をする頃になれば、そのような状態の人も出てくるはずです。
そのような状態になれば、上記2.で示した例のような取引くらいであれば、わざわざ書くまでもなく仕訳の形を思い浮かべることはできるはずです。取引の文章を見た瞬間、仕訳を即答できるはずです。
このように簿記に慣れてきたら、単に仕訳を正確に行うだけでなく、1つ1つの仕訳にかける時間を短縮していくと良いでしょう。仕訳にかける時間を短縮することで、学習の生産性を格段に上げていくことができます。
仕訳にかける時間を短縮していくには、学習状態に応じて次のような段階を踏むと良いでしょう。
(1) 書かないと仕訳を整理できない状態
→ まだ丁寧に書きながら練習していくが必要な段階です。
地道に練習を積み重ねましょう。
(2) 典型的な勘定科目であれば書くまでもなく思い出せる状態
→ 「現金」や「当座預金」、「売掛金」など当然に知っている勘定科目をいちいち漢字でしっかり書くのがメンドウになってくるはずです。そうなってくれば、どんどん略字を使って時短していきましょう。
(略字の例)
- 現金:Cashの「C」など
- 当座預金:「当ヨ」や「ト」など
- 売掛金:「売×」や「ウ×」など
(3) 典型的な取引であれば、仕訳自体を瞬時に思い浮かべることができる状態
→ 書かなくとも仕訳を考えることができるようになれば、あえて書かずに頭の中で考える練習が有効になります。
「考えるスピード」が「書くスピード」を上回る状態になれば、短時間でより多くの仕訳を勉強することができます。
4. 仕訳を書かないことのメリット
仕訳にかける時間を短縮し、最終的に仕訳は「頭の中で考える」ようにすることで、次のようなメリットがあります。
(1) より多くの問題を繰り返すことができる
1つの仕訳に2分(120秒)かけていた人が、20秒程度で考えて済ますようにすることで、時間は6分の1になります。同じ問題を6分の1の時間でできるようになれば、同じ時間でこれまでの量の6倍も勉強することができます。
同じ時間机に向かっていても、どれだけの量をこなしたか、どれだけ多くの情報を頭の中に通過させたかで成果は大きく変わってきます。単純な学習量を考えただけでも、学習の生産性が上がることがわかるはずです。
(2) 思考力の訓練になる
同じ仕訳でも「紙に書きながら整理する」のと「頭の中で整理する」のとでは、後者の方が思考力を要するはずです。より多くの仕訳を、より思考力を要する方法でこなしていくことで、より質の高い学習をすることができます。
(3) 総合問題を楽に解くテクニックがマスターしやすくなる
日商3級の第5問や日商2級の第3問で出題されることのあるB/S・P/L作成問題のように、ある程度ボリュームのある仕訳を反映する形で解答を作っていく総合問題があります。一般的には必要な仕訳を下書きし、その仕訳を集計しながら解答を作っていく方が多いと思われます。
しかし、仕訳自体の下書きを省略するテクニックを使うことで、短時間で解答を作っていくことができます。このテクニックを使うためには、典型的な仕訳はある程度頭で考えられる必要があります。
5. 最後に(上記4.(3)のテクニックについて)
総合問題を楽に解くテクニックですが、そのポイントは次のとおりです。
- ① 簡単な計算で済む科目、問題文からそのまま移すだけで済む科目については、それに気付いた時点で解答を埋めておく
- ② ある程度の増減を集計する必要のある科目は、問題文の決算整理前残高試算表などに直接増減をメモする
- ③ 問題文の余白に集計できなさそうな科目は下書き用紙にT字フォームなどを用意して集計する
今回の記事は紙幅の都合でここまでとさせていただきますが、具体的な解説は次回以降の記事で書いていきますので、引き続きよろしくお願い致します。