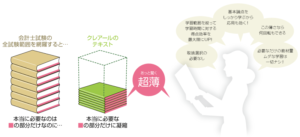はじめに
前回のVol.26.では、日商簿記1級の会計学・商業簿記のうち、純資産会計(資本金・剰余金等)と新株予約権・新株予約権付社債について、論点別の具体的な対策方法をご紹介しました。今回も前回に引き続き、主に日商簿記1級での新規論点・応用論点を取り上げ、それぞれの学習のコツをご紹介したいと思います。
ストック・オプション
ストック・オプションは、日商簿記1級で学習する新規論点です。前回のVol.26.で取り上げた新株予約権のうち、特に企業がその従業員等に報酬として付与するものがストック・オプションと呼ばれています。従業員等は一定の条件下で新株予約権の権利を行使し株式を取得することができますが、なぜ企業は現金ではなく新株予約権を従業員等に付与するのでしょうか。簡単に言えば、一般的に企業の業績が向上することで株価が上昇し従業員等の報酬が増加するため、従業員自身の報酬である株価が上昇するために(すなわち企業の業績向上のために)前向きに従業員等が働くことが期待されるからです。このように企業と従業員等の利害が一致することで、企業の業績向上のためのインセンティブを従業員が持つことができるため、多くの企業でストック・オプション制度が導入されています。
ところで、本記事を執筆している2023年10月時点では、主にベンチャー企業の界隈を中心として数あるストック・オプションのうちの一つである信託型ストック・オプションが大きな注目を浴びています。内容がかなり専門的となってしまいますので詳細は割愛しますが、国税庁が信託型ストック・オプションに対する税務上の取り扱いを発表したことにより税金の支払額が増加するというネガティブなケースが生じうるため、世の中の注目の的となりました。ストック・オプションは仕組みが複雑であることも多く、初めのうちは理解するのが大変ですが、日商簿記1級でその基礎を学習することはとても有意義ですので、前向きに学習していきましょう。
まず、ストック・オプションを学習するうえでは、論点の全体像を把握するようにしましょう。ストック・オプションは①基本的な会計処理(発行から権利行使又は失効まで)、②条件変更の会計処理、③未公開企業における会計処理の3つに大きく分類することができます。このうち①基本的な会計処理(発行から権利行使又は失効まで)については、固定資産の減損等の論点と同様にストーリー仕立てで一連の会計処理を理解すれば効率的に学習を進めることができます。ただし、権利不確定による失効の見込みがある場合には会計処理のパターンが変化しますので、注意して学習するようにしましょう。なお、②条件変更の会計処理については、”ストック・オプション数を変動させる条件変更”や”費用の合理的な計上期間を変動させる条件変更”に関する例題がテキストに掲載されていますが、これらの論点は主に公認会計士試験で取り扱われる応用的な論点ですので、日商簿記1級時点では時間に余裕がなければ対策しなくても問題ないかと思います(たとえ日商簿記1級の本試験問題でこれらの論点が出題されたとしても、公認会計士試験の対策をしていない多くの受験生は正答できないのではないかと思います)。
次に、ストック・オプションの問題を正確に素早く解答するためには、上手に下書きするように心がけることが非常に効果的です。クレアールのテキストでは例題の解答欄に下書き例が掲載されているので、真似して下書きしてみてください。特に、権利不確定による失効の見込みがあるストック・オプションの問題を回答する場合、暗算のみで計算をすることは困難ですので、素早く正確な下書きと計算ができるようになりましょう。
また、日商簿記1級の本試験問題を解くときには、問題用紙の重要な記載を見落とすことがないように問題文に下線や丸を付けるとスムーズに解答ができます。私の場合、ストック・オプションの計算問題を回答するときには、迷わず問題文のうち下記の記載個所を丸で囲むようにしていました。
・ストック・オプション数は1人あたりいくつ付与されるのか
・ストック・オプションの行使により与えられる株式数はいくつなのか
・権利確定日・権利行使期限はいつなのか
・ストック・オプションの権利行使時の払込金額は1株あたりいくらなのか
・付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価はいくらなのか
・株式発行による払込資本増加額は、全額資本金として計上するのか、それとも一部を資本剰余金等で計上するのか
・権利不確定による失効の見込みがあるか(もし失効の見込みがある場合、いつどれだけの人数分だけ失効することを見込んでいるのか)
・各年度のストック・オプションの失効数及び権利行使数の具体的な数値
ストック・オプションの問題が出題された場合、他の論点と比較して問題文の分量がかなり多いです。正確な素早い計算をするためには下書きに必要な情報を瞬時に問題文から読み取る必要があります。したがって、上記の記載個所に印を付けておけばスムーズに下書きすることができると思います(何度も問題を解いていれば問題文をべた読みすることなく、必要な情報の記載箇所をスムーズに把握することができるようになります。そのようなレベルまで対策が進めば、本試験問題でストックオプションが登場したとしても怖いものなしでしょう)。
おわりに
今回は、日商簿記1級の会計学・商業簿記のうち、ストック・オプションについて、具体的な対策方法をご説明しました。次回も今回に引き続き、論点別の具体的な対策方法をご説明しますので、乞うご期待ください。