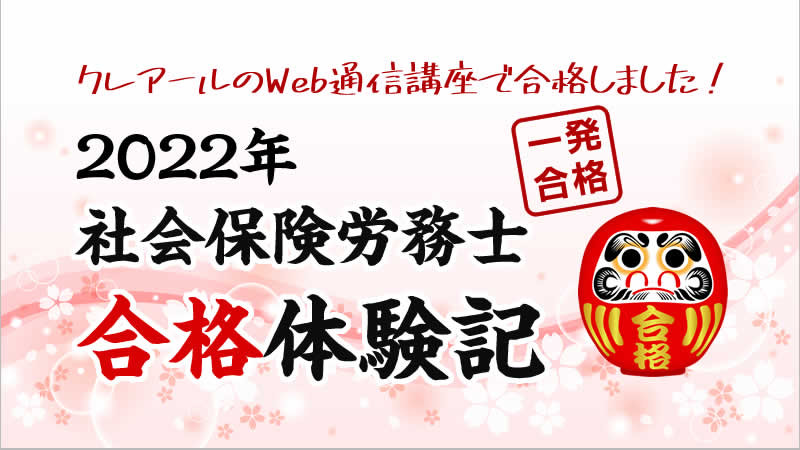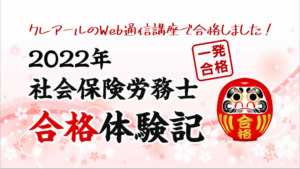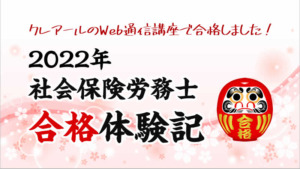津田 直暉さん

- 受験回数:1回
- 一発ストレート合格セーフティコース
社会保険労務士資格を目指したきっかけ
前職の民間企業で労働組合活動を行っていた際に、労働基準法に触れ、労働関係の資格を取ろうと思い、社会保険労務士の資格に興味を持っていました。前職の民間企業で働きながら、公務員への転職活動をしていましたが、公務員に転職してからも勉強する習慣を継続したいと思い、元々興味のあった社会保険労務士を受験しようと思いました。
情報収集の方法
インターネットの講座比較サイトを拝見し、金額、コース内容等を比較しながら、予備校選びをしていました。
クレアールを選んだ理由
セーフティコースの存在が決め手となりました。当初は2年コースで勉強しようと考えていましたが、1年目もお試し受験しようと考えていたため、1年目に仮に合格した際に返金のあるセーフティコースに魅力を感じ、クレアールを選びました。働きながらの受験でありましたが、実際に学習をはじめてみると、講義時間が短く要点がまとまっており、短時間で効率的に学習を進めることができました。
学習スケジュール
5月までは講義を聞いて1~2回過去問集を回していました。学習範囲が膨大であり、復習が追いつかないまま、次々先に進めましたが、失敗だったと思います。先に進むことも大事ですが、余裕を持った学習スケジュールで復習の時間を適宜入れ込んでおくのが適切であると考えます。5月以降は、答練の復習と過去問演習を繰り返し行いました。答練が終了した後は、過去問演習とテキストの読み込みを中心に行っていました。
学習方法
社労士試験において、以下三つの学習方法が効果的だと思います。
一点目は、過去問演習です。労働一般常識を除き、試験科目の大半は過去問の類似問題の出題であり、過去問を何回「回せるか」が一つの鍵であると考えます。私は、クレアールの過去問集を何度も回し、繰り返すうちに模試の点数が徐々に良くなっていきました。過去問を繰り返すことが、試験のスタートラインに立つ最低条件だと思います。
二点目は、テキストの読み込み並びに音声学習です。試験本番では、過去問で見たことのない問題やその場で考えさせる事例問題等が多数出題されます。合格には、学習を通じて培った基礎力から、その場で考えて答えを導く応用力が不可欠となります。そのためには、テキストの読み込みや音声学習を通じて、条文や通達、制度等の根本的理解を図り、過去問で学んだ点を線にして繋げていく必要があります。実際に、私は過去問演習が一段落した後、完全合格テキストの読み込みや授業の音声を聞くことをまとめて行っていましたが、普段の学習から行うことをオススメします。
三点目は、選択式対策並びに一般常識対策です。人それぞれだと思いますが、私は、選択式の足切りを回避すること、学習範囲が膨大で過去問がほぼ通用せず、また、学習が難しい統計問題が出題される一般常識が、社労士試験の最大の壁であると感じていました。その最大の壁を乗り越えるため、人一倍、選択式対策並びに一般常識対策に取り組んだと思います。選択式対策では、選択式専用の問題集を購入し、間違えたところを何度も復習しました。また、他予備校のオプション講座をいくつか受講し、選択式の解き方や予想問題を解き、選択式問題に慣れることを心がけました。一般常識対策も同様に、他予備校のオプション講座を受講し、普段の学習ではカバーできていなかった論点や今年出題されそうなテーマの情報収集を図り、受講したテキストの復習を何度か行いました。
印象的なエピソード
6月頃まで答練が続きましたが、選択式では足切りが当たり前、択一式では10問中2問しか解けないなど、散々な成績でした。6月に受けた外部模試では、選択式は何科目か足切り、択一は35点であり、試験2か月前にして、合格にはほど遠い状況でした。その後、何度も過去問演習を行い、テキストの読み込み等を行っていく中で、模試の成績が徐々に上がっていき、大逆転合格を果たすことができました。
今後の展望
現職を辞めるつもりはないので、現職の中で労務管理や保険事務等の業務に活かせたらと思います。合格率の低い難関資格を10か月の勉強期間で一発合格できたことは自信となったので、より難易度の高い難関資格に挑戦することも考えています。
合格を目指している皆様へ
社労士試験は最後までどうなるか分かりません。私は試験の数か月前時点で合格にはほど遠い状態から最後まで粘り続け合格まで持っていくことができました。キーワードは、「アウトプット+インプット」です。過去問を活用してアウトプットを行い、テキストの読み込みでインプットしていく、それが合格に近づく王道の勉強法だと思います。最後まで諦めず頑張ってください。