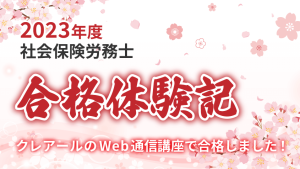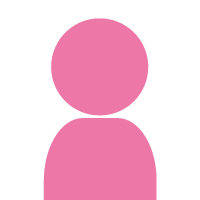 Y.U.さん
Y.U.さん講義のわかりやすさと問題演習の豊富さが合格につながった
社会保険労務士資格を目指した理由
自分自身が仕事をしている業界の働き方・労働環境に疑問を抱いている中で、「今ある法律の中で、どうやったらよりよい環境作りをしていけるのか」ということを考えていた際、「社会保険労務士」という資格があることを知り、目指してみようと考えました。
予備校選びのポイント
インターネットで調べる中で、独学での合格の難しさを知りました。
仕事・家庭との両立の観点から通信講座を選びました。
クレアールを選んだ理由
クレアールの前に他社の通信講座で2年ほど勉強をしていました。
ただ、妊娠・出産が重なって受験できずじまいでした。
育休中に「今度こそ受験したい」と通信講座を考え直していた中で、授業の質の高さ・演習面の充実といった理由からクレアールを選択しました。セーフティコースで2年目も保証してもらえる、というのも、職場復帰後の生活が見えていない自分にとっては大変魅力的でした。
印象的なカリキュラム・教材
- 過去問題集
従前の通信講座ではどうしてもインプットに偏りがちだったのですが、クレアール受講中は、講義の中で北村先生が口を酸っぱくして言ってくださることもあり、【講義視聴⇒過去問】の流れが徹底されました。
また、(これも北村先生が口を酸っぱくして言ってくださることもあり)違う科目の講義・過去問中に、類似科目の理解があやふやだと思ったら、そちらの科目の過去問も解く…という癖がつきました。 - 答練
斎藤先生の講義のわかりやすさは衝撃でした。各科目を一通り終え、すっかり初期の知識があやふやになった頃、斎藤先生の答練マスターで再整理ができました。
答練マスターは、問題を解く⇒講義視聴⇒あやふやな箇所は単語帳にしたり、チェックマーカーで暗記⇒過去問題を解く、という流れで進めました(ちょっと時間がかかりすぎて厚生年金あたりで息切れをしたので、もっとやりようがあったと思います)。会社のお昼休憩や通勤電車の中でも、ちょっと隙間があれば答練マスターを解きなおす…ということもしていました。
答練マスターを丁寧にやりすぎたために、ハイレベル答練の講義を聞く時間が無くなってしまい、子供を寝かしつけているときに、寝っ転がってスマートフォンでハイレベル答練の問題だけ解いていました。
また、講義内で斎藤先生が「こんなの出ません」「これは覚えなくていいです」と、覚える情報をスリムにしてくださるのもありがたかったです。講義の中でのちょっとしたエピソード・語呂合わせ・笑いを交えた解説で法律の知識を覚えやすくしてくださったことも、大変助かりました。 - コンプリーションノート
これだけあればいいじゃないか、というくらいまとまっています。
届いてから試験当日まで、通勤電車・昼休みと、隙間があれば読んでいました。
また、付箋やメモ書きで、知識も極力コンプリーションノートに一元化するようにしました。
試験当日もコンプリーションノートで朝・行く電車内・昼休憩と、集中して4~5科目は振り返ることができました。試験終了後も知識を忘れないよう、今でも通勤中は毎日読んでいます。
苦労を乗り越えたエピソード(仕事との両立など)
4月の育休中まではコンスタントに毎日3~4時間程度勉強することができたのですが、職場復帰後、仕事・育児・家事の両立の大変さから体調を崩し、また、子供も頻繁に体調を崩したため、勉強時間を確保することができない日が続きました。 そのため、5月末には「今年はお試し受験にしよう」と決め、日々の勉強は通勤電車・(できたら昼休み)・寝かしつけ中・(できたら夕飯後)と、自分にストレスになりすぎない範囲で1~2時間を確保する程度でした。また、育休中に各科目の単語帳を作っていたので、トイレに入ったら2・3枚カードを振り返る…ということもやっていました。
法改正対策や白書対策、模試などは全く手も付けておらず、答練(と付随する過去問)/横断整理/コンプリーションノートだけを、コツコツと続けていました。 本試験では、本番の雰囲気と本試験の難易度を確認し、9月からの新しい勉強計画を立てるために役立てよう、というつもりで受けました。 そして受験後、自己採点をしてみたところ、まさかの合格ラインであったため、衝撃を受けました。 はなからお試し受験と決めており、回答するときにも変な緊張や雑念がなかったのが良かったのか…今でもなぜ合格しているのか、不思議な気持ちです。
今後の展望
自分自身は社労士とは違うフィールドの仕事をしているため、兼業にするのか、勤務社労士となるのか、まだわかりません。
いずれにしても、勉強不足なのに合格してしまった、という自覚があるため、事務指定講習までの間、コンプリーションノートだけは毎日欠かさず読んでおこうと思っています。