ますます高まる社労士の需要
社会保険労務士資格は、昭和43年に誕生しました。社会保険労務士の業務は多岐にわたり企業経営の4大要素「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち、ヒトに関する採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計などの相談に応じるエキスパートです。昨今の社会情勢は「無自覚パワハラ」「コロナ禍関連の労務相談」など時代の要請が増えています。社会保険労務士の重要性や需要はますます高まっているといえます。
社会保険労務士のおもな仕事
独占業務
1号業務 必要書類の手続き代行
労働保険や社会保険の手続きについて、必要書類の手続き代行を行います。これらの保険は会社設立時に加入する義務があり、社会保険労務士は顧客である事業主の依頼を受けて、手続きを行います。例えば、労働保険に加入する際に、労働保険の保険関係設立届を労働基準監督署又は公共職業安定所に提出しなければいけません。そのためには、概算保険料申告書に則って保険料を計算し納付します。また、社会保険で言えば、支払った給与や賞与を元に保険料を計算し、保険者報酬月額算定基礎届などを提出しなければいけません。その他にも労災保険の手続きや厚生年金の手続きなど数多くあります。このような仕事は社会保険労務士の独占業務で、有資格者でないと行うことができません。
2号業務 帳簿書類の作成
主な業務は「就業規則の書類」「労働者名簿の書類」「賃金台帳の書類」など帳簿書類の作成です。
① 「就業規則の書類」
始業・就業時間、賃金、休日などについて記載されています。労働者が常に10人以上いる企業では作成が義務付けられており、労働基準監督署に提出の義務があります。
② 「労働者名簿の書類」
労働者名簿とは、労働者の氏名・年齢・生年月日、住所、職種などが定められた書類で、労働者が常時30名以上いる会社での作成が義務付けられています。
③ 「賃金台帳の書類」
賃金台帳とは全ての労働者に対して作成する義務があり、賃金が支払われるたびに作成いたします。例えば、誰がどのくらい働き、どのような計算で給与を算出しているのか、具体的に書かれています。この賃金台帳は労働基準監督者が調査する場合、必ずチェックする書類で、作成されていなかったり、内容に不備がある場合は、罰則が課されます。
広がる市場
3号業務 コンサルティング
3号業務とはいわゆるコンサルティング業務です。社会保険労務士は書類作成や手続きだけではなく、人事や労務関係の相談・指導も行います。特に近年では、派遣や非正規雇用のような労働問題や賃金制度に関する相談が多くなっています。また、企業の業績アップには、年俸制や能力給等の導入といった賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制など、働く人の能力を活かせる職場づくりへの工夫が欠かせません。社会保険労務士は、その職場の実情を専門家の目で分析し、きめ細かいコンサルティングを行います。
その他 年金相談
少子高齢化時代を迎え、年金に対する不安がかつてないほど高まっています。年金は、個人が加入している年金の種類や期間などにより支給額が異なる上に、法改正や制度自体の変更などにより、見込み支給額が増減することもありえます。社会保険労務士は、こうした年金のしくみや受給資格などについて熟知していますので、年金のプロとして活躍できます。
業務の拡大 社会保険労務士法人
社会保険労務士の業務を組織的に行うことを目的として、1名でも社会保険労務士法人の設立ができるようになりました。裁判外紛争解決等、今後さらに多様化する社会のニーズに対応するため、個人の社会保険労務士では限界がある業務も、組織的に行うことで業務の拡大が図れ、スペシャリストとしてますます活躍分野が広がっていくことでしょう。
あっせん代理 裁判外紛争解決(ADR)
裁判外紛争解決とはADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれ、仲裁、調停、あっせんなどの裁判によらない紛争解決方法のことです。社会保険労務士も平成15年4月より、個別労働紛争について、紛争調整委員会において、紛争当事者に代わり意見の陳述を行うことができるようになりました。(あっせん代理)労務管理のエキスパートとして社会保険労務士への期待がますます高まり、今後活躍分野がさらに広がっていくことでしょう。
夢を実現した
開業社労士として活躍中のAさん
海外で生活していた経験もあり最初は行政書士資格を取得して、語学を活かして在留外国人向けの仕事をしていました。その後、日本で生活していく中で在留外国人の就労問題を目の当たりにし、社労士資格を取得することを決意、現在は社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスで業務を行っています。母国語で相談したいと考える在留外国人の方達に少しでも安心感が与えられるようになればとの思いで開業しました。
企業内社労士として活躍中のBさん
現場で働いていた時に怪我をして休職することになった際に総務部が休職中の手当などについて書類の作成や相談に乗ってくれた。話を聞くと社労士の資格を持っていると聞き、私も資格を取得して現場作業の職員たちに安心を与えらえれる仕事に就きたいと資格を取得しました。現在は転職をしていますが、企業内社労士として社労士資格を活かして就業しています。社労士会の勉強会に参加しているので、いずれは人脈を広げて独立したいと考えています。
定年後も資格を活かして活躍中のCさん
生命保険会社で勤務している時に、実務に直結する知識としても、自身の生活設計上としても興味がわき受験を思い立ちました。2社の生命保険会社で2度の定年退職を経験したのち、社労士試験に合格、その後資格が活かせる職場に入職し、労働者、事業主などの相談を受けています。定年後の小遣い稼ぎにとの感覚でしたが、仕事を通して社会貢献ができることも実感しており、今後は開業も視野に入れて1人1人のお悩みを解決できる存在になっていきたいと考えています。
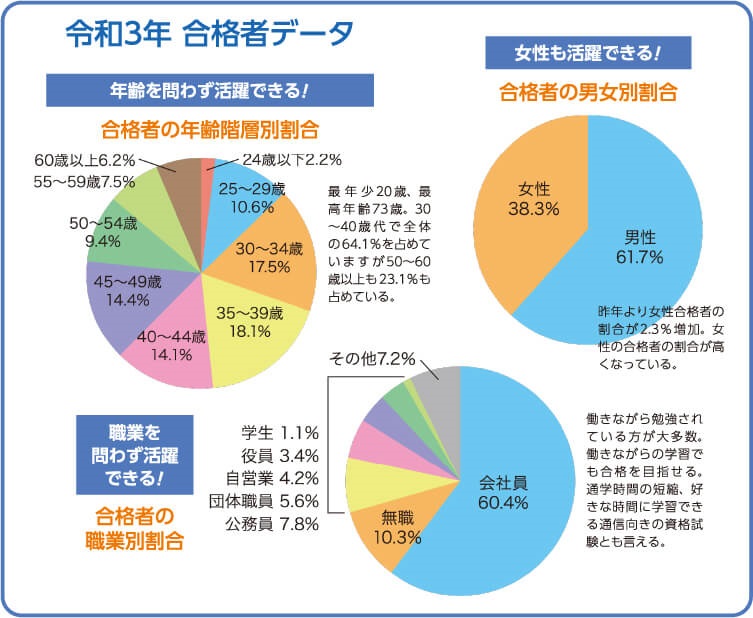
社労士資格取得後の2つの道
社労士試験に合格!
本当のスタートはここからです。
実務経験2年以上。もしくは
実務研修(事務指定講習)修了。
全国社会保険労務士
連合会に登録し、都道府県
社会保険労務士会に入会。
独立開業
独立開業は社労士の魅力の一つ。自分でやりたいように仕事ができ、稼ぎも自分次第です。しかし、独立してもお客さんは待っているだけでは来てくれないので、自ら顧客を開拓しなければなりません。社労士は独占業務があるという意味ではうまみのある資格です。しかし、競争相手が同じ社労士同士になるため、競争に勝たなければなりません。そのためには「顧客にどのような情報を提供すれば喜ばれるのか」を考え、常に最新情報を入手しておく必要があります。
企業内社労士
「社労士の資格を取得して独立」だけが資格を活かす手段ではありません。社労士の資格は、会社のスペシャリストとして活躍する企業内社労士という道があり、最近特に重要性が増しています。「人事」「労務」「社会保険」の専門家として人事・総務部や保険会社における営業マン、金融機関での年金相談窓口など、活躍の道が広がっています。また、就職や転職の際には非常に有利となります。
社労士資格取得後の活躍
“無限の可能性”を秘めた社会保険労務士資格。合格後の夢は膨らみます!
活躍できるフィールド その1 人材教育・育成
社員一人一人が、笑顔で活き活きと仕事ができる世の中に!
「企業は人なり!!」社員一人一人が、経営理念や会社の使命を共有し、組織の一員として、目標を持ち、笑顔で活き活きと仕事をしている企業は、必ず、発展します。労使トラブルやパワーハラスメントが発生しない会社、社員が自己実現できる会社、そして、明るい職場づくり。そのためには社員の教育と社員が成長し、働きがいを得ることができるしくみづくりが必要となります。「教育・育成」と「しくみづくり」私はこの2つの軸を中心に仕事をしています。「教育・育成」は新入社員研修から管理職研修まで、その企業により効果的なオーダーメイドの教育、研修を行っています。「しくみづくり」は教育計画の策定や人を育てるための人事制度づくりを行っています。もちろん、採用面接のサポートもさせていただいています。現在、特に人の質が仕事の質に大きく左右する医療や介護、保育などの福祉業界の人材育成、しくみづくりに力を注ぎ、特に福祉の現場に「感動と感謝と輝きを」をテーマに人材育成・組織活性化を全国で展開しています。

Naka Shoko
・ 株式会社マリン代表取締役
・ 人材育成・組織活性化コンサルタント
・ 中昌子社会保険労務士事務所所長
・ 社会保険労務士
福岡県出身。新日本製鐵で輸出業務に携わるも専業主婦に憧れ、3年で退職。子育てをしながら、2年間、公文式英語教室の先生も経験。10年間、主婦業に専念した後、スーパーマーケットにパートとして就職。3年後に店長になり、「顧客満足は従業員の満足から」をモットーに従業員の育成と従業員が成長する仕組みをつくる。平成15年に社員教育・人財育成の会社を立ち上げ、19年に社会保険労務士事務所も併設。現在までに延べ3万人の教育・育成を行う。2012年2月に明るい職場づくりの促進として、笑顔体操をリリースした。FM KITAQでレギュラー番組をもつ。
●株式会社マリン http://marin25.com/
●にこにこのたねプロジェクト http://niconiconotane.com/
活躍できるフィールドその2 労災 手続き
労働者が、安心して働くために。
労災保険は、労働者が、日々安心して働き続けるために必要不可欠な保険制度です。なぜなら、業務中、通勤中において、労働者の身に災害が降りかかり働けなくなってしまったなどの場合でも絶対的な保障をしてくれる制度だからです。この労働者の保護、遺族の援護という労災保険の特色と趣旨を損なうことの無いよう、会社は、労災の手続き方法や手順、判断基準などを把握しておかなければなりません。しかし、労災は突然発生します。そんな時、何より大切なことはすぐに対応できることです。さらに、労災は認定されなければ支給されません。認定されるためには「コツ」があるのです。労働者が安心して働ける環境を作りたい――村松先生は、これまでの豊富な経験を生かし、労災認定を受けられるようにスピーディーに手続きをする、「労災手続き」のプロフェッショナルとしてご活躍されています。

Muramatsu Satoshi
・ 社会保険労務士
・ AFP
1974年、静岡県浜松市生まれ。富山大学経済学部卒、明治大学大学院経営学研究科経営学専攻博士前期課程修了。大学卒業後、出版社に入社、社会保険労務士事務所2社、大手税理士法人の勤務を経てTFS社会保険労務士事務所を開業する。企業の活性化と従業員満足の向上の実現をモットーにサービスを提供。DVD『労災手続き完全マニュアル』(ブレイン・コンサル)、DVD『初めての給与計算・社会保険手続き実践マスター講座』(ブレイン・コンサル)、『ど素人がとりもどす年金の本』(翔泳社、共著)、SMBC経営懇話会『Netpress』(SMBCコンサルティング)、月刊『総務』(ナナ・コーポレート)、DVD『これで解決!モメゼロ規則の作り方』(ブレーン)、『かいけつ!人事・労務』労災事故Q&A監修(ブレイン・コンサル)、SOS総務『労災(労働災害)』『労務管理』相談室監修(ナナ・コーポレート)、産経新聞『知っ得!年金・健保・仕事』など多数執筆している。
●スパイラル社会保険労務士事務所 http://www.tfs-sr.com/
活躍できるフィールド その3 ハラスメント研修
職場環境を快適にするために、社会保険労務士ができること。
セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント…よく聞く言葉ですが、具体的に、どういった行為が該当するのでしょうか。一番の問題はセクハラ、パワハラをしている本人が、「セクハラ、パワハラ」をしているということを認識していないこと、そして、「この環境はよくない」と言い出せない職場であることなのです。職場のハラスメントをなくし、快適な職場環境を作りたい――福田先生は、ハラスメント研修を多数行なっていらっしゃいます。ハラスメントは、「これはダメですよ」と企業の経営者や管理職の方に言ったところで、すぐに解決するわけではありません。どう言えば伝えることが出来るのか、これが社労士の腕の見せどころです。企業のコンプライアンス委員会などの顧問を務められるなど経験豊富な福田先生の研修は、定評があります。2008年7月、パワハラが原因で企業側に3,100万円の支払を命じる判決が下りました。さらに、パワハラが労災の認定事由になるなど、今後さらに注目が集まることは必至です。労務管理のプロとして、社会保険労務士が活躍できるフィールドはたくさんあります。

Fukuda Kazuko
・ 社会保険労務士福田事務所所長
・ 社会保険労務士
・ キャリア・デベロップメント・アドバイザー
・ 産業カウンセラー
民間企業で経理、人事労務の業務に従事した後、平成10年に社会保険労務士事務所開設。公的機関での労働法セミナー、銀行における年金相談会のほか、ハラスメント問題の防止をはじめとする職場のリスク管理、メンタルヘルス支援についての研修を専門とする。現在、企業のコンプライアンス委員会、セクシュアルハラスメント防止委員会の顧問として、事業所の担当者と協力して問題の解決にあたるほか、外部相談窓口として多くの働く人の相談を受け、働きやすい職場環境の推進を図っている。
●福田事務所 http://fukudaoffice.jp/





