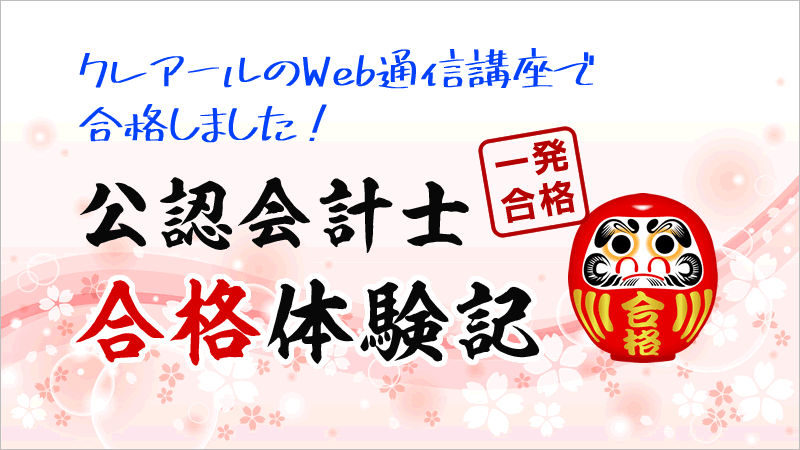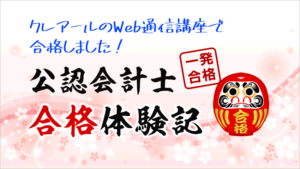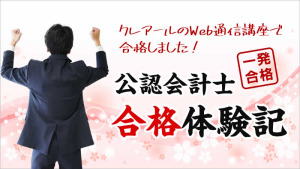学習スタートから合格までの軌跡
2023年6月 簿記1級から勉強開始
2023年11月 日商簿記1級⇒不合格
2023年12月 第Ⅰ回短答式試験(試し受験)⇒不合格
2024年5月 第Ⅱ回短答式試験⇒合格
2024年8月 論文式試験⇒合格
公認会計士を目指したきっかけ・理由
私が公認会計士を目指したきっかけは、大学の講義で教授が公認会計士をお勧めしていたことでした。その時ちょうど簿記の勉強も2級の範囲まで進んでおり、会計の分野の勉強が楽しく感じられ、これを仕事にできたら自分に合っているのではないかと感じました。
私が公認会計士を目指した理由は2つあります。
1つ目は、会計士という資格をもつことで、安定したキャリアを積むための助けとなり、なおかつ得た知識や経験により将来できることの幅が広がると思ったからです。まだ私の興味の方向性は決まっていないのですが、もし将来やりたいことができた際、会計士という1つ目のキャリアステップを生かすことができると思い、志望しました。
2つ目は、もともと私自身、日本企業を応援したいという気持ちがあったからです。公認会計士の監査やアドバイザリー、IPO支援などの業務の中で企業に直接かかわることができ、その成長を手助けできると思いました。
クレアールを選んだ理由
クレアールを選んだ理由としては、学生である私が通学での学習が困難であったため、通信専門の予備校であるクレアールを選びました。通信講座であるため、学校の勉強との両立がしやすく、自分の好きな時間に学習できるのが強みでした。
また、他校と比較したときに、圧倒的に低価格であることも魅力の一つであり、私が選んだトータルセーフティコースでは、受験料の負担をクレアールにご負担いただけるだけでなく、さらに早期合格することで合格お祝い金や未受講の講義料としてさらに返金があったので、モチベーションの維持にもつながりました。
学習方法
短答式対策
◆ 財務会計論(簿記)
1周目は講義とテキストを中心に学習しました。できるだけ早く試験範囲を一周したかったので倍速で視聴し、分からないところだけ数分巻き戻して聞いていましたが、基本的には動画単位で戻って復習はしないと決めて、1周目を終わらせることだけに集中しました。
その後は、時間をかけて分野ごとにテキストの例題を中心に復習し、今日は〇章と〇章を完璧にする、といったペースでの勉強を繰り返していました。
短答式試験の3カ月前から短答式過去問集に挑戦し始め、本番形式の問題に慣れる練習をしました。クレアールの過去問集の良いところは問題が年度別ではなく、分野別に分かれているため自分の苦手分野を中心にできるところです。
年度別だともちろん、時間配分などの調整には使えるのですが、そういったところは答練や模試で体感できますし、なにより、簡単で分かる問題を解いて安心してしまったり、時間を浪費してしまったりするのが個人的にはもったいないと思っていたので、分野別の過去問集は重宝しました。
7年分の過去問集を時間は測らずにじっくり2周したのち、2カ月前頃から時間を測って答練を解き始めました。
はじめのうちは本番の目標点数の半分も取れず、自信を無くしていましたが、分からないことがあるたびその都度テキストに戻って復習し、周辺知識もおさらいすることを徹底していました。
答練は非常に難しく、これを繰り返せば本番も解けるであろう、という自信がつきました。自分は時間的制約で答練を2周しかできなかったのですが、2周目で間違えた問題や苦手分野だけに絞って3周目をできていたらより良かったかなと思います。
◆ 財務会計論(財務諸表論)
基本的には計算分野の知識を信じ、1カ月前までは対策はしていなかったです。そのツケが直前になって回ってきて苦しい思いをしたので、理論科目の中では一問あたりの得点が高いですし、できれば早くに手を付けることをお勧めします。
◆ 管理会計論
この科目は、短答式試験では特に差がつく科目だと思っており、特に計算でいかにアドバンテージを得るかを念頭に勉強していました。流れとしては講義→過去問→答練の流れで、過去問を3カ月前、答練を2カ月前から始めました。
◆ 監査論
この科目は、5、60点台まではすぐあがるものの、そこからの頭打ちに大きく悩みました。基準が頻繁に変わるため、過去問もほかの教科に比べると使いづらかった印象があります。
そのため、私は監査基準集を読むことにし、答練で出てきた問題の原文を読むことを意識して、細かな論点を詰めていきました。
◆ 企業法
講義を見終わったのが2月であり、そこから過去問集を使いながら分野別にテキストの復習を中心にしていきました。
4科目の中で一番暗記要素が強く、過去問と似た論点が問われることも多々あったので、テキストの文章に過去問出題歴とその頻度が書いてあったのは非常に役立ちました。
特に企業法は直前の詰め込みでも点数が最後まで伸びる科目だと思っているので、最後まであきらめず重要度順にテキストを繰り返し読み込むことが大切だと思います。
論文式対策時
「ごっぱち」と呼ばれる5月短答→8月論文という非常にタイトなスケジュールであるにも関わらず、租税法、経営学に手を付けておらず、とにかく時間がなかったので、その二科目に集中して取り組みました。
短答期の貯金を信じ、7月中旬というところまでその二科目以外触れていなかったので、監査論や企業法の対策は役に立たないかもしれませんが、短期間で目指すことを考えている方にとっては逆に参考になるかもしれません。
論文式試験は点数を調整した偏差値での勝負になり、完全な相対評価になるのですが、総合偏差値が52%以上で合格、と思っていただけたら大丈夫です。
その中で、自分は租税法と経営学で60%以上とり、勉強しても不確実性が高い企業法、監査論は足切り回避で40%以上あればいいや、という気持ちで勉強し始めました。
◆ 会計学
この科目は午前中が管理会計論、午後が財務会計論で、どちらも短答期より理論の比重が重くなっています。
そのため、計算分野は短答期の貯金を信じ、1カ月前からメンテナンス程度で答練を解く形がベストだと思います。特にテキストに戻って復習するのは、本当に苦手分野だけでよいと思いました。
◆ 監査論
勉強時間が限られているなかで、一番勉強に対して点数の上り幅が少なそうだと思ったこの科目は、試験1週間前に講義をみて答練を解き始めました。
それまで触っていなかった分、答練がたまりまくっていたので、実際に書いて解くことはせず、問題を見て、基準集をみてこの部分を引き抜こう、など考えながらすぐ解答をみていました。典型論点とみんなが押さえてくるような重要事項だけを暗記して、あとは基準集を見て解くつもりでした。
短答期に基準集を読む習慣をつけていたのがここで生きたかな、と思ってます。どの文も見たことあるな、というものが多かったですし、短期間で詰め込んだことで暗記もしやすかったです。
ただ、結果として52%を超えたものの、難易度が高かったため、他の受験者が解けなかったこともあって差がつかなかったのかな、と思っており、例年通りなら40%台をとっていたと思っています。
◆ 企業法
企業法は短答と論文で一番毛色が違う試験だなと思っております。というのも、短答は暗記で済ませることが多かったのが、論文は法律の型に沿って書かなければならず、一番苦労しました。
そのため、早めに慣れるためにも租税法、経営学を除く科目のなかで一番早く勉強をし始めました。論文対策講義を見たのち、論証をひたすら繰り返し、条文を引くことを徹底してました。
企業法の答練も全部書くことはしないで、問題提起、条文、事例の当てはめ等を箇条書き程度でとどめて解答を見るようにしていました。答練の解説は非常に分かりやすく、細かなところまで理解を深められるのでぜひ活用してほしいです。
◆ 租税法
この科目は短答式試験が終わった後一番時間をかけた科目であり、学習方法としては、講義と例題、章末問題をなるべくすぐに一周し、2周目で章ごとに細かい知識まで入れていく作業を繰り返しました。
自分の中で体系立てて理解できたらその後は答練に移り、時間配分と得点戦略を練りました。
答練の時点では計算分野でかなりアドバンテージがあり、理論はだいたい25/40%を目安に、計算は50/60%を最低ラインとして、本番で必ずアドバンテージをとれるようにかなり演習を重ねました。
◆ 経営学
租税法の次に時間をかけたこの科目ですが、思っていた以上に範囲が広く、どこまでやるかはその人の余裕次第となりそうな科目だと感じました。これも、講義後に答練と過去問を繰り返し解くことで演習を重ねました。
クレアールで学習してよかった点
クレアールを選んでよかった点といたしましては、Web通信なので自分の学習ペースで勉強でき、時には倍速モードを活用しながら効率的に進めていくことができたところです。
もちろん、学習の最中に浮かんだ疑問や相談等があれば、私はクレアールの事務局にその都度メールをしてお答えいただきまして、非常に助かった記憶があります。
また、私は2年セーフティコースであり、1年を念頭に学習ができ、受かったら合格お祝い金や未受講分の返金がもらえ、落ちてももう一年分のコースがセーフティーネットとしてある、という安心感もあったため、モチベーションの維持に役立ちました。
最後に
公認会計士という資格は一度手にしたらその後の人生のキャリアプランに必ず役に立ちます。もちろん、合格までの道のりは苦しく、泣きながら勉強を重ねましたが、その結果として勝ち取った合格という喜びは何物にも勝ります。
ぜひ皆さんも、自分を信じて合格を勝ち取り、公認会計士になってください。