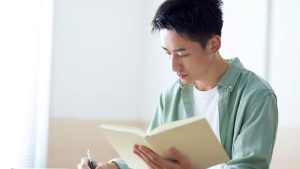はじめに
7月に入り、いよいよ論文式試験が近づいてきました。論文式試験の1ヶ月前の勉強について、科目別編と題して私が実際にどのように勉強したのか、当時の反省点も踏まえながら科目別に執筆したいと思います。今回は後半ということで、企業法、監査論、管理会計論の3科目について書きたいと思います。
大まかな直前期の勉強方法や過ごし方は概略編で書いていますので、そちらをご覧ください!
企業法
既に論文講義は視聴済みかと思いますので、とにかく論文テキストの問題をスピーチしていました。山本先生は講義の中で、実際に答案を書いてみることを推奨していたと思いますが、私は時間が足りず、実際に答案を書いてみたのは答練だけで、論文テキストの問題はひたすらスピーチとテキストの読み込みをしていました。
論文テキストの中でも追加問題は論文講義を視聴して一通り読んだのみで、主にテキスト前半をスピーチしていました。
スピーチについても解答の全文を覚えようとはせず、まずは結論、判例を押さえます。その次に結論に至るまでの過程を波線が引かれている部分を中心に押さえるように意識しました。また、過程の中には条文の趣旨に触れている箇所がありますから、そこは重点的に押さえるようにしました。
企業法の論文式試験は、短答式試験と違い、条文の趣旨を覚えることが重要です。判例は覚えるのは当然として、なぜ、そのような判例なのか、条文の趣旨に立ち返って本番では答案を書きます。趣旨は法令基準集には記載されていませんから、そのような箇所はスピーチで正確に覚えました。企業法の論文式試験特有の三段論法については、テキストを見るだけでは掴めない部分が多々ありますから、2倍速でいいので論文講義をもう一度視聴して、なんでこのような文章構成になるのか、理解して覚えられると記憶も定着しやすいと思います。
また、問題の中には、絶対に押さえるべき用語の解釈や定義がいくつかあります。例えば、取締役の競業避止義務について、「会社の事業の部類に属する取引」の解釈や「事業譲渡」の定義などです。これは必ず覚える必要があるため、このような解釈や定義を覚えるために、夜寝る前と朝起きた直後に暗唱していました。暗記すべきものは寝る前と起きた直後の2回、反復すると定着しやすいのでおすすめです!
監査論
監査論は答練と論文レジュメの問題をスピーチで繰り返していました。事例問題については問題の形式に慣れることが大切なので、スピーチで反復する必要はないと思います。そのため、問題の少ない答練は本番直前に詰め込むようにして、それまでは論文レジュメを中心にスピーチで押さえるようにしていました。
ちなみに、直前期になると時間がなかったため、監査論と後述の管理会計論は優先度を落として勉強していました。
特に監査論は、勉強時間を確保してもそこまで点数が格段に伸びる自信がなかったためです。そのため、最低限の点数を取れるようになることを意識して、論文レジュメの基本的な問題を重点的に勉強しました。
管理会計論(会計学:午前)
計算は簿記1級、短答式試験のレベルで十分です。私は、直前期に計算論点を見直しできるよう、論点の一覧表のようなものを作成して本番直前に見直すようにしていました。
そのため、管理会計論で直前期に勉強すべきは理論だけです。その中でも理論問題集のAランク論点だけをスピーチである程度精度を高めて覚えるようにし、その他は流し読みする程度に抑えました。私は管理会計論よりも優先して勉強すべきことが山積みでしたので、本当に最小限に抑えていたと思います。それでも本番の会計学午前の偏差値は52.0をほんの少し下回る程度でしたので、足を引っ張らずに乗り越えることができました。
ちなみに、管理会計論は短答式試験と同様、本当に時間が足りません。ですが、大切なことは早く解くのではなく、正確に解くことです。丁寧に時間をかけて解いた方がよかった、となることが多いと思うので、スピードよりも正確性を重視していきましょう。簿記1級まで取得していれば、スピードも他の受験生よりも早く、それだけでアドバンテージです。自信を持って臨みましょう。
終わりに
2回に渡る科目別学習法はいかがだったでしょうか。至る所に書かれている通り、私の直前期の勉強は、すべての科目を網羅的に勉強するのは不可能だったので、要点を絞りに絞って限られた時間でいかに勉強するか、という感じでした。こんな学習方法でも、得点できる箇所を確実に取ることができれば合格できるのが公認会計士試験です。最後まで諦めず、直前期でも基礎基本を大切に最後の追い込みをしていただければと思います!