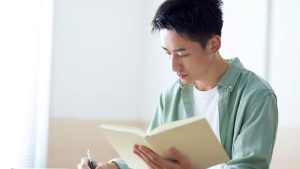はじめに
7月に入り、いよいよ論文式試験が近づいてきました。今回はそんな論文式試験の1ヶ月前の勉強について執筆したいと思います。
詳細の科目別の勉強方法については、科目別編で書いていますので、そちらをご覧ください!
最後まで諦めない!
当たり前のことかもしれませんが、最後の最後まで諦めないことが何より大切です。勉強の進捗や模試・答練の結果が思い通りにいかず、今年はダメかもしれない、と不安になってしまう方も中にはいると思います。しかし、1ヶ月前の直前期は最も力が伸びる時期です。最後まで何が起こるかわかりません。
実際に私が合格したときも、他校の模試の判定はE判定で絶望しました。それでも直前期に集中して勉強することで来年の論文式試験にも必ず生きるはず!と信じて勉強した結果、E判定だったにもかかわらず、合格することができました。それほど直前期は力が伸びます!最後まで頑張りましょう!
新しい論点には手をつけない!
直前期だと不安になるあまり、つい新しい論点を深堀りして勉強してしまいます。論文式試験は周りが得点する箇所で自身も確実に正答することが重要です。そのため、新しい論点ではなく、既存の知識の定着を重視して勉強しましょう。今までやってきた答練の反復をメインに、基礎基本の徹底を意識して勉強するとよいと思います。
理論科目を中心に勉強する!
社会人で働きながら論文式試験を目指す場合、6科目を満遍なく勉強するにはとにかく時間が足りません。そのため、ある程度の割り切りが必要です。不安な気持ちはわかりますが、財務会計や管理会計の計算は最小限にしましょう。理由は、費用対効果が悪いからです。短答式試験の計算レベルで論文式試験も十分に戦うことができますから、理論科目を中心に勉強をしましょう。私の場合、直前期は管理会計の計算は一切勉強せず、1週間前くらいに計算論点をパラパラとテキストを振り返った程度、財務会計も週1回くらい簿記答練を解き直す程度です。それよりも会計学の理論や租税法、経営学に多くの時間を費やしていました。
本番と同じ時間で問題を解いてみる
過去問や他校の模試など、本番と同レベルの問題を、本番と同じ時間配分で解いてみましょう。これは本番の時間配分を掴むためです。
例えば、会計学(午後)は3時間と最も試験時間が長いですが、実際は悠長に問題を解いている時間は全くありません。問題も多いため、大問それぞれにどれくらいの時間を割けばいいのか、実際に解くことで本番のシュミレーションを事前にやりましょう。時間配分が合否の分かれ目の場合もあり、とても大切なので、1度やってみてください。
なお、解けなかった新しい論点の問題が出てきても深掘りは不要です。簡単に解説を読んで、へー、こんな論点があるんだ、程度で終わらせて、過度に復習しなくても大丈夫です。
今までのルーティンを大切に
特に社会人の場合、働きながら論文式試験の勉強はかなり不安になると思います。専念している学生に比べると勉強時間も少ないからです。それでも今までの勉強スケジュールのルーティンを崩さずに継続しましょう。私も短答式試験の頃から40h/週間を意識して勉強していましたが、論文式試験の直前期でも勉強時間が増えることはありませんでした。睡眠時間を削って追い込んでしまうことで、体調を崩すほうがよっぽどよくないです。そのため、あくまでも今まで通りのルーティンを継続することを意識し、一方で限られた時間を集中して取り組むことで、効率的に勉強しましょう!
最後に
私は論文式試験の直前期もいつも通り会社に出社し、働きながら勉強を継続していました。そのため、これで本当に大丈夫なのか、と不安になる気持ちはとてもわかります。周りの受験生もみんな同じ気持ちです。
それでも私が継続して勉強できた理由は、トップ層で合格する人たちは意識せず、あくまでもギリギリの合格を目指していたため、今の勉強時間でも十分可能だ、と信じていたためです。私と同じレベルの人は、専念している人でもどうせ8~9時くらいに起床し遅めに勉強を始め、結局早く起きて勉強している自分と勉強時間に大きな差はついていないだろう、と高を括っていました。そんな安直な考えが功を奏し、最後まで頑張ることができました。直前期で勉強時間について周りと比べることはせず、自分は大丈夫!と自分を信じて最後まで諦めず駆け抜けてください!