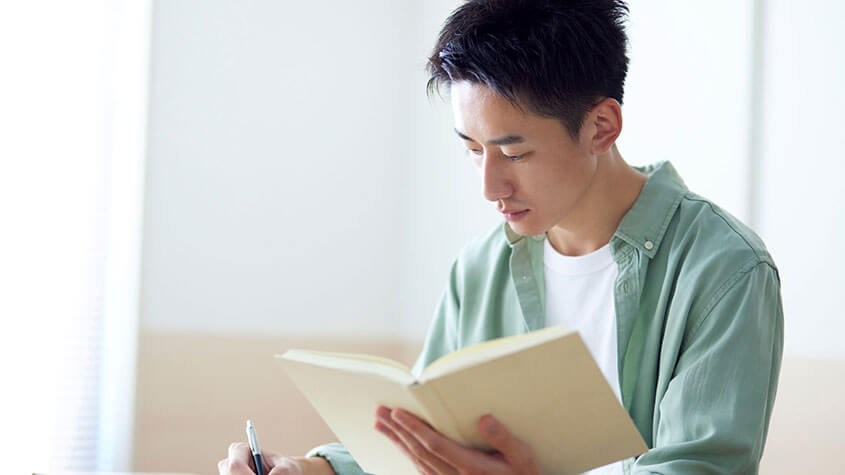はじめに
7月に入り、いよいよ論文式試験が近づいてきました。論文式試験の1ヶ月前の勉強について、科目別編と題して私が実際にどのように勉強したのか、当時の反省点も踏まえながら科目別に執筆したいと思います。今回は私が直前期に特に時間を割いた、経営学、租税法、財務会計論の3科目について書きたいと思います。
大まかな直前期の勉強方法や過ごし方は概略編で書いていますので、そちらをご覧ください!
経営学
直前に受けた模試の結果が最も悪く、私が直前期に最も時間を割いた科目です。特に財務管理論の計算方法が定着しておらず、急ピッチで仕上げました。
財務管理論の主な学習方法はひたすら答練の反復です。計算問題は同じ問題を2~3日空けてはひたすら解いていました。理論対策としては、出社の準備や食事中に直前講義を流していたくらいで、そこまで手を着けられなかったです。計算の知識で理論もカバーできる部分があるので、とにかく計算を中心に勉強しました。
経営管理論はスピーチで文章を暗記できるだけの時間の余裕はなかったので、記述は割り切って捨て、用語や単語の暗記に絞りました。例えば、組織のメリット、デメリットなどは単語で羅列する感じで単発的な単語で手早く覚えるように意識しました。
用語の暗記については、答練で出た用語は一通り覚えました。また、テキスト付録の復習スピーチ課題を解答→定義スピーチと辿るようにして活用し、用語の暗記に用いました。直前講義は回す余裕はなかったので手を着けられなかったです。答練で出た内容についてのみ、関連する論点を直前講義テキストでざっと見る程度です。中途半端に押さえるのであれば、あえて捨てる勇気が大切だと思います。それよりも当然に覚えなければいけない部分を確実に押さえることに時間を割きましょう。
元々、模試の結果は最悪だったので、最低限周りと戦えるレベルに、を意識して勉強していました。そのため、今振り返ると割り切って捨てた部分が大いにあったと思います。それでも基礎基本を押さえるだけで十分戦えます。
租税法
租税法は2番目に時間を割きました。全8回のマスター答練を反復しました。所得税、消費税は若干物足りなかったので、模試の問題を活用して反復しました。法人税は部分点が狙えるので、マスター答練の反復で基礎を固めればちゃんと得点できます。
所得税、消費税も同じですが、こちらは税額算出までの「計算の流れ」を掴むのが大切です。なので総合問題のような一通り税額算出するような問題を何度も解いて、今自分がどの部分の計算をしているのか、ちゃんと把握できるようになることを意識しました。
また、租税法の本試験では法令基準集が配布されます。そのため、基準集に記載がないため暗記すべき事項と、基準集に載っている場合はどこに記載されているか、の2点を区別して覚えるように意識しました。
最後に租税法については、理論、各税法の計算について、時間配分を事前に決めることをおすすめします。私は理論問題は30分~40分くらいで解いて、計算問題により多くの時間を確保したいと考えていました。また、法人税の計算は、1番最後に解くようにして、最低でも45分は確保しようと考えていました。租税法はその年によって各税法の難易度が大きく変わるので、大まかな時間配分だけあらかじめ決めておいて、その場で臨機応変に対応できるとよいと思います。
財務会計論(会計学:午後)
財務会計論は理論をメインに勉強しました。租税法、経営学の2科目の計算対策で手一杯で、直前期は計算の勉強をする余裕はありませんでした。私は簿記1級を勉強してから公認会計士試験に臨んだこともあり、これまでにより多く簿記の勉強をしていたので、ある意味自信を持って他の科目に集中できたと思います。それでも、週1回ほどは簿記の答練を解いていました。また、本番の1週間前には、事前に作っておいた計算論点の総まとめ表を一通り見て計算論点を押さえるようにしました。
そんなこともあり、理論が勉強の中心だったのですが、論文テキストの読み込みはできず、すべての範囲を網羅的に勉強することはできませんでした。そのため、勉強の中心は答練です。経営管理論は用語中心の暗記でしたが、財務会計論の理論はできるだけスピーチをして文章で覚えるように意識しました。答練に絞ったからこそできたと思います。
一方で、財務会計論の論文式試験では、2~3 行ほど記述させる問題も多いため、なんとなく問題を見たことがあるかどうか、で答案の出来が全然違います。なので、答案を白紙にしないということを意識して、答練を中心に繰り返しスピーチ練習することと同時に、関連する分野はテキストをパラパラめくって正確性よりも多くの問題を見るようにしていました。そんな形で論文テキストを活用していました。
3科目を振り返って
私は社会人で働きながら論文式試験を目指していたため、振り返ると本当に時間が足りなかったな、と思います。それでも論文式試験を一発で合格できたのは、時間を割く分野をしっかり絞り、捨てる所は勇気を持って捨て、割り切って集中することができたからだと思います。初めて論文式試験に臨む方は、やはりこの3科目により多くの時間を費やすことになると思うので、ぜひ参考にしてみてください!