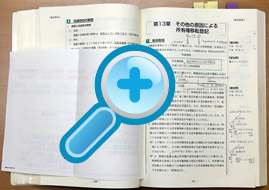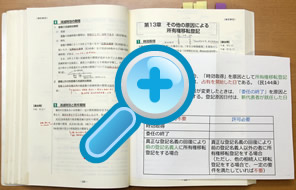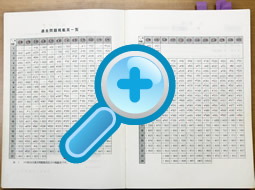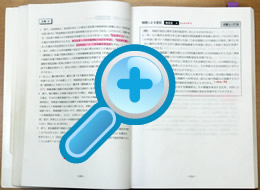具体的な学習計画の立て方と実行方法
清水 では、具体的な学習計画の立て方と実行方法について伺います。クレアールのカリキュラムで学習を進めていく上で、具体的にどのように学習計画を立てて実行したか、学習計画を立てる際の注意点をお聞かせください。
豊田 私自身はあまり長期的な計画を立てずに、取りあえず試験から逆算して毎日講義を1単元か2単元聞ければ本試験までに間に合うかなと思ったので、講義を聞いて択一六法を読んで過去問題集を解くのを1日最低1単元、講義の時間のボリュームなどにもよるので短めの講義の時は2単元繰り返すというやりかたでした。なるべくこのペースを崩さずにやっていけば間に合うかなということで着実に進めていきました。講義を受けた日付をクレアールさんからの予定表に記入して、ペースを維持できているかを時々チェックしていた程度で、この部分やこの科目をいついつまでにやるという計画は全く立てずに、取りあえず1単元2単元という自分のルールをなるべく崩さないようにするというところだけ意識して進めました。
清水 あまりきっちりしたスケジュールではなく、大ざっぱなスケジュールで本試験から逆算して、ここまでに大体これぐらい進めるという感じですね。
豊田 はい、そうです。
清水 あまりかつかつに予定を組んでしまうとそれをこなすのが厳しいですし、予定が遅れてしまった時にはどうしても取り返すのが大変になりますよね。
豊田 スケジュールを組もうとすると大体かつかつなスケジュールを組みがちになってしまいます。実際自分の頭の中で考えていると無理なスケジュールを組んでしまうので、取りあえず自分でルールを作ってそれを崩さないということだけは意識して進めました。
お試し受験について
清水 それでは続いて、お試し受験についてお聞きします。クレアールでは、合格目標年度の前年に司法書士試験のお試し受験を勧めています。豊田様はお試し受験を受けていただいておりましたが、お試し受験を通してどのような感想、あるいは手応えがあったか。そしてお試し受験がその後の学習にどのようにプラスになったのかをお聞かせください。

一発合格者 豊田 崇宏さん
豊田 勉強をスタートしてしばらくは結構時間がかかってしまったので、大体民法・不動産登記法一体講義が最後まで終わり、一通り復習を終えて、会社法の株式の章ぐらいまで終わったぐらいでお試し受験になりました。まだこの時は解ける問題が少なく、午後の部の科目の試験は、暇で仕方なくて周りの風景を観察したり来年なるべくこの雰囲気になじめるようにというところを意識しました。会場の雰囲気とか具体的にお昼ご飯は買っていった方がいいとか、机が狭いというイメージが掴めたということ、あとは学習がある程度終わっていて復習をした科目については、ある程度正誤判断はつくようになっていたことがわかりました。解いた問題の正答は多分8割ぐらいだったと思います。
清水 民法・不動産登記法については8割くらいできていましたか。
豊田 はい、できていました。その時の段階で勉強したところは8割くらい理解できているということで、自分の今進めている勉強方法が合っているのかなという自信にはつながりました。だから、なるべくお試し受験が終わった後も休まずにこのペースで続けていくことを意識してやり続けました。これを続けていくと合格につながるという自信にもなりました。
清水 本試験で初めて会場に行くと、机の狭さが気になって集中力が途切れてしまうということもあるかもしれませんから、そういう意味でも一度本試験会場を知っておくのはプラスになりましたか。
豊田 はい。特に記述がいかに早く書けるかということが勝負になってくるので、机のイメージがないまま、家の広い机と全く違うあの狭くてちょっと斜めになったような大学独特の机に初めて接すると、やはり普段書けるものが書けなかったりするのかなと感じました。
清水 家とはまったく違いましたか。
豊田 そうですね。問題を広げるスペースとかも全然違うので、特に直前期の答練とか模試を受けるときはなるべくそれに近づくように記述の答案用紙を、駄目かも分からないですが半分に折って書くようにして、狭いスペースで書く練習をしていました。特に記述の答案を解くときは本試験をなるべく意識して解くようにはしていたと思います。
清水 お試し受験をしたことによって、実際の本番の試験では落ち着いて受験することができましたか。
豊田 はい。会場の雰囲気も、ほとんどお試し受験の時と同じような環境で座席の位置も左側で同じでした。
教材の利用方法
清水 では今度は、教材の利用方法について伺います。司法書士試験は出題される科目が多く、クレアールではいろいろな復習教材をご用意しています。学習を進めていく上でどの時期にどのような教材を利用したか、お聞かせください。
豊田 私はあまりノートを取るのが得意ではないですし、ノートを取ることに集中してしまって大事な講義をしっかりと聞くことに意識が向きにくかったりするのでノートを取ることは一切していなかったです。
その分、テキストや択一六法にメモを集約させていくかたちにしていました。先ほどの繰り返しになりますけど、講義で話される理由付けや具体的イメージなどをテキストの空きスペースに記入して、講義が終わった後は択一六法で該当する条文を確認して、講義で話された重要部分をチェックしたり関連知識をメモするというかたちで進めていきました。
清水 過去問題集には、この問題は正解できたとか間違えたとか何か印をつけたりはしていましたか。
豊田 そうですね。1回1回解くごとに正解できたのかを、問題の欄外に○×をつけて2回目以降にここを間違えたんだなとか合っていたんだなときちんと分かるようにしていました。最後の方は肢ごとにここを間違ったとか、解答は合っていても理由が分かっていない、たまたま合っていた問題はきちんとチェックして、直前期はもうそこだけ読み返すようにしていきました。最初からチェックしていくことで、直前期に弱点に集約させていく段階では、自分はどういうところが弱いのか絞り出されてくるので、最初からきちんと○×はつけるようにしていました。
過去問の学習方法
清水 過去問の学習方法について、もう少し掘り下げてお聞かせください。司法書士試験の学習では、ご存じのとおり過去問の攻略が合否に直結します。過去問をどのような方法で学習したのか、お聞かせください。併せて○×テスト、1000問ノックWEBテストの利用の有無や活用方法もお聞かせください。
豊田 過去問を解くときは、ノートを作らずにコピー用紙などに書いていって、きちんと正誤のところに理由を記しながら書く、解説部分では理由付けとか重要な部分にラインを引くとかチェックしていって、特に必要があれば紙に解説の重要な部分を書いて覚えるということを基本的にやっていました。あとは問題ごとに正誤をつけたり間違えた肢に印をつけたりして活用していました。
清水 1000問ノックWEBテストも使われましたか。
豊田 科目の講義を聞いて択一六法を読んで過去問を解くという一通りの学習が終わった段階で、どのくらい自分が分かっているかを測る意味で活用していました。
記述式の学習方法
清水 次に、記述式の学習方法について伺います。初学者の中には記述式の学習に不安を持つ方がいらっしゃいます。記述式の学習を進めていく上で注意したこと、工夫したことをお聞かせください。また答案構成用紙をどのように使用したか、不動産登記、商業登記それぞれお聞かせください。
豊田 これは講師の方がおっしゃられたとおり、ひたすら手を動かすことです。合格体験記にも書きましたとおり、今は治りましたけど、親指にペンだこができてイボコロリを貼って取りながら、親指が痛くてぶよぶよになりながらも手を動かすくらい、本当に書きました。
清水 まず、基本的なひな形を体に覚えさせるようなかたちですね。
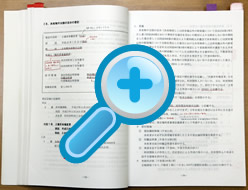 豊田さんが使用した合格書式マニュアル (クリックすると拡大します)
豊田さんが使用した合格書式マニュアル (クリックすると拡大します)
豊田 そうですね。書式講義を聞いて、そのときも講師の方が書かれるのを一緒にメモを書きながら、講義を聞いた後は該当する合格書式マニュアルのひな形を1回書いて、合格書式マニュアル対応問題集と記述式ハイパートレーニングを解くというかたちですね。不動産登記の例えば所有権の分野が終わったところでひな形の解説の講義も活用していき、その時も復習する意味で聞きながらずっと書いていくようなかたちで進めました。ただ聞くだけでなくて、紙に書きながら講義を聞くような感じで、取りあえず手を動かしながらやっていきました。あとは、合格書式マニュアルの解説も丁寧に読みました。択一の復習という意味にもなりますから。やはり記述式だと問題文をどう実体判断していくかというところを間違えてしまうと大変なことになるので、そこをきちんと押さえる意味でも、合格書式マニュアルの解説もきちんと読むようにしながら進めていきました。
清水 ひな形を覚えながら実体法も意識していったということですね。もう少し教材の使い方について教えてください。記述式の教材ですと、合格書式マニュアルと合格書式マニュアル対応問題集を一通りやってから、記述式ハイパートレーニングを学習するという順番ですか。
豊田 まず講義を受けてから、講義の論点に該当したり関連する合格書式マニュアルのひな形を書いていきました。合格書式マニュアル対応問題集でもまた同じように解きながら書いていきました。講義が進んでいくと記述式ハイパートレーニングの問題も段々と解けるようになってくるので、その時はなるべく早めに解いていきました。直前期には、またひな形を書きながら少し書くのに飽きてきたら記述式ハイパートレーニングを解いて勉強していました。
答案構成につきましては、人それぞれやり方があるとは思います。私の場合、不動産登記はなるべく実体関係を誤って枠ずれを起こすのが怖かったので、基本的に雑ですけれども土地と建物があって今どういう関係でどう権利変動が動いたということをきちんと書くようにしていました。ここを誤ってしまうのが不動産登記では一番怖かったので、ここは丁寧に書いて答案構成用紙を使ってまとめていくようにしていました。
清水 権利関係を図に描くようなかたちですか。
豊田 そうですね。権利変動の図を描きながら、登記の目的、原因日付、権利者、義務者などを簡単にメモしたり、承諾書などの重要な添付情報をメモしたりしていました。多少時間はかかるんですけれども、不動産登記は答案構成用紙を使用しました。商業登記は時間がなくなってしまうことがあるので、答案構成用紙は使わずに問題文に直接全部書き込むやり方を取っていました。
ただ、これをやると事業年度が変更されたりして役員の任期が複雑な時は、かなり危ないですけれども、そうでないことを祈っていました。役員関係が複雑なときは、さすがに答案構成用紙に、役員は誰がいて誰がいつ退任したとかを書き出していました。
清水 問題文に直接書き込んでいくというスタイルですね。
豊田 問題文の議事録などに登記事項や添付書面などを直接チェックしていって、なるべく答案を書く時間を増やすようにしていました。
清水 もし、例えば先ほどのように事業年度の変更などの複雑な事情があった時は臨機応変に答案構成用紙に書くということですか。
豊田 臨機応変に役員だけは書き出します。だから午後の試験が始まると先に、商業登記の記述式の問題の役員関係と定款の任期規定と最後の聴取メモのところをチェックして、そこでまずどっちの作戦でいくのかを5分くらいで決めるようにしていました。役員が複雑ではないときは問題文に直接書き込んでいって、役員が複雑なときはなるべく役員だけは答案構成用紙に書き出そうと択一を解く前にあらかじめ決めておいて、対応していました。
清水 少しまとめますと、不動産登記に関しては実体判断を間違えないように権利関係をしっかり図に描いて判断していった。商業登記に関しては答案を書く時間などを考慮して直接問題文のほうに書いていくが、複雑な事案である場合には臨機応変に対応していくというやり方ですね。
豊田 そうです。
清水 そういったやり方も答練などを通じて、徐々に自分なりのスタイルを確立していったということですね。
豊田 最初は講義で教えていただいたようにきちんと書いていたりもしたんですが、どうしても商業登記の最後は時間がなくなってしまい、分かっているのに書けないのが一番もったいないと思ったのと、商業登記はあまり実体関係を間違うことが少なかったので、それを信じてなるべく書く時間を確保するという方を選びました。
学習を効率よく進めていくうえで工夫したこと
清水 では続いての質問です。学習を効率よく進めるために1日、1週間をどのように過ごしていらっしゃったか。そしてクレアールの通信講座をどこでどのように学習したか、復習講義の利用の有無、および活用方法をお聞かせください。
豊田 大体朝7時ぐらいに起きて、ちょっと一服したりコーヒーを飲んで子どもと遊んでから勉強をスタートします。午前中に講義を視聴してから、択一六法を読んで過去問を解く、昼からも違う講義を視聴していくように1日1~2講義進めていくのを目安にしていました。ただし、講義のボリュームが多くて1単元しか聞けなかったときは残りの空き時間で択一六法の復習に時間を割いたり、どうしても講義を視聴する気分にならないときなどは択一六法の復習に充てていたような感じです。択一六法を読むときは、もちろん最初は講義を聞いたところから順番に読んでいくんですけども、2回目、3回目に読むときはなるべく自分があまり得意でないところ、例えば民法で言うと代理とか根抵当権の章だけを読んでいく、昨日ここまで読んだからというのではなくて今日はこの章、今日はこの章と苦手な部分をなるべく重点的に読むような感じで学習を進めました。
清水 学習場所は主に自宅でしたか。
豊田 はい。休憩時間に子どもと遊べるように常に自宅でした。
清水 復習講義は利用されましたか。
豊田 はい、利用しました。1週間ぐらい経過すると徐々に最初の方の記憶がなくなっていくので、大体講義1週間分くらいの10単元進んだぐらいを目安にまとめて復習講義を聞いて、そのときも復習講義を聞きながら、紙などに重要な部分、話されている内容などメモを取りながら記憶をよみがえらせるような感じでした。
清水 1週間ぐらいでかなりの記憶がなくなってしまうといいますからね。
豊田 1週間くらいで復習講義を利用するのはちょうど良かった気がします。