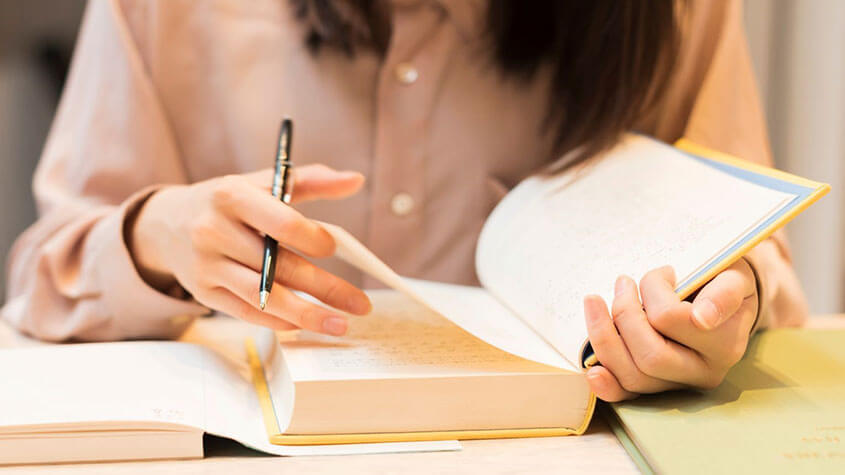中小企業診断士試験の合格には、1,000時間程度の勉強時間が必要といわれています。科目ごとにどの程度の勉強時間がかかるのか、効率よく試験合格を目指すためにはどのような方法があるのかポイントをまとめました。ぜひ参考にして、短期間で中小企業診断士試験合格を勝ち取ってください。
中小企業診断士試験突破に必要な勉強時間の目安
| 第1次試験のための勉強時間 | 800~1,000時間程度 |
| 第2次試験のための勉強時間 | 300~400時間程度 |
中小企業診断士試験の勉強時間は、第1次試験に800~1,000時間程度、第2次試験に300~400時間程度、重複する部分もあるため合計約1,000時間は必要とされています。1日2~3時間程度勉強するなら、1年~1年半かかります。中小企業診断士試験を受験する回数は平均で3回なので、勉強時間も含めて2~3年を見込んでおく必要があります。ただし、大学で経営理論や経営情報システムなどを学んでいる場合や、社会人として会計や経済に関する知識を身につけている場合は、勉強時間の短縮が可能です。
そもそも中小企業診断士試験ってどんな試験?

中小企業診断士とは、中小企業に対して経営診断や助言を行うための国家資格です。中小企業診断士試験は第1次試験と第2次試験があり、順に合格したのちに実務補習を経て正式に中小企業診断士として登録されます。
第1次試験の内容
| 科目 | |
|---|---|
| 1日目 | 経済学・経済政策 財務・会計 企業経営理論 運営管理(オペレーション・マネジメント) |
| 2日目 | 経営法務 経営情報システム 中小企業経営・中小企業政策 |
第1次試験は2日間にわたって実施されます。7科目をすべて受験し、総得点の6割以上、各科目においても満点の4割以上の獲得が必要です。いずれも多肢選択式で、マークシートを使って回答します。また、「企業経営理論」と「運営管理」、「中小企業経営・中小企業政策」の3科目のみ試験時間が90分(他は60分)と出題範囲が広く難しいことが予想されます。
第2次試験の内容
| 科目 | |
|---|---|
| 筆記試験 | 中小企業の診断および助言に関する実務の事例Ⅰ 中小企業の診断および助言に関する実務の事例Ⅱ 中小企業の診断および助言に関する実務の事例Ⅲ 中小企業の診断および助言に関する実務の事例Ⅳ |
| 口述試験 | 個人面接 |
第1次試験の合格者は第2次試験に進めます。第2次試験は筆記試験と口述試験の2日に分けて実施されますが、口述試験は筆記試験の合格者のみ受験可能です。ただし、筆記試験と口述試験には3カ月ほど離れているため、筆記試験受験後に口述試験の対策をしても十分に間に合います。筆記試験だけでなく、面接対策もしっかりしておくようにしましょう。

中小企業診断士試験の科目ごとに必要な勉強時間の目安
【第1次試験】
| 試験科目 | 勉強時間の目安 |
|---|---|
| 経済学・経済政策 | 約150時間 |
| 財務・会計 | 約130時間 |
| 企業経営理論 | 約120時間 |
| 運営管理(オペレーション・マネジメント) | 約120時間 |
| 経営法務 | 約110時間 |
| 経営情報システム | 約110時間 |
| 中小企業経営・中小企業政策 | 約60時間 |
【第2次試験】
| 試験科目 | 勉強時間の目安 |
|---|---|
| 中小企業の診断および助言に関する実務の事例Ⅰ 中小企業の診断および助言に関する実務の事例Ⅱ 中小企業の診断および助言に関する実務の事例Ⅲ | 合計で約100時間 |
| 中小企業の診断および助言に関する実務の事例Ⅳ | 約100時間 |
第1次試験の「財務・会計」と「企業経営理論」、「運営管理」は2次試験の範囲と関連が高いるため、重点的に勉強する必要があります。とりわけ「財務・会計」と「企業経営理論」は難易度が高いとされているので、時間をかけて学習することが必要です。また、科目ごとの特徴をつかむと、勉強効率が高まります。テキストを読むだけでなく、過去問も解きつつ勉強を進めていきましょう。
効率良く中小企業診断士試験を突破する方法

1,000時間をかければ、誰もが中小企業診断士試験合格に必要な知識が身につくわけではありません。効率よく勉強するためのポイントを3つ紹介します。
学習スケジュールを立てる
学習スケジュールは週単位・日単位で目標を立てましょう。受験日をゴールとし、各自のペースにあわせて逆算すると予定が決めやすいです。ただし、学習を進めていくうえで、得意科目や不得意科目が見えてきます。その時は新たに計画を練り直すとよいでしょう。
テキストと問題集で反復学習する
記憶を定着させるには、反復学習が効果的です。テキストで学び、学んだ範囲を過去問などの問題集で実際に解いてみましょう。スムーズに解けない部分については、再度テキストで学び直します。テキストによる学びと問題集による実践を繰り返して、記憶を定着させてください。
6割得点を目指して学習範囲を絞る
効率性にこだわって学習するなら、すべての範囲を網羅するのではなく、頻出範囲に特化して学ぶのも一つです。中小企業診断士試験では、6割得点が合格ラインです。過去問から頻出分野を割り出し、集中して勉強してください。ただし、合格基準は総合得点だけでなく、各科目の最低点も4割以上である必要があります。頻出範囲だけでなく、最低点をクリアするための学習も並行して実施しましょう。
予備校や通信講座を利用する
自己流で勉強してもよいですが、効率性を重視するなら予備校や通信講座を活用しましょう。たとえば予備校であれば講師に直接質問できるため、理解が難しい点をピンポイントで尋ねられます。また、通信講座なら好きな時間に勉強できるため、忙しい学生や社会人にも利用しやすいでしょう。
講師に質問できるWeb通信スクールのクレアールでは、学習範囲を絞った効率的な勉強方法「非常識合格法」で短期合格を目指します。ぜひ活用して、中小企業診断士試験合格を勝ち取りましょう。
中小企業診断士試験の勉強時間にまつわるQ&A
効率性を重視して試験勉強を進めていこう
中小企業診断士試験の勉強時間は1,000時間ほどといわれています。また、試験は第1次試験と第2次試験(筆記・口述試験)の受験だけでも約半年は必要です。短期間で合格を目指すためにも、効率性を重視して試験勉強を進めていきましょう。
クレアールでは、学習対象を合格に必要な最小限の範囲に絞った「非常識合格法」という忙しい人でも効率よく合格を目指せる勉強法を採用しています。興味のある方は、下記のフォームより無料書籍をご請求ください!

監修:古森 創
ソニー(株)にてマーケティング、営業、経営監査、新規事業開発の仕事に従事した後、中小企業診断士として独立開業。株式会社古森コンサルタンツ代表取締役。ソニーでの経験をベースとした「売上改善プログラム」、「新規事業開発推進支援」を中心にコンサルティング・セミナー・研修など実務の第一線で活躍しながら、受験のプロとしてもこれまで多くの合格者を輩出し、「スゴ腕講師」として高い評価を受ける。