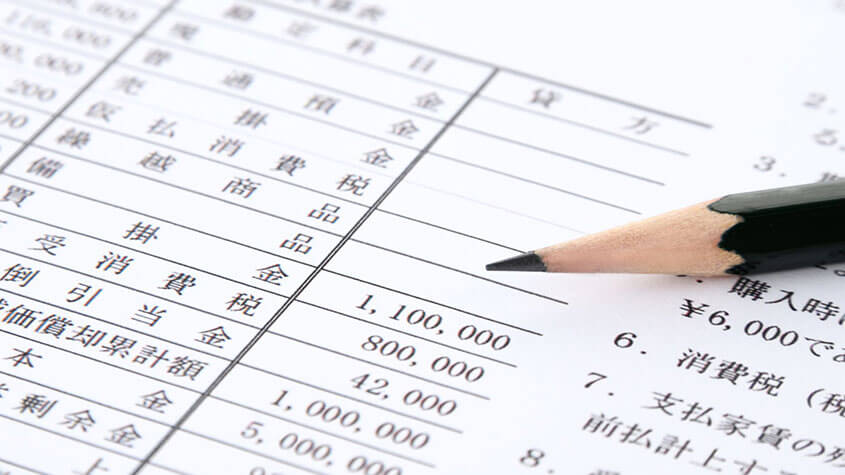「中小企業診断士と簿記の資格はどっちも取るべき?」と悩む方もいらっしゃるでしょう。
本記事では中小企業診断士試験と簿記試験に焦点を当てて、それぞれの試験の概要や難易度、簿記の中小企業診断士試験への活かし方などについて解説します。中小企業診断士や簿記の資格取得を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
中小企業診断士と簿記はどっちが難しい?簿記何級レベル?
中小企業診断士と簿記は、試験範囲が重複していない部分もあるため、一概にどちらが難しいとはいえないのが実情です。
ただ、中小企業診断士試験の中の「財務・会計」科目は、日商簿記2級レベル相当の問題が出題されます。そのため、簿記2級以上の知識があれば、中小企業診断士試験で有利に働くでしょう。
中小企業診断士試験と簿記試験の違い
中小企業診断士と簿記は試験においてさまざまな違いがあります。本章では、中小企業診断士試験と簿記試験のそれぞれの概要について解説します。
中小企業診断士試験
中小企業診断士試験は第1次試験(筆記試験)と第2次試験(筆記試験・口述試験)に分かれています。第1次試験と第2次試験の筆記試験それぞれに「財務・会計」があり、これが簿記の知識を役立てられる科目です。
中小企業診断士の試験に合格するためには、最低でも1,000時間の勉強時間が必要とされています。両試験を合わせた最終的な合格率は4~6%程度と、かなり難易度の高い資格です。
中小企業診断士第1次試験の「財務・会計」
中小企業診断士第1次試験は全7科目のマークシート形式で行われます。7科目のうち、「財務・会計」は試験1日目に実施される科目で、配点は100点、試験時間は60分です。
実際の「財務・会計」の試験では、財務に関する「資金調達」「投資等」や、会計に関する「財務会計」「管理会計」などのテーマを中心に出題されます。「財務・会計」は7科目の中でも難易度が高いため、優先的に勉強時間を確保する必要があるでしょう。勉強時間の目安は180時間前後といわれています。
中小企業診断士は実務において数字を扱うスキルが必須です。そのため「財政・会計」は、第1次試験の中でも最も重要な科目として位置づけられています。
【出題範囲】
簿記の基礎/企業会計の基礎/原価計算/経営分析/利益と資金の管理/キャッシュフロー/資金調達と配当政策/投資決定/証券投資論/企業価値/デリバティブとリスク管理/その他財務・会計に関する事項
中小企業診断士第2次試験(筆記試験)の「財務・会計」
中小企業診断士第2次試験(筆記試験)は全4科目の記述式です。その中で「財務・会計」は4科目目の「事例IV」として出題されます。配点は100点、試験時間は80分です。
第1次試験と同様、第2次試験においても「財政・会計」は重要な科目として位置づけられています。
実際の試験では、財務諸表が与えられ「現状分析」「課題発見」「改善提案」についての計算・論述問題が出題されるケースが多いです。
簿記試験
簿記試験は、簿記(企業における日々のお金の動きを帳簿に記録すること)に関する技能を測る試験です。簿記試験には主催団体別に、日商簿記・全経簿記・全商簿記の3種類があり、最も広く知られているのは日商簿記です。
日商簿記の合格率は3級が30%前後、2級が20%前後、1級が10%前後となっています。また、日商簿記の合格に必要な勉強時間は、3級で100時間前後、2級で200時間前後、1級で600時間前後が目安です。
【級別】簿記の中小企業診断士試験への活かし方

前述の通り、中小企業診断士試験と簿記試験では内容に重複している部分があるため、簿記の知識があると中小企業診断士試験を有利に進められます。本章では、簿記の知識を中小企業診断士試験へ活かす方法を見ていきましょう。
簿記3級
簿記3級は、社会人が身につけるべき知識として、最も基本的な商業簿記の知識の修得を目的とした資格です。簿記3級試験の合格には、小規模企業における経理業務をこなせる程度のスキルが必要とされます。
中小企業診断士試験の方がより高度な知識を要求されるため、簿記3級は「財務・会計」をゼロから勉強するための導入としても有効です。
簿記2級
簿記2級は経営管理に役立つ知識レベルとして、より高度な商業簿記・工業簿記の修得を目的とした資格です。簿記2級レベルのスキルがあれば、年商数億円ほどの中小企業における経理業務をこなせるといわれています。
簿記2級の試験は、中小企業診断士試験の「財務・会計」と同じ出題範囲をカバーできるため、試験へも大きく活かせるでしょう。さらに、簿記2級を持っていれば、中小企業診断士のメイン業務となる、「財務・会計における企業状況の把握」にも役立てられます。
簿記1級
簿記1級は、極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の修得を目的とした資格です。合格には、上場企業の経理業務をこなせるレベルの知識や、経営者視点で会計管理ができる知識が要求されます。
簿記1級は非常に難易度が高く、中小企業診断士試験よりも高度な会計知識が必要なので、中小企業診断士試験の合格を目指すうえで、簿記1級取得の優先度は高くないでしょう。
中小企業診断士試験と簿記に関するよくある質問
中小企業診断士試験と簿記試験の相性は抜群!
中小企業診断士試験と簿記試験は親和性が高く、簿記2級レベルの知識があれば、中小企業診断士試験の勉強を効率的に進められます。また、簿記の資格を有していればスキルの幅が広がるため、実務にも大いに役立つでしょう。
簿記の知識や資格がある人は、中小企業診断士とのダブルライセンスを目指してみてはいかがでしょうか。
クレアール中小企業診断士講座では独自の「非常識合格法」を採用しています。重要な論点にポイントを絞って学習するため、効率良く、かつ質も落とさない学習で合格を目指すことができます。短期合格して早くキャリアアップしたい人には最適の学習法です。
クレアールの通信講座では、働きながらでも無理なく自分のペースで合格を目指せます。興味のある方は、下記より無料パンフレットをご請求ください。

監修:古森 創
ソニー(株)にてマーケティング、営業、経営監査、新規事業開発の仕事に従事した後、中小企業診断士として独立開業。株式会社古森コンサルタンツ代表取締役。ソニーでの経験をベースとした「売上改善プログラム」、「新規事業開発推進支援」を中心にコンサルティング・セミナー・研修など実務の第一線で活躍しながら、受験のプロとしてもこれまで多くの合格者を輩出し、「スゴ腕講師」として高い評価を受ける。