中小企業診断士とMBAのどちらを取得すべきか迷う方は多いでしょう。本記事では、中小企業診断士とMBAの違いについてさまざまな面から比較します。また、どちらの取得が向いているか判断できる適正チェックも用意しているので、どちらの資格をとろうか考えている方はぜひ参考にしてみてください。
中小企業診断士とMBAは比較されやすい
中小企業診断士とMBAは、取得する際にどちらも主に企業経営の知識を学べるため、比較されるケースが多い資格です。まず、中小企業診断士とMBAとは何かについて見ていきましょう。
MBAとは?
MBAは資格ではなく、ビジネススクールと呼ばれる大学院の修士課程を修了した人に与えられる学位です。「Master of Business Administration」の略で、日本語では「経営学修士(経営管理修士)」と呼ばれます。
1881年に設立されたアメリカのウォートン・スクールが世界初のビジネススクールであり、1908年にハーバード大学に設立されたハーバード・ビジネス・スクールがMBA課程の基礎を確立したとされています。
MBAの学位を取得すると企業経営に必要な知識を持っていると評価され、コンサルティング業務や企業内での管理業務に活かすことが可能です。
中小企業診断士とは?
中小企業診断士とは経営コンサルティングに関する唯一の国家資格です。取得すると中小企業の経営課題の診断・助言を行う専門家として認定されます。
資格取得後は、主に中小企業からの依頼に対し企業の経営内容を診断し、改善策や解決策などを提案するコンサルティング業務を行います。
一般企業だけでなく、行政や金融機関で中小企業施策の支援を行う職務に活かすことも可能です。
中小企業診断士とMBAの違い
中小企業診断士とMBAはどちらも経営について深く学べますが、さまざまな点で違いがあります。中小企業診断士とMBAの違いについておさえておきましょう。
学位か資格かの違い
MBAは大学院の修士課程を修了した人に与えられる学位であり、資格ではありません。大学院を卒業すると得られるものであり、一度取得すると生涯有効となります。
一方、中小企業診断士は国家資格です。資格には有効期限が定められており、5年に一度の更新が必要です。資格を更新するためには、研修の受講や実務への従事が求められます。
取得方法の違い
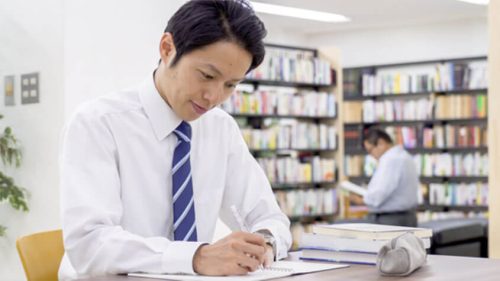
MBAを取得するには、国内や海外の大学院において所定の単位を取得し、修了要件を満たす必要があります。修了要件や授業形態は大学院によって異なるので、複数の大学院を比較するとよいでしょう。
授業形態は、平日の日中に通しで授業が行われるものと、平日の夜間や週末にのみ授業が行われるものがあります。働きながらMBAの取得を目指す人には後者のパートタイム型が人気です。
ほとんどの大学院は通学形式ですが、最近はオンラインで学べる大学院もあります。
一方、中小企業診断士を取得するためには、国家試験である中小企業診断士試験に合格する必要があります。中小企業診断士試験は第1次試験と第2次試験があり、第1次試験の合格者が第2次試験を受験可能です。
第2次試験合格後に15日以上の「実務補習」を受講するか、15日以上の「診断実務」に従事すると中小企業診断士として登録できます。
もしくは、第1次試験の合格後に中小企業基盤整備機構や登録養成機関が実施する養成課程を修了すれば、中小企業診断士として登録可能です。
学習内容・学び方の違い
MBAは基本的に、経営資源の3要素「ヒト・モノ・カネ」について学び、経営に関する知識を身につけます。大学院では、グループワークを取り入れた事例研究やプレゼンテーションなど、実践的な学習方法が中心となるのが大きな特徴です。
細かい学習内容や方法は大学院それぞれに特色もあり異なるため、自分に合った大学院を選びましょう。
中小企業診断士の学習内容は、基本的に中小企業診断士試験の試験科目です。
第1次試験の試験科目である「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理(オペレーション・マネジメント)」「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・中小企業政策」の7科目を学習します。
さらに、第2次試験の科目である「組織・人事」「マーケティング・流通」「生産・技術」「財務・会計」の学習も必要です。
中小企業診断士の勉強方法は座学が中心で、内容理解や暗記などを中心に試験対策を行います。
人脈形成のしやすさの違い
MBAを取得する過程では、人脈を作りやすいとされています。大学院でグループワークなど共同作業を行うことで、学生同士で交流が深まるためです。大学院で築いた人脈が将来的にビジネスで役立つケースも多いため、生涯を通して大きな財産となるでしょう。
一方、中小企業診断士試験の勉強は、1人での座学が中心となるため人との交流は生まれにくいかもしれません。しかし、試験に合格したあとは研修や実務で有資格者同士のつながりも出てくるでしょう。
取得後のキャリアの違い

MBAを取得していれば、管理職や経営陣への昇進といったキャリアアップが期待できます。経営の専門家として転職や独立・開業を目指すのも可能なため、キャリアの選択肢が大きく広がるでしょう。
ただし、大学院によって育成したい人材像は異なるため、どこの大学院でMBAを取得したかもその後のキャリアに関わる点には注意が必要です。そのため、目指したいキャリアに合ったカリキュラムを組む大学院を選ぶのが重要といえます。
中小企業診断士の取得後のキャリアは、主に2つの道が考えられます。1つは「企業内診断士」としてコンサルティングファームや民間企業などに所属する働き方です。もう1つは「独立診断士」として独立・開業する働き方があります。
どちらの診断士であっても、相談員として国や地方自治体、商工会議所などの公的機関から業務を請け負う場合もあります。
中小企業診断士とMBAの共通点
中小企業診断士とMBAにはさまざまな違いがありますが、中にはいくつか共通点もあります。
たとえば、経営に関して幅広い領域を学べるのは共通点です。経営について深い知識を有する人材は貴重なため、どちらを取得した場合も重宝される人材となるでしょう。
また、取得後に独立を目指せる点も共通しています。独立するために、中小企業診断士の資格とMBAはどちらも活かせるということです。独立・開業を目指している方は、その他の観点からどちらを取得するか選択するのがよいでしょう。
中小企業診断士とMBAを取得する難易度は?
MBAは学位、中小企業診断士は資格であり、取得の過程も異なるため、難易度を単純に比較することはできません。ただし、合格率や倍率でそれぞれの難易度を予想することは可能です。
MBAの入学試験の倍率は、大学院によって異なるものの例年2~3倍で推移している大学院が多く見られます。たとえば、人気の大学院のひとつである一橋ビジネススクールのMBAプログラムでは、入学倍率は例年2倍を超えています。
一方、中小企業診断士の合格率は、年度によって異なるものの例年約4~8%です。
以上の数値から、中小企業診断士とMBAはどちらも簡単に取得できるものではなく、取得には多くの勉強時間が必要といえるでしょう。
【適性チェック】中小企業診断士とMBA、どちらの取得が向いている?
MBAと中小企業診断士のどちらを目指すべきか悩んでいる人に向けて、それぞれの適性チェックリストを作成しました。AとBのチェックリストのあてはまる項目の数を数えてみましょう。
【MBAと中小企業診断士の適性チェックリスト】
※このチェックリストは、結果を保証するものではありません。結果に進路を委ねるのではなく、あくまでもご参考程度にご活用ください。
A
☐経営の全体像を体系的に学びたい人
☐論理的思考力やコミュニケーション能力を養いたい人
☐実務で成果を出したい人
☐人脈を形成したい人
B
☐中小企業の経営に関して診断や助言を行う業務につきたい人
☐経営に関してより広く学びたい人
☐公的機関でのキャリアを形成したい人
☐国家資格という肩書を活かして活躍したい人
Aのチェックが多かった方はMBA、Bのチェックが多かった方は中小企業診断士に適性があるといえます。ただし、上記のチェックリストはあくまで目安であるため、参考程度にご活用ください。
中小企業診断士とMBAに関するよくある質問
中小企業診断士とMBAどちらを取得すべきか選択しましょう
中小企業診断士とMBAの取得過程では、どちらも経営に関して幅広い領域を学べます。どちらを取得した場合でも、経営に関する専門知識を持つ貴重な人材として重宝されるでしょう。
しかし、取得方法や取得後のキャリアなど、両者にはいくつか違いもあります。どちらを取得するか迷っている方は、チェックリストを参考にしながらどちらが自分に向くか考えてみましょう。
中小企業診断士の取得を検討している人は、「クレアールの中小企業診断士講座」で学習するのがおすすめです。クレアールでは中小企業診断士を目指す方に向け、効率的かつ質の高い学習環境を提供しております。
時間や場所を問わないweb学習のため、忙しい方でも自分のペースで学習を進められるのが魅力です。また、講師からの手厚いサポートも受けられるため、苦手な部分を解決しやすいでしょう。興味のある人は、ぜひ下記よりお問い合わせください。

監修:古森 創
ソニー(株)にてマーケティング、営業、経営監査、新規事業開発の仕事に従事した後、中小企業診断士として独立開業。株式会社古森コンサルタンツ代表取締役。ソニーでの経験をベースとした「売上改善プログラム」、「新規事業開発推進支援」を中心にコンサルティング・セミナー・研修など実務の第一線で活躍しながら、受験のプロとしてもこれまで多くの合格者を輩出し、「スゴ腕講師」として高い評価を受ける。




