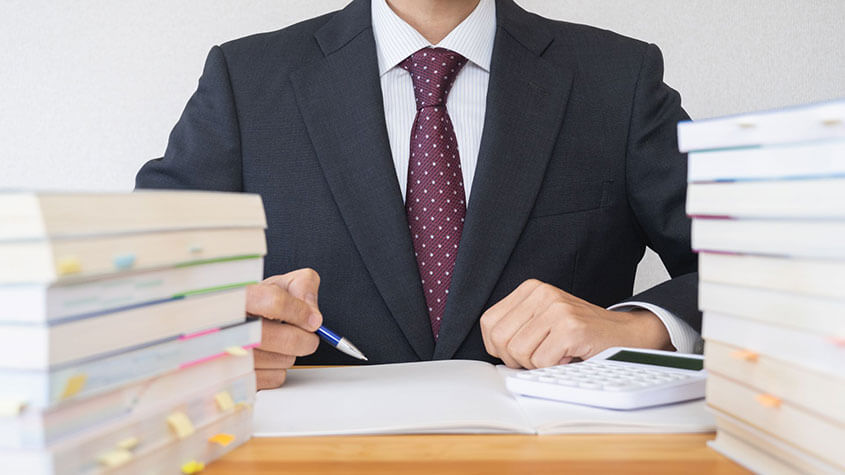中小企業診断士と社労士のダブルライセンスにはどのようなメリットがあるのでしょうか。本記事では両方の資格を取得するメリットや、仕事内容・試験概要・合格難易度の比較も解説します。社労士と中小企業診断士のダブルライセンスを視野に入れている方は、ぜひ参考にしてみてください。
社労士と中小企業診断士の資格は相性が良い

社労士と中小企業診断士は、どちらも企業の経営を支える専門家として親和性が高く、ダブルライセンスとしても非常に相性のよい組み合わせです。
企業には人事や労務問題以外にも、経営全般にわたる課題が多くあります。社労士と中小企業診断士の両方のスキルを有していれば、労務リスクの管理に併せて成長戦略を提案するのも可能です。
労務管理と経営改善の専門知識はどの業界においても重宝されやすいため、社労士と中小企業診断士のダブルライセンスにより、多方面でキャリアが築ける可能性が高まります。
社労士と中小企業診断士のダブルライセンスを取得するメリット
社労士と中小企業診断士は、業務内容の親和性が高いため、ダブルライセンスの取得がおすすめとされています。ここでは、社労士と中小企業診断士のダブルライセンスを取得するメリットを解説します。
顧客から信頼を得やすくなる
社労士と中小企業診断士のダブルライセンスにより、複数の難関国家資格を有している状態となります。顧客にとっても、複数の国家資格を持つ優秀な人材に業務を任せるのは安心感につながるでしょう。
また、社労士の業務も中小企業診断士の業務も一手に引き受けることができるため、コミュニケーションをスムーズに取れる点もメリットといえます。
提案の価値が向上する
社労士の観点から「労務」の、中小企業診断士の観点から「経営コンサル」のアドバイスを行えれば、経営に対する提案の価値が上がるでしょう。
労務環境の整備は、企業にとって重要な課題です。企業が抱えているさまざまな課題を、労務だけでなく経営コンサルにも熟知した人材に任せられるのは、顧客にとっても大きなメリットになります。このことから、集客アップも見込めるでしょう。
業務の幅が広がる
中小企業診断士が行う経営コンサルティング業務は、中小企業診断士のみに認められた独占業務ではありません。
しかし、中小企業診断士の資格は、唯一国から認められた経営コンサルタントの資格です。中小企業診断士の資格を保有しているだけで無資格者との差別化が図れるため、業務の幅を広げることができるでしょう。
社労士と中小企業診断士の仕事を比較

社労士と中小企業診断士は、専門分野や資格の性質が異なるため、さまざまな点で違いがあります。ここでは、社労士と中小企業診断士の仕事の違いについて、「業務内容」「働き方」「独占業務」「年収」の4つの観点から解説します。
| 社労士 | 中小企業診断士 | |
|---|---|---|
| 業務内容 | 人事・労務管理 | 経営コンサルティング |
| 働き方 | 企業や事務所勤めが中心 | 企業勤めが中心 |
| 独占業務 | あり | なし |
| 年収 | 約780万円 | 約780万円 |
業務内容の違い
社労士の業務内容は、人事・労務管理に関するものがメインとなります。具体的には、書類作成や手続き代行、相談を受けるなどの業務があります。
一方、中小企業の経営課題の分析や問題解決のためのアドバイスを行うのが主な業務内容です。中小企業診断士は「経営コンサルに」関する唯一の国家資格といわれています。
働き方の違い
社労士の働き方として、一般企業のほか社労士事務所・社労士法人で働くのが一般的です。中小企業診断士は、一般企業に勤める方が多い傾向にあります。
また、社労士、中小企業診断士のいずれの場合も、企業に所属して実務経験や実力をつけてから独立開業するケースが多いです。
独占業務の違い
社労士の扱う業務は「独占業務」を含んでおり、資格を持っていないとできない業務があります。独占業務の内容は、公的機関や法律に関わるものです。
一方、中小企業診断士に独占業務はありません。国家資格として認められているものの、中小企業診断士の資格がないとできない業務はないということです。
年収の違い
年収については、平均値として公表している機関や、アンケートをとって調査している組織などでさまざまな結果が出されているため、一概に比較することはできません。
ただし、どちらの職種においても、正社員の全体と比べると比較的高い年収が期待できます。また、勤める企業や独立後の状況によっては、年収1,000万円以上を目指すことも可能です。
社労士と中小企業診断士の試験概要を比較
社労士と中小企業診断士の難易度は、受験資格や学習時間などさまざまな観点から判断する必要があります。ここでは、社労士と中小企業診断士の資格取得の難易度を解説します。
試験日程
| 中小企業診断士 | 社労士 |
|---|---|
| 1次試験:8月上旬の土日 2次試験(記述):10月下旬の日曜 2次試験(口述):1月下旬の日曜 | 8月下旬の日曜(マークシート試験のみ) |
中小企業診断士試験は1次試験→2次試験(記述)→2次試験(口述)の順に行われ、例年8月から翌年の1月にかけて実施されます。
一方、社労士試験はマークシート試験のみとなっており、試験日は例年8月下旬の日曜日です。
受験資格
| 中小企業診断士 | 社労士 |
|---|---|
| なし | 一定の学歴・実務経験が必要もしくは所定の国家試験の合格いずれかを満たすことが必要 |
社労士と中小企業診断士の受験資格は上記の通りです。中小企業診断士には受験資格がないため、学歴や年齢関係なく誰でも受験できます。
対して、社労士の試験では受験資格が細かく定められています。社労士の詳しい受験資格は以下をご覧ください。
【社労士の受験資格】
・大学、短大、高等専門学校卒業、または学校教育法により短大卒と同等以上の学力があると認められた人
・公務員としての行政事務、社会保険労務士や弁護士、またはそれぞれの法人の補助事務、労働社会保険諸法令に関する事務などの実務経験が3年以上ある人等
・厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した人
試験内容
| 中小企業診断士 | 社労士 |
|---|---|
| 1次試験:マークシート形式試験 2次試験:記述式試験+口述試験 | 択一式試験+選択式試験 |
中小企業診断士試験は1次試験のマークシート形式試験に加えて、2次試験の筆記試験・口述試験の2部構成となっています。
1次試験は「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理」「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・政策」の7科目で、配点はそれぞれ100点です。
2次試験の筆記試験は「組織」「マーケティング・流通」「生産・技術」「財務・会計」の4科目で、配点はそれぞれ100点となっています。口述試験は、筆記試験で問われた事例を基に個人面接形式で行われます。
社労士試験は選択式試験と択一式試験の2種類あります。試験方式は両者共にマークシート形式が採用されています。
試験科目は「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」「労務管理その他の労働に関する一般常識」「健康保険法」「厚生年金保険法」「国民年金法」「社会保険に関する一般常識」の10科目です。
選択式試験は1問5点の8問形式、択一式試験は1問10点の7問形式で出題されます。
中小企業診断士と社労士の合格難易度を比較
中小企業診断士の合格率:5.4%
社労士の合格率:6~7%
中小企業診断士と社労士はどちらも難関資格として知られています。
中小企業診断士試験の令和5年度の合格率は、1次試験は29.6%、2次試験は18.9%です。1次試験・2次試験通しての試験合格率は5.4%となっています。
一方、社労士試験の合格率は例年6~7%で推移しています。それぞれの合格基準は以下のとおりです。
【社会保険労務士試験の合格基準(令和5年度)】
・選択式試験は、総得点26点以上かつ各科目3点以上である
・択一式試験は、総得点45点以上かつ各科目4点以上である
【中小企業診断士の合格基準(令和5年度)】
・総点数の60%以上(420点以上)であること
・満点の40%未満(40点未満)の科目がないこと
中小企業診断士試験では、科目での取得点数に応じて「科目免除制度」を採用しています。各科目に難易度には差があるため、数年かけて科目を分散させて受験する人も少なくありません。例年、中小企業診断士の合格率の計算には、科目免除者の人数も含まれています。
合格するために必要な学習時間を比較
中小企業診断士試験の合格に必要とされる一般的な学習時間は1,000時間以上とされています。このうち、1次試験に800時間、2次試験に200時間を当てるのが目安です。
一方、社労士試験合格に要する一般的な学習時間は800~1,000時間です。
1日に確保できる勉強時間から必要な合格のために勉強期間を計算し、試験本番から逆算して計画的に学習を進めましょう。
社労士と中小企業診断士は兼業できる?

社労士と中小企業診断士には掛け持ちを禁止する規定は存在せず、兼業が可能です。実際に、両資格を活かして働いている方も珍しくありません。
企業は、会社経営のためのさまざまな課題を常に抱え続けています。そのため、社労士と中小企業診断士両方の知識を持つ人材は、どちらか片方の知識を持つ人材と比較して需要が高いでしょう。
また、兼業により包括的なサービスを提供できるようになるため、クライアントからのニーズに応えやすいのもポイントです。
社労士と中小企業診断士を取得するならどっちが先?
人によって考え方は異なるものの、先に中小企業診断士の取得を目指すのが理想といえます。
前述の通り、中小企業診断士試験には科目合格制度があります。全ての科目を一度に合格できなくても、合格基準に達している科目は翌年・翌々年の試験で免除を受けることが可能です。
中小企業診断士試験は受験資格がないうえ、複数年にかけて試験合格を目指せるため、社労士と比べて取り掛かりやすい資格と感じる方も多いでしょう。
また、中小企業診断士試験に合格することで、社会保険労務士試験の受験資格を得られます。その点を考慮しても、先に中小企業診断士を目指すのが効率的といえます。
中小企業診断士の資格取得を目指す方は「クレアール」の通信講座をご検討ください。クレアールの中小企業診断士講座では、重要な論点にポイントを絞って学習できるため、働きながらでも無理なく合格レベルに達することができます。
また、好きな場所や時間にオンラインで学習できる通信講座のため、効率よく勉強を進めたい方や忙しくてまとまった勉強時間を確保しづらい方にもおすすめです。まずは学習相談もできるので、気になる方はぜひお気軽にクレアールにお問い合わせください。
社労士と中小企業診断士のダブルライセンスを目指そう
社労士と中小企業診断士は業務の親和性が高く、ダブルライセンスにより多方面でのキャリア構築が可能となります。ただし、社労士試験と中小企業診断士試験は、共に合格率10%未満の難関試験であるため、合格するには計画的な学習が必要です。
社労士と中小企業診断士のダブルライセンスを目指す方は、まず受験資格のない中小企業診断士の資格取得を検討してはいかかでしょうか。
中小企業診断士の取得を目指す方は、「クレアール」の中小企業診断士講座がおすすめです。クレアールでは、重要な論点にポイントを絞って学習する「非常識合格法」を採用しております。
時間や場所の融通が利く通信講座のため、働きながらでも効率的に合格を目指すことが可能です。興味のある方は、ぜひお気軽にクレアールへお問い合わせください。

監修:古森 創
ソニー(株)にてマーケティング、営業、経営監査、新規事業開発の仕事に従事した後、中小企業診断士として独立開業。株式会社古森コンサルタンツ代表取締役。ソニーでの経験をベースとした「売上改善プログラム」、「新規事業開発推進支援」を中心にコンサルティング・セミナー・研修など実務の第一線で活躍しながら、受験のプロとしてもこれまで多くの合格者を輩出し、「スゴ腕講師」として高い評価を受ける。