中小企業診断士は中小企業の経営課題を診断し解決する専門家です。中小企業診断士は国家資格であり資格試験の難易度は高く、合格するには幅広い知識を求められます。この記事では、中小企業診断士資格試験の難易度と勉強に必要な時間、さらに効率的な勉強法などをご紹介します。
中小企業診断士試験の合格基準
【中小企業診断士試験の合格基準:1次試験】
・得点率が60%以上であり、かつすべての科目で40点以上
・科目合格基準は満点の60%以上を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率
【中小企業診断士試験の合格基準:2次試験】
・筆記試験の得点率が60%以上であり、かつすべての科目で40点以上
・口述試験の評定が60%以上
中小企業診断士試験には受験資格がなく、年齢や学歴などで制限されません。また、企業の経営に関する実務経験がなくても受験できるため、会社から証明などを発行してもらう必要もありません。
この試験では、中小企業診断士に関連する資格を取得していると、試験科目が一部免除となります。免除科目があると、学習時間を削減できるため、試験要項などで調べるとよいしょう。
また、1次試験で合格した科目については、3年間有効となります。3年以内であれば、過去の1次試験ですでに合格した科目については免除されるため、再受験で合格につながりやすいのが中小企業診断士試験の特徴です。
中小企業診断士試験の合格率

2024年において、中小企業診断士試験の1次試験の合格率は27.5%、2次試験は18.7%でした。中小企業診断士試験は合格率10%を切る難関だということがわかります(中小企業診断会より)。
中小企業診断士試験は1次試験と2次試験からなっており、1次試験は筆記試験、2次試験は筆記試験と口述試験が課されます。1次試験、2次試験ともに企業経営に関する幅広い知識が必要です。
合格率の低い中小企業診断士試験ですが、さまざまな経歴の人が受験し合格しているため、出身大学やその偏差値とは関連性が薄いともいえます。
中小企業診断士試験の難易度【1次試験】
中小企業診断士試験の1次試験はマークシート方式で合計7科目あります。科目合格するにはそれぞれ6割以上の正解率を出さなければいけません。
科目によって難易度が異なりますが、財務・会計の科目が最も難しいとされています。次いで、企画経営理論、経営情報システムなどの科目も難しいとされています。
7科目ごとの合格率は毎年変動があり、一概にどの科目が合格しやすいともいえないため、時間配分など注意が必要です。

中小企業診断士試験の難易度【2次試験】
中小企業診断士試験の2次試験は、筆記試験と口述試験から構成されており、1次試験と異なり、いずれも応用力を問われる内容となっています。
2次試験の筆記試験は記述式で合計4科目あり、筆記試験は合格が難しいことから難関とされ、一方、口述試験では合格しやすいといわれています。
なお、2次試験は「相対評価」となっているのが特徴で、受験者全体の上位約20%に入らないと合格できないため非常に難関な試験とされています。

国家資格内での中小企業診断士試験の難易度ランキング
中小企業診断士試験は、国家資格の中でもビジネスに関連する分野に属しています。そもそも、ビジネス関連の国家資格の難易度を正確にランク付けすることは困難で、国家資格の中でもかなり難易度が高い資格試験といえます。
ただし、同様にビジネスに関連する国家資格である、公認会計士や税理士などの資格試験よりはやや合格しやすいでしょう。
中小企業診断士試験合格に必要な勉強時間
独学で中小企業診断士試験に臨んだ場合、1次試験および2次試験に合格するのに必要な時間は、最低1,000時間といわれています。
1次試験は7科目それぞれで100時間以上の勉強時間を確保する必要があるといわれており、苦手科目があれば、さらに勉強時間が必要です。また、2次試験は1次試験を踏まえた出題がなされ、300時間以上の勉強時間が必要です。
仕事をしながら合格を目指すのであれば、年単位で考えることが大切です。できるだけ短時間で効率的に合格したい方には、最短での合格を目指す「非常識合格法」を採用しているクレアールの通信講座をおすすめします。
中小企業診断士試験の合格を効率よく目指すには

中小企業診断士試験は難関ではあるものの、しっかりと学習プランを立てて臨めば決して突破不可能な試験ではありません。ここでは、中小企業診断士試験に効率よく合格する方法を解説します。
戦略的な学習スケジュールを立てる
短時間で効率的な合格を目指すのであれば、戦略的な勉強方法をとる必要があります。中小企業診断士試験には、1次試験および2次試験を合わせて複数の試験科目があるため、自分がどの科目が得意、あるいは不得意なのかを見極め、それぞれの学習にかける時間をうまく配分することが重要です。さらに、同じ科目内でも頻出する箇所を重点的に学習し、出題されにくい部分には時間をかけすぎないことが大切です。
学習ツールや通信講座を活用する
せっかく学習スケジュールを立てても、独学の場合は自分一人での時間管理が難しく、計画倒れしがちです。無駄なく学習を進めるには、明確なカリキュラムのある学習ツールや通信講座を利用することをおすすめします。クレアールの中小企業診断士講座では、初学者向けコースや2次試験対策コースなど、合格を目指す方の現段階の進捗に合わせた講座をご用意しています。
1次試験・2次試験を分けずに勉強する
中小企業診断士資格試験では、1次試験がマークシート方式であるのに対し、2次試験は記述式のため、後者のほうが難しいといわれています。しかし、1次試験と2次試験で関連度の高い科目もあります。そのため、効率的にご合格するためには、1次試験の学習を開始する時点で、2次試験でも出題頻度の高い内容を重点的に学習しておくと良いでしょう。
まずは他資格から取得し、中小企業診断士試験につなげる
中小企業診断士の資格取得者の中には、簿記やファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士などの他資格とダブルライセンスを所持している人もいます。1次試験で最も難しいとされる財務・会計の知識を習得するには日商簿記3級の資格が有効であるため、あらかじめ簿記3級を取得しておくと、中小企業診断士試験の学習に役立てることができます。
難易度の高い中小企業診断士に合格するには効率的な勉強が大切
この記事では、中小企業診断士試験の合格率や、1次試験および2次試験に必要な勉強時間と効率的な勉強方法などについてご紹介しました。中小企業診断士試験に合格するためには最低でも1,000時間必要といわれており、数年単位で合格を目指す方がほとんどです。そのため、特に社会人の方が仕事をしながら合格を目指すためには、効率的かつ戦略的に学習していく必要があります。
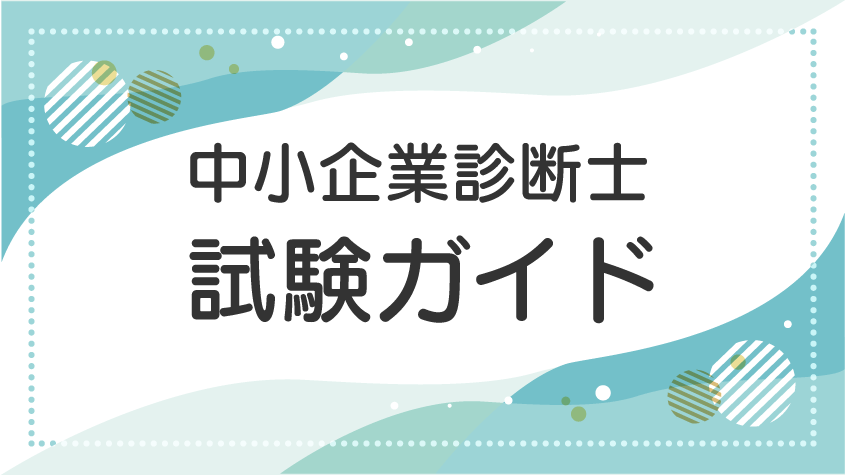
クレアールでは、学習対象を合格に必要な最小限の範囲に絞った「非常識合格法」という忙しい人でも効率よく合格を目指せる勉強法を採用しています。興味のある方は、下記のフォームより無料書籍をご請求ください!

監修:古森 創
ソニー(株)にてマーケティング、営業、経営監査、新規事業開発の仕事に従事した後、中小企業診断士として独立開業。株式会社古森コンサルタンツ代表取締役。ソニーでの経験をベースとした「売上改善プログラム」、「新規事業開発推進支援」を中心にコンサルティング・セミナー・研修など実務の第一線で活躍しながら、受験のプロとしてもこれまで多くの合格者を輩出し、「スゴ腕講師」として高い評価を受ける。


