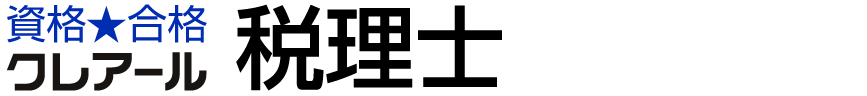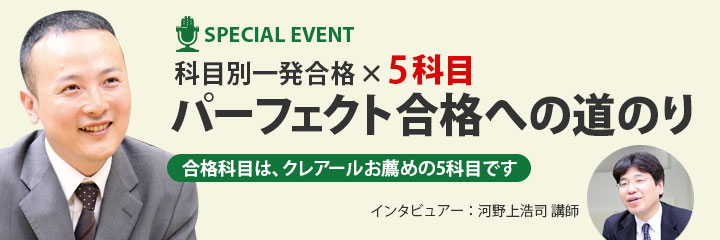
毎年、「合格できなかったらこれで終わり」と背水の陣で税理士試験に臨まれたという宮本さん。各科目1回合格のパーフェクト合格を実現した宮本さん自身に、合格までの道のりとその秘訣を語っていただきました。
- 宮本光一朗さん

働きながら科目別一発合格で5科目合格
1979年生まれ。大学在学中に簿記2級を取得。2003年卒業後、メーカーへの就職。人事部に配属となり、退職金制度の改定に携わり、その関係でFP取得。その後、専門的な資格と、人に誇れる資格を取得したいと考え、税理士資格を目指す。
FPから、より専門性の高い税理士に挑戦

河野上:では、座談会を始めさせていただきます。改めまして、合格おめでとうございます。
宮 本:ありがとうございます。
河野上:通信で受講されていたので、宮本さんとお会いするのは初めてですね。それでは、簡単で結構ですので、自己紹介とか、受験のきっかけとか、クレアールとの出会いについて、お話しいただければと思います。
宮 本:私の自己紹介という点では、大学を卒業してからすぐの就職で人事部門に配属になりました。その関係でFPの勉強をすることになりましたが、FPという資格では、税務的な話をするには、業法の壁があったことから、若いうちに人に自慢できるようなもっと大きな専門性のより高い資格を取りたいと思ったのがきっかけで、税理士を始めました。
河野上:なるほど。合格科目は、簿記・財表、必須科目で、あと法人税法、選択科目では消費税法、相続税法ですよね。
宮 本:クレアールお薦めの5科目。
河野上:その通りですね。合格の順番は、まず簿財の同時合格、次に、消費、相続、ここまで2年ですね。
宮 本:2年で4科目です。
河野上:プライベートでご病気があったので、1年空きましたが、最後に法人税ですね。受験は各科目1回ずつで合格されたわけですね。
宮 本:そうですね。
河野上:税理士を目指したきっかけだとかキャリアについては良くわかりました。
河野上:クレアールとの出会いについてですが、クレアールに入学される決め手になった点を教えてください。
宮 本:税理士目指そうと思ったときに色々と受験スクールをインターネットで調べていたのですが、「非常識学習法」についての内容と学費の面がすごくリーズナブルだったのが、決め手でした。どちらかというと、学費の面から入学した気がします。「非常識合格法」の範囲を絞り込み基礎を徹底的にやるという点については、別に非常識ではなくて、ごく当たり前のことではないのかと思っていました。
河野上:実際に入学してみて、簿記論・財務諸表論を1人の先生が教える点、重要なところを徹底的にやるからテキストが薄いという点は、どうでしたか。
宮 本:簿記論・財務諸表論を最初から最後まで区別して考えたことがなかったので。ずっと一体でやっていました。
河野上:講義をしている時は、簿記や財表の内容ということを強調せず、徹頭徹尾で会計学を教えていたつもりでやっていますが、受講生の立場から見て、宮本さんには、その点は感じていただいていましたか。
宮 本:実感しました。もう全然区別なく、逆に、簿記だけ、財表だけというと、損する感じがしたぐらいでしたから。
河野上:非常識合格法の中で、簿財を1人の先生が教える点は、違和感はなかったと。
宮 本:全くなかったですね。
河野上:次に教材についてですが、薄いとか厚いとかということに関しても違和感はなかったですか。
宮 本:法人を除いてはなかったです。法人税はさすがに構えました。
河野上:簿財の学習をスタートされてから、他の学校の教材と比較されたことはありますか。
宮 本:会社の同僚に税理士試験受験者が、何人かおり、クレアールのテキストは薄いと言っていました。
河野上:そこで不安にはならなかったですか。
宮 本:なりませんでしたし、クレアールのテキストの量でないと逆に消化できませんでした。
河野上:消化できませんか。時間もそうなのでしょうけど、たくさんあり過ぎてもすべてをマスターできませんからね。
宮 本:結局、どんどん教材が送られてくると、消化できずに、気持ちの面で負ける気がします。
河野上:簿財アドバンスのカリキュラムは、週2コマぐらいで回せるようなカリキュラムになっていますが、やはり社会人の方はそれが限界だと思うのです。宮本さんは、ドロップアウトせずに続けられたという点では、気持ちの面では負けなかったということですよね。
宮 本:そんなことはないです。点数が全然伸びないときは、負けそうになりました。年明け答練がスタートしてからは特にそう感じました。講義の未視聴もあるのにも関わらず、どんどん応用答練が送られてきますので、そこで、明らかに回っていないなという感じが出てきます。
河野上:答練で点数が伸びないと、やっぱり気持ちの面でモチベーションが下がってしまうものですね。
河野上:宮本さんの場合、仕事もご家庭もある中、勉強時間をどのように捻出されたのかを、お聞かせ願いたいのですが。

宮 本:勉強時間は、とりあえずスキマ時間を利用するしかないので、平日は仕事が終わって子どもが寝た後の22時や23時から1コマ。1コマといっても3時間のうち1時間だけをしかも、1.5倍速で視聴していました。平日は、半分寝ながらでもいいので必ず1時間は視聴していました。また、休みの日は、少なくても3時間から4時間はやっていましたが、年明けぐらいから徐々にエンジンをかけていって、ゴールデンウイーク明けからが勝負と決めていたので、その時期はちょっとお金が掛かるのですが、自習室を借りてやっていました。
河野上:仕事が終わって、お子さんが寝られた後に勉強するというのは、たとえ1時間でも毎日続けることは、相当強い意志がないと続けられないと思いますが、モチベーションを維持するための方法みたいなものはありましたか。
宮 本:特にはありませんでしたね。もう勢いの世界でした。
河野上:1.5倍速で視聴していたとありましたが、1.5倍速での視聴というのはそんなに支障はないものですか。
宮 本:ありませんでしたね。ただ、難しい論点や、頭に入りづらい論点は、倍速の速度を落としたりしていましたが、ほとんど1.5倍速で視聴していました。
河野上:さて、いよいよ具体的な学習方法の話に入っていきたいと思います。色々な制約の中での勉強時間を捻出される方法として、例えば暗記は電車の中でやるとか。
宮 本:暗記は、寝る前にベッドでゴロゴロしながら覚えたりしてました。あとは、問題集とかは必ず全部コピーして、ガンガン書き込んでいました。
河野上:解答用紙だけをコピーされるという話はよく聞きますが、問題集もコピーして、ガンガン書き込むと。
宮 本:PDFで取っておいて、必要なときに印刷していました。目だけで追うのではなく、体で覚えておきたいと思い、自分なりのマークの付け方とかも体で覚えるよう、問題集もコピーして書き込んでいました。
河野上:先ほど、宮本さんの理論集や問題集を拝見させていただきましたが、やり込んでいることがすごく分かりました。本当に各論点をつぶしているんだなということが分かりました。
宮 本:ひたすら理論集と問題集はやっていました。
河野上:受講生の方から、よく勉強方法を含めた、やり方を聞かれますが、正直、勉強方法に正解はないと思います。その人がストレスをためないことと、あとは気持ちが途中で折れないようにする勉強方法を自分で見つけていくしかないと思います。
宮 本:全くその通りだと思います。私の場合、気持ちの面では、とにかく「来年はない」という負ければ次はないという強い気持ちで自分自身を追い込んでいましたね。あとは、1年1科目というデッドラインを決めていました。
1年目、簿記論、財務諸表論からスタート
次に簿財の具体的な勉強の仕方を教えてください。8月に入学されて、基礎期から直前期、本番までを、時系列に区切って、聞いていきたいと思います。12月までの基礎期の勉強は、WEBを視聴して、テキストの例題だとか、問題集を解いていった。
宮 本:それで精一杯でした。
河野上:12月までは講義中に話したことをやっていたと。
宮 本:答練を受けなさいといわれれば、たとえ点数がボロボロでも受けて提出していました。
河野上:年内までの、授業内容は楽しかったですか。
宮 本:楽しかったですね。たとえ疲れていても受けたいと思える授業でした。
河野上:クレアールの講義では単元別ということで、実は1コマ3時間の講義を学校側の方で、1時間単位で単元ごとに区切っています。理由としては仕事で疲れて、平日視聴するには、1時間というのが集中力の面でも限界と考えたからですが。
宮 本:そうですね。1時間の講義というのは、ちょっと頑張ろうという、学習を継続するためには、ちょうど良い時間だと思います。
河野上:年明けから答練が始まります。講義中、応用答練は、ぜひ6回は復習してくださいと話しているのですが、宮本さんはどうでしたか。
宮 本:ゴールデンウイークぐらいまでは答案を提出するので精一杯でした。応用答練の復習は、点数が取れたものに関しては2回ぐらい。内容によっては、相性の合わない問題もあったので、試験の直前になってくると、そういう問題を重点的に繰り返していました。
河野上:直前の答練は、2~3回の復習でいいですよといっていましたが。
宮 本:直前答練も2回ぐらいやりました。
河野上:応用と直前で答練の復習回数に差がなかったと。
宮 本:直前答練は、どちらかというと試験直前のチューンナップという意味合いで使っていました。
河野上:チューンナップという点では、自分でこの問題をいつ解くかという、組み立てができるところが、通信講座の良さの一つですね。
宮 本:いつ解くかについては応用期から決めていました。答練の回数もかなりあったので、計画的に解いていましたが、講義の視聴もあったので、やっとでしたけれども。直前期も、1日に1題、1時間分ぐらい、財表だと、計算問題。簿記論は、平日2時間通しで解く時間がなかったので、1時間問題だけとかやっていました。基本毎日解いていました。
河野上:基本毎日ですか。簿財アドバンスの講座は、非常識合格法のコンセプトにより、インプットは、他校より少ないのですが、アウトプット(答練)の回数は、特に簿財はこれでもかというぐらい多いのですが、受講していて多いと感じていましたか。
宮 本:確かに、皆さん回数は多いと思っていたはずです。

河野上:公開模試は、本試験より難しいレベルの出題をしていますが。公開模試の出来はどうでしたか。
宮 本:芳しくなかったですね。
河野上:精神的なダメージが大きかったと思うのですが、切り替えはできましたか。
宮 本:先生が講義の中で、初学者の人は、公開模試の後から大きく伸びるというのを信じてやっていました。私の場合、公開模試もあまりよくありませんでしたが、とにかくこんなところで負けていたら、本番で合格することはできないだろうと思い、意地でも食らい付くという感じで、答練を繰り返していました。
河野上:次に、簿記と財表での問題の解き方というのを教えてもらっていいですか。
宮 本:問題の解き方が、はっきりとしていたのは財表でした。解く順番とかは、決めていて、必ず理論から解いていました。第1問20分、第2問20分で40分。
河野上:そうしないと、時間を計算に回せないですよね。残りの80分の中で第3問の計算は、財表の場合はどの分野から解かれたのですか。
宮 本:有価証券か減価償却で、問題をざっと見た感じでのフィーリングの合うほうから解いていました。この2つからまずは勝負します。そこから負債に飛んでいきます。しかしながら、これは解けそうにないなと思ったら、後回しにしていました。それから、現金預金の分野、次に金銭債権でした。金銭債権が苦手だったので。
河野上:答練の解説のなかでよく、まずは現預金と金銭債権、有価証券を、20分から25分で通過してくださいと話していたと思うのですが、あえて自分が苦手な金銭債権を最後に持ってきて、何かリスクを感じたりしませんでしたか。
宮 本:リスクに感じることはありませんでした。得意分野と不得意分野があるので、まずは自分の解き方のパターンと一番治まりのいい分野から解いていました。どのみち時間内に全部解くことはできませんから。
河野上:それはすごく大切な点ですけど、財表の問題は、時間内で全部最後まで解ききれないという認識でいいですよね。そうすると、あとは自分のストレスのないやり方で、順番にどんどんやっていくと。あと簿記はどうですか。簿記の場合、部分だけを解くことができないので、解く順番としては、第1問からか、第3問から解くかの、あとは順番に解いていくと。何かルールはありましたか。
宮 本:簿記は第1問から、順番でした。ただ第3問は、分量も多いので、やはり得意なできそうなところからやっていました。
河野上:なるほど、分かりました。非常に安心しました。
河野上:それ以外にも、受講生の方が気になされている点として、点が伸びない時の対処法というものがあります。個別問題はできるけど、総合問題になると急にできなくなってしまう。どこから解いていいか分からない、解き方も分からないという悩みを、相談されるのですが、これについてはどう思われますか。
宮 本:時間をかけても解けないのなら、論点が理解できていないのだと思います。また、限られた時間の中で得点が上がらないのであれば、問題を解く量が不足していると思います。総合問題を解く時のパターンができていないということが原因だと思います。
河野上:解くパターンというのは、インプットで身に付くものなのでしょうか。それとも答練を数多く解くことで身に付いてくるものなのでしょうか。
宮 本:答練のやり直しの中で、一番重視していたのは、解き方というか、自分の中で解くスタイルを確立することを常に心がけていました。自分だけが分かる記号とか、この印が付いていたら、ほかの論点にも結び付いているとか、マークとかに自分だけに分かる意味を決めていました。とにかく試験中は時間がないので、頭を使って解かないと駄目なのですが、思い出している時間ももったいないので、反射レベルで解けるようにすることを重視していました。
河野上:結局は、解くパターンとおっしゃっているのは、頭を使わなくても普通に自分が解けるようになる状態まで持っていくということですね。宮本さんの場合、解くパターンが身に付いたというのは、いつぐらいだったのですか。
宮 本:直前期の答練を回しているときでしたね。公開模試のときは、まだちょっとモタモタしていた記憶があります。
河野上:初学者の方が、公開模試の後でも解くパターンが身に付けることができれば合格できるということですよね。
宮 本:1カ月以上前に直前答練が終わるので、1日1題と考えても30回は解けるので、30回も解いていると、さすがに問題を半分ぐらい覚えるようになりますので。

河野上:そうですか。解く順番がすごく気になっていたのですが、意外と宮本さんのレベルでも、金銭債権という苦手な分野があったのだなということと、あまりそこについては引け目を感じられずにやられたのだなと。要は、もうできないのだから、後回しにして時間があったら解こうと割り切られていらっしゃったのだなというのは、すごく皆さん参考になると思います。それから、要は解くパターンは最後の最後に身に付ければいいという意味では、公開模試の後になっても、あきらめずにやっていたら、合格は見えてくるということですね。
宮 本:一番伸びたと実感できたのは、たぶん私は公開模試の後だと思います。
河野上:時期でいうと、7月ですよね。
宮 本:そうですね。そこまで本当に合格できる自信はなかったのですが、試験を受けるときにはかなり自信が付いていました。
河野上:結果として簿財は一発で合格をされたということですね。
河野上:次に試験後の受験生の動向についてなんですが、一般的な受験生は、試験の出来がどうであれ、発表までに4カ月間空くにも関わらず、次の科目へ踏み出すのが、遅い人が多いんです。そこで、クレアールでは、毎年改正がある法人とか、所得ではなく、改正が少なくボリュームも少ない消費税を早めに学習するよう勧めています。試験終了後から消費税を学習していれば、万が一、12月の合格発表で簿財のどちらかが駄目でも、次の年の2科目合格を十分狙えますから。宮本さんの場合、次年度の税法はもう、消費と相続で決めていらっしゃったのですか。
宮 本:簿財を受講して、クレアールには信頼が持てたので、浮気はしないでクレアールで受講しようとまず決めて。色々考えていたらダメだと思って、試験が済んだら勢いで8月中に次の消費税法と相続税法を申し込みました。申し込んでしまったら次に向かって勉強せざるえない状況になりますから。気持ち的には一息入れてからという気持ちもありましたが、自分を追い込むために、お盆には申し込みました。
河野上:だから、あえてボリュームのある重たい法人税を最終科目にしたと。
宮 本:それも本当です。
河野上:宮本さんは、自分を追い込むタイプですね。申し込みも早く、かつ終わりも気を抜かないように重たい科目にすると。合格体験記の中で、法人税を最後の科目にされた理由を「ボリュームの少ない科目を最後にすると、性格上、油断してしまう」とありましたよね。ご自身の性格が分かっているから、そういったプラニングができるということなのですね。
宮 本:今までの自分の成功体験からすると、最後の3カ月で大きく伸びたという経験があり、ボリュームの少ない税法を最後に持っていくと、ピークの持っていき方が難しいと感じていました。本試験当日にいかに最大瞬間風速を吹かせられるかが大事なので。
河野上:最大瞬間風速を吹かすために、当日の朝、ちょっとした問題を解くことは効果ありましたか。
宮 本:ありましたね。講義の中で先生が、試験当日に問題を解くといいですよとおっしゃっていたので当日、「この問題はいいですよ」という問題を解いたのですが、普段間違えないようなところをぼこぼこ間違えてしまいました。試験を受ける前に我に返る時間が持てたことが、合格につながったと思います。
2年目、消費税法、相続税法へ
河野上:次に2年目の税法についてですが、まずは、消費税は勉強されてみてどうでしたか。
宮 本:イメージが最後まで湧かずにつらかったです。課税取引、非課税取引とか、全部の答練をまとめて回しだした時に、あ、消費税はこうなってつながっているのだという、入り口と出口が全部見えてきたというのが、実感です。簿財の場合は、最初から最後まで分かっていないと、解けないというのは、ほとんどなくて、好きなものからのつまみ食いでも解けましたが、税法は最初から最後まで理解して初めて意味が分かるようになると思います。
河野上:全体の消費税の最後の納付税額を出すころまで学習して、スキームが分かってからでないとやっていることが分からないということですよね。よく、会計と税法は何が違うのかと質問されますが。会計は、貸借が合っていなかったら、自分が間違っているとすぐ分かりますよね。それに比べ税法は最後まで一方通行だから、自分が合っているかどうかは、最後まで分からないですよね。そこが、簿財から消費税に上がってきた方が最初に陥ってしまうポイントです。消費税の全体像がつかめるようになるには、講義の8割程度ぐらいまで進まないと、消費税が何をやる税法なのかが見えてきません。そこに消費税の難しさがあると思います。一方、相続税については、合格体験記でもFPの知識があったので比較的すんなり頭に入ったとありましたが。
宮 本:相続の財産評価に関してはFPで学習した知識を思い出していく程度でよかったという感じではありましたが、複雑な問題は、気を抜くと間違えてしまうところはありました。

河野上:次に税法の理論と税法の計算の勉強の仕方について教えてください。
宮 本:消費に関しては、計算主体という感じはしました。消費の理論には、算式、数式を言い換えただけのものが結構あるので。まず計算から入って、計算を理解した後で理論を暗記したほうが、暗記がしやすかったです。対して、相続は理論主体です。相続税の条文は、長文でかつ日本語が少し難しいため、覚えにくいという感じでした。
河野上:相続税というのは税法の中でもちょっと毛色の変わった科目だと理解してよろしいでしょうか。
宮 本:そう捉えても良いと思います。まず相続は、計算方法自体が全然違っていたり。そもそも物の値段を与えられていないところを計算するというものなので、そういう意味ではちょっと違うと思います。
河野上:先ほどの簿財でのドロップアウト感というのは、最後まで学習しないと分からない点の多い税法の場合は、どうだったのでしょう。税法は、どこでドロップアウトしてしまうのでしょうか。
宮 本:講義を聞いていても、分からないので面白くないというところですかね。
河野上:その面白くない税法とどう付き合うかという点は、自分の中でクリアされましたか。
宮 本:とりあえずは「やる!」という感じです。
河野上:学習を継続させるためには、小さな成功体験を積み上げていくことだと言われますが、宮本さんの場合、達成感はどういうところに置かれていましたか。例えば、初めて総合問題が解けるようになったとか、そういう点はどうでしたか。
宮 本:消費税は最初、答練を丸写し、答練を中心に繰り返して解いていくなかで、ある程度パターンが身に付いてきました。そうなると、何を意味しているかが徐々に分かってきます。そういうことの積み重ねで、何か達成した感はありました。
河野上:相続税だと一つ一つの財産評価のやり方が分かるたびですかね。
宮 本:そうですね。1個また理解できたみたいな。財産評価は完全に個別問題の組み合わせなので、ある時から急に視野が開けるような感動というよりも、一つまた一つと、理解できた項目が増えていく毎に喜びを見い出していました。
河野上:今日は、宮本さんの受験時代の消費税法の理論問題集も拝見しましたが、理論集がぼろぼろになっていましたね。本当にクレアールの理論集と心中してもらったということがよく分かりました。最近、税法の理論集が段々薄くなってきており、行間も広げて極力文字数を減らす、言い換えれば、キーワードを押さえてキーワードをつなげて書くという指導傾向が他校に見られますが、宮本さんの経験として、税法の理論の暗記というのは、本当にキーワードだけで対応できると思いますか。
宮 本:合格点を別としたら、対応できると思いますが、合格点となると、難しいと感じます。 理由が2つあり、1つは時間面です。とにかく税理士試験は、時間との勝負なので、頭を使ってキーワードをつないでいる時間がもったいないという点。覚えたものをそのまま答案用紙に書くほうが早いと思います。もう1つは、法律というのは、本当に一言一句、無駄がありません。場合によっては、この一文、一語を逃してしまうと、意味が全く変わってしまう場合があるからです。特に相続をやっている時は、その点をすごく感じていたので、キーワードだけでは難しいという感じがします。
河野上:合格体験記でも税法は一字一句の意味をおろそかにすると、たった一字の違いで大減点になるという恐ろしさを知ったと書かれていましたよね。やはりキーワードではなく、意味があって条文になっているのだから、条文をきちんと、まずは暗記をしないと駄目だよということですね。
宮 本:やはり日本の頭脳が集った上で作られている法律なので、条文には無駄がないと思います。
河野上:分かりました。理論集については葛藤することが多く、受講生の皆さんにとって、税法の理論って、簿財の理論と比べるとハードルが凄く上がったように感じるようです。「理論集は、全部覚えなければいけないのですか」という質問をたくさん受けます。「全部ですよ」という応え方をしていますが、その「全部」の意味を、丸暗記と解釈している方もいますが、単に丸暗記とも違うわけです。理論は、丸暗記して覚える必要があるもの、丸暗記はしなくても本番で書けるものと、理論集を全部覚えるにしても、僕は色分けというか峻別というのが必要だと思うのですが。

宮 本:その通りだと思います。計算式が理論になっているようなものだったら、多少は完璧に暗記していなくても対応できますから。例えば文字で言うと、何を言っているかよく分からないのですが、式に直して冷静に考えると、日本語にしていけると思うのです。そういうところは逆に、一字一句覚える必要はないと思います。特に定義のところは、一字一句覚えなければいけないと思います。以上と未満とか、等だとか理論集のそういうところにマーカーの線を入れてました。
河野上:ちょっと安心しました。学習というのは、全体を見せた上で、後でカスタマイズして、自分で覚えやすくするとか、暗記しやすくするというのは、皆さんがそれぞれ工夫されることで、実力が付くものだと思います。最初からキーワードだけ覚えておきなさいという理論集であれば、受講生にとって、かえって効率が悪くなるだけだと思うのですが。
宮 本:税法科目の本試験の問題も、覚えた理論がそのままになって出題されていたので、法律の文章を書いてバツが付くはずがないと思います。キーワードだけを覚えているとどうしても作文になってしまうので、少し不安は感じますね。もし、採点者とフィーリングが合わなかったりすると、大減点されてしまう可能性も考えられます。
河野上:クレアールとしては、他校の状況を踏まえた理論集を作るつもりはないのですが、皆さんから、「理論集を全部覚える必要があるか」というご質問がすごく多いので、今回の宮本さんの話を聞いて、受講生がモチベーションを上げるきっかけになってもらえればと思います。
宮 本:比較的、会計の理論は、合格ボーダーラインはすごく取りやすいと思うのですが、ボーダーラインを大きく飛びぬけるレベルまで持っていくには、かなりの数の財務諸表論の本を読み込んだりしないと、そのレベルにまで持ち込むことは難しい気がします。一方で税法科目の理論は、理論集さえ、しっかり覚えておけば、ボーダーを大きく飛びぬける合格確実ラインまで乗せられます。
河野上:なるほど。
いよいよ最後の科目! 法人税法

河野上:いよいよ最後の科目の法人税法についてです。私は法人税を勉強される方には、心から敬意を表するのですが、あのボリュームのある科目をよく受験されるなと。所得税か法人税は選択必須なので、「別に受けたくて受けているのではない」と言われればそれまでなのですが。
宮 本:法人税はボリュームが多かったですね。ボリュームが多いこと以外にも、取っ付きにくかったところが1つあって、できなかった会計の決算をどんどん逆算していって元に戻していったりする点は、全くはまらなかったですし、講義を聴いても、分かったような、分からないような感じがして、二重苦、三重苦みたいな感じで勉強していました。 法人税は、とにかくボリュームに圧倒されるところに打ち勝っていくところからがスタートだと思います。ただ私は、ボリュームが多いとどうしても、得意分野、不得意分野が出てくるので逆にチャンスになるのかなとも思っていました。
河野上:ボリュームが多いことで、全部を得意分野にしなくても、多少の苦手分野があっても、負けない程度に押さえていれば合格できるということですね。宮本さんの体験記の中でも全科目に共通しているのは、とにかく合格の確実性を上げるためには、勝つのではなくて負けないことだと。僕はすごくよく分かります。合格者でも試験が終わって合格できたと思える人はごく一部の人だけだと思います。最終的には、ミスが少ない人間が勝っただけの話であって、合格者でもミスはするわけですよ。税理士試験は、10%から20%の方が毎年、必ず合格されているわけですから、合格は必ず巡ってくると。そう考えれば、勝たなくても負けなければいいのだと。
宮 本:そうです。プロ野球の野村監督がおっしゃっていた、「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という言葉がありますけど、本当にその通りだなということは、5科目通して感じました。
河野上:最後に通信で学習される中で、不安の一つとして、目に見えない競争相手と闘うわけですよね。その辺りは、宮本さんはどうお考えですか。

宮 本:正直、自分がどのぐらいのレベルにいるかという点で不安な面はありました。ただ、友達がいるということは、プラスに働くこともあれば、マイナスに働くこともあると思います。傷のなめ合いになってしまうケースというのが出てくると思うので、逆に私は友達がいなくてよかったかなという感じはあります。だから合格体験記でも、通学して人脈を広げたい人は別だけれども、とにかく合理的に合格したければ圧倒的にクレアールが向いていますと、書かせていただきました。
河野上:そうですね。資格ホルダーというのは、全人格でお客さまとぶつからなければいけないのです。単に条文に詳しいとか、税金の計算が早くできるだけでなく、お客さまを諭したり、説得もしていかなければなりません。お客さまによっては、うまくいっていないケースも多く、うまくいってないからこそ我々専門家が必要とされるのです。そして、最後は自分で判断することになります。お客さまにファイナルアンサーをする時は、最後は自分一人で条文と向き合って、自分がどのようにお客さまに報告しなければいけないかを、決定しなければなりません。ある意味孤独といえば孤独ですし、それができないと本当の税理士にはなれません。合格体験記の最後のところで、宮本さんも官報合格して思われた「税理士試験の合格者というのは、単に税金が詳しい人や科目合格者と違って、今までの自ら発する言葉の責任の重さがまったく違います」と。社会的に認められた試験に合格するという重みについて、語っておられるのは、同感です。そういう意味では、勉強段階でのフィールドや、人脈が多い、少ないというのは、あまりこの職業をやっていく上では、絶対的条件ではないのかなと、思いました。これからも、頑張ってください。本日はありがとうございました。
宮 本:こちらこそありがとうございました。
宮本光一朗さんの税理士合格体験記
こちらもあわせてご覧ください。