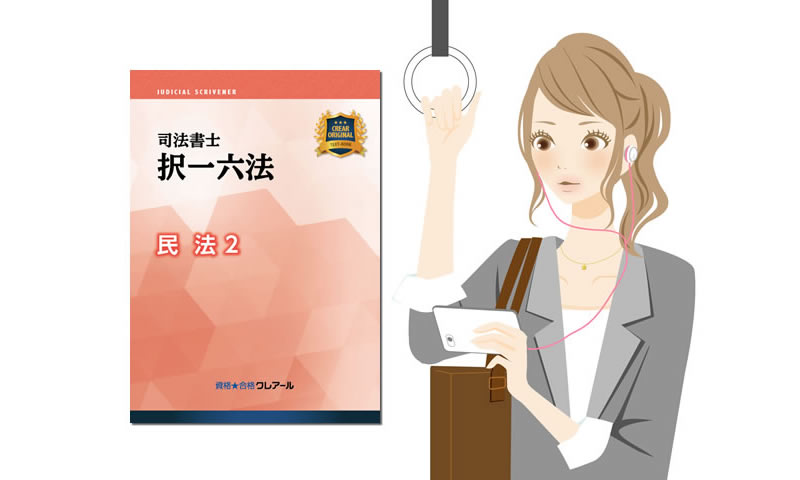第768条【財産分与】
① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
【超訳】
①②③ 離婚した当事者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できるが、当事者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる。この場合、家庭裁判所は分与させるかどうか、また、分与額や方法を一切の事情を考慮して決定する。財産分与請求権は、離婚してから2年の除斥期間の経過で消滅する。
【解釈・判例】
1.財産分与の要素
(1) 夫婦の財産関係の清算(婚姻中の夫婦共有財産の清算、過去の婚姻費用の清算)
→ 裁判所は、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額・方法を定めることができる(最判昭53.11.14)。
(2) 離婚後の生活についての扶養
→ 未成熟子の養育費も含まれると解されている。
(3) 離婚による精神的損害の賠償(慰謝料)
2.財産分与請求権と慰謝料請求権の関係
(1) 財産分与請求権の中に離婚による慰謝料を含めるか否かで解釈上の争いがあるが、離婚した当事者の一方は、有責配偶者に対し、財産分与に慰謝料を含めて請求しても、同一訴訟で両方を併合して請求してもよいとするのが判例である(最判昭53.2.21)。
→ 離婚訴訟に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されない(最判令4.12.26)。
(2) いったん財産分与がなされた場合であっても、それが損害賠償を含めた趣旨と解されないか、又は分与の額及び方法が請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるときは、別個に慰謝料を請求することができる(最判昭46.7.23)。
3.債権者代位権・詐害行為取消権との関係
(1) 財産分与請求権は、協議又は審判によってその具体的な内容が形成される前は、債権者代位権の目的とならない(最判昭55.7.11)
(2) 離婚に伴い財産分与をした者が既に債務超過の状態にあったとしても、当該分与が768条3項の趣旨に反して過大でない限り、詐害行為取消権の対象とならない(最判昭58.12.19)。
(3) 離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は、その損害賠償債務の額を超えた部分について、詐害行為取消権の対象となる(最判平12.3.9)。
4.内縁関係に対する財産分与の規定の準用・類推適用の可否
(1) 当事者の意思による内縁関係の解消の場合、準用されると解されている。
(2) 内縁夫婦の一方の死亡によって内縁関係が解消した場合、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできない(最決平12.3.10)。
5.関連判例
(1) 夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、当該第三者が単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない(最判平31.2.19)。
(2) 離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は、婚姻関係の破綻を生ずる原因となった行為がされた時点ではなく、離婚の成立時に遅滞に陥る(最判令4.1.28)。
【問題】
財産分与の内容には、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めることができるが、慰謝料の支払としての損害賠償のための給付を含めることはできない
【平24-22-オ:×】