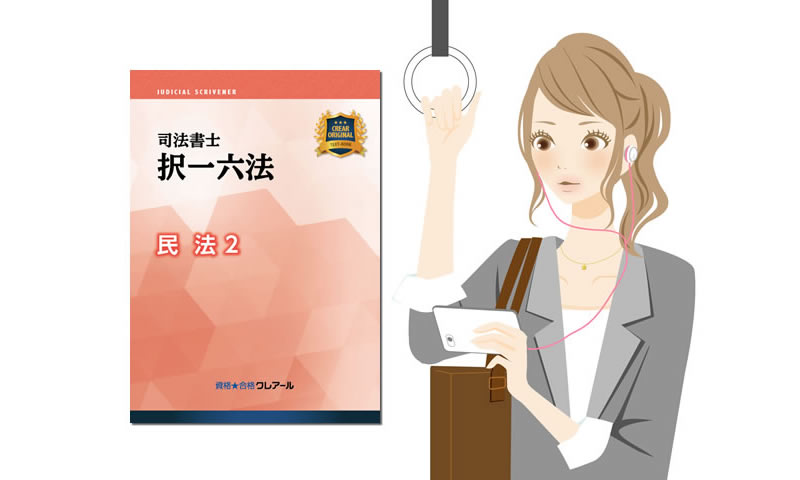第557条【手付】
① 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
② 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。
【超訳】
①② 解約手付の場合、契約の当事者の一方が自己の債務の履行として債務の内容である給付の実行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍返しをして、契約を解除できる。この場合には、損害賠償請求をすることはできない。
【解釈・判例】
1.手付とは、契約の締結に際して、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。売買契約などの主たる契約に付随してなされる従たる契約であり、手付の交付によって効力が生じる。
2.民法は解約手付についてだけ規定を設けているため、交付された手付の性質が明らかでない場合は、その手付は解約手付であると推定される(最判昭29.1.21)。
3. 相手方が契約の履行に着手した後は、手付による解除は認められない(1項ただし書)。「履行の着手」とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部を行い、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をいう(最判昭40.11.24)。
4.履行の着手に該当する場合
(1) 第三者所有の不動産の売買契約において、売主が当該不動産を買主に譲渡する前提として所有権を取得し、かつ自己名義の所有権移転登記を得た場合(最判昭40.11.24)
(2) 農地の売買契約において、売主及び買主が連署の上、知事宛ての許可申請書を提出した場合(最判昭43.6.21)
5.関連判例
(1) 履行期前の行為であっても、常に履行の準備にとどまるわけではなく、履行の着手となり得る(最判昭41.1.21)。
(2) 当事者の一方は、自らが履行に着手していても、相手方が履行に着手しない間は手付による解除ができる(最判昭40.11.24)。
(3)履行の着手の前後を問わず、履行が終了するまでは手付による解除権を行使できる旨の特約がある場合、当事者の一方は、相手方が履行に着手した後でも解除することができる(大判昭14.5.26)。
(4) 売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには、手付金の倍額を償還する旨を告げてその受領を催告するのみでは足りず、倍額につき現実の提供をすることが必要である(最判平6.3.22)。