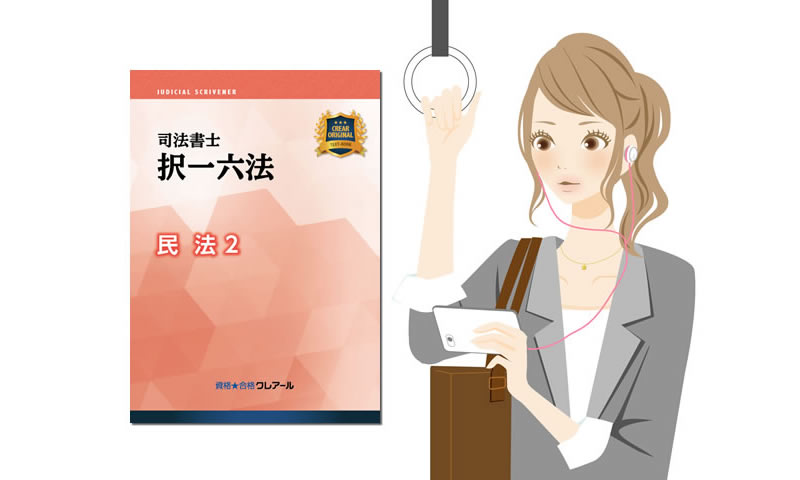第493条【弁済の提供の方法】
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
【超訳】
債務者が債務を支払うには、債権者との約束どおりに、口頭でなく、実際に債権の目的物を差し出さなければならない(現実の提供)。ただし、債権者があらかじめ受け取ることを拒絶している場合は、支払いや引渡しなどの準備をして、その旨を通知して受け取るように催促すればよい(口頭の提供)。履行について債権者の指図や指示を必要とするときも、同じように準備ができていることを通知するだけでよい。
【解釈・判例】
1.弁済の提供は、原則として現実の提供を要するが、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合や債務の履行につき債権者の行為を必要とする場合は、口頭の提供で足りる。
2.「現実の提供」といえるためには、債務者は、債権者が給付を受領する以外には何もしなくてもよいほどに提供しなければならない。その程度は、取引上の慣習や信義則に従って判断される。
3. 「口頭の提供」とは、債務者が現実の提供をするために必要な準備をして、債権者に対して、弁済の準備をしたことを通知し、かつ、その受領を催告することをいう。口頭の提供としての弁済の準備は、債権者が翻意して受領しようとすれば債務者の方でこれに応じて給付を完了しうる程度で足りる。
4.口頭の提供が認められる場合
(1) 債権者があらかじめその受領を拒絶したとき(ただし書前段)
(2) 履行のために債権者の行為を必要するとき(ただし書後段)
5.口頭の提供を要しない場合に関する判例
(1) 債務者が口頭の提供をしても、債権者が契約そのものの存在を否定するなど弁済を受領しない意思が明確と認められる場合には、債務者は口頭の提供をしなくとも債務不履行の責任を免れる(最判昭32.6.5)。
(2) 弁済の準備ができない経済状態にあるため、口頭の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても、弁済の提供をしない限り、債務不履行の責任を免れない(最判昭44.5.1)。