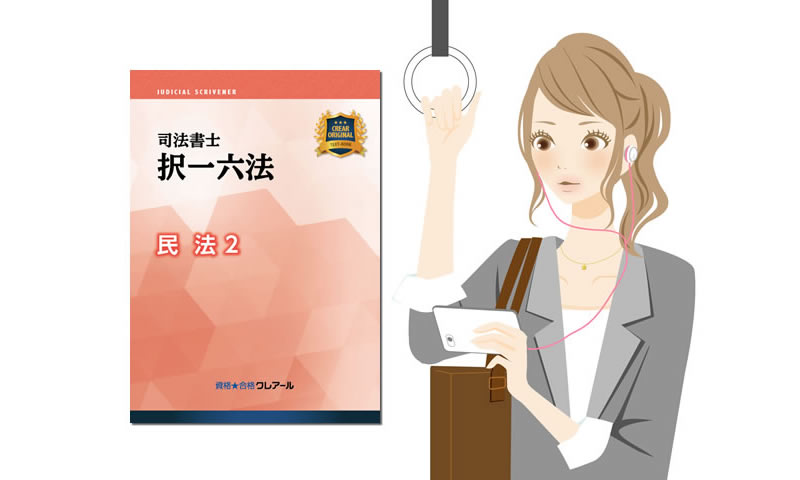第467条【債権の譲渡の対抗要件】
① 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
② 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
【超訳】
① 債権を譲渡するときは、譲渡人である旧債権者から債務者に対して、「誰々に譲渡した」という通知を出すか、または債務者の承諾がなければ債務者に債権の譲渡があったことを対抗することができない。
② 前項に規定する債権譲渡の通知または承諾は、債務者以外の第三者に対しては、「確定日付ある証書」がなければ、債権の譲渡を対抗することはできない。
【解釈・判例】
1.債権譲渡は当事者間では意思表示のみによって効力を生ずるが、その効果を債務者に対抗するためには、債務者への通知又は債務者の承諾を要する(1項)。
2.意義
(1) 通知とは、債権譲渡があったという事実を知らせる行為である。債権譲渡の債務者に対する通知は意思表示ではなく、観念の通知である。
(2) 承諾とは、債権譲渡の事実を了知したことを表示する債務者の行為である。
3.通知又は承諾の方法
(1) 通知は、譲渡人から債務者に対してしなければならず、譲受人が代位してすることはできない(大判昭5.10.10)。
→譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、譲渡人の代理として債権譲渡の通知をすることは可能である(最判昭46.3.25)。
(2) 承諾の相手方は、譲渡人又は譲受人のいずれでもよい(大判大6.10.2)。
4.通知又は承諾の時期
(1) 通知は、譲渡行為と同時になされる必要はない。譲渡後になされた場合は、その時から対抗力を生ずる。譲渡前の通知は無効である。
(2) 承諾は、譲渡行為と同時になされる必要はなく、譲渡の後でもよい。譲渡前にあらかじめされた承諾であっても、債権譲渡の目的たる債権及び譲受人が特定されていれば、対抗要件となる(最判昭28.5.29)。
5.債務者以外の第三者に対する対抗要件
(1) 債権の譲受人が債権譲渡の効果を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知又は承諾を具備する必要がある(2項)。
(2) 確定日付ある通知・承諾が複数存在する場合の優劣の基準
① 原則
債権が二重に譲渡され、確定日付ある通知・承諾が複数存在する場合、譲受人相互間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって決する(最判昭49.3.7)。
② 複数の通知が同時に到達した場合
複数の確定日付ある通知が同時に到達した場合、各譲受人は債務者に対して全額弁済を請求することができる。債務者は単に同順位の譲受人が他に存在することを理由に弁済を拒むことはできない(最判昭55.1.11)。
③ 複数の通知の到達の先後が不明の場合
複数の確定日付のある通知の到達の先後が不明の場合、同時到達と扱われる(最判平5.3.30)。各譲受人は互いに自己が優先的地位にあることを主張できない。
(3) 関連判例
① 債権が二重譲渡された場合に、第1の譲渡の通知に確定日付がなく、第2の譲渡の通知に確定日付があるときは、第1の譲受人は第2の譲受人に債権を対抗することができず、第2の譲受人が債務者に対する関係でも唯一の債権者となる(大連判大8.3.28)。
② 第1の債権譲渡の後、当該債権が弁済等により消滅したにもかかわらず、その後、第2の債権譲渡が行われ、確定日付ある通知が具備されても、その譲渡行為は無効である(大判昭7.12.6)。
【問題】
債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、譲渡人の代理として債権の譲渡の通知をしたときは、譲受人は、その債権の譲渡を債務者に対抗することができる
【平31-17-ウ:〇】