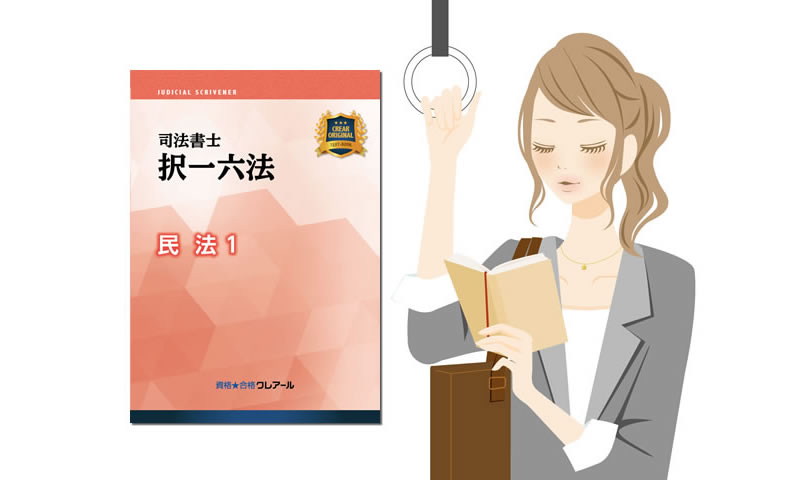第249条【共有物の使用】
① 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
② 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
③共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
【解釈・判例】
1.共有物の使用
(1) 各共有者は、共有物の全部について、自己の持分に応じた使用をすることができる。本条1項の「使用」には収益も含まれる。処分については、変更行為として251条による。
(2) 共有者間の協議で具体的な使用収益の方法が定められた場合はその方法による。当該協議は共有物の管理に関する事項として、持分の過半数で決定する(252条1項前段)。
2.使用の対価
共有者を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。ただし、共有者間で使用の対価を無償とするなどの別段の合意がある場合は、その合意の内容に従う(本条2項)。
3.善管注意義務
共有者は、善良な管理者の注意をもって共有物を使用しなければならない(本条3項)。自己の財産に対するのと同一の注意では足りない。
4.持分権の対外的主張
(1) 確認請求
第三者が共有者の持分を争うときは、当該共有者は単独で自己の持分権の確認を求めることができる(大判大13.5.19)。
(2) 妨害排除請求
不動産の共有者の一人は、その持分権に基づき、共有不動産に対する妨害排除請求ができることから、当該不動産について持分移転登記を経由している者に対し、単独でその抹消登記の手続を求めることができる(最判平15.7.11)
(3) 損害賠償請求
① 共有物の侵害に対する損害賠償は、各共有者は自己の持分について請求することができる(最判昭51.9.7)。
→ 第三者が共有物を侵害した場合における損害賠償請求権は、各共有者の持分の割合に応じた分割債権となる。共有者の収益として生ずる賃料(法定果実)についても同様である。
② 共有者の1人が自己の持分を超えて共有不動産を単独で使用していた場合、他の共有者は、当該不動産の地代相当額のうち自己の持分割合に応じた額について、不当利得金又は損害金の支払いを請求できる(最判平12.4.7)。
【問題】
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、甲土地につき、真実の所有者でないDが所有権の登記名義人となっている場合、Aは、B及びCの同意を得なくても、Dに対し、その抹消登記手続を請求することができる
【平27-10-ウ改:〇】。
【問題】
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び甲土地上の立木を共有している場合、Aは、甲土地上の立木を不法に伐採したDに対し、単独では、その損害賠償を求めることはできない
【平30-10-エ改:×】