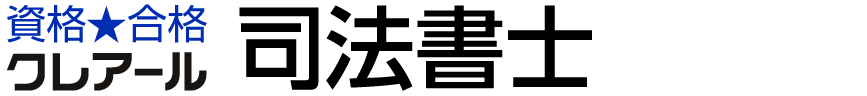第177条【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【超訳】
不動産についての物権の得喪変更は、その登記を具備しなければ、当該登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に対抗することができない。ただし、第三者の側から物権変動の効果を承認することは認められる。
【解釈・判例】
1.登記を要する権利
(1) 登記を対抗要件とする物権
① 登記を対抗要件とする不動産物権は、所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権である(不登法3条参照)。
② 一般の先取特権は、不動産につき登記がなくても特別担保を有しない債権者に対抗できる(336条)。
③ 弁済その他の原因により債権が消滅し、その債権を担保する抵当権が消滅した場合には、抵当権の付従性により抵当権消滅について登記を要しない(大決昭8.8.18)。
【問題】
物権でない権利は、登記をすることができない
【平19-9-2:×】
【問題】
民法に定められている物権は、いずれも登記をすることができる
【平19-9-4:×】
(2) 登記以外を対抗要件とする不動産上の権利
建物所有目的の賃借権や地上権には、借地借家法が適用され、土地の上の建物の登記を借地権の対抗要件とし(借地借家法10条)、また、建物の引渡しをもって借家権の対抗要件とすることができる(借地借家法31条)。
2.登記
(1) 効力
① 登記の公信力
→ 我が国の不動産登記には公信力がない(通説)。そこで、登記名義人を所有者だと信じて取引をしても、あるいは、登記どおりの物権変動があると信じて取引をしても、所有権その他の物権を取得することはない。
② 登記の推定力
→ 登記の付随的効力として、登記に対応する実質的権利の存在が推定される。ただし、事実上の推定にとどまる(最判昭34.1.8)。
(2) 登記請求権
① 物権的登記請求権
→ 現在の実体関係と登記が一致しない場合に、その不一致を除去するため、物権そのものの効力(物権的請求権)として当然に生じる登記請求権。
ア 真実の所有者から不実の登記をした者に対する所有権移転登記請求権(最判昭30.7.5)
イ 登記記録上所有者として表示されているにすぎない架空の権利者に対する所有権移転登記請求権(最判昭34.2.12)
② 物権変動的登記請求権
→ 実質的な物権変動があったにも関わらず、登記がそれに伴っていない場合、実体と登記を一致させるため、物権変動の事実そのものから当然に生じる登記請求権。物権変動の過程を忠実に公示すべきとする不動産登記法の理念から認められる。
ア 不動産がA→B→Cと転売された場合、Bは所有権を有しないが、Aに対して物権変動的登記請求権を行使できる(大判大5.4.1)。
イ 不動産につき権利変動の当事者となったものは、既にその物権を他に移転し、現在においては不動産の実質的権利者でなくなっていても、その登記の是正に関して利害関係を有する限り、登記名義人に対し抹消登記請求権を有する(最判昭36.4.28)。
③ 債権的登記請求権
→ 当事者の合意によって生じる。物権的登記請求権や物権変動的登記請求権と異なり、債権的登記請求権は債権である以上、時効にかかると解されている。
ア 不動産が順次譲渡され、登記名義は依然として最初の譲渡人にある場合に、現在の所有者が登記名義人に対し直接に移転登記請求することは、登記名義人及び中間者の同意のない限り許されない(最判昭40.9.21)。
イ 賃借権の登記をする旨の特約がない場合には、賃借人は賃貸人に対して賃借権の登記を請求する権利はない(大判大10.7.11)。
【問題】
不動産が所有者AからB、BからCに順次売買され、それぞれ所有権の移転の登記がされたが、各売買契約が無効であった場合において、BがCに対してBからCへの所有権の移転の登記の抹消を請求するときにおけるBのCに対する登記請求権は、物権変動それ自体から生じる登記請求権である物権変動的登記請求権に分類される
【平20-8-ア改:○】
(3) 登記引取請求権
① 実体法上の登記請求権については、通常は登記手続上の登記権利者が登記義務者に対して有するものとされている。
② しかし、真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、登記を真実の権利関係に合致させることを内容とする登記請求権を有するとともに、他方はそれに協力する義務を負う(最判昭36.11.24)。
③ したがって、登記義務者も登記権利者に対して登記請求権(登記引取請求権)を有していると解されている。
(4) 中間省略登記の有効性
① 意義
→ 登記が現在の権利関係とは一致しているが、それまでの物権変動の過程と一致していない場合を中間省略登記という。
② 中間省略登記の効力
→ 不動産登記法の理念は、物権変動の過程を忠実に公示すべきこと、及び現在の権利関係を正確に公示することの2点にあるが、重要なのは後者の方である。そうとすれば、中間者に抹消の利益がない以上は、その同意がなくても中間省略登記は有効とすべきである(最判昭44.5.2)。
ア) 不動産がA→B→Cと転売されたとき、BをとばしてA→Cという登記を請求することができるのは、ABC三者の合意がある場合に限られる(最判昭40.9.21)。
イ) 中間省略登記の抹消を請求し得るのは、中間者に限られる。中間者以外は中間省略登記によって害されないからである(最判昭44.5.2)。
ウ) 中間者が抹消登記を請求し得るのは、中間者に抹消登記請求を求める正当な利益がある場合に限られる(最判昭35.4.21)。
3.「第三者」の範囲
(1) 「第三者」の意義
「第三者」とは、当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう(大判明41.12.15)。
(2) 第三者に該当する者
| ① 二重譲渡の譲受人(最判昭33.10.14) ② 共有持分が譲渡された場合の他の共有者(最判昭46.6.18) ③ 差押債権者(最判昭31.4.24、39.3.6) ④ 仮差押債権者(大判昭9.5.11) ⑤ 処分禁止の仮処分債権者(最判昭30.10.25) ⑥ 賃貸不動産が譲渡された場合の対抗要件を備えた賃借人(最判昭49.3.19) → 新賃貸人が賃借人に賃料請求・解約申入れをする際にも登記が必要。 |
【問題】
Aが所有する土地をBに売却した場合において、CがAからその土地を賃借していたときは、Bは、登記をしなければ、Cに対して賃貸人たる地位を主張することができない
【平20-9-ウ改:○】
【問題】
甲土地を所有するAが死亡し、その子であるB及びCのために相続の開始があった。Aは、生前に、甲土地をDに譲渡したが、その旨の所有権の移転の登記をしないまま、死亡した。B及びCは、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした後、Cは、甲土地の自己名義の持分をEに譲渡した。この場合において、Eは、Cの持分についての移転の登記をしなければ、Dに対し、その持分を主張することができない
【平25-7-エ改:○】
【問題】
Aが、その所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間に、Aが甲土地をCに売却してその旨の登記がされ、その後、CがAに甲土地を売却してその旨の登記がされたときは、Bは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない
【平31-8-エ:×】
(3) 第三者に該当しない者
| ① 無権利者及びその譲受人・転得者(最判昭34.2.12) ② 不法行為者、不法占拠者(最判昭25.12.19) ③ 一般債権者(大判大4.7.12)④ 不動産が転々と譲渡された場合の前主(最判昭39.2.13) ⑤ 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた者(不登5条1項)⑥ 他人のため登記を申請する義務がある者(不登5条2項) → 法人の代表者、親権者、未成年後見人、不在者の財産管理人、遺言執行者等の法定代理人、委任による代理人が該当する。 |
【問題】
AとBとが甲不動産を共有していたところ、Aは、その共有持分をCに譲渡したが、その旨の持分移転登記をしていない。この場合において、Cは、Bに対し、甲不動産の共有持分の取得を対抗することができる
【平16-11-ア:×】
(4) 「第三者」に悪意者は含まれるか
| 悪意者といえども自由競争を建前とする現行法の下では、保護されるべきであるし、条文上も善意は要求されていないので「第三者」に含まれる(最判昭32.9.19)。 |
(5) 「第三者」に背信的悪意者は含まれるか
| 含まれない(最判昭43.8.2)。<理由> 背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有さないし、不動産登記法5条も背信的悪意者の登記欠缺の主張を禁止している。 |
|
→ 特定の人に対する復讐目的で取得した者(最判昭36.4.27)や、最初の譲渡の立会人・代理人(最判昭43.11.15)等が、背信的悪意者に当たる。 |
【問題】
A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成したところ、当該取得時効が完成した後にCがAから甲土地を買い受け、その旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bが多年にわたり甲土地を占有している事実をCが甲土地の買受け時に認識しており、Bの登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情があっても、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない
【平26-8-エ改:×】
(6) 背信的悪意者からの転得者
| 転得者自身が第1譲受人との関係で背信的悪意者であると評価されない限り、「第三者」に当たる(最判平8.10.29)。
<理由> 背信的悪意者は譲受人との関係では信義則違反があるために登記欠缺の主張が許されないにすぎず、背信的悪意者も物権を有効に取得している以上、転得者も原則として権利を取得できる。 |
【問題】
Aはその所有する甲土地をBに売り渡したが、その旨の所有権の移転の登記がされない間に、Aが甲土地をCに売り渡してその旨の所有権の移転の登記がされ、さらに、Cが甲土地をDに売り渡してその旨の所有権の移転の登記がされた。この場合には、Cが背信的悪意者に当たるときでも、Dは、Bとの関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、Bに対し、甲土地の所有権を主張することができる
【平28-7-イ:○】
4.登記を要する物権変動
(1) 二重譲渡の法的構成
| ・不完全物権変動説(通説)
→ 登記の有無に関わらず、当事者間でも第三者に対する関係でも物権変動の効果を生ずるが、登記を備えない限り完全に排他性のある効果を生ぜず、したがって譲渡人も完全な無権利者とはならないから、譲渡人はさらに他の者に譲渡することが可能である。 |
| <理由> 取消後においては、登記できるのにこれを放置していたという点で、二重譲渡の場合の登記放置に類似する。 |
(2) 取消しと登記
| ① 取消前の第三者と登記
ア 制限行為能力、強迫による取消し → 取消しの遡及効により第三者は無権利者となるため(121条)、制限行為能力者、強迫の表意者は、登記なくして第三者に対抗することができる。 イ 詐欺による取消し → 善意・無過失の第三者は、登記なくして詐欺の表意者に対抗することができる。 |
| ② 取消後の第三者と登記
→ 取消しの効果としての所有権の帰属を復帰的物権変動と捉え、二重譲渡の関係として、先に対抗要件を備えた者が勝つと考える(大判昭17.9.30)。 |
【問題】
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売してその旨の所有権の移転の登記をした。その後、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる
【平27-7-ア:○】
【問題】
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Aは、Bの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消したが、所有権の移転の登記の抹消をする前に、Bが甲建物をCに売り渡してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合、Cは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる
【平27-7-イ:○】
(3) 取得時効と登記
| ① 時効完成前の第三者 → 登記不要。時効完成前の第三者は時効完成当時の当事者であるから「第三者」にあたらない(大判大7.3.2、最判昭41.11.22)。 |
| ② 時効完成後の第三者 → 登記必要。時効完成後の第三者と時効取得者は対抗関係にある(大判大14.7.8)。※ |
※ 時効完成後の第三者が登記をした後、改めて取得時効に要する期間の占有を継続して時効が完成した場合、その第三者に対しては、登記を経由しなくても対抗できる(最判昭36.7.20)。
【問題】
Aが、Bの所有する甲土地の占有を継続し、取得時効が完成した後、Bが死亡し、Bの相続人であるCが甲土地を単独で相続してその旨の登記がされたときは、Aは、取得時効を援用しても、Cに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない
【平31-8-ウ:×】
(4) 解除と登記
| ① 解除前の第三者
→ 解除の効果は遡及効であるから、解除前の第三者と解除権者は対抗関係に立たない。しかし、解除前の「第三者」が545条1項ただし書によって保護されるためには対抗要件を備えることが必要である(最判昭33.6.14)。 |
| ② 解除後の第三者
→ 解除権者が解除後、登記を備えないうちに第三者が出現したときは、解除による所有権の復帰と、第三者への所有権の移転は二重譲渡の関係にあり、先に登記を備えたものが優先する(最判昭35.11.29)。 |
【問題】
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる
【平27-7-ウ:×】。
【問題】
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Aは、Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した。その後、Bが甲建物をCに転売し、その旨の所有権の移転の登記をした場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる
【平27-7-エ:×】
(5) 相続と登記
① 共同相続と登記
| <問題点> 共同相続人の一人が不動産を単独相続した旨の虚偽の登記を備え、これに基づいて第三者へ譲渡した場合、他の相続人は登記なくして自己の相続分を主張できるか。 |
| <結 論> 単独登記は名義人の相続分を超える部分に関しては無権利者の登記であり、登記に公信力がない以上、第三者は権利を取得できないから、他の相続人は登記なくして自己の相続分を主張できる(最判昭38.2.22)。 |
【問題】
Aが死亡した後、Cは、Bに無断で、Aの遺産である甲土地につきCが単独で相続した旨の登記をし、甲土地をDに売却してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合に、Bは、Dに対し、登記なくして甲土地の2分の1の持分の取得を対抗することができない。なお、Aが死亡した当時、Aには、亡妻との間の子であるB及びCがいたが、他に親族はいなかったものとする
【平28-22-5改:×】
② 遺産分割後の第三者と登記
| <問題点> 遺産分割によって自己の相続分と異なる権利を取得した者は、登記なくして、分割後に相続財産を取得した第三者に主張できるか。 |
| <結 論> 遺産分割後の第三者との関係では、分割によって二重譲渡と同様の関係が生じ、登記がなければ自己の権利を主張できない(最判昭46.1.26)。 |
【問題】
Aが死亡した後、子のB及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産である甲土地の所有権を取得することに合意した。その後、Cは、Dに対し、甲土地の2分の1の持分を売却し、その旨の所有権の移転の登記をした。この場合に、Bは、Dに対し、登記なくして甲土地全部の所有権の取得を対抗することができる
【平28-22-2改:×】
③ 相続放棄後の第三者と登記
| <問題点> 相続放棄後、放棄した者が自己の相続分について第三者に譲渡した場合、他の相続人は登記なくして第三者に対して権利を主張できるか。 |
| <結 論> 相続放棄の遡及効(939条)は絶対的であるから譲渡人は相続開始時に遡って無権利者となり、第三者は権利を取得できない。したがって、他の相続人は登記なくして権利を取得できる(最判昭42.1.20)。 |
【問題】
Aが死亡した後、Cが相続の放棄をした。Cの債権者であるDは、Aの遺産である甲土地につき子のB及びCが各2分の1の持分を有する旨の相続登記をした上でCの持分を差し押さえた。この場合に、Bは、Dに対し、登記なくして甲土地全部の所有権の取得を対抗することができない
【平28-22-3改:×】
④ 特定遺贈の効力発生後の第三者と登記
| <問題点> 不動産の特定遺贈の効力発生(遺贈者の死亡)後、その所有権移転登記をしないうちに、相続人の債権者が当該不動産を差し押さえた場合、受遺者は登記なくして第三者に対して権利を主張できるか。 |
| <結 論> 特定遺贈は遺言者の生前における意思表示に基づく物権変動であるから、受遺者は登記がなければ第三者に自己の権利を主張することができない(最判昭39.3.6)。 |
【問題】
Aは、子のBに対してA所有の甲土地を贈与したが、その旨の所有権の移転の登記がされないまま、子のCに対して甲土地を遺贈する旨の遺言をし、その後に死亡した。この場合に、Bは、Cに対し、登記なくして甲土地全部の所有権の取得を対抗することができない
【平28-22-4改:○】
⑤ 「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)による取得と登記
| 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)によって不動産を取得した者は、法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、その権利を第三者に対抗することができない(民899条の2第1項)。 |
《参考》 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、民法第900条及び第901条の 規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない(民899条の2第1項)
5.明認方法
(1) 明認方法とは、立木及び稲立毛・未分離の果実のように、土地に定着するものについてなされる慣習法上の公示方法をいう。具体例としては、次のものがある。
① 立木の樹皮を削って所有者の氏名を墨書する(or焼印を押す)。
② 立札を立てて所有者名を表示する。
③ 薪炭用の立木について、山林中に薪炭製造設備を作って製炭事業に従事する。
(2) 判例は、立木の対抗要件として、立木のみを譲り受けた場合には「明認方法」、土地とともに立木を譲り受けた場合には「土地の登記」が必要であると考えている。
① 立木とともに土地が譲渡された場合
→ 土地についての移転登記があれば立木についての明認方法は不要(大判昭9.12.28)であり、逆に土地についての登記がなければ、立木にだけ明認方法をしたとしても、立木の所有権を第三者に対抗することはできない(大判大14.3.31)。
② 立木のみの二重譲渡の場合
→ 優劣は明認方法の先後によって決する(大判大10.4.14)。また、ともに明認方法を備えていない場合は、相互に対抗できない。
③ 甲が乙に立木を、丙に立木及び土地を譲渡した場合
→ 立木所有権の優劣は、乙の明認方法と丙の土地の登記の先後によって決する(大判昭9.10.30)。
④ 明認方法の消滅
→ 権利の帰属がわからなくなってしまうので、明認方法は継続して存在しなければ対抗要件とならない(最判昭36.5.4)。
⑤ 立木所有権の留保
→ 甲が立木所有権を留保して、乙に土地を譲渡した後、乙が立木とともに土地を丙に譲渡した場合、甲は明認方法を備えておかなければ、立木の所有権を丙に対抗できない(最判昭34.8.7)。
⑥ 甲が乙から地盤を譲り受け、未登記のままで自ら立木を植栽した場合
→ 甲は乙から後に土地を譲り受けて登記を経た丙に立木所有権を対抗できない(最判昭35.3.1)。
【暗記】
丙からの譲受人である甲・乙間の優劣の決定方法
| 甲(第一譲渡) | |||
| 立木のみの譲受 | 土地と立木の譲受 | ||
| 乙(第二譲渡) | 立木のみの譲受 | 明認方法の先後で決する | 乙の明認方法と甲の土地の登記の先後で決する |
| 土地と立木の譲受 | 甲の明認方法と乙の土地の登記の先後で決する | 土地の登記の先後で決する | |
【問題】
Aは、A所有の立木をBに仮装譲渡し、Bは、当該立木に明認方法を施した。その後、AがCに当該立木を譲渡した場合、Cは、明認方法を施さなくても、Bに対し、当該立木の所有権を主張することができる
【平21-9-イ:○】
【問題】
A所有の土地をBが自己所有の土地と誤信して立木を植栽していたところ、Cが当該立木を伐採して伐木を持ち出した場合には、Aは、Cに対し、当該伐木の所有権を主張することができる
【平21-9-エ:○】
【問題】
Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗することができない
【平31-8-ア:○】