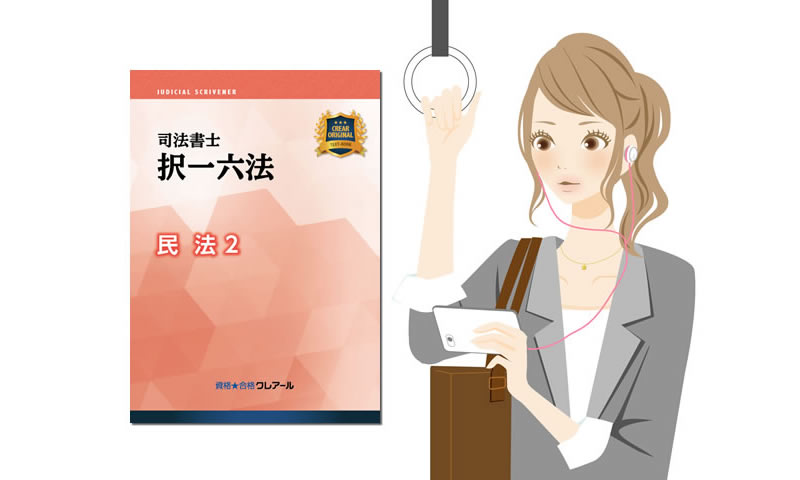第787条【認知の訴え】
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
1.原告
(1) 子は意思能力さえあれば、認知の訴えを提起できる。法定代理人の同意は不要。
(2) 未成年の子の法定代理人は、子に意思能力がある場合でも、子を代理して認知の訴えを提起することができる(最判昭43.8.27)。
(3) 子が生存している場合、その直系卑属は認知の訴えを提起できない。
2.被告
→ 父(例外的に母)。父(例外的に母)の死亡後は検察官。
3.認知請求権
(1) 子の父に対する認知請求権は放棄することができない(最判昭37.4.10)。
(2) 認知請求権は、長期間行使しなかった場合であっても、その性質上、行使できなくなるものではない(最判昭37.4.10)。
4.父の死亡の日から3年以内に認知の訴えを提起しなかったことがやむをえないものであり、また、当該認知の訴えを提起したとしてもその目的を達しえなかった場合には、他に特段の事情がない限り、死後認知の訴えの出訴期間は、父の死亡が客観的に明らかになった時から起算される(最判昭57.3.19)。
5.死後懐胎子と死亡した父との間の法律上の親子関係
→ 保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に、法律上の親子関係の形成は認められない(最判平18.9.4)。
【問題】
妻が、夫の死亡後に冷凍保存された当該夫の精子を用いた人工生殖によって、子を懐胎し出産した場合には、当該夫と当該子との間に実親子関係は生じない
【平31-20-3:〇】