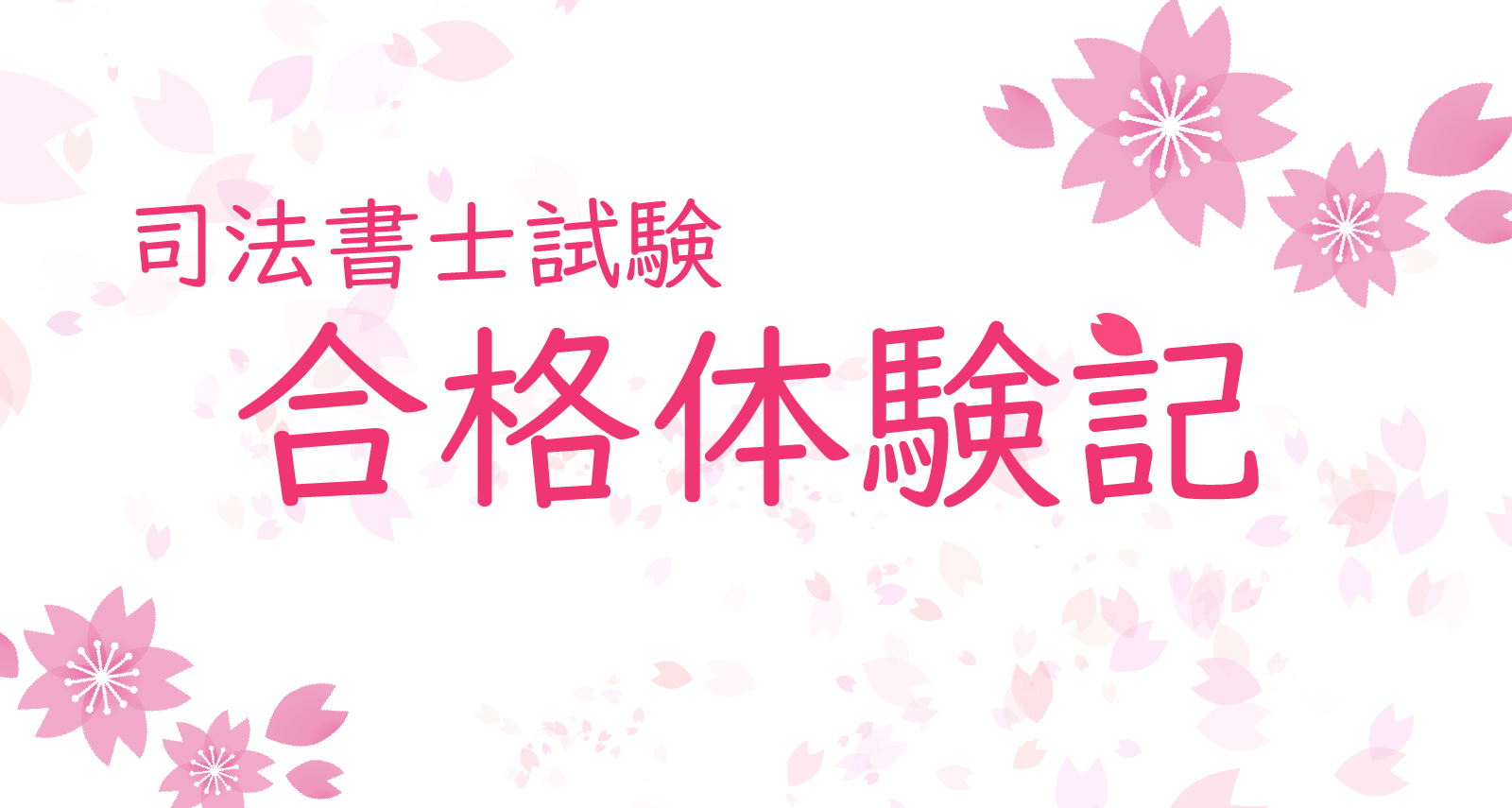奥山 明子さん
受講コース:上級パーフェクトコース
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」と申します。
令和5年に司法書士試験にチャレンジしはじめてから3回目の令和7年、幸いにも合格することができました。しかしこれすらも私にとっては「不思議の勝ち」であり、こうすれば合格できる、といった、いわゆる「勝利の方程式」は私自身にもよくわかっておりません。心残りなことも多く、とても胸を張って「合格しました」とは言えないような有り様ですが、私なりの学習の記録を書き記してみますので、これから受験を目指す方の参考に少しでもなれば幸いです。
司法書士資格を目指した理由
恐縮ながら、強い動機があったわけではありません。年も年だからボケ防止のために頭を使うようにしなければ、それなら手に職をつけられるように資格試験の勉強でもするか…と思ったのがきっかけです。
士業事務所に勤務していますので、どうせなら仕事に実益のあるものをと思い、まずは行政書士、次に社会保険労務士とチャレンジしてきました。その2つは無事パスできまして、次に選んだのが司法書士だったというわけです。
クレアールさんを選んだ理由・良かった点
択一六法
数ある司法書士対策講座の中からなぜクレアールを選んだか。それは『択一六法』の存在が大きいです。
初学者の方なら共感していただけることと思いますが、法律というのはまず言葉が難解なら構造も難解。括弧書きが入れ子になった条文を見てうんざりしたり、ものの本で「括弧書きは隠して読め」と言われたからそのとおりにしてみたらかえって意味がわからなかったり…。そんな経験があるのは私だけではないはずです。
「もうちょっとわかりやすい条文解説がないものか」、とインターネット検索した折に見つけたのが、クレアールがHPで公開している民法・会社法の条文サイトでした。[超訳][解釈]がとてもわかりやすく使い勝手が良かったので、「もし来年も受験することになったら次はここの講座を受講してみようか」と思ったのが令和6年。そしてその年まんまと不合格となり、クレアールにお世話になることになった次第です。
民法・会社法はもちろんですが、不動産登記法や商業登記法等といった普段馴染みのない手続法も、『択一六法』の[超訳]によって要旨がわかりやすくまとめられていて、長い条文でも全体像が把握しやすいため、スムーズに学習を進めることができました。
答練
他に魅力的な点としては、アウトプットの機会(科目別ベーシック答練 択一式編・記述式編、実力完成総合答練等)が豊富なことが挙げられます。特に記述式の答練の機会が多かったのはありがたかったです。
今年は『記述式ハイパートレーニング』なども含めて過去3年間で一番申請書を書いた1年でしたし、それが今回の合格につながっていると思います(正直なところ、他社でも答練回数の多い講座はありますが、受講料が大変高価だったりしますので…コストパフォーマンスの意味でも、クレアールを選択することにしました)。
合格オンラインゼミ
2026年合格目標のコースからはじまったオンラインゼミ。こちらはお時間が許す限りリアルタイム受講されることをおすすめします。
出題されるのは択一式と同様の◯✕問題ですが、単に正誤を答えるだけでなく、「なぜその結論に至ったか」を自分の言葉で説明することが求められます。『択一六法』や過去問題集の解説で何度も目にして頭でわかっているつもりでも、口頭で説明するのはまた違うということが実感できて、いずれは口述試験の糧となるのではないでしょうか。
学習方法
使用テキスト
クレアールからの配布テキスト及び市販の登記六法を利用しました。
学習スケジュール
学習は主に土日祝日。1日あたり3講義のペースで受講し、その後『択一六法』の読み直し、過去問演習など。学習時間は1日あたり4~5時間、1週間あたり8~10時間といったところでしょうか。
平日にノータッチだったのは、私はいわゆる「スキマ学習」が苦手で、長時間腰を据えて取り組むほうが性に合っていたからです。
「学習目標」のようなものは立てず、基本的には講義の配信スケジュールにしたがって下記のとおり進めていきました。
- 配信講義の受講+『択一六法』での復習
- 講義を受講し終わった単元の過去問&CROSS STUDY
- 合間に『記述式ハイパートレーニング』の問題演習
- 答練
あえて目標を立てなかったのは、学習初期のやる気があるときを基準にすると何かと無謀な計画を立てがちで、後々進捗が遅れた際に「目標に達していないこと」がストレッサーになりうるからです(実際、私の場合、その後仕事や私事が多忙な時期と重なり、基本4法+憲法・刑法以外は受講が追いつかなかったので……)。
スケジュールを組むことがモチベーション維持につながる方も多いでしょうから、このあたりは人によりけりということでご了承ください。
その他学習上の工夫
学習環境を整えるために、コワーキングスペースを契約しました。自室だとついつい睡魔に負けてしまったり、買ってきた本が気になったりと誘惑が多いですが、人目のあるところで、周りも仕事や勉強をしている人ばかりという環境は、ほどよい緊張感があって集中できました(図書館も同様の環境と言えるでしょうが、中高生と席の取り合いになりますので、確実に座席を確保できる安心感にお金をかけた方が有益と判断しました)。
具体的対策
択一式
これはひとえに過去問演習に尽きると思います。
特にCROSS STUDYでは、過去問の各選択肢が一問一答形式で出題されます。択一式では通常、どの科目においても、「正しい選択肢or誤った選択肢の組み合わせを選べ」という出題のされ方をしますから、多少あやふやなところがあっても、消去法で正解できてしまったりします。しかし、各選択肢について単独で正誤の判定をすることで、予断を排し、各肢に対する自分の理解度を明確に把握することができました。それが結果として、今年の択一式の基準点クリアにつながったと思います。
私は手で書く&紙面上の文字を読む方が記憶に繋がりやすいタイプなので、基本的には紙冊子の過去問題集をメインに取り組みましたが、「『正しいものの組合せはどれか』『誤っているもの組合せはどれか』といった前提となる問題文を読まずに、各選択肢の正誤を判断する」というCROSS STUDY形式で解くことを心がけました。
その後、理解が不十分なところは『択一六法』で復習→CROSS STUDYで再度演習→それでも間違った問題は「要復習」のユーザータグをつけて後日再チャレンジという方法で正答率を高めていきました(もちろんこれはあくまで学習をする際の話で、本試験ではちゃんと問題文を読んでから取り掛かります。[アイ]が正解だとわかっているのにウ~オを読むのは時間がもったいないですから)。
記述式
一に答練、二に答練です。
テキストや問題集で単元ごとのひな形を書いて覚えることは、もちろん基礎固めとして重要ですが、それと本試験さながらの出題方式での演習は全く異なります。不動産登記であれば前提登記の要否や登録免許税額も含めた最適な登記申請方法の総合的な判断、商業登記であれば実体法上の有効・無効の切り分け、そして実際の登記申請書の起案。これらを制限時間内で行うようにするには経験値がものを言います。
まだ本試験レベルの記述式問題に取り組むことに不安がある、という場合でも、まずは答練に取り組んで見ることをおすすめします。自分の理解の不十分なところやミスしやすいところ、そしてどうすれば時間が足りないなりに点数を積み重ねることができるか…それは、自己採点よりも他人(採点者)の目を通すことでより明確になるからです。
回数を重ねていけば、「出題者はここがわかっているかを確認したいんだな」「ここで受験生が引っかかるかどうかを見ているんだな」ということがおぼろげながら見えてくるようになります。その頃には記述式の答案構成や解答を書きあげるスピードも精度も上がってきているのではないでしょうか。
気をつけるべきこと
択一式
推論・学説問題にハマらないことです。
学習意欲が高い人ほど面白く感じるでしょうし、解けると気持ちがいい。解説も読んでいて興味深いものではありますし、そういった内容に紙幅を割いている参考書もありますが、本試験での出題数は多くはありません。すでに基準点を超えていて+αを積み上げたい人が余力で学習する分にはいいと思いますが、まずは条文や頻出判例に関する問題を確実に正解していくことが大事だと思います。
正答率も出題率も低い問題にとらわれるより、正答率も出題率も高い問題を落とさないこと。これが択一式で基準点に達せず不合格とならないためには重要なことではないでしょうか。
記述式
とにかく制限時間に気をつけることです。
答練である程度制限時間内で解答できるようになっても、本試験会場での緊張感は、想像以上に影響してきます。後述しますが、令和7年度本試験では散々な目に合いました。
本試験当日
あれやこれやと悪あがきをしたい気持ちをぐっとこらえて、試験会場のお供には「出題予想論点総チェック講義」のレジュメのみを持参。本試験前の緊張感で集中して読み込めるわけでもないのですが、かといって丸腰で会場に座っていられるほど図太くもない。なんとなくそわそわしながらテキストに目を通しつつ、試験官の説明開始まで過ごしました。
午前の部の択一式は迷わず解けたのが9割程度。過去問やCROSS STUDYでも似たような正答率でしたので、まあこんなものか、といった感じです。
問題は午後の部です。前述のとおり民事訴訟法等・供託法は学習不足の状態で挑んだのですが、直前1週間で『択一六法』に目を通したのがそれなりに功を奏し、8割程度確信を持って解答ができたため、記述式に取りかかるときには完全に欲が出ていました。
その結果、完全に冷静さを欠き、普段の答練ならほぼ迷わないような問題で散々時間を取られて、不動産登記記述式を解答し終えた頃には試験時間残り15分足らずという体たらくに(そもそも私の場合、商業登記の方が点数を取りやすいと答練でわかっていたのに、なぜ不動産登記から着手してしまったのか…)。
結局、商業登記記述式の方は、1件分の申請書すら書き切ることができなさそうでしたので、少しでも加点を狙おうと、急いで議事録に目を通し、登記の事由と添付書面だけ列記して…そのうちに、試験時間終了を迎えました。
わからなくてパニックになるのはイメージしやすいですが、想定以上に出来すぎて動揺することがあるのは予想外でしたね…。
筆記試験結果と総括
どうやら最後の悪あがきが実を結んだようで、何とか筆記試験を合格することができました(個人的には「試合に勝って勝負に負けた」といった感覚ですが)。
今年含めて3回受験した印象では、択一式はおおむね過去問や模試のとおりの正答率に収束します。基準点未達とならないためにも、また総合点で合格点に達するためにも、まずは択一式の練度を上げることが大事だと思います。
記述式については、私の場合、受験年度によって浮き沈みが大きく、合格した今年ですら上述のような有り様ですので、参考になるようなことは申し上げられそうにありません。ただ、商業登記記述式でわずかながらでも点数を稼ぐことができたのは、登記の事由から必要な添付書面を導き出すスピードが学習初期に比べて格段に上がっていたから。これは答練で培った経験のおかげだと思います。
令和8年度以降合格を目指される皆さんへ
例年発表される司法書士試験の合格率は一桁%を推移していて、ハードルが高い難関資格、という印象を抱かれている方も多いと思います。実際私もそうでしたし、受験会場が県外ということもあり、初回の令和5年度はあまり学習も進んでいない中、お試し受験・会場視察感覚で受けました。
逆に言えば、9割を超える不合格者の中には、令和5年度の私のように、そもそも受かる気がない人たちも多分に含まれており、いわゆる「ガチ勢」の合格率はまた違う数字になるのではないか?ということです。
もちろん難しい試験であることは間違いありません。民法、会社法は条文も頻出判例も多いですし、不動産登記法、商業登記法は多くの人は馴染みがありません。しかし、過去問をやり込んでいけば、突拍子もなく難しい問題が出題されるわけではないということも見えてくるのではないかと思います。
決して恐れず、されど油断せず。着実に基礎を固めていけば、突破できない試験ではありません。学習が楽しくて仕方がない人も、難しくて壁にぶつかっている人も、取り組んだ日々の積み重ねは確実に合格の礎となるはずです。皆さんのご成功をお祈り申し上げます。