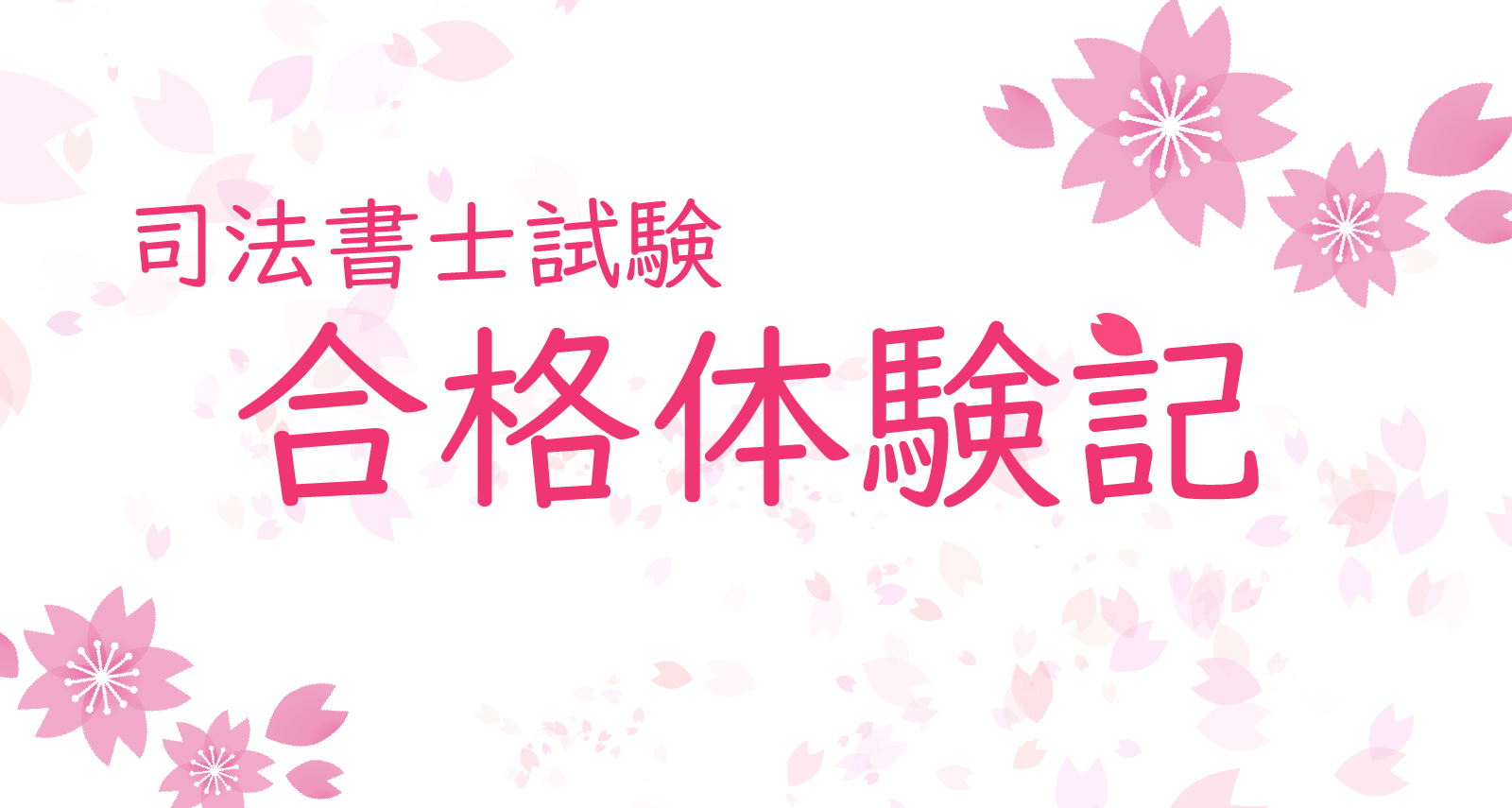F.Tさん
受講コース
中上級パーフェクトBコース安心保証プラン
ふりかえり(反省)
71歳になり8回目でやっと合格できました。内3年が現役で仕事をしながら、その後退職し受験に専念したのですが、図らずもさらに5年を費やしてしまいました。若い頃、宅建士を独学1回で合格できたため、「司法書士も簡単に取れるだろう」と考えていましたが、実に甘かったです。
受験勉強が長引いた理由をいくつか挙げてみます。
(1) 受験初期が民法の大改正にまたがってしまい、旧法と新法の両方を初級講座で延長も含め4年間受講したため、回り道してしまったこと。
本試験の択一式問題の正答率が悪くても、中上級コースに進み、「【中級】択一六法マスター講義」を受講すれば、早く論点の理解が深まったと思われます。条文の法的論理立てを理解できていないと、択一式の応用問題に対応できず、暗記しても忘れやすく非効率でした。
(2) 4回目でやっと択一式の基準点をクリアーしたにもかかわらず、その後3回も記述式の基準点をクリアーできず、午後の部の択一式のスピードアップと記述式対策の壁を中々超えられなかったこと。
記述式試験において、ひな形の暗記は必要条件ですが、論点と解法の理解が不十分だとひな形を覚えただけでは歯が立ちません。
(3) 勉強の仕方が間違っていたこと。
辛いことではありますが、試験結果は冷静かつ冷徹に分析し、なぜ間違えたのか、理解が不十分な点はどこか、同じミスを繰り返さないためにはどうすればいいのかなどを明確にし、対策を練る必要があります。ところが当時の私は、それを行わず、戦略も戦術もないまま、やみくもに勉強していました。
① 当初、限られた勉強時間の中で択一式の勉強としてはテキスト読込に重点を置き、勉強に時間のかかる過去問を後回しにしていました。過去問は条文や論点そのもので、過去問の正答率を高めることが、択一式基準点攻略の要であること、択一式の肢が記述式の論点に繋がっていることを十分理解していませんでした。
② 司法書士試験は択一式が11科目と範囲が広く、各科目の専門知識の習得も大変で、記述式では設問の文章と添付書面が膨大で、ひっかけの問いもあって複雑な記述式は読解力・判断力・頭の回転力が試されます。特に午後の部の試験は3時間で処理しなければならず、コツコツ勉強していればいずれ受かるだろうという甘いものではありませんでした。YouTube等で、各予備校の試験結果の分析と今後の対策や、午後の択一式を早く正確に解く方法、記述式の解法の解説が見られるので、それをもっと活用すべきであったと後悔しています。
司法書士を目指した理由
超高齢社会が進行する中で、定年退職後も生涯現役で、社会的貢献できる仕事を通して、生きがいを持ち続け、人間関係づくりが拡大できるためです。
なぜクレアールを選んだか
(1) 料金が他校に比べ格安であること。
(2) 信頼でき、教材・講義がわかりやすいこと。
特に、『択一六法』は、他校にないとても優れた教材です。その『択一六法』の解説講義である「【中級】択一六法マスター講義」と択一式過去問の解説講義(基本4法過去問解説講義)等の音声データをスマホにダウンロードすれば、日常生活の各場面で繰り返し復習のヒアリングができ、時間の有効活用ができます。
クレアールで学習して良かった点
(1)『択一六法(全科目)』と「【中級】択一六法マスター講義」
条文の解説だけでなく論点が列挙されているので、繰り返し学習することによって理解を深めることができました。過去問の論点等を余白に付記し、改訂版が提供されるたびに、日数がかかっても旧版の書込みを転記しました。
(2)『合格書式マニュアル』
ひな形・登記記録・解説がコンパクトにまとまって使いやすかったです。余白に、教材や答練等で学習した論点、注意点、関連するひな形等を書込み、ポストイットで横断的に整理すべき事項を貼付し、自分なりの「虎の巻」にしました。
※(1)(2)は実務でも活用できると思います。
(3)過去問題集(基本4法)の解説講義
「基本4法過去問解説講義」は机上で解く際よりも、後日復習用に早回しで視聴し、効果的・効率的に活用できました。
(4)答練
記述式の添削は、シビアできめ細かく、自分では気づかなかったミスの修正に役立ったほか、採点も本試験に近いのではと思っています。択一式は、法改正や未出論点も出され、過去問を補填できました。
(5)講師
先生方の講義やパワーポイントのスライドはわかりやすく的確で、また先生方が個性的で、特徴があり、視聴していて飽きませんでした。試験当日に向けた激励は、肝に銘じ本番に臨みました。
この1年の取組み
昨年7月の試験終了後、筆記試験の合格発表までの3か月間、受験勉強から離れ休養し、10月から気合を入れ直し勉強を再開しました。大まかな月単位の全科目のスケジュールを立て、自分で「週間学習表」を作成し、毎日の学習内容を翌日に記録するようにしていました。
試験2か月前頃からは、試験前日までにやるべきことと所要日数をリストアップし、スケジュール管理をしながら追い込みをかけました。
10月当初は、苦手な記述式から始めようとも思ったのですが、択一式の基準点を割っては意味がないので、択一式過去問の学習を先行しました。市販の問題集も活用し、平成元年から全問ストップウォッチで計測しながら解きました。
基本4法の択一式の論点が、記述式の論点になり、特に午後の部の択一式はマイナー科目を含めて正答率を上げることが、解答スピードアップと記述式に回す時間の確保につながります。
令和6年10月から民法・不動産登記法の択一式過去問に同時着手し、11月下旬から不動産登記の記述式を開始。令和7年1月から会社法・商業登記法の択一式過去問を同時並行させ、同月下旬から商業登記記述式を開始。2月中旬から民事訴訟法、民事保全法、民事執行法過去問と刑法過去問、3月下旬から憲法過去問。供託法・司法書士法は、昨年試験直前に択一式を全問やったので割愛し、『択一六法』等の熟読に重点化。
4月からは「実力完成総合答練」の他に、全科目『択一六法』の速読み通読を実施。上級講座(上級マスター講義 択一式編)のレジュメも隙間時間で通読。5月中旬から市販の問題集で不動産登記記述式過去問(平成10年から)商業登記記述式過去問(平成年18年から)を全問実施。虎の巻にした『合格書式マニュアル』も全ページ点検。
特定の科目に専念すると他科目は記憶からこぼれるので、過去問に取組中の科目以外は、タブレットやスマホで、「【中級】択一六法マスター講義」、「【上級】上級マスター講義 択一式編」、「基本4法過去問解説講義」を早回しで学習しました。外出時、ウォーキング、日常の家事、朝夕の筋トレ・ストレッチ、歯磨き、トイレあらゆる日常生活の中で、記憶喪失を防ぐためイヤホンで聞いていました(但し、食事と入浴は除きます)。暗記も欠かせないので、自分なりの語呂合わせや、市販教材も活用しながら定期的に記憶喪失を防ぎました。
初級講座の「基本テキスト」は、年数の経過で法改正に対応できなくなっていたので、市販の教科書をそろえていましたが、理解不十分の論点はテキストに戻りました。なお、疑問点は、インターネットで検索すると司法書士等の実務解説が即時に得られる場合が多く、有効でした。
記述式対策は、他校教材も活用し、「解法」の習得に重点を置きました。これまでにワード・エクセルで作成し独自資料を加筆訂正しながら何度か見直し、新たに「解法の虎の巻」を作成しました。復習としては、択一式と同じように、「【中級】記述式解法マスター講義」や「記述式ハイパートレーニング解説講義」を早回しでヒアリングしました。
【不動産登記作成資料】
論点:主・付記登記、登記の原因及び登記上の利害関係人の同意・許可、単独申請
登記名義人・債務者の死亡・合併・会社分割等
解法:設問の登記記録・文章・添付書面の読み順とチェック方法、当事者の関係把握、
登記原因の把握(簡潔な図解方法含む)、できない登記(根抵当権の元本確定等)
申請順序(名変・一般承継等の前提登記、設問による記載指示、一括申請等、省略可否)
申請人(単独・共同・代位)、構成用紙の書き方
解答点検ポイント(順位番号、持分、変更・更正、税率等)
ひな形:用益権を含むすべてのひな形(申請事項、添付情報、登録免許税)をエクセルの表に(272事例)
信託:『合格書式マニュアル』に掲載がないため、マニュアル化。(いつか突然出題されるおそれ)
【商業登記作成資料】
ひな形:ひな形を類型化し、ひな形ごとに登記の事由・事項、議決機関、添付書面、登録免許税、論点を整理
組織再編・設立は、吸収合併・新設合併等事由ごとに表にし、比較できるよう整理
株式・新株予約権・資本金の計算方法
添付書面:上記ひな形の逆引きで、添付書面ごとにそれを必要とする登記の事由を整理
解法:設問の会社情報・文章・添付書面・聴取記録等の読み順とチェック方法
登記申請事項、登記できない事項の把握(議決機関要件、前提手続き等)
構成用紙の書き方等(役員変更、株式・新株予約権・資本金の変更等)
論点(役員変更、株式・新株予約権の発行、機関設計変更、公開・非公開等)
持分会社:『合格書式マニュアル』では、合同会社の一部のひな形しか掲載されていないため、合名・合資会社を含む社員の加入退社、代表社員変更・責任変更、清算・解散等を作成
択一式、記述式共通の大問題が、ケアレスミス対策です。失敗ノートも有効ですが、同じミスを何度も繰り返すので、問題を解く手順としてミス防止方法を組み込むこと、そして解答を素早く点検できるポイントを用意しておくことが大事でした。
試験当日
午前の部
択一式は、他の受験生のペースが気にならないよう、まず第35問を先に解き、序盤に戻って憲法は第3問から着手しました。第1問は難問が多い傾向があり、最初からつまずかないためです。
「実力完成総合答練」でも正誤の選択を逆に見誤ったり、選択肢の見誤り、マークシートの転記ミスがあったので、防止手順を習慣化するとともに、肢の要件、文末の否定・肯定型、断定・非断定等のひっかけ論点にアンダーラインし、注意を促すようにしました。また、見直しを効率的に行うため、「戻るマーク」に軽重をつけ工夫しました。
午後の部
択一式、不動産登記記述式、商業登記記述式の順としました。
「実力完成総合答練」では他の順番も試しましたが、記述式が難問で時間を費やし、焦った状態で択一式をこなす自信がなかったことと、多くの受験生に合わせた方が、難問でつまずいた時も皆も同じなので平均点から外れないだろうと思ったからです。
今回は、択一式65分、不動産記述式65分で残る50分で商業登記に移ったため、商業登記は焦ってしまい、今までにない論点、多い記述量に対応ができず、2つ目の登記申請の登記事項を記載している途中で時間切れとなってしまいました。後5分あったら全部書けたのにと悔しさが残りました。
記述式の設問分量が増大している中で、択一式は60分以内に処理しないと最後まで到達できないのではないでしょうか。なお、商業登記記述式は時間切れを想定し、1点でも多く取れる記載順にする方法も用意しておくことが必要でした。
最後に
クレアールの先生及びスタッフの方々には本当にお世話になり感謝申し上げます。
他の合格者の方よりも長く受験勉強をしてしまいましたが、その分中身の濃い勉強ができたと思い、今後の実務に役立てていきたいと思います。