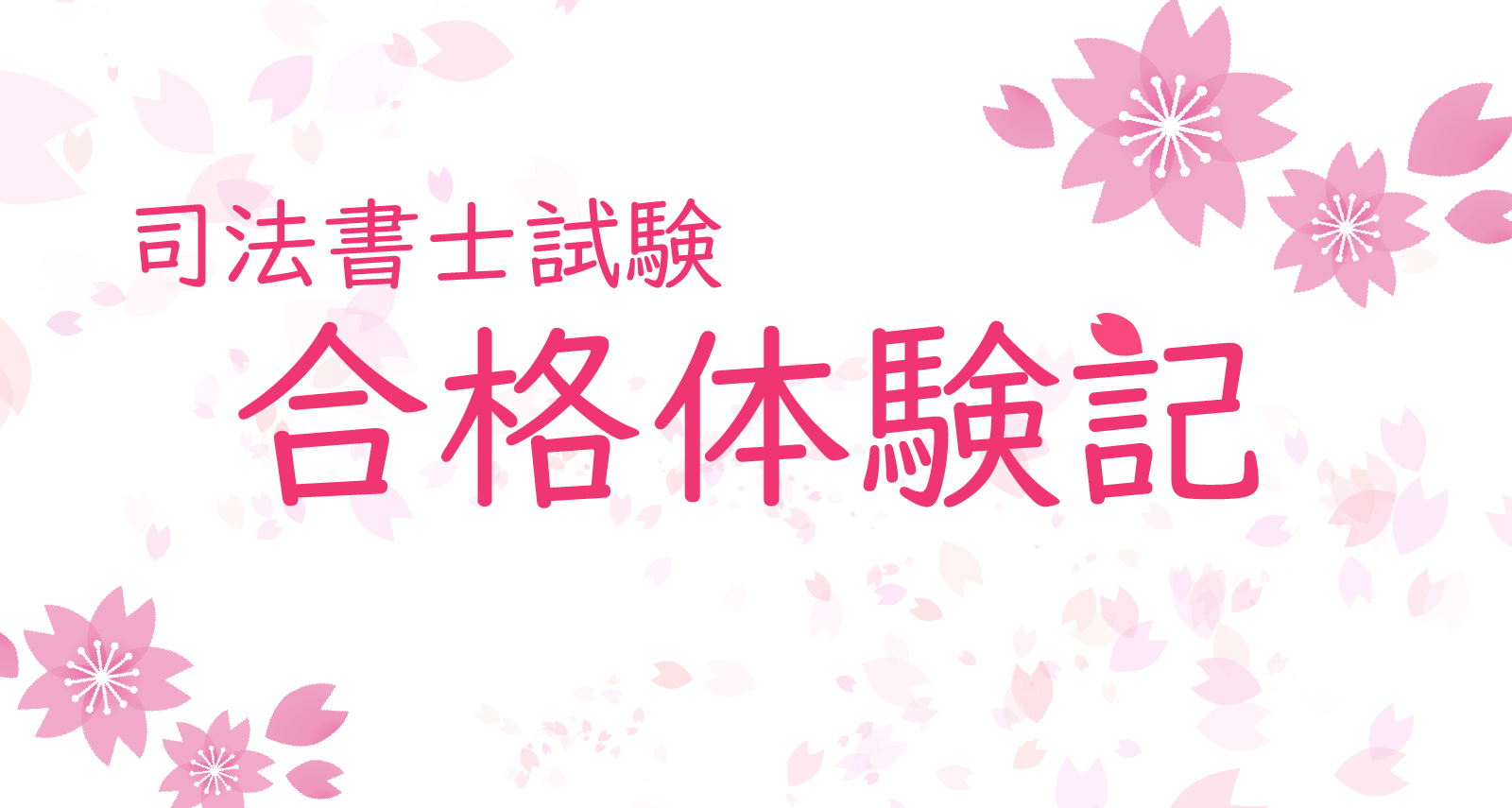K.Cさん
受講コース:行政書士受験経験者対象 1年スタンダードコース 安心保証プラン
※時期によって販売期間外の場合がございます。
なぜ司法書士を目指したか
以前に不動産を購入した事があり、その不動産登記を自分で行った事がきっかけ。定年の無い働き方もこのご時世にマッチしている事もあり、勉強する事となった。
なお、司法書士試験受験以前に社会保険労務士試験、行政書士試験にも合格している。
予備校選びのポイント
社会保険労務士は独学で取得したが、行政書士はクレアールを選んだ。インターネットで検索すると、他校と遜色ない内容であるが、受講料が安価であったため受講を決めた。自然と司法書士もクレアールを受講することとなった。
クレアールで学習して良かった点
民法・商法(会社法)・憲法は行政書士と司法書士とで科目が重なるので、「2024・2025年合格目標行政書士受験経験者対象1年スタンダードコース安心保証プラン」を申し込んだ。『択一六法』について、条文毎に解釈、判例の記載があり、また解説講義の1.5倍速音源のダウンロードが可能であった事が良かった。合格体験記が送付されるので、全て目を通して、学習法など参考とする事が出来た。
受験年度別の学習と試験結果について
1年目(~お試し受験)
学習方法
基礎期として、「基本マスター講義 択一式編」「基本マスター講義 記述式編」をオンライン受講した。講義を視聴してから「基本テキスト」の見直しと該当箇所の過去問を回すので精一杯であった。
本試験の解答
お試し受験という事もあり、過去問も回していない状態での受験であったので、場慣れの受験であった。午後の部の解答に時間を要すると感じた。昼の休憩時間は1時間あり、事前にコンビニで購入したおにぎりを昼食とした。休憩時間中に会場外に昼食を買いに行くのは難しいと感じた。休憩時間でも、部屋又は廊下などで教材を眺めて学習している人が多数いた。この休憩時間で眠気が出ると、午後の部に影響が出るので、昼休憩の使い方が午後の部に影響が生じると感じた。以後の受験での休憩時間は、目を覚醒するように心がけた。
本試験(令和5年度試験)の結果→基準点に達せず
| 令和5年度試験 | 午前の部 択一式 | 午後の部 択一式 | 午後の部 記述式 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 54/105 | 42/105 | – /70 |
| 基準点 | 78 /105 | 75/105 | 30.5/70 |
2年目(目標年度)
学習方法
応用期として、「【中級】択一六法マスター講義」「【中級】記述式解法マスター講義」「科目別ベーシック答練 択一式編・記述式編」をオンライン受講した。
『択一六法』をインプット教材として、過去問を解きながら不明な箇所は『択一六法』に戻り確認を行った。また、クレアールから送られてくる答練・模試など何度も繰り返し解答を行った。ただ、あまり見慣れない問題は解けず、『択一六法』を読み込んでいない状態であった。例えば、会社法の新株予約権の買取りの事例で会社が買い取り出来る場合、出来ない場合の整理などが不完全であった。
本試験の解答
午後の部は、択一式→不動産登記法記述式→商業登記法記述式の順で解答した。なんとか時間内に解答したが、午後の部の択一式の見直しは出来なかった。次年度の本試験では、午後の部の見直しが課題と感じた。
本試験(令和6年度試験)の結果→基準点に達せず
| 令和6年度試験 | 午前の部 択一式 | 午後の部 択一式 | 午後の部 記述式 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 75/105 | 42/105 | – /70 |
| 基準点 | 78 /105 | 72/105 | 83.0/140 |
3年目
学習方法
自宅では紙冊子の過去問題集を回した。基礎知識の再確認が必要と考え、通勤時には、МP3プレイヤーにインストールした1.5倍速の『択一六法マスター講義』の音声を聞きながら、『択一六法(主に基本4法)』を確認することに集中した。例えば、民法の条文の「過失」「重過失」の違いなど細かく学習が必要な部分に注力した。
紙冊子の過去問題集については、それぞれ分量が多いので、例えば1ページ飛ばし、2ページ飛ばしなど行い、全範囲を短期間で解答出来るように心掛けた。
直前期には、それまで解答した「出題予想論点総チェック講義」「実力診断模擬試験」「実力完成総合答練」「全国公開模擬試験」について繰り返し解答を行った。
本試験の解答
本試験の解答について、比較的時間のある午前の部は各問5肢すべてを検討しての解答を心掛けた。
午後の部の択一式と記述式は限られた時間で解答する必要があり、事前に解答順序も検討したが、問題番号通りに択一式→不動産登記記述式→商業登記法記述式で解答する事とした。午後の部は3時間で時間配分はそれぞれに1時間充てる事とした。また、午後の部の択一式は午前の部と異なり時間が少ないので、各問を見て、文章の比較的短い肢から解答し、2肢又は3肢で組み合わせの解答が出来るのなら全ての肢を見ないようにした。時間短縮し、記述式が終わってから見直しを行う予定とした。ちなみにクレアールの模擬試験等は理解促進のため各問の全肢を見てからの解答を心掛けた。
令和7年度の午後の部の択一式の商業登記法と不動産登記記述式の出題について、後日各スクールの解答が割れるような疑義が生じたこともあり、特に記述式の基準点が前年度より低かった。『記述式ハイパートレーニング』、『合格書式マニュアル』に記載の無いようなひな形が、この年度の不動産登記記述式法及び商業登記記述式で出題された。その場で悩んだが、記述式の欄に記載しないと得点出来ないので、わかる範囲で欄を埋めるようにしたが、択一式の見直しが出来る時間は残って居なかった。その時は記述式のひな形が分からない問題が出題されたので落ちたと思ったので、後の筆記試験合格発表で自分の番号を見つけた時には大変驚いた。とりあえず記述式の解答欄に分かる範囲で残り少ない時間の中、書き殴りになったが書いて良かったと感じた。
ちなみに、受験した7月から筆記試験合格発表の10月まで、ただ合格発表を待つだけでは時間が勿体ないので「2026年合格目標 上級パーフェクトコース」を申し込んで、学習継続を行っていた。商業登記法のレジュメが届いたタイミングで筆記試験合格発表があり、自分の番号を見つけたので司法書士筆記試験の勉強は終了となった。
(クレアール実力診断模擬試験)
得点 午前の部63点、午後の部択一式72点、記述式97点、判定D
(クレアール全国公開模擬試験)
得点 午前の部69点、午後の部択一式66点、記述式80点、判定D
本試験(令和7年度試験)の結果→総合合格!!
| 令和7年度試験 | 午前の部 択一式 | 午後の部 択一式 | 午後の部 記述式 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 90/105 | 75/105 | 90.0 /70 |
| 基準点 | 78 /105 | 72/105 | 70.0/140 |
CROSS STUDYの進め方
(A)どのように利用したか。
通勤電車の中でとか、ちょっとした合間に利用した。
(B)学習時期・段階ごとの利用方法の変化
ちょっとした時間に利用したので時期による変化は無し。
(C)復習の際に意識したこと
通勤電車の中で気になった問題には、重要度で分かるようにして、帰宅後『択一六法』などで確認した。
(D)紙冊子の過去問題集との使い分け
CROSS STUDYはちょっとした合間に、自宅では紙冊子の過去問題集の使用と使い分けした。自宅での問題演習では、その都度不明確な点は、『択一六法』に戻り確認したのが良かった。
学習全般
学習をすすめていくうえでのポイント、心構え
時期になれば、「科目別ベーシック答練択一式・記述式」が、直前期には「実力完成総合答練」等が送付されるので、タイムリーな解答・復習を心掛けた。
学習スケジュールをどのように立てて、学習をすすめたか
クレアールの「学習計画表・配信予定表」のスケジュールに沿って学習を進めた。
効果的な学習方法(科目別の学習方法、記述式対策の工夫等)
民法、不動産登記法、商法(会社法)、商業登記法の基本4法は、日々絶えずどれか一科目は音声学習、過去問、CROSS STUDYなどで触れるようにした。
基本4法に準じるの民事訴訟法等は、1週間に一度は触れるようにした。
マイナー科目である憲法、刑法、供託法、司法書士法は、それほど力を入れなかった。
直前期には、全ての科目を回すことに集中した。
記述式は、仕事が休みの週末の土日にそれぞれ不動産登記1問、商業登記1問を繰り返しノートに記載して演習し、確認した。『記述式ハイパートレーニング』の問題を何度も解答し、わからなければ『合格書式マニュアル』を確認するようし、ひな形を覚えるようにした。
職場では、夜勤もあり、時間があるときに解答出来るように過去問など持参して、隙間時間の有効活用を心掛けた。
学習初期、中期、直前期の学習方法の変化
年間を通じて、初期は基本4法過去問、中期は科目別ベーシック答練、直前期は模試・答練の見直しとともに平日は毎日『択一六法』の解説を音声で受講していた。
効果的であった択一式対策
通勤が2時間という事もあり、「【中級】択一六法マスター講義」の1.5倍速音源をMP3プレイヤーに落として、電車のつり革を片手で持ち、もう片手で『択一六法』を見ながら、該当の音源をずっと聞いていた。1年で基本4法を2~3回を回した。それをしたことで、受験3回目の令和7年度本試験の点数が飛躍的に伸びた気がする。
効果的であった記述式対策
択一式の過去問を解きながらでも、ひな形の記載はどうかと迷ったら、『合格書式マニュアル』の確認をするようにしていた。
苦手分野の克服について
不動産登記法・会社法・商業登記法が当初苦手であった。とりあえずテキスト・問題集は何回か回さないと理解出来ないと思う。どの科目も、条文を理解しても、似ているが異なる別の条文では違う事を記載している事もあるので(例:抵当権と根抵当権での債務者変更に印鑑証明書が必要となるかの取扱いが異なる)、比較して覚える事が必要である。
令和8年度以降の合格を目指すクレアール司法書士講座受講生へのメッセージ
司法書士試験の学習のため、土日・祝日は朝から記述式を解答し、それから基本4法を中心に過去問を回して、午後9時ごろまで断続的に時間を使った。平日は通勤時間片道2時間を、学習の時間に充てた。ただ、ジョギングなどリフレッシュは欠かさなかった。毎日ずっと学習するのは辛いが、合格発表を目指して頑張って欲しい。クレアールでは、直前期になれば、答練・模試が送付され予想問題も解答出来るので、丁寧に学習することを心掛けることが大切かと思う。また、模試の結果が悪くても、本試験で合格することもあるので、最後まであきらめずに学習を継続して欲しい。