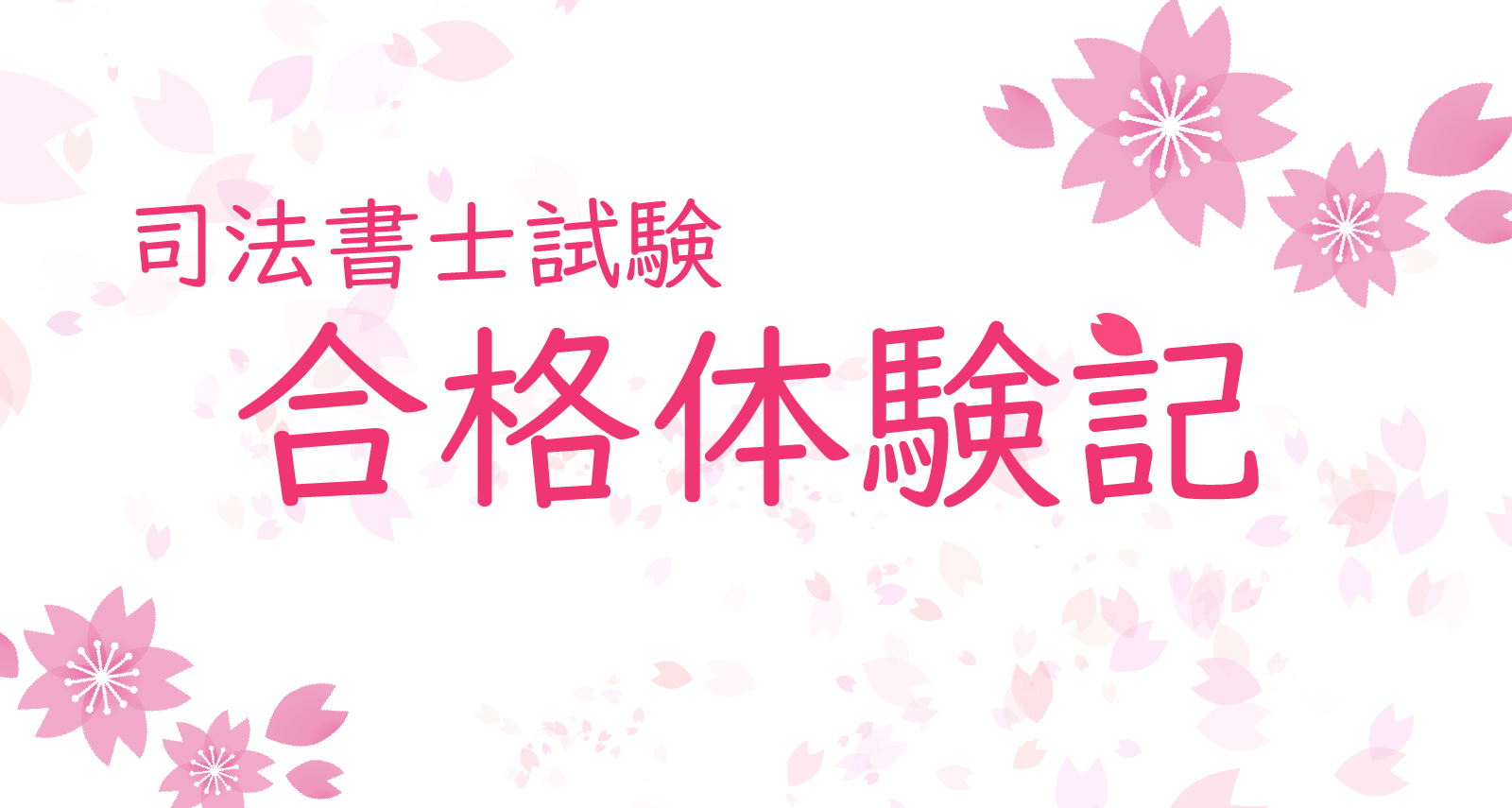M.Iさん
中上級パーフェクトAコース
司法書士を志した理由
もともと不動産に興味があり、宅建士の資格を取得したことをきっかけに、さらに法律を学ぶことで今後の人生に役立つと考え、司法書士を志しました。 また、司法書士補助者としてアルバイトをする中で、この業界の一端を経験することができ、司法書士の業務の幅広さを実感し、ぜひ自分も挑戦してみたいと思うようになりました。
クレアールを選んだ理由
受験初年度から前年までの5年間は、他校で学習を続けていました。令和6年度本試験では、択一式基準点を突破し上乗せも取れるようになっていたため、「択一式知識は現状維持しつつプラスアルファできればなんとかなりそうだ」と見当がつきましたが、記述式に関しては、安定した得点が取れないことに悩みました。
記述式の学習は単調に感じられたため、ひな形の学習もおろそかになってしまい、どのように取り組めばよいのかもわからなくなっていました。尊敬する先輩司法書士の先生に相談した際に、「今でも実務で使っている教材がある」と見せてくださったのが、クレアールの『合格書式マニュアル』でした。
その先生はクレアールの卒業生で、「実務に出てもこの『合格書式マニュアル』を見返すことがある」とおっしゃいました。実際に実務家が手元に置いて使っている教材を見て、私は直感的に「これだ」と確信し、クレアールの受講を決意しました。
クレアールで学習してよかった点
古川先生の「【中級】択一六法マスター講義」は、知識を詰め込むのではなく、「なぜそうなるのか」を重視して説明してくださいます。講義中の「これはなぜかというと」といった解釈や理由付けを添えて説明していただけたので、その部分を集中して聴くようにしていました。そのおかげで、条文・趣旨・判例がどのように結びついているかを理解でき、より具体的にイメージできるようになったと思います。
また、記述式では主に『記述式ハイパートレーニング』と『合格書式マニュアル』を活用しました。記述式は点数が伸び悩んでいたので、すぐに問題演習と講義視聴に取りかかりました。『記述式ハイパートレーニング』は、過去問をアレンジした問題が収録されているため、フルバージョンの半分程度の分量で、無理なくこなすことができました。また、詳しい解説講義と図表や要点などをまとめた解説レジュメがあり、本書の余白にすべて貼り付けて、何度も見返し、直前期まで活用しました。
『合格書式マニュアル 不動産登記』では、申請書のひな形だけでなく、登記記録の記録例の抜粋が多数掲載されており、登記記録例を確認することで、「実際にどのように登記されるのか」を具体的にイメージでき、ひな形の学習にも大いに役立ちました。
「合格書式マニュアル 商業登記」では、形式や登記事例だけでなく、「重要先例」や「解答に当たって注意する点」など、盲点になりやすいポイントが体系的に整理されており、これを意識して復習することで、商業登記の理解が深まったように思います。
CROSS STUDYの活用 ― 時期別の使い方 ―
学習初期 10~12月
前年度に午前の部、午後の部ともに択一式の基準点を超えていたため、全科目をまんべんなく回す目的で、全科目のカテゴリを選択してランダム出題で解いていました。
毎日休まず最低50問を目標とし、理解度に応じて重要度★1(完璧)・★3(あいまい)・★5(間違い)に分類しました。途中までユーザータグも使っていましたが、重要度のみで管理した方が、使いやすいと感じ、途中からは「あとで解答」のユーザータグだけを利用しました。
最も重宝したのは「メモ」機能で、勘違いしやすい点を自分の言葉で言い換えたり、条文を貼り付けて整理したりすることで、記憶の定着に大いに役立ちました。
学習中期 1~3月
紙ベースでの過去問演習と並行し、CROSS STUDYでは「選択中のカテゴリの苦手な問題を解く」機能を活用して弱点克服に集中しました。スキマ時間の活用にも最適で、食事中や就寝前に手軽に復習でき、知識が維持できました。
直前期 4~6月
全科目を横断的に解き、一度でも間違えた問題だけを選択して、ランダムで解きまくりました。また、「実力完成総合答練」で間違えた問題の範囲(例えば抵当権の特定の論点を間違えたなら、抵当権の分野全部の問題)を絞って再解答しました。
CROSS STUDYと紙の問題集の併用
令和7年度試験に向けて本格的に学習を再開した令和6年11月中旬頃は、紙の問題集とCROSS STUDYを併用しました。紙の過去問題集では、「基本4法過去問解説講義」を聴きながら要点をまとめ、図表や表を貼り付けて視覚的に整理しました。CROSS STUDYでは得られない「書いて覚える」作業を取り入れることで、理解がより深まりました。
まずは、最優先にAランク、余裕があればBランクを中心に全問演習し、間違えた問題だけ「基本4法過去問解説講義」を確認。その後、『択一六法』で該当条文を確認し、CROSS STUDYで該当問題を検索して「あとで解答」に設定し、スキマ時間に解き直しました。
4月以降は、紙の過去問題集にはあまり時間をかけないように、自分が書いたまとめメモや貼り付けた図表などをさっと目を通す復習用として使い、択一式対策の中心をCROSS STUDYへ完全に移行しました。
具体的な対策
年内は、択一式対策として、CROSS STUDYを一通り回すこととし、民法と不動産登記法は、弱点と思われる分野の「【中級】択一六法マスター講義」を最優先に視聴、商法・商業登記法は、過去問演習を優先、マイナー科目は、択一六法と過去問演習をメインにしました。可処分時間が少なかったので、できるだけ優先順位をつけ、「やらないこと」を増やしました。また、週単位で11科目をまんべんなく学習するようにバランスを意識し、特定科目への偏りを防ぎました。
年明けからは、「記述式は毎日フルサイズ各1問(不登法1問、商登法1問ですが、適宜省略して解答。書き慣れていないひな形はすべて書く)、択一式はCROSS STUDYで「1日50問」を目標に、ルーティン化して学習リズムを崩さないようにしました。
仕事との両立とモチベーション維持
アルバイトとして週4日、司法書士事務所で補助者業務を行っていました。短時間勤務ではありましたが、残業も多く、繁忙期には可処分時間が限られていました。
平日は多くて3時間、休日は9時間というペースを、直前期も変わらず維持しました。自習室を借りて、集中して勉強する日も決め、実行していました。
また、モチベーション維持の工夫についてですが、3回目の受験を迎えた頃から、7月の本試験後に少し勉強から離れるように意識した時期がありました。なんとなく勉強する気になれなかったのも理由ですが、大体10月か11月までは、法律関連書籍を読んだり、映画や買い物など一人で外出したりと、勉強から距離を置き、リフレッシュするように努めました。やったとしても択一式問題集を数問と記述式の小問1問程度で、あまり熱心に勉強はしないようにしました。あえて休む期間を設け、頭の中のパズルを組み直すような感覚で、私にとっては良い頭のリセット法でした。
このように頭をリセットする期間を設けることによって、再び勉強を始めたとき、以前は理解できなかったことがすっと腑に落ちることが何度もあり、すっきり理解することができました。ただ、この方法は、完全に忘れてしまうリスクもあり、万人向けではないかもしれません。
学習期間を通してモチベーションの上下はあまりなく、オンとオフを明確に区切る生活を意識しました。また、問題が解けなくても「今日はこの部分がわかった」「1つピースを埋められた」と、小さな発見に喜びを見出すことで、ポジティブに取り組む姿勢を心掛けました。
受験期の過ごし方
体調管理を最優先に考え、週3日は早朝にウォーキングや筋トレを取り入れました。長年の受験生活で腰痛を患っていたため、座り続けられなくなり、立って勉強する日もありました。最後の本試験まで朝5時前起床、夜は10時過ぎ就寝と生活リズムを守り抜きました。
この6年間は、大好きな旅行も封印し、友人との会食や旅行の誘いも断り続けました。最初のうちは理由を聞かれませんでしたが、受験のことを話すと「その年で資格を?今更?」といったネガティブな反応をされることもありました。今回晴れて合格できた今、ようやく胸を張って報告できることを本当に誇りに思います。
午後の部の対策
年明け以降は、午後の部の択一式で時間配分を体にしみ込ませるため、午後の部の択一式35問の単年度分のみを毎日解く練習を行いました。
また、クレアールの答練や模試は理解を問う良問が多く、2度解き直すことで知識の確認と弱点補強を同時に行いました。さらに、答練や模試の提出期限は必ず厳守し、合格レベルには程遠い成績であっても気にすることなく、淡々と進めました。点数ではなく課題発見の機会と捉え、提出・復習を徹底することで、最後まで学習ペースを維持しました。
記述式の対策
私はもともと書くのは速い方ですが、さらにスピードを上げるためにボールペンにもこだわりました。ボールペンを20本以上試してお気に入りを見つけました。
不動産登記記述式については、以前は苦手でしたが、クレアールの記述式対策講義を受講してから、一気に理解が深まり得点も大幅に伸びました。商業登記は得意科目でしたが、より完成度を高めるために問題演習を重ね、あらゆるパターンに対応できるように、問題数を多めに解きました。
記述式試験は「論点やひな形を知っているか知らないか」で差がつく試験なので、過去問研究を徹底的に行うことが最も効果的だと思います。
令和7年度司法書士試験に合格できた秘訣
司法書士試験合格の鍵は、「基礎を徹底、わからない問題を置き去りにしない」だと思います。
択一式は、受験勉強開始から3年くらいは、ただひたすら解いていただけで、正解できたとしてもぼんやりとした知識でしたが、最終年度は、毎朝前日の復習をし、毎週月曜日の朝にその週の学習計画を立て、「わからなければ何度でも戻る」という日々の積み重ねを淡々と実行しました。
記述式は『記述式ハイパートレーニング』と『合格書式マニュアル』で徹底練習し、択一式は「CROSS STUDY」で知識の精度を高める。この二本柱を軸に、最後までぶれずに取り組めたことが合格の決め手でした。
今後の展望
今後は、司法書士として登記や相続、成年後見、商業案件などいろいろ実務に携わりながら、依頼者に安心を届けられる存在を目指したいです。
クレアールで身につけた「知識を理解して使う」という姿勢を、実務でも常に意識していきたいと思います。
今後、司法書士として関わることのできる業務範囲がさらに広がっていくことを見据え、日々研鑽を積んでいきたいと思います。
来年度受験生へのメッセージ
司法書士試験は長く険しい道のりですが、正しい方向で努力を続ければ必ず合格できます。焦らず、一歩一歩積み重ねてください。クレアールの教材と講義を信じ、CROSS STUDYでコツコツ過去問演習を続ければ、確実に力がつきます。そして、合格の先には、法律家として新しい世界が待っています。皆さんが次の合格者として、この舞台に立たれることを心から願っています。
最後に
最後まで見守ってくれた先輩司法書士の先生や、いつも率先して家事を引き受けてくれた家族に感謝したいと思います。そして、クレアールの講師の方々や事務局・受験対策室のスタッフの方々にもお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。